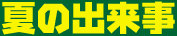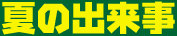〈2〉
薬が今日で無くなる。
爪水虫絶対治したい。
『あの先生のお喋りの相手はいやだけど、薬は欲しい。他の皮膚科はだいぶ歩かなければいけないし。・・・そうだ。今日は、薬だけもらうようにしよう。あんなぐうたらな医者なんだから、どうせ患部もろくに診もしないんだからくれるだろう。意外と、他の所よりゆうずうがきくかもしれないな、こういう医者の方が』と、彼は、またまたこの兎内皮膚科のビルに向か
った。
入口に“兎内ビル”とプレートが出ているのに気付いた。
『え、もしかしてこのビルは兎内皮膚科の持物。・・・そうか別に必死に仕事しなくてもいいってことか』
エレベーターに乗った。また来てしまった。
患者らしき中年の男性がひとり椅子に座り待っていた。
「すみません、今日は薬だけもらいに来たんですが」
受付の女性に診察券を提出して、彼はすかさず言った。品のよさそうな四十前後のこの受付の女性も、また、この皮膚科を異様な感じにするのに一役かっていた。といっても、別に変わったところはないのだが、その品の良いおっとりした話し方が、他では気にもとまらないことであろうと思われるその普通さが妙にここでは日常からかけ離れたものにしていた。
「・・あ、でも・・薬だけお出しすることは出来ない・・の
ですが・・。あの、先生に診ていただかないと・・」困ったように、その女性は言った。社会でもまれた中年女性とは違って、たぶんずうっと主婦をしていて何かの理由で最近仕事を始めた、
という感じだ。
「そうですか。じゃ、分かりました」
『この人と言い合ってもしかたがないんだ。なんだ、ゆうずうきかないのか。もしかして、真面目な所なのか?そんな訳ないよな。ああ、しょうがない、待つしかないか』彼は、聞こえないように小さくため息をついて、中年男性が座る斜前の椅子に座った。
年期の入った何処から見てもサラリーマン風の、前に座る男性。大人しくジッと座っている。会社の中でも、自我を殺して言われるままで何も考えない、一社員を演じている。従順さが身に染みていて、賢い?大人と言ったところである。
この異様な空間に背広にネクタイでいるから、ますます性格のない人間に見えるのだろうか。 『そうか、自分もそう見えているのだろうか。しかし、俺はサラリーマンの出来そこないだ。何回も転職し、いくつになっても夢は消えない。万年平。それにネクタイも、もう何年もしていない。ま、しなくてもいい職場ではあるのだけれど。この人のように無彩色のスーツを目立たないように着て生きれば、落ちこぼれなくてもすんだのだろうか・・・。・・ああ、何を俺はこんなところで反省しているのだろう』
午後の診察開始時間二時をちょっと過ぎた時刻だ。静かだ。まだ診察が始まっていないのだろう。しかし、時間もルーズだ。
『患者がいるからこんなぐうたらな医院でもなんとなく安心できるんだろう。もし、いつも待合室に誰もいなければ、薬だってもらっても飲めないかもしれない』彼は思った。
「山田さん」診察室から先生の声がした。その男性が入って行った。最初の二三分は患者の病状の会話があって、また、あの、世間話風お喋りが、この患者のように社会的に地位のありそうな人でも同じように一方的な会話が始まっていた。
『初診の人ばかりなんだろうか。そうだとすると、あの電話帳の広告の力だろう』等と思っていると、もう一人エレベーターのドアが開いて三十才くらいのOL風の女性が入って来て受付で診察券を出した。
『この人は、初診じゃない』彼は、自分の常識を少しずつ疑い始めていた。
『俺が常識に囚われているのか、今ここにいた、常識の巣とでも言わんばかりの精彩のないサラリーマンや、前で順番をやはり無表情で待っている女性の方が、この誰よりも自由や常識に囚われたくないと常々考えている俺よりも柔らかい精神なのだろうか。社会のなかの常識人達は、表面だけではなく中身もしっかり見ているのだろうか。俺も、しばらくこの先生の外観だけでなく精神も観察してみることにしよう』ドア越しに話声が聞こえる中、そんなことを色々と考えていたら、男性の患者が出てきた。
|
「鱗波さん」
『?今日は(さん)か。そういえばさっきの人も(さん)だったな。気分的なものか?』彼は、ドアを開けて入って行った。
「お願いします」丸椅子に座りながら言った。
「良くなりましたか」
『そんなに早く爪に入った水虫が治るわけないだろ。知らないと思っているのだろうかこの先生は』
「いいえ、まだ・・です。爪が生え変わるまで薬を呑むんですよね。前の時そうだったんですが。六ヶ月くらいですか」
「そうだねェ。そんなにはかからないけどネ。薬がいいからねェ。インターンで病院にいたころにね、患者さんにね、私が処方した薬を出してあげましてね。その患者さんがね、来ましてね。薬がよく効いて、すっかり治りましたってね。で私の先生がね、君、どうして治したんだねっていうんですよねェ」
『また始まった』と、彼は思った。ま、いいや、嫌な顔をするのも大人気ないのかも、と思い生返事をしながら、この先生と周辺に目をやっていた。
部屋の状態はこの前とまったく同じである。そして、驚いたことに先生の着ているものが上から下まで先週見たものと全く同じものなのである。同じものを何着ももっているのだろうと思ったのだが、どうもそうではないようである。
先週見た時よりも汚れがひどくなっている。何回もネクタイに目をやり、確かめた。このネクタイに、何か思い入れでもあるのだろうか。
若い頃に生き別れた女との思い出が込められているのだろうか。そんなことを思わせるような水色の何やら所々にイエローオーカーの模様の入った六、七十才代の人はたぶんしないだろうと思われる色鮮やかなネクタイだ。
『この人、その女と分かれた時以来ずーっとこのネクタイしているんじゃないのかな』と、願望も手伝って何故かロマンチックな想像が広がっていった。
『そうだとするとなかなか面白いではないか、ねえ、先生』で、御本人はというと、まるでそんなことはおかまい無しといった表情で、やはり先週と同じく、お喋りしながら書類にゴム印を探して押したり、何やら書き込んだりしている。で、水虫の爪も見ることもなく三十分ほどたって診察は終わった。
|
薬を一週間分もらって仕事場へ帰って、なにげなくその袋の中を見た。
『あれ、これ先週の薬と違うぞ』
前回のはカプセル。今度は何の説明もなく、錠剤が入っていた。彼は、一気に兎内皮膚科への不信感に襲われた。
『今まで呑んでいた薬は、だいじょうぶだろうか。この薬は飲めない』あのぐうたらなところを少しは好意的にみようとしたり、ひょっとしたら良い人なのかもしれないなと思うようになってきた矢先なだけに怒りのようなものまで込み上げてきた。
『普通、薬の名前と効能や禁止事項が書かれたものをくれるんだけど。俺もお人好しだな。何かの事情があって最小限の治療体制でやっているのだろう等と思いはじめだしていたけど・・・電話してみよう』
|
「はい、兎内皮膚科でございます」受付の女性が出た。
「あ、もしもし、私さきほど診察していただきました鱗波ですが、今日頂いた薬、先週いただいた物と違うんですがこれでいいんでしょうか」少々興奮ぎみだったのでいきなり切り出していた。女性はうろたえたようになって、先生に聞きに行った。
『別に、うろたえることはないだろう。何かこちらが悪いことをしているようじゃないか。変な女だな』
「もしもし」その女性が電話に戻ってきた。
「薬を、持って来てくださいということです。先生がそうおっしゃっています」
「はい分かりました」
『やっぱり間違っていたのか?なんだかおかしいな』
彼は、すぐに皮膚科に行って受付で女性に薬を見せた。彼女は、診察室にいる先生の所に薬を持っていった。薬についてなにやら話声が聞こえる。
「この薬でいいんだけどなあ」先生の声である。
『いいんだったら、いいと電話で言ってくれよ』彼は思った。
「味が違うから変えてくれというのもいるんだよ」等とも話している声が聞こえる。
彼は、呆気にとられていた。そして、何を考えているのかこの先生、前の薬と入れ替えたものを女性に渡した。
『味が違うから文句を言っていると思っているのかこの先生は』空いた口がふさがらないとはこのことか。
『こんなことでよく開業しているなあ』そして、「はい・・・」なんの薬の説明も無く窓口から女性は、その入れ替えた薬袋をさし出した。
『この人たちの問題意識が別の所にある。こちらの薬に対する心配とはよそに、何か他のことを勘ぐり案じているようだ』
「いや、皮膚の薬であればいいんですよ」とだけ言って薬をもらいそそくさと帰った。相手にするのも不愉快であった。
『この医者は、ほんとにおかしい』
|