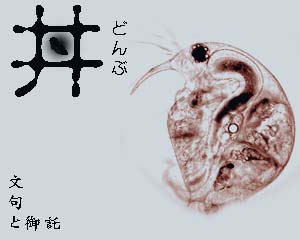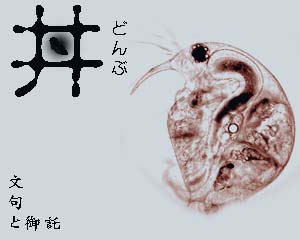勉強会、をひらこうと思う。
もちろん経済アナリストになるわけでもなく油絵画家になるわけでもなくて、当然文芸、ということになるのであるが。
で、なんかこう、迷っているのは「勉強会」ちゅて、何が勉強かよ、ということなのです。何をどうしたら勉強になるのか。昔小学校のときに勉強会って集まってもお菓子食べてファミコンに手が伸びて「ワーイ」とかいって遊んで御仕舞いだなんて。
あったでしょう、そういうの。
それじゃしょうがない。きょうびの小学生も忙しいだろうが、我々社会人もそれなりに忙しいのだ。なんかこう、短期間に少しずつやって長く続くようにするにはどうしたらいいか。
そもそも「勉強する」ってなんなんだろうね。
他の例で考えるとわかりやすいかね。数学の勉強ちゅと、公式を何とか覚えて、それを応用する。こういう問題が出たときはsinθ+cosθがどうの、というのを当てはめればいいのよ、ってあたしは公式を覚える記憶力がなかったんだな。あと計算力。3×2=12なんて平気でやってたものな。
同様のことを文芸の勉強といったものに当てはめるとすれば、過去の作品や論争をみんなで読んで、それについての意見交換をする、というのが一番スタンダードになる。文芸のように大きな前提として前提が機能しないから、それぞれの立場や切り口からはこういう読みや思考をした、という意見の交感が主になる、のか。
が、これでは足りない。大学のゼミナールなんてこう云う感じだが、実はこのシステムというのは、ある程度共通する知識がないとやってられないのです。誰かが川端康成の『雪国』やりたーい、といっても読んだことのない人はわからないし、読もうと思ってもその準備の時間がない。だいたいここで挫折するわけ、です。学究の徒と在野の士の大きな違いであります。文庫本を買うのだってそれなりのお金がかかるしね。
で、どうしようかと考え中。
ただ、やる以上は、お金や時間を費やしただけ得るものがなければならないと思う。少しでも志のある人が参加しやすいものでなくては、とも思う。
意見があったらください。
ちゅか「学ぶ」場所も「教える」人も少なすぎる。
|
|