「ルールのない危険なスポーツ」における危険の引受と民事上の注意義務
弁護士 溝手 康史
| 1、問題の所在 危険なスポーツ中の事故に関する損害賠償責任(不法行為責任、債務不履行責任)の問題については、サッカーや野球などの競技上のルールが存在する場合は、それを基準に行為の違法性を考えやすい。例えば、野球の試合中に打者の打った打球が守備選手の顔面を直撃したとしても、ルールに則ったプレーである限り違法性がないと考えることができる。 しかし、競技としてではなくレジャーとして行われるカヌー、ヨット、パラグライダー、ダートトライアル、スキューバダイビング、登山のように競技ルールが存在しない場合には、行為の違法性の判断の基準が明確ではない。例えば、冬山登山で斜面を登行中に雪崩事故があった場合、「冬山では登行ルートは斜面ではなく尾根にとるべきである」という原則はあるが、斜面しかルートにできない場合もあるし、冬の岩壁登攀では岩壁までのアプローチはたいてい雪崩の危険性のある雪の急斜面である。このように、「ルールのない危険なスポーツ」では、仮にルール的なものがあっても、その時の環境や条件、行為者の条件などによって変わり一義的に定まらないので、ルールを違法性判断の基準にしにくい。 一般に、危険なスポーツ中の事故については、自ら危険なことを承知のうえで行為を行っている点を違法性判断のうえでどのように考慮するかが問題となるが、ルールがあればルールを基準に考えることが可能である(その場合にはルールに従っている限り正当業務行為であるなどとして、民亊責任が阻却される)。しかし、ルールのないスポーツの場合には、ルールを基準にできない。 危険なスポーツにおける刑事責任に関しては、正当業務行為や被害者の承諾、社会的相当行為などの問題が議論されているが、民事責任に関しては、危険の引受を民事上の違法性阻却事由とする見解があるものの(注1)、法律家の間で十分に議論されていない。スポーツ関係者の間で「危険なスポーツ中の事故については、危険の引受があるので損害賠償責任は生じない」ことが、ある種の「常識」のように語られているが、後述のとおり、危険の引受法理が日本の裁判実務で受け入れられているわけではない。 通常の損害賠償と同様に考えて、予見可能性、予見義務、結果回避可能性、回避義務などを単純に当てはめた裁判例もあるが、たまたま結論が妥当だとしても、問題の本質を理解しているとは言えない。例えば、岩登り中の滑落事故の場合であれば、通常、加害者に予見可能性や結果回避可能性が容易に認定できるし、加害者の落度が事故の原因なので、古典的な過失理論によれば当然に加害者に注意義務違反が認定できるはずである。それにもかかわらず、岩登り中の事故について損害賠償責任が生じないことが多いのは、関係者がそのような事故の危険性を了解したうえで行っているスポーツだからである。この点を違法性の判断にどのように反映させるかという点に、まさに問題の核心がある。 日本でも、危険の引受の法理を認めて違法性阻却事由により加害者を免責とした裁判例があるが(注2)、これは例外的なものであり、後述のとおり、日本の実務では危険の引受を加害者の注義務違反を判断する事情の1つとして考慮するにすぎず、危険の引受を違法性阻却事由、つまり「抗弁」として取り上げることは稀である。 ルールのない危険なスポーツ中の事故は多いが、裁判になるケースは必ずしも多くはない。しかし、実際に事故が裁判にならなくても、法的紛争の処理の基準がスポーツ関係者に行為規範として作用するので、危険なスポーツに関わる者にとってはこの問題は非常に重要な問題である。しかし、現在は、その行為規範が曖昧なためにスポーツ関係者の間で混乱が生じているのが実情である。 2、危険の引受法理の内容 危険の引受法理は「同意は権利侵害の成立を阻却する」というラテン語に法源を持ち、1950年代以降のアメリカ不法行為法において認められた考え方である。 アメリカ不法行為法における危険の引受法理の適用要件は以下のように説明されている(注3)。 ①関係する事柄が危険な状態をひきおこすことがあるのを知っていた。 ②危険な状態に置かれていることを知っていた。 ③その危険の性格や程度を知っていた。 ④自ら進んでその危険に身をさらした。 危険の引受には、「明示の危険の引受」、「不合理な黙示の引受」、「合理的な黙示の引受」があるとされるが、アメリカでは「明示の危険の引受」の裁判例が多いとされる(注4)。危険の引受を個人の自己決定に基づく違法性阻却事由と考えれば、曖昧な基準で黙示の危険引受を広く認めることには問題がある。 その後、アメリカでは危険の引受法理を廃止して、加害者・被害者の過失の度合いに応じて各自の不法行為責任を相対的に認定するという「比較過失の法理」を適用する傾向がある。ただし、スポーツの観客に対する傷害に関する事件(例えば、野球の観客が打者のファウルボウルを受けて負傷するような場合)については危険引受法理が重要な役割を果たしているとされる(注5)。 後述のとおり、損害の公平な分担という観点から考えた場合、危険の引受による違法性の阻却という理論構成では柔軟な解決を図りにくいところから、アメリカ不法行為法における危険引受法理の地位の低下が生じたものと考えられる。 3、判例の検討 日本では、危険なスポーツに伴う事故の裁判は、ルールのある競技や学校のクラブ活動中の事故に関するものがほとんどであり、ルールのないスポーツに関する裁判例は少ない。 ルールのない危険なスポーツに関する裁判例のいくつかについて、危険の引受(危険の承認)の観点から検討したい。 (1)千葉地裁平成10年9月25日判決(判例時報1673号) ダートトライアル(荒地等に設置したコースで車両の走行タイムを競うスポーツ)競技場において、初心者が練習運転中の事故によりベテランの同乗者を死亡させた事件で、裁判所は、ダートトライアルにおいては過去に転倒や衝突事故は珍しくないが、死亡事故がなかった等の理由から、運転者に被害者の死亡の予見可能性がないとして運転者の損害賠償責任を否定した。 しかし、死亡事故は転倒事故や衝突事故の延長上にあるので、過去に死亡事故がなかったことから予見可能性がないという判旨には無理がある。判決がダートトライアルは「ある程度の危険を犯すことは当然に予定されていた」と述べているように、被害者が危険を承認していたことから加害者に注意義務を課すことができない事案だったと考えられる(注6)。 なお、この事件の刑事裁判については、危険の引受及び社会的相当性を理由に違法性が阻却されるとして、加害者を無罪とした(千葉地方裁判所平成7年12月13日判決、判例時報1565号)。刑事責任について危険の引受を理由に違法性を阻却した点には批判がある(注7)。 (2)大阪地裁平成13年1月22日判決(判例時報1750号) 有資格のダイビング経験者がスキューバダイビングのツァー中にパニック状態になり死亡した事故について、被害者はパニックになったとしても自ら適切に対処する技量を有していたとして、ツァーのインストラクターに注意義務はないとして損害賠償責任を否定した(注8)。 判決は被害者が一定の技能、経験を有していたことを重視してインストラクターの注意義務を否定している。 (3)長野地裁平成13年2月1日判決(判例時報1749号) スキー場の滑降禁止区域で滑降したスキーヤーが雪崩に巻き込まれて死亡した事故について、 裁判所は、スキーは危険を伴うのでスキーヤーは原則として自分の責任で危険を回避すべきこと、スキーグループのリーダーは幹事的立場にあった参加者の一員に過ぎず、他の参加者の指導やルート指示などを事細かに指示すべきリーダーないし指導者としての立場にあったとまでは言えないなどの理由から、リーダーの過失を否定した。 判決は、被害者が大学山岳部出身者で登山、海外でのヘリスキー、新雪滑降、山スキーの経験が豊富だったことを重視したものと考えられる。 (4)最高裁平成7年3月10日判決(判例時報1526号、判例タイムズ876号) スキー場での上級レベルのスキーヤー同士の衝突事故に関し、上方から滑降する者には衝突を回避する注意義務があるとして、スキーヤーが危険を承知したうえで滑降しているとして注意義務違反を認定しなかった原判決を破棄した(原判決は、スキーには相当の危険が伴い、スキーヤーはマナーに従っていれば注意義務違反はないと判断した)。 スキーヤーはゲレンデでは注意すれば相当程度に安全に滑降可能なので、被害者に危険の承認があったとは言えない事案である。 (5)名古屋高裁平成15年3月12日判決(注9) 冬の北アルプスの稜線を登山中の大学山岳部の学生が滑落して死亡した事故について、裁判所は、大学生は一定の体力や判断力を有するので自己責任が原則であること、被害者が滑落する点についての具体的な予見可能性がないこと、被害者は自律的な判断ができない者に該当しないなどの理由から、リーダーの損害賠償責任を否定した。 被害者側は「危険引受法理」を適用すべきではないと主張したが、裁判所は「危険引受法理」については触れていない。 裁判所は、被害者がこのパーティーのサブリーダーであり、一定の冬山経験を有していたことを重視したものと考えられる。 (6)横浜地裁平成3年1月21日判決(判例タイムズ768号)。 ゲレンデの岩場で、岩登りの経験者が上方にあるテラスで腰がらみの方法(ゲレンデでは通常行われない危険な確保方法)で岩登りが初めての者を確保している際、確保者の指示に従って、登っている者が岩から手を離したところ転落したという事故について、裁判所は、確保者に転落を防止する注意義務があったとして損害賠償責任を認めた。 この判旨について、「特段の事情がない限り加害者の責任は問えないはずであるが、被害者が初心者だったことや指示助言が不十分だったことなどから、加害者の責任が免れないかもしれない」という解説がある(判例タイムズ768号)。判決は危険の承認について考慮していないが、被害者は一定の危険を承認していたものの、加害者の確保ミスはクライマーの常識を超えており、加害者の行為の危険性が被害者の危険の承認の範囲を超えている事案だと考えられる。 (7)広島地裁平成6年3月29日判決(判例タイムズ876号) パラグライダースクールの受講生(パラグライダーが初めてではないが初心者だった)が講習中に負傷した事故について、パラグライダースクールが加入する賠償責任保険の保険会社と被害者との間で示談が成立して保険会社が被害者に損害賠償金を支払い、保険会社がパラグライダースクールの主催者に対し求償をした裁判である。裁判所は、主催者はパラグライダーの資格を有するインストラクターを配置すれば、自己の管理権が及ばない事故について安全配慮義務違反を問われることはないとして主催者の責任を否定した。 パラグライダースクールのインストラクターに過失がある前提で保険の支払がなされたと考えられるが、受講生が危険を承認していた範囲の事故ではないかと思われる事案である(判決はインストラクターの過失の有無について判断していない)。 (8)富山地方裁判所平成18年4月26日判決(判例時報1947号) 文部科学省登山研修所が主催した冬山研修会が大日岳周辺で行われ、大日岳山頂付近で講師及び研修生(大学生)ら27人が休憩している時に、雪庇が崩壊し、11名が転落し、2名の学生が死亡した事故について、裁判所は、、研修生の中には冬山登山の経験がまったくない者など、技術、知識の未熟な者がいたこと、講師はプロの山岳ガイドだったことなどの理由から、講師には、研修生の中に技術の未熟な者がいることを認識したうえで、研修生の安全を確保すべき注意義務があると判断した。そして、講師は過去の雪庇に関する情報等から25m程度の雪庇を予見可能だったとして、研修会の主催者である国に損害賠償責任を認めた。 研修生の中に冬山の未経験者がいたこと、講師にはプロの山岳ガイドがいたこと、登山行動中の事故ではなく休憩中の事故だったことから、研修生が危険を承認していたとは言えない事案である。 4、危険の引受法理と注意義務 (1)アメリカ不法行為法における危険の引受法理は、危険の引受を違法性を阻却する抗弁として位置づけるが、前記のように日本では危険の引受を抗弁として位置づけた裁判例は稀である。民事訴訟上の弁論主義もとでは、裁判の当事者が危険の引受を抗弁として主張しない限り、裁判所が抗弁として取り上げることはないが、当事者の代理人である弁護士は、裁判所が危険の引受を違法性阻却事由として扱わないので抗弁を主張しないという傾向が生まれる。 日本の裁判例の中には、被害者がそのスポーツに関する一定の技能や経験を有していたことを重視して、加害者の注意義務違反を判断したケースもあるが、一般的には、被害者及び加害者の事情を含めた種々の事情を総合考慮して、注意義務違反を判断していると考えられる。 したがって、日本では、実務上、アメリカ型の危険の引受法理は基本的に採用されていないと言ってよい。また、被害者に危険の承認(危険の引受)のあったことを、注意義務の判断のうえで明示的に考慮した裁判例もほとんどない。ただし、本来、行為者の自己責任が原則であることを指摘し、あるいは、被害者がそのスポーツに関する一定の技能や経験を有していたことを重視した判決はあるが、被害者が一定の技能や経験を有していることと被害者の危険の承認とは異なる。 例えば、前記3(3)の長野地裁判決は、スキーには危険が伴うこと、スキーヤーの自己責任が原則であること、被害者に登山や山スキーの技能や経験が豊富だったことなどを指摘しているが、「スキースクールの実態、本件スキーツアーの参加者のスキー技量、本件スキーツアーの趣旨及び実施状況等の諸事情」を総合考慮して、リーダーの責任を否定している。 この事件では裁判所は被害者の技術や経験を考慮しているが、このことと危険の承認は異なる。この事件は被害者が登山や山スキーの経験が豊富だったケースなので、どういう理論構成をとっても同じ結論になると思われるが、判決が指摘するように、被害者に経験や技術があることが加害者の注意義務に影響するとすれば、それは、一定の技術や経験がある者は危険を認識したり回避行動ができるので、加害者はその者の安全を配慮する必要がないという判断だと思われる。そこではもっぱら被害者の要保護性の有無が念頭に置かれているように思われる。このような考え方に立つと、被害者に登山や山スキーの技能や経験がそれほどない場合には、加害者の責任を認める可能性が出てくることになる。しかし、被害者が登山や山スキーの技能や経験がそれほどなくても、大人であればスキー場の滑降禁止区域が危険だということは容易に理解できるので、危険を承認しているとみなされることが多いはずである。注意義務違反を判断するうえで、被害者の技能や経験を重視することと、被害者の危険の承認の持つ意味が大きく異なるのは、被害者がそれほど技能や経験を有していない場合に顕著に表れる。自ら進んで危険な行為を行う者は、たとえ初心者だとしてもその事実だけから直ちに自己責任を否定することにはならないはずである。 以上のように、「ルールのない危険なスポーツ」における事故について、裁判所は必ずしも被害者の危険の承認を重視しているわけではない。 しかし、前記のように、「ルールのない危険なスポーツ」に関して、被害者自らが危険なことを承知のうえで行為を行っているという点に問題の核心があることからすれば、この点が注意義務違反の判断にどのように影響をするのかを明らかにする必要がある。判決が「諸事情を考慮して判断」する場合、その「諸事情」相互間の論理関係が明確でないために(通常、判決では諸事情が並列的に列挙される)、結局のところ裁判所の思考過程がよくわからないという印象が強い。また、「種々の事情を総合考慮して注意義務違反を判断する」というのでは、裁判例によってスポーツ関係者の行為規範としての基準を定立するのは困難である。 (2)この点で、アメリカ不法行為法における危険の引受法理が危険の引受を違法性阻却の抗弁として位置づける点は、違法性の判断基準として明確である。もっとも、アメリカでも危険を引き受けたかどうか自体が争われるケースも多いが、裁判例が蓄積すれば、ある程度は基準として明確になる。 しかし、危険の引受法理は、抗弁として、責任があるかないかを一義的に決めてしまう考え方であり、現実の危険を伴う行為は千差万別なので、危険を引き受けた行為とそうではない行為に2分することが困難なことがある。また、加害者、被害者の双方に落度がある場合には、過失相殺により損害を分担するのが公平だと考えられる場合があり、この点で、危険の引受法理は柔軟な解決を図りにくいという欠点がある。 近時、アメリカで危険の引受法理が衰退し比較過失の法理などが台頭しているのはこのためだと考えられる。 (3)危険の承認を違法性阻却事由と考えず、注意義務違反の判断の事情として位置づけたとしても、前記の「ルールのない危険なスポーツ」の性格から考えて、危険の承認の有無及びその範囲は、注意義務違反の判断のうえで決定的に重要な事情と考えるべきである。なぜなら、危険を承認している場合には、自分の判断で危険なスポーツをしないことが可能であること、行為の危険性は危険なことを行う行為者本人の支配下にあることから、危険を回避すべき規範は、第一次的には危険なことを行う行為者本人に課すのが公平だからである。かくして、危険の承認の有無とその範囲を検討することは、自己責任の範囲を確定する作業を意味する。 民事責任に関して危険の承認が違法性に影響を与える根拠は、当事者の意思だけではなく公平の観念にも基づいており、この点で、刑事責任において被害者の承諾による違法性の阻却の根拠が、自らの法益を放棄するという当事者の意思に求められる点と根本的に異なる。また、損害の公平な分担という観点から、危険の承認の対象となる「危険」とは、発生した結果についての具体的な危険までは不要であり、自己または他人の行為に関する一般的な危険で足りると考えられる。したがって、危険の承認は被害者の承諾とは異なる(被害者の承諾は生じた結果につい必要である。事前に被害者が承諾していることは損害賠償請求権を行使しないことの承諾であり、事後の承諾は損害賠償請求権の放棄である)。 危険の承認をこのように理解すれば、たとえ被害者が危険性を全く認識していなくても、危険の承認があったと見なされる場合がある。例えば、ヨットの初心者らの成人のグループがヨットでの太平洋横断に挑戦して遭難した場合、当事者が危険性を全く認識していなかったとしても(危険性を認識していないからこそ、このような無謀なことができるのである)、当然に危険を予見できるので公平の見地から危険の承認があったとみなされる。この場合、「要保護性」の観点から考えれば、リーダーは他の初心者を保護すべき注意義務があるのではないかと考えやすいが、関係者が危険を承認したうえで全員で無謀なことを行っているのだから、自己責任が妥当し、リーダーに注意義務を課すことはできない。 危険の承認の範囲は無制限ではなく、被害者の危険の承認の範囲は、被害者の意思、被害者が自己の判断で行動可能な範囲、公平の見地等から画される。危険の承認の範囲を超えた事態が生じた場合には、その者の安全を確保すべき立場の者がいるかどうか、予見可能性、結果回避義務等が問題となる。 また、教師と生徒のように一方が優越的地位にある場合には自ら進んで危険を引き受けたとはいえないこと、及び、公平の見地から、当事者が対等の関係にない場合には危険の承認の範囲が限定されると考えられる(注10)。かつて、パラグライダー、スキューバダイビング、カヌー、登山などは、ごく限られた人たちが仲間同士で趣味として行うスポーツであり、当事者の対等性と危険の承認が当然の前提とされていた。従来の日本で、学校のクラブ活動中の事故や「ルールのあるスポーツ」中の事故を除き、「ルールのない危険なスポーツ」に関する法的紛争が少なかったのはそのためだと考えられる。しかし、最近ではこれらの分野への商業主義の進出にはめざましいものがあり、営利目的の講習会や商業的ツァーなどでは、経験、技術、情報などの圧倒的な格差のもとに危険な行為が遂行され、そこには当事者の対等性は存在しない。したがって、これらにおいては、消費者の危険の承認の範囲が限定されると同時に、消費者の危険の承認の前提として事業者に対し危険性の説明義務が課されると考えるべきである(注11)。 危険の承認の範囲は、危険なスポーツの従事者にとって通常想定している危険の範囲をもとにおよその判断が可能であり、危険なスポーツの従事者に行為規範を提示するうえで有用だと考えられる。 5、個人の自由と自己決定 危険の承認の有無と範囲が危険を伴うスポーツにおける注意義務違反を判断するうえで重要な役割を果たすという考え方は、危険を伴うスポーツにおける自己決定と自己責任を強く意識した考え方である。 個人の自己決定と自己責任を重視しなければ、たとえ危険の承認があってもそれを重視せず、種々の事情を検討したうえで、加害者に対し危険を回避すべき注意義務を課すべきかどうかが判断されることになる。その根底には、国家が国民の安全を守るためには、被害者の危険の承認という自己決定にとらわれずに、後見的見地から被害者保護のために加害者に注意義務を課すかどうかを判断する方が好ましいという発想があるように思える。 従来から、日本ではパターナリズム(優越的立場にある者が一人前でない者のために、あれこれ指示、命令すること)の傾向が強く、自己決定の観念が稀薄であるが、英米ではパターナリズムに対する反感が極めて強いと言われている(注12)。 アメリカ不法行為法における危険の引受法理が日本の実務で採用されなかった背景には、日米のこのような価値観の違いがあるように思われる。免責同意書(権利放棄書、ウェイバー・フォーム)の拘束力に関して、アメリカでは被害者の利益を守るために厳格な解釈をしたうえで一定限度で肯定されているが、日本ではほとんど否定されるのも同じ理由が影響しているように思われる(注13)。 このように、「ルールのない危険なスポーツ」における危険の承認の位置づけには、個人の自己責任と自己決定に関する価値観が大きく影響するが、日本では、一般に自己責任と自己決定が尊重されているとは言い難い状況がある。危険な冬山登山をして遭難をすれば遭難した当人らが社会から非難され、彼らは「迷惑」とは関係のない人たちにまで、「ご迷惑をかけました」と謝罪して回る。そこでいう「迷惑」は、「社会を騒がせた」という社会に対する迷惑を意味しているが、その実体は、往々にして社会的多数者の価値観の少数者への押し付けであることが多い。J・S・ミルが「個人は彼自身に対して、すなわち彼自身の肉体と精神とに対しては、その主権者なのである」と述べているように(注14)、本来、自己責任に基づく行動は他人からとやかく言われる筋合いのものではないはずだが、日本では「自己責任論」が社会的非難の合言葉になるという奇妙な現象がある。日本で自己責任と自己決定が重視されないという傾向が、「ルールのない危険なスポーツ」における注意義務の判断に関して、被害者の自己責任の範囲よりも要保護性の方に関心が向く傾向を生んでいる。 本来、危険なスポーツは、それが義務や職務でない限り、自己責任のもとに行われることを想定しているので、生じた事故が自己責任の範囲かどうかが、何にも増して優先的に問題とされなければならない。他方で、日本では、自己決定と自己責任の自覚がないままに行動をする人が多いので、危険なスポーツにおける自己決定を尊重して、それを判断の前提とするにはかなりの勇気が必要である。個人の自己決定と自己責任に対する観念の弱さは、日本における契約の意識の弱さにも反映していると考えられる(注15)。 「ルールのない危険なスポーツ」における注意義務の問題は、一方では、それは個人の自己決定と自己責任に基づいて行われるべきだということを、他方では、個人の自己決定と自己責任に基づく行動に対する国家や社会の干渉は可能な限り排除されるべきことを提起している。 (注1)「スポーツ事故における損害賠償責任」(佐藤千春、日本スポーツ法学会年報6号)は、スポーツにおける一定の事故の損害賠償責任は、社会的相当説や正当行為説ではなく、被害者の「同意」及び「引き受け」によって違法性が阻却されるとする。 (注2)東京地裁昭和45年2月27日判決(判例時報594号)、ただし、これはルールのあるスポーツ(バレーボール)の事例である。なお、スポーツクラブにおける工作物責任が争われた事件で免責特約が抗弁として主張されたが、裁判所が抗弁を認めなかった事例として、東京地裁平成9年2月13日判決(判例時報1627号)がある。 (注3)「スポーツ事故と危険引受の法理」(及川伸、日本スポーツ法学会年報第2号) (注4)「スポーツ事故と危険引受の法理」(及川伸、日本スポーツ法学会年報第2号) (注5)「スポーツ事故における危険引受の法理に関する考察」(諏訪伸夫、日本スポーツ法学会年報第5号) (注6)同様の見解として、同判決の判例評論492号(斉藤修) (注7)「危険の引き受けについて・ダートトライアル同乗者死亡事件を素材にして」(塩谷毅、立命館法学253号)は、刑事事件における危険の引受が違法性を阻却するためには、危険引受の対象は「結果」についてでなければならないとして、危険の引受が違法性を阻却するとした点を批判し、予見可能性がないとして無罪にすべきだったと述べる。確かに、刑事責任に危険引受法理を適用することはできないと考えられるが、運転を誤れば死傷事故が起こることは容易に予見できたと考えられるから、許された危険ないし社会的相当行為により刑事責任における違法性が阻却されるべき事案だと考える。 (注8)スキューバダイビングにおける安全配慮義務について、「ダイビングの事故・法的責任と問題」(中田誠、杏林書院) (注9)下級裁主要判決情報 (注10)最高裁平成4年12月17日判決は、スキューバダイビングの初心者を対象とし講習会における溺死事件について、「絶えず受講生のそばにいてその動静を注視すべき注意義務がある」としてインストラクターに業務上過失致死罪の成立を認めたが、初心者を対象にした講習会では危険の承認は狭い範囲に限定されると考えられる。 (注11)「説明義務・情報提供義務と自己決定」(潮見佳男・判例タイムズ1178号) (注12)「私事と自己決定」(山田卓生、日本評論社)。 (注13)「スポーツ事故とウェイバー・フォーム」(井上洋一、日本スポーツ法学会年報第5号)、スキューバダイビングにおける免責同意書について「ダイビングの事故・法的責任と問題」(中田誠、杏林書院) (注14)「自由論」(J・S・ミル、岩波文庫)25頁 (注15)「日本人の法意識」(川島武宜、岩波新書)、なお、これに対する批判として、「人間の心と法」(加藤雅信外、有斐閣) (広島弁護士会会報80号、2006年) |
関連コラム
![]() 弘前大学医学部山岳部事故控訴審判決(名古屋高等裁判所平成15年 3月12日判決)について
弘前大学医学部山岳部事故控訴審判決(名古屋高等裁判所平成15年 3月12日判決)について
![]() 大日岳事故訴訟の判決(富山地方裁判所平成18年4月26日判決)について
大日岳事故訴訟の判決(富山地方裁判所平成18年4月26日判決)について
![]() ツアー登山における法的問題
ツアー登山における法的問題
![]() 「山の法律学」
「山の法律学」
![]() 「登山の法律学」、溝手康史、東京新聞出版局、2007年、定価1700円、電子書籍あり
「登山の法律学」、溝手康史、東京新聞出版局、2007年、定価1700円、電子書籍あり

![]() 「山岳事故の責任 登山の指針と紛争予防のために」、溝手康史、2015
「山岳事故の責任 登山の指針と紛争予防のために」、溝手康史、2015
発行所 ブイツーソリューション
発売元 星雲社
ページ数90頁
定価 1100円+税
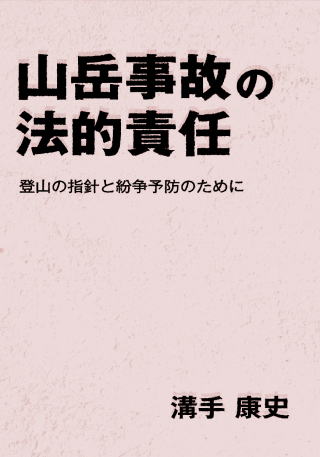
![]() 「真の自己実現をめざして 仕事や成果にとらわれない自己実現の道」、2014
「真の自己実現をめざして 仕事や成果にとらわれない自己実現の道」、2014
発行所 ブイツーソリューション
発売元 星雲社
ページ数226頁
定価 700円+税

![]() 「登山者ための法律入門 山の法的トラブルを回避する 加害者・被害者にならないために」、溝手康史、2018
「登山者ための法律入門 山の法的トラブルを回避する 加害者・被害者にならないために」、溝手康史、2018
山と渓谷社
230頁
972円
