�@�@
�@�@
�@�@
�@�@
| �c�A�[�o�R�ɂ�����@����̖��i���S�z���`���𒆐S�Ƃ��āj �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ٌ�m�@�a��N�j �P�A�͂��߂� �i�P�j�c�A�[�o�R���̎��̂Ƃ��ẮA �@�@�@�J��x�K�C�h�o�R���́i���a�T�O�N�T���Q�X���j �@�@�@�����x�É����̋�����́i���a�T�R�N�S���Q�X���j �@�@�@�䍂�x�K�C�h�o�R���́i���a�U�R�N�P�P���S���j �@�@�@�t�̑���U��c�A�[���́i�����P�O�N�P���Q�W���j �@�@�@�r���R�c�A�[�o�R���́i�����P�P�N�X���Q�T���j �@�@�@�\���x�c�A�[�o�R���́i�����P�S�N�U���X���j �@�@�@ �g�����E�V�E�c�A�[�o�R���́i�����P�S�N�V���P�Q���j �@�@�@���v����o�莖�́i�����P�U�N�T���S���j �@�@�@�����x�K�C�h�o�R���́i�����P�W�N�R���P�T���j �@�@�@���n�x�K�C�h�o�R���́i�����P�W�N�P�O���V���j �@�@�@���R�c�A�[�o�R���́i�����Q�P�N�V���P�U���j �Ȃǂ���������B �@�����̎��̂̊T�v�͈ȉ��̒ʂ�ł���B �J��x�K�C�h�o�R���� �@���a�T�O�N�T���Q�X���ɒJ��x��m�q��ŃK�C�h�ƂƂ��Ɋ�o����I���āA�A�C�[���Ȃǂ̃f�|�n�_�ɖ߂�A���[�v���͂���������ɁA�q�̂P�l�i�T�Q�A�����j���������Ď��S�����B �@�Ɩ���ߎ��v�������Ƃ��đ������ꂽ���A�N�i����Ȃ������i�u�R�Ŏ��ȂȂ����߂Ɂv�X�X�ŁA���c���j�A�����V���Ёj�B �����x�É����̋������ �@���a�T�R�N�S���Q�X���ɁA�É����Љ�l�̈當������̐E���P������ʌ��債���R�O���̎Q���҂��������āA���x�t�߂̊�ł��g���o�[�X���ɂQ�V�̏������������Ď��S�����B���̏����̓A�C�[���𒅗p���Ă��炸�A�����҂��炻�̂悤�Ȏw�����Ȃ������B �@�����ٔ��ŐÉ����Љ�l�̈當������y�ш��������E�������Q�����𖽂���ꂽ�i�É��n���ٔ������a�T�W�N�P�Q���X�������A�����P�O�X�X���j�B �䍂�x�K�C�h�o�R���� �@���a�U�R�N�P�P���S���A�K�C�h�ƂƂ��ɏ��S�҂Q�l�̋q���A����[�O�䍂�x�k�����T�E�U�̃R���[���䍂�x���c�����ɁA�G�܂ł̐V��̂��߂Ɏ��Ԃ�������A�\���ύX���Ēݔ����̓r�����矿��ɉ��~�����B���~���ɐ���ɑ����Q�l�̋q�i�Q�X�Βj���A�S�O�Ώ����j�����S�������A���̉��~���[�g�͈�ʓI�ȃ��[�g�ł͂Ȃ��K�C�h�͏��߂ĉ��~���郋�[�g�������i�u���[�_�[�͉������Ă������v�Q�U�W�ŁA�{������A�����V���Ёj�B �t�̑���U��c�A�[���� �@�����P�O�N�P���Q�W���A�j�Z�R�A���k�v���R�t�߂̒ʏ̏t�̑�t�߂ŁA�X�m�[�V���[�ɂ��c�A�[���A��Łi�X�R�O�x����J�̉����j�x�e���Ă������ɐ�����������A�P�������S���A�P�������������B�Q���̃K�C�h�͓o�R�A�X�m�{�[�h�A�X�m�[�V���[�C���O�̃K�C�h�Ƃ��s���Ă���A�����\�肵�Ă����R�[�X�͔�Q�҂炪�s�������Ƃ�����A���̃R�[�X�ɕύX�������A�����́A����댯���Ɏw�肳��A�R�O�`�S�O�Z���`�̍~��̒���ł���A���̓����A���A������ӕo�Ă����B �@�Y���ٔ��ŁA�Ɩ���ߎ��v�����ŃK�C�h�Q���̂�����������W�����s�P�\�R�N�̔����������B�i�D�y�n���ٔ������M�x�������P�Q�N�R���Q�P�������A�����P�V�Q�V���j�B �R�x�ی��ɉ������Ă��� �@ �r���R�o�R�c�@�[���� �@�����P�P�N�X���Q�T���ɁA�k�C���̗r���R�i�P�W�X�W���j�ŗ��s��Ђ���W�����c�A�[�o�R�ɎQ�������T�T�`�V�P�̂P�S�l�̋q�̂����Q���i�U�S�A�T�X�j�������������́B���̓����͑䕗�̒ʉߒ���ŁA�\���E��J�E�^���x�o�Ă����B�Y����i�S�X�A������̏c���o���̂݁j�P�����������A�R���ځA�T���ځA�W���ڂŊe�P�����E�����A�W���ڂŏW�c�����ꗣ��ɂȂ�A���̌㎀�S�����Q�����x�ꂽ�B�Y����͂��̂Q����҂��ƂȂ��o�����A���R���Ďn�߂ĂQ�������R���Ă��Ȃ����ƂɋC�Â����B�����A�R���t�߂́A�����P�T���A���E�͂P�O�`�R�O���ł���A�Q���͓��ɖ����ĎR���t�߂Ńr�o�[�N���A���������B �@���s��Ђ̕����͕s�N�i�A�Y����́A�Y���ٔ��i�Ɩ���ߎ��v���߁j�ŁA�����Q�N���s�P�\�R�N�̔����i�D�y�n���ٔ��������P�U�N�R���P�V�������j�B�����ٔ��ł́@���s��Ђ��⑰�ɑ��Q�������x�������ƂŘa�������B �\���x�c�A�[�o�R���� �@�����P�S�N�U���X���A�\���x�i�Q�O�V�V���j�ŗ��s��Ђ���W�����c�A�[�o�R�i�q�P�W���A�K�C�h�P���A�Y����P���j�ŁA�o�����͓܂肾�������܂��Ȃ������ƉJ�A���̌�݂͂��ꂩ�琁��ɕς�����炵���B�����A�����Œ��H�x�e��A���������J�̒��ŎR����ڎw�������A�ߑO�X���S�O������A�R���߂��̕W���P�X�Q�P���[�g���n�_�łU�T�̒j���q���|��A�ċz��~�ƂȂ�A���S�����B�j���͉J����o�X�Ɏc���A�x�X�g�̏�ɔ���̃E�C���h�u���[�J�[�ŁA�����g�͂��Ԃʂꂾ�����悤�ł���B �@�����P�T�N�P�O���W���A�x�ǖ�x�@�������������߂��ƕ��ꂽ���A���̌�A�s�N�i�����ƂȂ����B �g�����E�V�E�K�C�h�o�R���� �@�����P�S�N�V���P�P���A�g�����E�V�i�Q�P�S�P���j�ŁA�䕗���ڋߒ��A�K�C�h�P���A�q�V���Ƃ����K�C�h�o�R�ŁA�R���t�߂łT�W�̏����������Ȃ��Ȃ����B�K�C�h���ߑO�S���R�O�����܂ŕt���Y�������A���̌�K�C�h�͔����Ɍ������A���̏����͎��S�����i�u�h�L�������g�C�ۑ���v�X�S�ŁA�H�������A�R�ƌk�J�Ёj�B �@�Y���ٔ��ŃK�C�h�͋����W���A���s�P�\�R�N�̔��������i����n���ٔ��������P�U�N�P�O���T�������j�B ���v����o�莖�� �@�����P�U�N�T���S���A���v���ŃK�C�h�ƂƂ��ɑ�o�蒆�A����O�����ʉ߂��A�������J�̒������R���邽�߂ɓn�����悤�Ƃ��A���̓r���ŋq�̂P�l��������ӎ��s���ɂȂ����B���̋q���ӎ���������A������x�n�����݂��Ƃ���q��������A�R�l�����S���P�l���d�������B�����ӔC�ی��ɖ������B �@�Y���ٔ��ŃK�C�h�͋����R�N�A���s�P�\�T�N�̔��������i�������n���ٔ��������P�W�N�V���P�P�������j�B �����x�K�C�h�o�R���� �@�����P�W�N�R���P�T���A�K�C�h�o�R�Ŕ����������瓂���x�ɓo�����A���R�r���ŕ���̂��߂Ƀ��[�g���������A�ᓴ���@���ăr�o�[�N���ɃK�C�h�����S�����B ���n�x�K�C�h�o�R���� �@�����P�W�N�P�O���V���A�c��J���甒�n�x���߂������K�C�h�o�R�i�K�C�h�Q���A�q�T���j�ŁA�~�^�̋C���z�u�ƂȂ蕗��̂��߂ɎR�������̋߂��ŋq�S�l�i53�A61�A66�A61�j�����S�����B �i�Q�j��ʂɁA�c�A�[�o�R�Ƃ́A�K�C�h�������͓Y����i�ȉ��A�c�A�[�K�C�h�Ƃ����j���q����������`�Ԃ̓o�R���w�����A����ɂ́A�@�R�x�K�C�h���q����������o�R�A�A�c�A�[�Ǝ҂���Â��A�c�A�[�K�C�h�������̋q����������o�R�A�B�����̂�R�x�c�̓�����Â������^�̓o�R�Ȃǂ�����B��ʂɁA�c�A�[�o�R�Ƃ������t�́A�A���������t�Ƃ��Ďg���邱�Ƃ��������A�{�e�ł����c�A�[�o�R�́A��L�@�Ȃ����B���܂ރK�C�h�o�R�A�ƎҎ�Ẫc�A�[�o�R�A����o�R�������Ă���i����́A�@�Ȃ����B�̌`�Ԃ̓o�R�̖�萫�������Ŏ��グ�Ă��邩��ł���j�B �@�O�L�̏t�̑���U��c�A�[���́A���v����o�莖�́A�g�����E�V�E�c�A�[�o�R���́A���n�x�o�R���͇̂@�̌`�Ԃł���A�r���R�c�A�[�o�R���́A�\���x�c�A�[�o�R���́A���R�c�A�[�o�R���͇̂A�̌`�ԁA�����x�c�A�[�o�R���͇̂B�̌`�Ԃ̓o�R���̎��̂ł���B�ŋ߂́A�@�ƇA�̌`�Ԃ̓o�R���̂������Ă��邪�A�@�ƇA�̈Ⴂ�́A�A�̑����͗��s�Ɩ@�̓K�p�̂��闷�s�Ǝ҂���Â��邪�A�@�͗��s�Ɩ@�̓K�p���Ȃ��Ƃ����_�ɂ���B�������A�@�̏ꍇ�ł��A�R�x�K�C�h���h���̎�z������A���s�Ɩ@�̓K�p������A�A�̏ꍇ�ł��A�h����A���̎�z�����Ȃ��ꍇ�ɂ͗��s�Ɩ@�̓K�p���Ȃ��B �@�Ȃ��A�B�ɑ�����c�A�[�o�R�̂����A���[�_�[���K�C�h������̂ł͂Ȃ��A�����܂œo�R�̒��Ԃ���A�o�R�̋@����������Ƃ����`�Ԃ̓o�R������B�Ⴆ�A�����P�T�N�P�P���Q�U���ɋN�����[�������E���Ȍ������ŎQ���҂Q�V�l�̃n�C�L���O�ɂ�����u������v�̃p�[�e�B�[�Ȃǂ�����ɂ�����i�u�h�L�������g����������v�P�U�S�ŁA�H���c���A�R�ƌk�J�Ёj�B�@���I�ɂ́A����̓��[�_�[���K�C�h�̒n�ʂɗ����̂ł͂Ȃ��A���ԓ��m�̓o�R�ɂ����郊�[�_�[�Ɠ��������ɂȂ�̂ŁA�����ł͈���Ȃ�(�u�x�l�v�Q�O�O�U�N�V�����P�V�Q�ŎQ��)�B �@�{���A�K�C�h�o�R�́A�o�R�̋Z�p��o����L����R�x�K�C�h���������x�̋q��A��ēo�R������Ƃ����`�Ԃ��z�肳��Ă����B�������A�����N�𒆐S�Ƃ���o�R�҂̐��������������ƁA�o�R�̏��i���X�������܂�A���s��ЂȂǂ����̋ƊE�ɎQ���������ƁA���{�̎R�x�̂قƂ�ǂ��R���܂ŕ����ēo���Ƃ������ꐫ�����邱�Ƃ���A�o�R�����s�̌`�Ԃōs����悤�ɂȂ�A�c�A�[�K�C�h�������̋q�����������c�A�[�o�R�Ƃ������{���L�̓o�R�`�������܂ꂽ�B �@�Ƃ���ŁA�c�A�[�o�R�ł͂������Y����Ƃ��������̗��s��Ђ̐E�����q���������A�Y����̓K�C�h�ł͂Ȃ��v�Ƃ̎咣���Ȃ����̂ŁA�Y����̖@�I���i�����ƂȂ�B �@�_��̎��ԁA�o�R�̌`�Ԃ��炷��A�Y����͋q���ē����邱�Ƃ��_����e�ɂȂ��Ă���ƍl�����邩��A�ē�����҂Ƃ����Ӗ��ł͓Y������K�C�h�̈��ł���B�܂��A�T�u�K�C�h�Ƃ����A�K�C�h�Ȃ̂��A�K�C�h�łȂ��̂��B���ȕ⏕�҂��t�����Ƃ����邪�A�K�C�h�łȂ��Ƃ��Ă��@���I�ɂ̓K�C�h�����s�⏕���ɂȂ�̂ŁA�K�C�h�Ɋ܂߂čl���邱�ƂɂȂ�B�{�e�ł́A�R�x�K�C�h�A�T�u�K�C�h�A�Y����A�c�A�[�R���_�N�^�[���c�A�[�o�R���ē�����҂��c�A�[�K�C�h�Ƒ��̂��Ă���B �@�c�A�[�K�C�h�̒��Ӌ`���̓��e�͋�̓I�ȏɉ����ĈقȂ�̂ŁA�Y����̒��Ӌ`���Ƃ��ĎR�x�K�C�h�Ɠ������x���̂��̂�v���ł��Ȃ����Ƃ͓��R�ł���A�Ⴆ�A�댯�ȏꏊ�ł̓��[�v�ŋq���m�ۂ��ׂ��`����Y����ɗv�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A���܂ł̍ٔ��Ŗ��ƂȂ��Ă���c�A�[�K�C�h�̒��Ӌ`���́A�c�A�[�K�C�h�Ƃ��Ă̊�{�I�ȃ��x���̒��Ӌ`���ł���A���x�ȓo�R�o���A�Z�p�A�m����K�v�Ƃ��钍�Ӌ`�������ƂȂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B���������Ӗ��ł́A�����ł̓c�A�[�K�C�h�ɋ��ʂ�����������Ă���B �i�R�j���̂悤�ȃc�A�[�o�R�́A�����̃c�A�[�K�C�h�������̋q��A��ēo�R���s�����ƁA�c�A�[�o�R�̎Q���҂̒��ɂ͓o�R�̏��S�҂������܂܂�Ă��邱�ƁA��������c�A�[�K�C�h�̓o�R�o����Z�p���K�������\���ł͂Ȃ��P�[�X�����邱�ƁA�c���ړI�ōs����ꍇ�ɂ́A�c�A�[�̓��e��s���A�K�C�h�̐��Ȃǂ��c���I�Ȋϓ_���猈�߂��邱�Ƃ������A�c���D��̂��߂Ɉ��S�y�������X�������邱�ƂȂǂ̎����A����̂ɂȂ���댯��������B �@�����x�c�A�[�o�R���́A�r���R�c�A�[�o�R���́A�\���x�c�A�[�o�R���́A�g�����E�V�E�c�A�[�o�R���̂́A������������̎Q���҂������̃c�A�[�K�C�h���������Ă���A�����҂����S�҂̈��S�Ǘ����ł���̐��ɂ͂Ȃ������B�܂��A�����҂̃K�C�h�Ƃ��Ă̔\�͂Ɋւ��Ė��炩�ɖ�肪�������P�[�X������B �@���R�c�A�[�o�R���́i�����Q�P�N�V���P�U���j�́A�P�T�l�̋q�ɂR�l�̃K�C�h�����A�o���̂���K�C�h���������A�c�A�[�o�R�Ƃ����`�Ԃ��A�K�C�h�̔��f�~�X�̉e�������傫�Ȏ��ԂɎ��点�Ă��܂����Ƃ�����B �@����A�c���I�c�A�[�o�R�͑�������ƍl������̂ŁA���S�ȓo�R���������邤���ŁA�y���ł��Ȃ���肪����B�����ŁA�ȉ��ł́A�c���I�c�A�[�o�R�Ɋւ�����ɂ��āA�@�I���𒆐S�Ɍ����������B �Q�A�c�A�[�o�R�ɂ�����@���W �@�c�A�[�o�R�ɂ����āA�c�A�[�K�C�h�ƎQ���҂̊Ԃɑ��݂���@���W�͌_��Ɋ�Â����̂ł���B���s��Ђ���W�����c�A�[�o�R�ł���A���s��ЂƋq�̊Ԃ����s�_�������݂��A�c�A�[�K�C�h�͗��s�_��̗��s�⏕�҂ƍl������B���s�_��́A���ϔC�_��ގ��̌_�����_���������邪�A���ϔC�_��ގ��̌_��ƍl����ׂ��ł���B�c�A�[�K�C�h�́A���s�_��Ɋ�Â��ċq���ē����A�q�̈��S�ɔz������`�����B���S�z���`���͓����_��W��O��Ƃ�����s���s�ӔC�ɂ����Ė��Ƃ���邪�A���݂ł́A�_��W���Ȃ��ꍇ�ɂ܂Ŋg�債�ĔF�߂��Ă���B���S�z���`���́A�x�z�A�w���A�g�p�W�Ȃǂ̓��ʂȊW�����݂���ꍇ�ɔF�߂��钍�Ӌ`���ł���B �@�c�A�[�K�C�h�ɉߎ�������ꍇ�ɂ́A�c�A�[�Ǝ҂��g�p�ҐӔC�i���@�V�P�T���j�܂������s���s�ӔC�i���@�S�P�T���j���A�c�A�[�K�C�h�ƘA�т��đ��Q�����ӔC���B��������c�̂��c�A�[�o�R�̎�Î҂̏ꍇ�ɂ͌����c�̓������Ɣ����@�Ɋ�Â����Q�����ӔC���A���̏ꍇ�ɂ̓c�A�[�K�C�h�͑��Q�����ӔC�͂Ȃ��A�c�A�[�K�C�h�Ɍ̈ӂ܂��͏d��ȉߎ�������ꍇ�ɂ̂����c�̓��̓c�A�[�K�C�h�ɑ������ł���i���Ɣ����@�P���j�B �@�c�A�[�o�R�ɂ����ẮA�q���݂̊Ԃɂ͉���@���W���Ȃ��̂ŁA�q���݊ԂŁA�݂��ɉ���������A���̂̏ꍇ�ɒʕ�`���͂Ȃ��B�ʏ�̓o�R�p�[�e�B�[�ɂ����đ���̂��������ꍇ�ɁA�Q���҂��W�@�ւɒʕ��A���u����A�ی�ӔC�҈���ߓ��ɖ��ꂽ��A���Q�����ӔC�����ƂȂ邪�A�c�A�[�o�R�ł̓c�A�[�K�C�h�������Q���҂ɂ��̂悤�ȐӔC�͐����Ȃ��̂͂��̂��߂ł���B�@ �@����ɑ��A�c�A�[�o�R�ȊO�̒ʏ�̓o�R�p�[�e�B�[�ɂ����ẮA�p�[�e�B�[��Ґ�����Ƃ����s�ׂɊ�Â��ĎQ���҂��݂��Ɉ��S�ɍs�����邽�߂ɉ����A���́A�⏕����`�����B���̋`���͓w�͋`���ƌĂԂׂ����̂ł����ċ����ł���悤�Ȑ��i�̂��̂ł͂Ȃ����A�ʏ�̓o�R�p�[�e�B�[�ł́A���[�_�[���܂߂��Q���҂����͂��������Ƃɂ���āA�Q���҂̈��S�ʂ�⊮���邱�Ƃ����҂ł���̂ł���A����p�[�e�B�[�̈��S�����W�c�I�ɒS�ۂ����ʂ�����B�o�R�p�[�e�B�[�ɂ����邱�̂悤�ȋ@�\���W�c�I���S�`�F�b�N�@�\�ƌĂԂ��Ƃ��ł���(�u�x�l�v�Q�O�O�S�N�R�����P�W�P�ŎQ��)�B�o�R�p�[�e�B�[��Ґ������ȈӖ��́A�Q���҂��݂��ɋ��͂��邱�Ƃɂ��o�R�\�͂��������ƁA�y�сA�W�c�I���S�`�F�b�N�@�\�ɂ����S�������߂�_�ɂ���ƍl������B �@�c�A�[�o�R�ɂ����ẮA�W�c�I���S�`�F�b�N�@�\�������Ȃ��̂ŁA�c�A�[�K�C�h�͂��ׂĂ̎Q���҂̈��S�ʂɔz�����Ȃ���Ȃ炸�A�c�A�[�K�C�h�̕��S�͋ɂ߂ďd���B���̓_����A�c�A�[�o�R�ɂ����Ă̓c�A�[�K�C�h�������ł���Q���҂̐��ɂ͂��̂�������E������B�����҂������ł���Q���҂̐��́A�o�R�̓��e�A�댯���̒��x�A�Q���҂̃��x�����ɂ���ċK�肳��A��`�I�ɒ�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����Ƃ��A�c�A�[�o�R�ɂ����ďW�c�I���S�`�F�b�N�@�\���F�����Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ��A���ۂɂ́A�c�A�[�o�R�̋q���݊Ԃő����̉������͊W�����݂��邱�Ƃ������Ǝv���邪�A����͒P�Ɏ�����̐l�ԊW�ł����Ȃ��A�܂��A��ɂ��ꂪ���҂ł���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���������āA�Ⴆ�A���[�_�[�P���A�Q���҂P�O���̃O���[�v�ł����Ă��A���ꂪ�o�R�p�[�e�B�[�ł��邩�A�c�A�[�o�R�̃O���[�v�ł��邩�ɂ���āA���̃p�[�e�B�[�̈��S�ʂɑ傫�ȈႢ��������B���Ƃ��c�A�[�o�R�ȊO�̃p�[�e�B�[�ł����Ă��A���[�_�[�ȊO�̎Q���҂����ׂď��S�҂ł���Ƃ��A���[�_�[���g�����S�҂ł���悤�ȃp�[�e�B�[�ł́A�W�c�I���S�`�F�b�N�@�\�͂قƂ�Ǔ����Ȃ��B �@ �R�A�c�A�[�K�C�h�̒��Ӌ`�� �@�c�A�[�o�R�ɂ���������҂ƎQ���҂̖@���W�͌_��ɂ���ċK������邪�A���S�ʂɊւ��Ă͌_����e���B���Ȃ��Ƃ������B�c�A�[�o�R�ɂ�����c�A�[�K�C�h�̒��Ӌ`���́A�_����e�A�o�R�̓��e�A�댯���̒��x�A�o�R�̎����A�Q���҂̐��A�o�R�o���Ȃǂɂ���Ē�܂�B �@��ʂɁA�c�A�[�o�R�ɂ�����c�A�[�K�C�h�̒��Ӌ`���Ƃ��Ă͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂��l������B �@�o�R�R�[�X���ē�����`�� �A�h�����o�R�̏ꍇ�ɂ͏h���ꏊ����z���A�m�ۂ���`�� �B�Q���҂��o�R���Ɉ��S�ɍs���ł���悤�ɔz�����A�A�h�o�C�X����`�� �C�o�R�̓r���ŎQ���҂Ƀg���u��������Ή����A�⏕����`�� �D���̂����������ꍇ�ɂ͋~���̂��߂̘A�������s���`�� �E����҂��~�����邱�Ƃ��e�Ղȏꍇ�ɂ͋~������`�� �@�� �@�����钍�Ӌ`���͋�̓I�ȏɉ����đԗl���قȂ�(�u�x�l�v�Q�O�O�S�N�V�����P�V�Q�ŎQ��)�B�����ł́A�r���R�c�A�[�o�R���������グ�ċ�̓I�Ɍ����������B �@���̎��̂́A�����P�P�N�X���Q�T���ɁA�k�C���̗r���R�i�P�W�X�W���j�Ŏ��{���ꂽ�o�R�c�@�[�łQ�������S�����Ƃ������̂ł���B���̓o�R�c�A�[�͂T�T�`�V�P�̂P�U���y�ѓY����P���ō\������A�Y����͂P���i�S�X�j�ł���A������̏c���o�������Ȃ��A�R�x�K�C�h�̎��i�������Ȃ������B�䕗�̒ʉߒ���ŁA����������A�\���x��A��J�A�^���x�o�Ă������A�o�R���ł͉J������߂ɓY����͓o�R�����肵���B�P�U���̋q�̂����P�S�����o�R�ɎQ�����A�R���ځA�T���ځA�W���ڂŊe�P�����E�����A�W���ڂŏW�c�����ꗣ��ɂȂ�A���̌㎀�S�����Q�����x�ꂽ���A�Y����͒x�ꂽ�Q����҂��ƂȂ��A�o�����A�Y������܂ނQ�����o�����A���̂T�����x��ēo���������A�x�ꂽ�Q���́A���ɖ����Ă����B�R���t�߂͕����P�T���A���E�͂P�O�`�R�O���������B�Y����͂��̂܂܉��R�������A���S�����Q�����܂ނR�����s���s���ƂȂ�A�R�����R���t�߂Ńr�o�[�N�������A�Q���i�U�S�A�T�X�j�����������B �@���̎��̂̌Y���ٔ��́A�c�@�[��Ђ̕����͕s�N�i�A�Y����͋����Q�N���s�P�\�R�N�̔����������B�����ٔ��ł́A�c�@�[��Ђ��V�P�T�O���~���x�������ƂŘa�������������B �@�r���R�o�R�����́A�䕗�̒ʉߒ���ł���R���t�߂͈��V��̉\���͂��������A�o�R���t�߂ł͉J�����ł����̂ŁA���̎��_�Ńc�A�[�K�C�h�ɓo�R�𒆎~���ׂ����Ӌ`�����ۂ����Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂��A�o�R�𒆎~���ׂ����ǂ����Ƃ����_���A����ƒ��ڂ̈��ʊW�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B �@�X���ڕt�߂łQ�����x�ꂽ���A�c�A�[�K�C�h�͂��̂Q������u���ēo�R���p�������B�q���ē����邱�Ƃ̓c�A�[�K�C�h�̊�{�I�ȐE���ł��邪�A�����ӂ����_�������Ƀc�A�[�K�C�h�̉ߎ��ƂȂ���̂ł͂Ȃ��B�V�ǂ���A�̗́A�o��������q�́A�K�C�h���������u���Ă����͂œo���ł�����Ȃǂ��Ȃ�����ł���B �@�������A�����̗r���R�R���t�߂̋C�ۏ́A�������b�P�T���[�g���A�C���R�x�A���E�͂P�O�`�R�O���[�g���A�R���t�߂͓o�R�����������A�n�`�I�ɂ������₷�����ƁA�q���W�c���痣��Ă��܂��Ɩ����댯�������邱�ƁA�W�c�̃y�[�X�ɂ��ė���Ȃ������Q���̋q���̗́A�o�R�o�����ɗ�邱�Ƃ��������������Ƃ���A�K�C�h�͂��̌�̗\����\�����邱�Ƃ��ł����B�{���A�K�C�h�ɂ͂��̌�̎��Ԃ�\������`��������Ƃ����ׂ��ł����āA�\���`���ᔽ�������K�C�h�̉ߎ��̂悤�ɂ��l�����邪�A�ٔ������ł́A���ʉ���`���ᔽ���ߎ��ƂƂ炦�邱�Ƃ������B �@�c�A�[�K�C�h�͂��̌�̎��Ԃ�\���\�������̂ŁA�p�[�e�B�[�����U���Ȃ��悤�ɒ��ӂ��A���ɁA�p�[�e�B�[����x���҂�����A���̎҂�҂��A�W�c���痣�E����҂����Ȃ��悤�ɂ��ăp�[�e�B�[������`�����������B�c�A�[�K�C�h�̖@����̒��Ӌ`���Ƃ��ẮA�q���p�[�e�B�[���痣�E���邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɒ��ӂ��A���ɁA���E����҂�������̎҂�҂��āA�q�����[�g�ɖ������Ƃ��Ȃ��悤�ɔz������`�����������B�c�A�[�K�C�h�����̋`����s�����Ă���A�Q�������ɖ�������邱�Ƃ͂Ȃ���������A���̋`��������ƒ��ڂ̈��ʊW�������ʉ���`���ł���B���̂悤�ȃc�A�[�K�C�h�̋`���́A�����܂ŁA���̓����̋C�ۏ�Q���҂̏Ƃ�����̓I�ȏ̂��ƂŐ����钍�Ӌ`���ł���B �S�A�c�A�[�K�C�h�̐��ƐӔC �i�P�j�A��ʂɖ�����̑��Q�����ӔC�Ɋւ��钍�Ӌ`���́A�s�҂̔\�͂���ɂ������ϓI�Ȑl�̔\�͂���ɔ��f����Ƃ���邪�i���̈Ӗ��Œ��ۓI�ߎ��ƌĂ�邱�Ƃ�����j�A�c�A�[�K�C�h�̏ꍇ�ɂ͕��ϓI�ȃc�A�[�K�C�h�̔\�͂���ɔ��f���邱�ƂɂȂ�B �@�Ƃ��낪�A���{�ł̓c�A�[�K�C�h�̎�ނ��]��ɂ����l�ŃK�C�h�̌l�����傫���A�c�A�[�K�C�h�̈�ʓI���x�����l���ɂ����Ƃ������Ԃ�����B���{�ł̓c�A�[�K�C�h�̎��i�͏]������o���o�����������A���ꂪ�ŋߑg�D�I�ɓ������ꂽ���̂́A�]�����瑶�݂���K�C�h�̎��i�����������Ȃ̂ŁA�K�C�h�̃��x�����ψꉻ���ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B�ĎR�̏c���o�����������闷�s��Ђ̓Y����ƁA�o���L�x�ȃv���̎R�x�K�C�h�ł͂��̋Z�p�A�o���̈Ⴂ�͗]��ɂ��傫�����A�����ʐ����̃c�A�[�K�C�h�������R��œ����Ɩ��ɂ��Ă���̂����{�̎���ł���B �@��ʓI�ɂ����ΑΏۂƂȂ��Ă���R�̃��x���ƎQ������q�̃��x���ɉ����ăc�A�[�K�C�h�ɗv������钍�Ӌ`���̓��e����܂�B�]���̊댯���̂����łł͕��s�̗���Ȃ��q�ɂ��Ă̓c�A�[�K�C�h�̓��[�v��p���Ċm�ۂ���`�������邪�A�m�ۋZ�p�̂Ȃ��Y����ł̓��[�v���g�p�����q�̈��S�m�ۂ����҂ł��Ȃ��B�������A���̂悤�ȃ��[�g�ł͓Y����ɂ͈��̊m�ۋZ�p��~���Z�p���v�������̂ł����āA�Y����̃��x���ɉ����ċq�ɓo�R�\�͂��v�������̂ł͂Ȃ��B�Ăł����R�ł͈��V��Ɍ�������A�̊����x���O�x�߂��ɂȂ邩��A���̂悤�ȏꍇ�ɑΉ��ł���\�͂��c�A�[�K�C�h�ɂ͗v�������B���������āA���R�ł̃c�A�[�K�C�h�ɂ͓~�R�o���������͈��V��̒��ł̑Ώ����@���P�������o���Ȃǂ��v�������B�������A�o�R���ɓ�����ꂽ��A�r�o�[�N���邱�Ƃ����肤��̂ŁA��ԓo�R�̌o����r�o�[�N�̌o�������K�v�ƂȂ�B �@�c�A�[�K�C�h�ɂ͂��̃��[�g�ɉ������Z�p�A�o�����v������A����͋~���Z�p�A��}���̑Ή��┻�f�́A�����̋q������\�͂܂ł��܂߂������I�ȃK�C�h�Ƃ��Ă̔\�͂ł���B �i�Q�j�A���{�̎R�x�ɂ́A�قƂ�ǂ̎R�ɎR���܂ł̓o�R��������̂ŁA�V�̏��������悯��Γo�R�Z�p���Ȃ��Ă��o���ł���Ƃ�������Ȑ��i������B���̂��Ƃ���A�K�C�h�ɓo�R�Z�p���Ȃ��Ă��A���������悯��q���ē��ł��邱�ƂɂȂ�A���s��Ђ̎Ј����ȒP�ɓY����Ƃ��ēo�R�̃K�C�h������Ƃ������Ԃ����܂�Ă���B�������A���̂悤�ȓo�R�ł��A�ЂƂ��ѓV�r���A�~�R�ɕϖe���邱�Ƃ����邵�A���̂̏ꍇ�̋~���ɂ̓��[�v���[�N�Ȃǂ̓o�R�Z�p���������Ȃ��B �@�@���������āA���̂����Ȃ���K�C�h�ɓo�R�Z�p�͕s�v�����A���̂�����K�C�h�ɓ~�R�o���A�o�R�Z�p�A�~���Z�p�Ȃǂ��v������邱�ƂɂȂ�B�K�C�h�̖@�I�ӔC�͎��̂̏ꍇ�ɖ��ƂȂ�̂ŁA���_�I�ɂ́A�K�C�h�ɂ͂���Ȃ�̓o�R�o����Z�p���v������邱�ƂɂȂ�B �i�R�j�A�c�A�[�K�C�h�Ƌq�̋Z�p�A�o���̍����傫���ꍇ�A�����q�̓K�C�h�̎w���ʂ�ɍs�����邱�ƂɂȂ�B�Ⴆ�A��o��̃K�C�h�o�R�̏ꍇ�A�K�C�h�����[�v���o���Ƃ������f�����Ȃ���A���S�҂ł���q�͂��̉ӏ��Ń��[�v���K�v���ǂ����̔��f���ł��Ȃ��B���̑�o�ł��邩�A�������ł��邩�A�����Ƀ��[�v���K�v���A���S�Ɍ������~�ł��邩�Ȃǂ��ׂăK�C�h�̔��f�Ɉς˂��邱�Ƃ������B�K�C�h���u����قNJ댯�ł͂Ȃ��v�ƍl���Ă��A�q�ɂƂ��Ă͏\���Ɋ댯�Ȃ��Ƃ�����A���̂悤�Ȕ��f�͂��ׂăK�C�h�Ɉς˂���B���S�҂��댯���̍����c�A�[�o�R�ɎQ������ꍇ�ɂ́A�c�A�[�K�C�h�̐��ƂƂ��Ă̐ӔC�͋ɂ߂ďd���B�����ŁA���Ȃ�o���̂���q���c�A�[�o�R�ɎQ������ꍇ�ɂ́A������x�͋q���g�ɂ��댯���̉�������҂ł���B �T�A�c�A�[�o�R�ɂ����鎩�ȐӔC�͈̔� �@�����Ȃ�o�R�ł����̊댯��������A�o�R�ɎQ�����邱�Ƃ͂��̂悤�Ȋ댯�𗹉����Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B���H��������s�҂́A�����Ԃ̒ʍs�ɂ��댯�����F���������ŕ��s����킯�ł͂Ȃ�����A�����Ƃ��ĕ��s�҂Ɋ댯���̏��F�͂��肦�Ȃ��B�������A���s�҂Ƃ����ǂ��A���f�����ȊO�̏ꏊ�Ŏԓ������f����Έ��̊댯�������F���Ă���Ƃ݂Ȃ����B �@���{�̍ٔ����͊댯�̏��F����@���j�p���R�Ƃ��Ĉ���Ȃ��X��������A�댯�̏��F�͒��Ӌ`���ᔽ�f���鏔����̂P�Ƃ��čl�����邱�ƂɂȂ邪�A�R�x�n�т͖{���I�Ɋ댯�ł���ɂ�������炸�A�����̈ӎv�Ŋ����čs���̂��o�R�ł��邩��A�댯�̏��F�̗L���͒��Ӌ`���ᔽ�f����d�v�Ȏ���ƍl����ׂ��ł���(�u�x�l�v�Q�O�O�U�N�X�����P�V�Q�ŎQ��)�B �@�����Ƃ��A�c�A�[�o�R�ɂ����ẮA�_��Ɋ�Â��ăc�A�[�K�C�h���ē����邱�Ƃ��O��ƂȂ��Ă���̂ŁA�Q���҂̊댯�̏��F�͂����܂Ńc�A�[�K�C�h�̈��S�z���`����O��Ƃ������̂ƂȂ�B�����ł́A�K�C�h����ʓI�ȃ��x���̔\�́A�Z�p�A�o����L���A�K�C�h�Ƃ��Ă̈�ʓI�ȃ��x���̈��S�z���`����s�������Ƃ�O��Ƃ��������ŁA����ł��ʏ�\�z�������x�̊댯�͎Q���҂����F���Ă���Ƃ݂Ȃ����B �@�Ⴆ�A�~�ɖk�A���v�X�̓o�R���s���̂ł���A�Q���҂͓~�R�̊��C��댯�����F���ĎQ���������̂Ƃ݂Ȃ����B�~�R�Ȃǎ��R�̎��댯���́A�K�C�h�����Ă��Ă����Ȃ��Ă��ς��͂Ȃ�����ł���B���������āA�ʏ���x�̓~�R�̕���̒��Ŕ�J�Ɗ����̂��߂ɑ̗͂����Ղ��A���V��ɂ���ؒ��ɔ�J���������Ƃ��Ă����ȐӔC�ł���B�܂��A�V�����������߂ɁA�r�ꋶ������̒������R���ɓ����Ȃ��Ȃ�A�������Ă����ȐӔC�Ƃ����ꍇ���������낤�B�����Ƃ��A���̂悤�Ȏ��Ԃ��K�C�h���e�Ղɗ\���ł��邾���̎������A�e�Ղɉ���ł���悤�ȏ�����A�K�C�h���\���`���ᔽ�A���ʉ���`���ᔽ�̐ӔC�����邱�Ƃ�����B �@�ł́A���Ⴊ�������œ~�R�o���̖L�x�ȋq�������ēo�����邱�Ƃ�]�݁A�R���A�^�b�N�����݂����A�\�z�ȏ�̈��V��̂��߂ɑ�����ꍇ�A���Ⴊ�������Ŋ����ĎR���A�^�b�N�����݂��K�C�h�ɖ@�I�ӔC�������邾�낤���B �@�u�K�C�h�͋q�̈��S�����`��������v�Ƃ����_���`���I�ɗ�������A�u�����ɓV�������ōs�������A���̂��߂ɑ�����̂�����A�����\�����邱�Ƃ͉\�ł���A�K�C�h�ɂ͓o�R�𒆎~���ׂ����Ӌ`�����������v�ƌ��_�Â��邱�Ƃ͗e�Ղ��낤�B�������A�����ŏd�v�ȓ_�́A���̒��x�̊댯�����F���������ŋq���s����I�������_�ł���B�����ɂ́A���V��͗\�z�ȏ�ł���A���̂��߂ɑ�����̂ł��邪�A�R�x�Ƃ������R�̎��댯����\�ߐ��m�ɗ\�����邱�Ƃ͕s�\�ł���A������x�̓~�R�o���̂���q�����V��̒��ōs�����邱�Ƃ������đI���������Ƃ͊댯�̏��F�Ƃ�����B�������A�K�C�h���s�����ɑ���̊댯��e�Ղɗ\���ł����Ƃ���A�K�C�h�͓r���œo�R�𒆎~���ĉ��R���ׂ����Ӌ`�����B���̏ꍇ�A���V��̒��œo�R�����s�������Ƃ��K�C�h�̉ߎ��ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A����̊댯��e�Ղɗ\���ł����̂ɁA�r���œo�R�𒆎~���Ȃ��������Ƃ��ߎ��ƂȂ�B �@�����A�~�R�o�R�̎Q���҂����S�҂ł���悤�ȏꍇ�ɂ́A�q���u�ǂ����Ă��o�肽���v�ƌ����Ă��A�V������K�C�h�͓o�R�𒆎~���ׂ����Ӌ`�����B���̏ꍇ�A���S�҂̋q���u�ǂ����Ă��o�肽���v�ƌ������Ƃ��Ă��A�o�R�̊댯�����\���ɔ��f�ł��邾���̔\�͂Ɍ�����̂ŁA�����̌��n����댯�̏��F���������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B �@�O�L���䍂�x�K�C�h�o�R�����ł́A�V��̃��b�Z���Ɏ��Ԃ��Ƃ��r���Ŏ��Ԃ����肸�r�o�[�N���������Ȃ��Ȃ����Ƃ��Ă��A����͂P�P���̖k�A���v�X�ł͑z�肳�ꂽ���Ԃł���A�댯�̏��F�͈͓̔��̍s���ł���B���������āA���ɁA�r�o�[�N���ɔ�J���������Ƃ��Ă��K�C�h�̐ӔC��₤���Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A���ԕs���̂��߂ɗ\���ύX���Đ���̊댯�̂��郋�[�g�����~���邱�Ƃɂ��댯�́A�P�P���̖k�A���v�X�̏c���o�R�ł͑z��O�̂��̂ł���B���������āA���̎��̂ɂ��q����������ƂɊ댯�̏��F���������Ƃ͂����Ȃ��B �@�����x�K�C�h�o�R�����ɂ��ẮA���V��̂��߂ɉ��R���[�g���������A�r�o�[�N���邱�Ƃ͓~�R�o�R�ŗ\�z�����댯�͈͓̔��̂��Ƃł���i�o�����ɁA���R���[�g���������댯��\�����邱�Ƃ��\�������ꍇ�͕ʂł��邪�j�A�K�C�h�ɖ@�I�ӔC�͐����Ȃ����낤�i���̎��̂ł͎��S�����̂��K�C�h�Ȃ̂Ŗ@�I�����ɂȂ�ɂ����j�B �@�����A�O�L���J��x�K�C�h�o�R�����͎c����̊�o��ł��邩��A�����̊댯�������邱�Ƃ͋q���z�肵�Ă���Ƃ�����B�������A�K�C�h���������邱�Ƃ��\���ł���悤�ȏꏊ�Ń��[�v���͂����悤�Ɏw�������Ƃ���A�K�C�h�̈��S�z���`���ᔽ������邱�ƂɂȂ邪�A���̎��̂̋�̓I���s���Ȃ̂ʼn��Ƃ������Ȃ��B �@��ʓI�ɂ́A���V��ł���A���R�ɃK�C�h�ɓo�R�𒆎~���ׂ����Ӌ`�����Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�q�ɂ���Ȃ�̗̑͂�Z�p������A���X�̈��V��ł��o�R�����S�Ɏ��{�ł��Ȃ��킯�ł͂Ȃ����i�����ɁA�r���R�c�A�[�o�R�A�\���x�c�A�[�o�R���́A�g�����E�V�E�c�A�[�o�R���́A���n�x�o�R���̂ł��A����邱�ƂȂ��s���ł����q������j�A�q�Ɉ��V��ɂ��댯���̏��F������q�̎��ȐӔC�ɂȂ邩��ł���B�������A��ʂɃc�A�[�o�R�ł͋q�̓K�C�h�ɂƂ��ď��Ζʂł��邱�Ƃ������A�K�C�h���q�̗̑͂�Z�p�𐳊m�ɔ��f���邱�Ƃ�������Ƃ������̂ŁA�K�C�h�͋q�ɂ���قǑ̗͂�Z�p���Ȃ����Ƃ�O��Ƃ��������ōs�����l���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���X�̈��V��ł��s�������邱�Ƃ��������̂́A�K�C�h������܂łɋq�ƍs�������ɂ������Ƃ�����A�q�̗͗ʂ𐳊m�ɔc���ł��A�o�R�̌`�Ԃ����q���o�R�̊댯�����\���ɗ������A���f���Ă���Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���ꍇ�Ɍ�����B���̏ꍇ�ł��A����A�K�C�h�̗\�z�ɔ����ċq�����V��ɑς��邱�Ƃ��ł�������Ɏ���K�C�h�̔��f���I�m���������ǂ������@�I�ɖ��ƂȂ�̂ŁA�K�C�h�Ƃ��Ă͊����Ă��̂悤�ȃ��X�N��Ƃ��Ȃ����������ł���B �@�O�L���r���R�c�A�[�o�R�����̏ꍇ�Ō����A�䕗�̒ʉߒ���ł���A�o�R�����͈��V�\�z����A�o���O�ɂQ�l�̋q�͓o�R��f�O�����B���̋q�͎Q�����邱�Ƃɂ����̂����A�Q���҂͂�����x�̈��V���\�z���Ă����ƌ����A���̌���ł͏o�����_�ł͈��̊댯�����F���Ă����Ƃ݂Ȃ����B�������A�X���ڕt�߂ŕ������b�P�T���[�g�����炢����A�p�[�e�B�[�������ԂƂȂ����̂ł��邩��A���̂܂܂ł͈��S�ɋq���K�C�h�ł��Ȃ����Ƃ��c�A�[�K�C�h�͗\���ł����͂��ł���B���̎��_�ŁA�o�R�s���邩�A���邢�́A�ǂ̂悤�ɍs�����ׂ����̓c�A�[�K�C�h�̔��f�ɂ���Č��肳���ׂ����Ƃł���A�q�ɂ͑I�����ׂ��\�͂����ꂾ���̏ɂ��Ȃ������B���̂܂ܓo�R�s�������Ƃ͋ɂ߂Ċ댯�Ȃ��Ƃł��������A������q�����猈�肵���Ƃ��Ċ댯�̏��F���������ƌ������Ƃ͂ł��Ȃ��B �@�v����ɁA�r���R�c�A�[�o�R���̂̏ꍇ�ɂ́A���S�����q�͏o�����ɂ����鈫�V��ɂ����̊댯�����F���Ă������A�X���ڕt�߂ł̓K�C�h�ɑS�ʓI�ɗ��邵���Ȃ��A�R���t�߂ł̋q�̍s���͎��Ȍ���Ɋ�Â��댯�̏��F���������Ƃ͂����Ȃ��B �@�Ȃ��A���̃P�[�X�ł̓K�C�h�Ɉ��S�z���`���ᔽ������̂����A�����ɂ́A�q���o�����ɂ����ė\�z����鈫�V��ɂ��o�R�̊댯��F�����Ă����Ƃ͎v���Ȃ��t�V������B�]��ɂ����Ղɗ��s��Ў�Ẫc�A�[�o�R�ɎQ������X�������Ƃ���Ă���i����̓K�C�h�̐ӔC�Ƃ͑S���ʂ̖��ł���j�B�n�}�A���A�J��A�w�b�h�����v�A���H���������Ȃ��c�A�[�o�R�Q���҂͎Q�����鎑�i���Ȃ��̂����A�Y�������̑�l��ɏ����i�����͂ł����A�A���������A�u�J��A�w�b�h�����v�������Ǝ����Ă��܂��ˁH�v�ƌ������炢�̂��Ƃ����ł��Ȃ��̂������ł��낤�B�V��̂悢�Ƃ��ł���ΓY����ł����S�ɃK�C�h�ł��邩������Ȃ����A���V���~�Ⴊ���������ɁA�Y����ɂ��̂悤�ȓo�R�̌o�����Ȃ���Ώ\���ɑΉ��ł��Ȃ����A���邢�́A�q���R����]�������������悤�ȏꍇ�ɓY������K�ɋ~���ł���Z�p�������Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B�Y����ɂ��c�A�[�o�R�̏ꍇ�A���̂悤�Ȋ댯�𗹉����������ŎQ������Ƃ������o���K�v�ł���B���ɃK�C�h�Ɉ��S�z���`���ᔽ�̐ӔC���������Ƃ��Ă��A����ꂽ�����̖��͖߂��Ă��Ȃ��̂ł���A�o�R�҂ɂ́A�u�����ƂȂ�A�����̖��͎����Ŏ��v�Ƃ������o���K�v�ł���B �@�r���R�c�A�[�o�R���́A�\���x�c�A�[�o�R���́A�g�����E�V�E�c�A�[�o�R�����́A��������A�K�C�h���A�q�̗̑͂�[�g�t�@�C���f�C���O�\�͂�����������Ƃ�����Ɍq�����Ă���B�u���̒��x�ł���A���̋q�͂��Ă����͂����v�Ƃ��A�u���̋q�͂܂�������͂��v�ƃK�C�h�͍l�����̂����A����ɔ����ċq�̏�Ԃ͂����ƈ��������B�K�C�h�͂��̋q�ƂقƂ�Ǐ��Ζʂł���ɂ�������炸�A�Ȃ��A�����܂ŋq�̔\�͂��ߐM���邱�Ƃ��ł����̂��낤���B���炭�A�g�����E�V�E�c�A�[�o�R���̂̏ꍇ�ɂ́A�u�ł���A���̋q��o�点�Ă�肽���v�Ȃǂ̃K�C�h�̐S�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�r���R�c�A�[�o�R���̂̏ꍇ�ɂ́A�ŏ��ɓo�������͓̂Y����Ƌq�P�l�������Ƃ������炷��A���̓Y������g���l�I�ɂǂ����Ă��o�������������̂ł͂Ȃ����Ǝv����t�V������B �@�K�C�h�́A�q�̔\�͂��ÂɊώ@���A���f�ɖ����A�q�̓o�R�\�͂��߂Ɍ��ς����Ĕ��f���ׂ��ł���B �@�K�C�h�����R�����肵���ɂ��ւ�炸�A�q����������ēo�R�s����ꍇ�́A���̌�̋q�̎��ȐӔC�ɑ�����B���邢�́A�K�C�h���J���t����悤�ɋq�Ɏw�������ɂ��ւ�炸�A�J��𒅗p���Ȃ��ꍇ�ɂ́A����͋q�̎��ȐӔC�Ɋ�Â��s���ł���B �@�K�C�h�Ƌq���~�̊�Ǔo��������悤�ȃK�C�h�o�R�Ƃ��A�q�}�����̍���̃K�C�h�o�R�ȂNjɂ߂Ċ댯���̍����o�R�ł́A�K�C�h���q�̈��S���m�ۂ��邱�Ƃ�����Ȃ��Ƃ������̂ŁA�q�̎��ȐӔC�͈̔͂��L���Ȃ�B �U�A�Ɛӏ����̌���(�u�x�l�v�Q�O�O�U�N�P�O�����P�V�Q�ŎQ��) �@����Ҍ_��@�W���͕�I�Ɛӏ������Ƃ��Ă���B�r���R�c�@�[�o�R�����ł́u��Ђ͈�؎��̂̐ӔC���܂���v�Ƃ������������������A����͖����ł���B�܂��A�̈ӂ܂��͏d��ȉߎ��Ɋ�Â��s�ׂɂ��ẮA�ӔC�̈ꕔ��Ə���������������ł���B �@�c�A�[�o�R�ɂ����ẮA�_�Ɂu��Ɏ҂͈�̐ӔC��Ȃ��v�Ƃ������������Ă���P�[�X�����������Ӗ��ł���B��������A�o�R�̊댯���ɂ��ďڂ������������A�Q���҂̊댯���ɑ��鎩�o�𑣂����Ƃ̕����Ӗ�������B �V�A�c�A�[�o�R�ɂ�����댯���̐����`�� �@��ʂɁA���s�Ǝ҂͋q�ɑ��A�T�[�r�X�̓��e���������`��������i���s�Ɩ@�P�Q���̂S�j�A�_����e�Ɋւ��ĕK�v�ȏ������悤�ɖ��߂�`��������i����Ҍ_��@�R���j�B�܂��A���s�Ǝ҂�c�A�[�K�C�h�͋q�ɑ��A�_���̐M�`���ɏƂ炵�āA�q���c�A�[�o�R�ɎQ�����邩�ǂ��������肷�邤���ŕK�v�ȏ������`��������B���������āA���s�Ǝ҂�c�A�[�K�C�h�͋q�ɑ��A�o�R�̊댯���Ɋւ���������`��������B �@�r���R�c�@�[�o�R�ł́A�H�̖k�C���̂Q�O�O�O���[�g���߂��R�Ɋւ���댯���ɂ��Ă̏��̒��\���ł͂Ȃ������悤�ł���i�c�A�[�K�C�h���g�����̓_���\���ɔF�����Ă��Ȃ������悤�ł���j�B �@�����`���ᔽ�����S�������̑ΏۂƂȂ�ꍇ�����邪�A�_��̏d�v�Ȏ����Ɋւ��ċ��U�̐������Ȃ��ꂽ�ꍇ�ɂ͌_��̎�����\�ł���i����Ҍ_��@�S���j�B �@�܂��A�\�ߋq�ɓo�R�̊댯����������邱�Ƃ��q�̊댯�̏��F�̓��e�ƂȂ�A�c�A�[�K�C�h�̒��Ӌ`���̓��e�ɉe������B�Ⴆ�A�p���t���b�g���Ŏ��O�ɁA�o�R�ł͉��R���x���\�������邱�ƁA���R���x���w�b�h�����v���K�v�ƂȂ邱�ƁA�w�b�h�����v�Ȃ��ɍs�����邱�Ƃ��댯�ł��邱�Ƃ�������Ă������Ƃ��K�v�ł���B�����āA���̂悤�Ȏ��O���������Ă����A�q�̕����y�[�X���x�����߂ɉ��R�̓r���œ������āA�w�b�h�����v�����Q���Ȃ������q���]�|���ĉ�������Ă��A�c�A�[�K�C�h�ɓ��i�̕s���ӂ��Ȃ�����A�q�̎��ȐӔC�Ƃ���邱�Ƃ��������낤�B���̏ꍇ�A�q�����w���łȂ�����A�c�A�[�K�C�h���o���O�ɋq���w�b�h�����v�����Q�������ǂ����̏����i����������`���͂Ȃ��B �W�A�c�A�[�o�R�ɂ�������_�� �i�P�j�c�A�[�o�R�Ȃǂ̈����o�R�Ǝ���o�R�͂܂������قȂ�`�Ԃ̓o�R�ł���B �@���҂ł͎�������o��^���قȂ��Ă���B����o�R�ł́A�ʏ�A�T���̖k�A���v�X�ɓ~�p���b�P�������Ă������A�J�b�p�̂ݎ��Q���A�V�����t�͂R�V�[�Y���p���g�p���A�~�Ƀe���g�����Q������Ƀc�F���g�g�p����o�R�҂�����B�������A�c�A�[�o�R��K�C�h�o�R�ł�����s���A�����s���ƂȂ�A���ꂪ�����Ŏ��̂��N����A���Q�����ӔC��������B �@���ԓ��m�̓o�R�ł́A���V��ł��o�R�𒆎~���Ȃ����Ƃ͑����A�䕗�����邱�Ƃ��킩���Ă��Ȃ��猕��Ŗ��c�������Ƃ�����B�e���g�Q����̂����P�̓e���g���Ԃ�A�|�[�����Ȃ���A�t���C�V�[�g�Ȃǂ���ꂽ�B�V�����t�J�o�[�ɐ������܂�����Ԃň�ӂ��߂����i�ʏ�A�Ăɂ̓V�����t�������Ă����Ȃ��j�A�����͔��c��A�`���l�̓o���Ɍ����������A�O�̑��ł����ԔG���ԂŃc�F���g�ƃV�����t�J�o�[�Ők���Ȃ����Ӊ߂������B����ł��A�����͂����ƃ`���l�ɓo�����B�܂��A��A�J�̒����O�̑����猕��܂ł̊�ł�����A��̂P�O���Ƀx�[�X�ɋA���������Ƃ�����B���ꂪ�c�A�[�o�R�ł�����̂悤�ȓo�R�͂��肦�Ȃ��B �@���Ƃ��ƁA�o�R�ɂ͖`���I�v�f������A�`���I�v�f�̂Ȃ��o�R�͓o�R�ł͂Ȃ��Ƃ������邪�A�c�A�[�o�R�ɂ͖`���͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��B���������Ӗ��ŁA�����o�R�͖ʔ��݂̂Ȃ��A�܂�Ȃ��o�R�ɂȂ邪�A����͎d�����Ȃ��B���[���b�p�A���v�X�ł̌��n�K�C�h�̍s���o�R�̘b���ƁA�u�ʔ��������Ƃ��Ȃ��o�R�������v�Ƃ������z���悭�������A���{�l�K�C�h�̏ꍇ�̓T�[�r�X���_�������ŁA�q�̖����x���������������悤�ł���B���[���b�p�̃K�C�h�o�R�ł́A�u�K�C�h�������I�v�A�u�₽���v�A�u���ߌ����v�A�u�₽��Ƌ}������v�A�u�����ɓo�R�𒆎~����v�Ƃ������z���悭�����B �@�}�b�^�[�z�����œ��{�l�K�C�h�Q�����U�l�̋q�ƂP�{�̃��[�v�œo�����P�[�X�ŁA���n�K�C�h���獌�X������𗁂т��Ƃ����L����ǂ��Ƃ����邪�A����Ŏ��̂��N����Ζ@�I�ӔC�������邱�Ƃ͖����ł���B �@���{�̃K�C�h���q�ɖ��������悤�Ƃ�����ꂾ���댯��`���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���邪�A�q�ւ̃T�[�r�X�������S���̕���D�悳���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �i�Q�j���{�ɂ�����c�A�[�K�C�h�̒n�� �@�c�A�[�K�C�h�̌����Ƌ`���͈�̂̂��̂ł���(�u�x�l�v�Q�O�O�S�N�X�����P�V�Q�ŎQ��)�A�c�A�[�K�C�h���d�����S�z���`�����Ƃ������Ƃ́A�����ŁA�c�A�[�K�C�h�ɂ͋q�ɑ���w�����ߌ������邱�Ƃ��Ӗ�����B�c�A�[�K�C�h�͋q���K�C�h�̎w���ɏ]��Ȃ���A����Ƃ�����A�q�ɉ��R�𖽂��邱�Ƃ��ł���͂��̂��A�ʂ����ē��{�̓Y����ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ��ł��邾�낤���B����Ȃ��Ƃ�����A���̓Y����͌�ʼn�Ђ̏�i���玶�ӂ��ꂽ��A�ň��̏ꍇ�ɂ͉��ق܂ł��ꂩ�˂Ȃ��B���{�̘J���@�����ɂ�����J���҂̒n�ʂ��ی삳��Ă��Ȃ��Ƃ������i�Ⴆ�A���{�̊�Ƃ͊ȒP�ɘJ���҂�]�A���X�g���A���i���ʂ����Ă��邪�A�����i�ׂő����ɂ��Ă��A�@���}�����x�����s�\���ȓ��{�ł͏������ٌ�m�Ɉ˗����邱�Ǝ��̂��e�Ղł͂Ȃ��j���W���Ă���A�n�ʂ��ۏႳ��Ă��Ȃ��c�A�[�K�C�h�͋q�Ɍ}���I�ȑԓx���Ƃ�����A�q�̐��b�W���ē��W�Ƃ����̂�����낤�B �@�c�A�[�K�C�h�̒n�ʂ�ۏႷ�邽�߂ɂ͎��i�����Ǝ��i�Ƃ��A���i�擾�v�������������邱�Ƃɂ���āA���̎��i�����炩�̕t�����l�����悤�ɂȂ�A�K�C�h�g���������̗͂����ĂA�c�A�[�K�C�h�Ƃ����E�킪����s����`�����A���̑ҋ������P�����͂��ł���B �@�܂��A�����P�U�N�U���ɗ��s�ƃc�A�[�o�R���c��u�c�A�[�o�R�^�s�K�C�h���C���v�𐧒肵�����A���̂悤�ȋƊE�̎���K���ł͎��������Ȃ��B�c�A�[�o�R���c���D��Ŏ��{����邱�Ƃ̕��Q�������Ύw�E����邪�A�c����Ƃł���Ƃ������ƂƁA�u���v��ǂ����߂Ȃ��v�Ƃ������Ƃ͖������Ă���̂ŁA��Ƃ̎���K���ɂ͌��E������B�����ŁA�c���D��̕��Q���K�����邽�߂ɍs���̐��K�v�ƂȂ�B���Z�����u���ƂɊւ���K�C�h���C���v�𐧒肵�A����Ɉᔽ����Α��Ǝ҂��s���������Ă���悤�ɁA�������̂���K�C�h���C�����������肷�邱�Ƃ��K�v�ł���B�����ڂōl����A���̂悤�ȍ��̐���ɂ���ăc�A�[�o�R�̎������サ�A���S�ȗ��s�Ƃ̔��W�Ɋ�^����͂��ł���B �i�R�j���������҂̃��x����c�����邱�Ƃ̏d�v���Ƃ��̓�� �@�c�A�[�K�C�h�̈��S�z���`���̑O��Ƃ��āA�q�̗̑͂�Z�p�A�o���̃��x�����d�v�ł��邪�A�c�A�[�K�C�h�������c�����邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ��B���ɁA���s��Ў�Ẫc�A�[�o�R�̏ꍇ�ɂ͎Q���҂���҂Ə��Ζʂ̂��Ƃ������̂ŁA���̓_�����ƂȂ�B �c�A�[�K�C�h�Ƃ��ẮA�q�̗̑͂�Z�p�A�o���̃��x�����Ⴂ���̂Ƒz�肵�đΉ����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B �i�S�j�����҂̓o�R�\�͂Ǝ��̂�h�~����\�� �@���{�̃c�A�[�K�C�h�́A�Y����͗��s��Ђ̈�Ј��ł���K�C�h�Ƃ��Ẵ��x���̕ۏ��Ȃ��A�R�x�K�C�h���]���͎��i�����ꂳ��Ă��Ȃ������B���݁A�R�x�K�C�h�̎��i�����ꂳ�ꂽ�Ƃ͂����A���[���b�p�R�x�K�C�h�Ɋr�ׂ�Ύ��i�t�^�͎G�ł���(�u�x�l�v�Q�O�O�T�N�P�O�����W�R�ŎQ��)�B�]������A���{�ł͂���Ȃ�̓o�R�̎��т�����ΊȒP�ɎR�x�K�C�h�̎��i��^���Ă������A�o�R�̔\�͂ƃK�C�h�̔\�͕͂ʂ̂��̂ł���B �@�o�R�Ɋւ���\�͂Ƃ��ẮA�@�o���\�́A�A�̗́A�B�댯���@�m�����̂�h�~����\�́A�C���l��o�点�邽�߂Ɏw���ł���\�́A�D���l�̔��R�ɔz���ł���\�́A�E�~���\�͓������邪�A�������o�邽�߂̔\�͂ƁA���l�����S�ɓo�点�邽�߂̔\�͕͂ʂ̂��̂ł���B�������o�邽�߂̔\�͂��ǂ�Ȃɂ����Ă��A�q�̈��S������Ƃ͌���Ȃ��B�܂��A�~���Z�p�͓��ʂ̌P�������Ȃ���A�ǂ�Ȃɍ��x�ȓo�R�����H���Ă���ɐg�ɂ��Ȃ��B�q�̈��S����邽�߂ɂ́A�����Ɋւ��o�R�\�́i����͓��R�K�v�ł���j�Ƃ͕ʂɁA�K�C�h�Ƃ��Ă̌o����Z�p���K�v�ƂȂ�B�v���̓o�R�Ƃƃv���̃K�C�h�͈قȂ�B �@�Ƃ���ŁA�N�ł��A�����̂��Ƃ͂悭�����ł��Ă��i���ꂷ�玩���ŔF���ł��Ȃ����Ƃ��������j�A���l�̋Z�p�A�o���A�S���A�l�����A����Ȃǂ͂킩��Ȃ����̂ł���A���l���ǂ�Ȏ��Ƀ~�X��Ƃ����f���邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ��B�q�̈��S����邽�߂ɕK�v�ȃm�E�n�E�́A���ԓ��m�̓o�R�ł����S�҂����������x�o���Őg�ɂ��邱�Ƃ��ł��邪�A�݂��ɗ͂̂���ғ��m�̃p�[�e�B�[�ł͐�ɐg�ɂ��Ȃ����낤�B�����g�ɂ���P���Ƃ��Ă̓K�C�h�Ƃ��Ă̏C�{�������Ƃ��m���ł���A��l�O�̃K�C�h�ɂȂ邽�߂ɂ̓K�C�h�̕⏕�҂Ƃ��ĉ��N�Ԃ��o����ςނ��Ƃ��K�v�ł���B�q�̌o����Z�p�A�̗͂̒��x��f�����������P���A�q���ǂ̂悤�ȏꏊ�łǂ̂悤�Ȏ��ɂǂ̂悤�Ȋ��Ⴂ��~�X��Ƃ��₷�����A�q�̏�Ԃ̉����ċq�ɗv���ł��邱�ƂƗv���ł��Ȃ����Ƃ���������\�͓��́A�K�C�h�Ƃ��Ă̌o���ɂ���Đg�ɂ����̂ł���B �@��t�́A��t�Ƌ����������Ɏ�p���ł���Ƃ������̂ł͂Ȃ����A�ٔ����͂P�O�N�Ԃ͔�����ł����ĒP�Ƃōٔ���S���ł��Ȃ����i�������A���݂͕X�I�ɂT�N�Ԕ����������ΒP�Ƃōٔ����ł���^�p���Ȃ���Ă���j�A�ٌ�m�����i���Ƃ��������ł����ɂ͈�l�O�Ɏd���͂ł��Ȃ��B�ǂ̐E��ɂ����Ă��A����Ȃ�̌o����ςނ��Ƃɂ���Ĉ�l�O�Ɏd�����ł���悤�ɂȂ�̂ł���B �i�T�j���R��m�邱�Ƃ͓���B �@�u�o�R�͊댯�ł���v�Ƃ������t�͌����Â���Ă��邪�A���̌��t�̐[���Ӗ��𗝉����邱�Ǝ��̂�����قNJȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B �@�P�̎R�ɉ��\����o���Ă��A���R�������قȂ�A����ɓo�鎞�Ɉ��S���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B���R�̌v��m��Ȃ����Ђ̑O�ł́A���\�N���x�̐l�Ԃ̓o�R�o���œ�����o���͂������m��Ă���B����ł��A�����R�ɉ��\����o���Ă���A���ꂪ�Q�A�R��ڂ̐l���͂��̎R�̎��R�������悭�m���Ă���Ƃ������Ƃ͌�����B�@ �@�c�A�[�o�R�̑����͈�������K�C�h�����̎R��ɂ��Đ�����x�̌o�������Ȃ��Ƃ����P�[�X������B��B���Z�̃K�C�h���k�C����M�B�ōs�����c�A�[�o�R�ŋN�������̂������B��B�̃K�C�h�����A�M�B�ɋ��Z���k�A���v�X�̃K�C�h�𑽂����Ȃ��Ă���������̎R��ɏڂ������낤���A�����ɂ͑����̃K�C�h�̎d���͓�������Ȃǂɂ���K�C�h�Ɉ˗����Ȃ���A���n�ɏZ��ł��邩��K�C�h�̎d���������Ƃ��������Ƃł͂Ȃ��悤���B���͂��̎R��ł̓o�R�o�����ǂꂾ���L�x���Ƃ����_�ł���A���ꂪ������Α����قǂ����S�ɃK�C�h���Ղ����낤�B �@���s��Ђ̓Y����̏ꍇ�A�������{����O�ɂ��̎R��������������x�̌o�������Ȃ��A�Y��������̎R���m�����Ă��邱�Ƃ͂��悻���҂ł��Ȃ��B�H�̃c�A�[�o�R�ł����Ă��A�~��̉\�������邪�A���̎R�ɓ~�ɓo�����o����Y����Ɋ��҂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B���������āA�s�ӂɍ~�Ⴊ�������悤�ȏꍇ�ɂǂ����댯���ƂȂ邩�Ƃ����m����Y����Ɋ��҂���͖̂����ł���i�~�R�o���̖R�����Y����������̂ł͂Ȃ����Ǝv����j�B �@���[���b�p�[�A���v�X�ł́A���{����q���������Ă������{�l�K�C�h�������n�̃K�C�h�̕�����قǂ��̎R��ɏڂ����B���{����q���������Ă������{�l�K�C�h�́A�t�����X��X�C�X�Ȃǂ̃K�C�h�̍��Ǝ��i�������Ă��Ȃ�����A�u�t�����X��X�C�X�Ȃǂ̃K�C�h�̎��i���Ȃ���K�C�h�ł��Ȃ��v�Ƃ����@���ɔ�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ����o��̂́A�P�ɁA�`���I�Ȗ@���_�����ł͂Ȃ��A�u���ۂɓ��{���痈���K�C�h���q�����S�Ɉē��ł���̂��v�Ƃ������Ԃ��l���������̂ł�����i�ނ��A���{�l�K�C�h�����n�K�C�h�̎d����D���Ƃ����o�ϓI�Ȗ��_������̂����j�B �i�U�j�l�Ԃ̓~�X��Ƃ������ł���B �@�l�Ԃ͕K���ǂ����Ń~�X��Ƃ����̂ł���A�R�x���͕̂K���N����B����́A��ʎ��̂͐�ɂȂ��Ȃ�Ȃ����ƁA�u��s�@�͓�d�A�O�d�̈��S���邩����S�v�ƌ����邪�A����ł��l�דI�Ȏ��̂��N���邱�Ɠ����l����Ηe�Ղɗ����ł���B �@�l�H���͂��ׂĐl�Ԃ���������̂Ȃ̂ł��̍\�����킩���Ă���A���̃��J�j�Y���𗝉����邱�Ƃ��\�ł��邪�A���R�̃��J�j�Y���͊��S�ɂ͉𖾂���Ă��Ȃ��̂ŁA�\���s�\�ȕ����������B���ꂾ���ɓo�R�ɂ����Ă͂����ΐl�Ԃ̗\���������A�K�C�h�̔��f�~�X��������B�l�Ԏ��̂����R���Ȃ̂ŁA�q�̍s�����\���ɔ����邱�Ƃ������A�Ⴆ�A�K�C�h���q�ɑ̗͂��c���Ă���Ɣ��f���Ă��A���ۂɂ͋q���̗͂̌��E���Ƃ������Ƃ�����B�q���g���K�C�h�Ɂu�����̗͂̌��E���v�ƍ�����킩��₷�����A�q���g���u�܂��A���v �v�ƍl���Ă���ꍇ�������B�K�C�h�����̒��x�̉ӏ��͒N�ł��ȒP�ɒʉ߂ł���͂����Ǝv���Ă��Ă��A���̋q�ɂƂ��Ă͐S���I�ȋ��|�����瑫�������݁A�]�����Ă��܂��P�[�X�����肦�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B �@�댯�ȓo�R�ł́A�K�C�h���q���܂߂āA�l�Ԃ͕K���ǂ����Ń~�X������O��ōl���Ă������Ƃ��̗v�ł���B���̂͐l�Ԃ̂P�̃~�X�ŋN��������A�ނ���A�������̃~�X�������I�ɏd�Ȃ��ċN���邱�Ƃ������̂ŁA��ɐl�Ԃ��~�X��Ƃ��\����z�肵�Ă������Ƃɂ���Ď��̂̊m�������������邱�Ƃ��ł���B �i�V�j���̂��N����q�ϓI�v���ƐS���I�v�� �@�R�x���̂��N����̂͂���Ȃ�̗v��������A���̂̋q�ϓI�v���ƐS���I�v���͂��邱�Ƃ����ɏd�v�ł���A����̉ۑ�ł���B �i�W�j���̂��@�I�����Ɏ��郁�J�j�Y�� �@�R�x���̂ɂ���Ė@�I������������̂ł͂Ȃ��A�l�Ԃ��@�I�����������N�����̂ł���B�l�ԂƐl�Ԃ̊W���@�I�����Ɏ��郁�J�j�Y�����𖾂��邱�Ƃ́A�R�x���̂Ɍ��炸�A�����镴���Ɋւ��ďd�v�ȉۑ�ł���B �@��ʓI�ɂ́A���̑O�y�ю��̌�̐l�ԊW�A���O�̑z��ƌ��ʂ̃M���b�v�̑傫���A�Ӎ߂���K�����̗L�������@�I�����̌��݉��ɑ傫���W����B���̌�̔�Q�҂Ƃ̑Ή����d�v�ȏ��Ȃł���B �i�X�j���Q�ی��ւ̉��� �@���̂�h�����߂ɍő���̓w�͂����ׂ��ł��邪�A����ł��l�Ԃ̓~�X��Ƃ����Ƃ���ɂȂ��킯�ł͂Ȃ��B�����āA�^����������ꂪ�@�I�ȃ~�X�Ƃ݂Ȃ���A���Q�����ӔC��������B���̏ꍇ�͌����ӔC��F�߂ĎӍ߂��A���Q�����ӔC�ی��ő��Q��⏞���邵���Ȃ��B������l�Ԃ̉^���̂P��������Ȃ��B |
�֘A�R����
�@�@![]() �u���[���̂Ȃ��댯�ȃX�|�[�c�v�ɂ�����댯�̈���Ɩ�����̒��Ӌ`��
�u���[���̂Ȃ��댯�ȃX�|�[�c�v�ɂ�����댯�̈���Ɩ�����̒��Ӌ`��
�@�@![]() �O�O��w��w���R�x�����̍T�i�R�����i���É������ٔ�������15�N 3��12�������j�ɂ���
�O�O��w��w���R�x�����̍T�i�R�����i���É������ٔ�������15�N 3��12�������j�ɂ���
�@�@![]() ����x���̑i�ׂ̔����i�x�R�n���ٔ��������P�W�N�S���Q�U�������j�ɂ���
����x���̑i�ׂ̔����i�x�R�n���ٔ��������P�W�N�S���Q�U�������j�ɂ���
�@�@![]() �u�R�̖@���w�v
�u�R�̖@���w�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
![]() �u�o�R�̖@���w�v�A�a��N�j�A�����V���o�ŋǁA�Q�O�O�V�N�A�艿1700�~�A�d�q���Ђ���
�u�o�R�̖@���w�v�A�a��N�j�A�����V���o�ŋǁA�Q�O�O�V�N�A�艿1700�~�A�d�q���Ђ���
�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@
![]() �@�u�R�x���̂̐ӔC�@�o�R�̎w�j�ƕ����\�h�̂��߂Ɂv�A�a��N�j�A�Q�O�P�T
�@�u�R�x���̂̐ӔC�@�o�R�̎w�j�ƕ����\�h�̂��߂Ɂv�A�a��N�j�A�Q�O�P�T
�@�@�@�@�@�@�@�@���s���@�u�C�c�[�\�����[�V�����@
�@�@�@�@�@�@�@�@�������@���_��
�@�@�@�@�@�@�@�@�y�[�W���X�O��
�@�@�@�@�@�@�@�@�艿�@�P�P�O�O�~�{��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@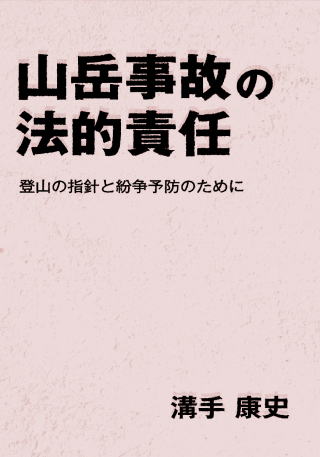
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@