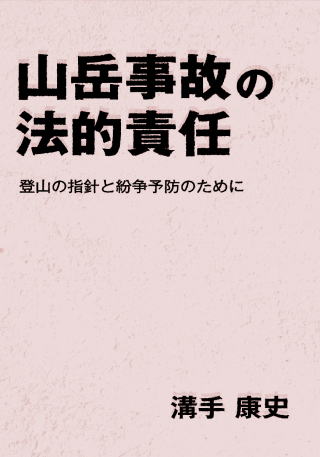|
大日岳事故訴訟の判決(富山地方裁判所平成18年4月26日判決)について
弁護士 溝手康史
この裁判は、国が主催した研修会における山岳事故について、講師の過失の有無が問題となったケースである。従来、山岳事故に関して、民事上の損害賠償責任が問題となる主なケースとしては、①学校登山、②ガイド登山、③講習会(研修会)があるが、本件は③の場合に関するものである。
講習会における山岳事故については、ゲレンデ等比較的危険性の少ない場所での事故と、山岳地帯という危険性の高い場所での事故に分けることができるが、本件事故は後者の場合である。
本件裁判は、危険性の高い山岳地帯での講習登山における講師の注意義務に関する重要な裁判例であり、今後の講習登山に与える影響は大きいと考えられる。
この判決に対し控訴がなされたが、控訴審で国が損害賠償金を支払うことで和解が成立した。
1、事故の概要
文部科学省登山研修所が主催した冬山研修会が北アルプスの大日岳周辺で行われ、平成12年3月3日、大日岳山頂付近で講師及び研修生(大学生)ら27人が休憩している時に、雪庇が崩壊し、11名が転落し、2名の学生が死亡した。雪庇は全体で幅が40メートルあり、雪庇の先端から長さ15メートルの部分が崩落したことが事故の原因である。
2、裁判の構造
死亡した学生の遺族が国を相手に損害賠償請求がなされた。国家賠償法に基づく請求であるが、同法は不法行為責任の特則をなす。
研修会の主催者は文部科学省の登山研修所であり、運営主体は国である。国家賠償法では、研修会の講師に過失がある場合に国が損害賠償責任を負うが、講師は責任を負わない(ただし、講師に故意または重大な過失がある場合に、国が講師に求償することは可能)。
3、法律上の争点
法律的には一般に以下の点が問題となりうるが、 (1)の②、③は争点となっていないし、
(2)の①、②は被告が主張していない。抗弁とは、講師に注意義務違反がある場合に違法性や責任を阻却、減縮させる事由で、被告が主張して始めて裁判所がとりあげるという性格の主張をいう。
(1)注意義務違反の有無
①予見可能性
②予見義務
③結果回避可能性
④結果回避義務
(2)抗弁
①危険の引受
②過失相殺
4、講師の注意義務の内容
(1) 、注意義務違反の有無を考えるうえで、その行為にルールがあるかどうか、自己責任の範囲としてどのようなものが想定されているか、加害者とされる者と被害者とされる者の優劣関係などが、重要である。
登山は、ルールのない危険なスポーツなので注意義務違反の規準を一義的に定めにくいという問題がある。いわゆる引率登山は自己責任の範囲が最初から狭いものとして想定され、研修会や講習会はもともと講師と受講生が優劣の関係にあることから、引率型の研修登山では研修生の自己責任の範囲は狭いものとなる。
これに対し、引率型ではない登山、すなわち、いわゆる自主登山では、自己責任の原則が適用され、リーダーに安全配慮義務(安全を確保すべき義務)が生じる場合は極めて限定される。
(2)、判決は、講師の注意義務について、以下のように述べている。
「本件研修会は,各大学山岳部等のリーダーなどを対象に、主として山岳スキー技術を中心とした冬山登山に関する研修,講習を行いリーダーとしての資質の向上を図ることを目的とするものであること,本件研修会の講師らは,、いずれも冬山登山に関する十分な知識及び経験を有する者であり,Gにおいては,
国際山岳ガイド連盟の国際ガイドの資格等を有するプロの山岳ガイドであり、ナムチャバルワ峰の初登頂等の海外遠征を含む四十数年の登山歴を有し,冬山研修会には昭和48年度から講師として、平成3年度からは主任講師として延べ22回にわたって参加するなど日本有数の登山家であったこと、一方、研修生らは,各大学における山岳部等のリーダーまたは次期リーダー候補者ではあったものの、各大学山岳部等の構成員数,活動内容等は千差万別であり,また,研修生の登山歴及びスキー技術のレベルなどは様々であって,中には冬山登山の経験が全くないなど,冬山登山の技術及び知識が未熟な者もいたことが認められる。
以上からすると,本件研修会がリーダー養成目的のために行われる実践的な研修会であるとはいっても,亡E及び亡Fら本件研修会の参加者は,雪崩や雪庇崩落等の危険性の判断については,最終的には講師らにその判断を委ねていたものであり,本件研修会が冬山登山に関する十分な知識及び経験を有する講師らによって安全に実施されることを期待していたものということができる。したがって,講師らは,本件研修会を行うにあたっては,各研修生の登山歴及びスキー技術のレベルなどは様々であって,中には冬山登山の技術及び知識が未熟な者がいることを十分認識した上で,研修生の生命身体に対する安全を確保すべき注意義務を負っていたというべきである。」
以上のように、判決は、研修会が大学のリーダーを対象に行われたものであるが、研修生の中には冬山登山の経験がまったくない者など、技術、知識の未熟な者がいたこと、講師はプロの山岳ガイドだったことなどの事実認定をし、このことから、登山の危険性の判断は講師らに委ねられていたと認定し、講師には、研修生の中に技術の未熟な者がいることを認識したうえで、研修生の安全を確保すべき注意義務があると判断した。
登山研修所の募集要項のタイトルは「大学山岳部リーダー冬山研修会」だったが、「冬山登山の経験がまったくない者」が参加していれば、これは「大学のリーダーを対象とした研修」とはいえない。
また、研修生の判断に基づく登山行動中の事故であれば、研修生の自律的判断の部分が多少はあるが、この事故は、講師が指定した場所で休憩している時に起こった事故であり、研修生は休憩場所について講師の指示に従うことになっていたと思われる。休憩場所の選定は研修生の自律的判断の余地がなく、研修生の自己責任を問題とする余地がほとんどない場面での事故だった。
判決は、この研修会の性格として、未熟な者を引率して実施する研修会、すなわち、参加者の自己責任の範囲が極めて狭い引率型の研修会と認定したものと理解できる。
恐らく、裁判官の判断のうえで、「冬山登山の経験がまったくない者」が研修会に参加していたという点と、講師が指定した場所で休憩している時に起こった事故だという点が重要だと考えられる。
(3) 、注意義務の具体的な内容
この点について、判決は以下のように述べている。
「以上で認定した事実によれば,確かに,本件事故当時の登山界において,雪庇の吹き溜まり部分は,先端部分と同様に危険であるとまでは認識されていなかったものの,その危険性を指摘する登山家も存在し,構造上の危険を有するものであって,時間の経過により雪が固まり安定することもある反面,気温や天候の変化等により不安定になることもあるところ, その外見からは内部の構造や安定度等を把握することは困難であること,また,実際は,先端部分と吹き溜まり部分とを区別することは極めて難しいことが認識されていたといえる。そのため,Gらは,本件研修会においては,吹き溜まり部分を含む雪庇全体を避けるように登高ルートの選定を行ったものというべきである。そうすると,本件事故当時の登山界においては,雪庇の吹き溜まり部分についても,先端部分に比べればかなり低いものの崩落する危険性があること,また,先端部分との区別ができないことから,誤って先端部分に進入し,踏み抜きなどにより転落する危険性があることが認識されていたというべきであって,しかも本件研修会の性格を考慮すれば,講師らは,危険を回避するために,原則として,雪庇の先端部分のみならず吹き溜まり部分にも進入しないように登高ルート及び休憩場所を選定すべき注意義務を負っていたというべきである。」
以上のように、判決は注意義務の具体的な内容として、「雪庇の先端部分及び吹き溜まり部分に進入すべきでない注意義務」を認定した。
この事故は雪庇の吹き溜まり部分が崩壊したので、雪庇は庇部分をさすのか、吹き溜まり部分も含むのか、吹き溜まり部分も危険なのかといった点が争点となった。判決では、「吹き溜まり部分」とは、山頂から雪庇の先端までをROOFと呼び、ROOFのうち雪庇の庇部分以外の部分をさしている。なお、「雪氷辞典」(日本雪氷学会編、古今書院)では、雪庇とは、「地表面の起伏が緩斜面から急斜面に変化する場所に、風下側に形成される吹きだまりの一種」とされている。
判決は、山頂部分から風下部分は、庇部分でなくても崩落する危険があるとしているが、「雪が安定していなければ、どんな斜面でも積雪が雪崩れたり崩落する危険がある」という意味では、当然の指摘である。例えば、雪庇がなくても、狭い山頂が積雪のために広い山頂に変貌していることがあるが、このような山頂の積雪の崩壊によって、「雪の山頂が崩壊する」ことがあり、危険である。また、雪庇がなくても積雪によって細い尾根が広い尾根に変貌することがあり、雪が安定していれば無雪期よりも歩きやすい尾根になるが、雪が不安定だとどこで尾根が崩壊するかわからないので危険である。
重要なことは雪の安定度であり、雪庇の庇部分は雪の安定度が特別に低い部分である。登山者は、雪庇の吹き溜まりに限らず、安定せず崩壊したり雪崩れる危険のある積雪部分も注意すべきである。
ただし、、雪庇の庇部分と吹き溜まり部分では崩落の危険性の程度が大きく異なるので、予見可能性にも大きな違いが生じる。すなわち、雪庇の庇部分が崩落することは容易に予見できるが、吹き溜まり部分の崩落は稀であり予見可能性の程度が低い。ただし、吹き溜まり部分の崩落の予見可能性の程度が低いのであって、予見可能性がゼロということではない。予見可能性の程度が低いことが、法的な予見可能性の認定にどのように影響するのかという問題が生じる。
また、この事故当時、吹き溜まり部分が安定しているように講師らに見えたために、休憩した場所が崩壊することは予測していなかった。そこで、講師らが吹き溜まり部分の崩壊を予見できたかどうかがまさに問題となるのである。
5、予見可能性と過失
法的責任の有無を判断するうえで、予見可能性が重要であるが、この点は事実認定により左右される。
判決は予見可能性について、以下のように述べている。
「以上で認定した事実及び証拠によれば,本件雪庇は,本件事故が発生した年の冬の前期(12月から1月末)に,少雪・強風により吹き溜まりが形成され,当該吹き溜まりの先端下部が大きな雪庇が形成される地形的要因となる崖状の急傾斜となり,後期(2月から3月初め)の豪雪・強風によって巨大な雪庇となったものであって,特殊な気象条件によるものであること,本件事故後に,大日岳山頂付近でも本件雪庇と同規模の全体の大きさが40mを超えるような雪庇は確認されていないこと,また,LやKにおいても,それまで上記規模の雪庇が形成されることを認識していなかったことが認められ,そうすると,本件事故当時の登山界においては,本件雪庇の大きさを正確に予見することが可能であったということはできない。しかしながら,本件事故後の調査結果等によれば,大日岳山頂付近では,従来,全体の大きさが少なくとも25mから30m程度の雪庇が形成されていたことがうかがわれるところ,いわゆる残雪期に大日岳山頂に登り,大日小屋付近から山頂付近を観察するなどすれば,目測によっても,残雪の状況等から,山頂付近では冬期には少なくとも全体の大きさが25m
程度の雪庇が形成されることを把握することは十分可能であったし,また,大日岳山頂付近の雪庇のおよその規模については,地元の登山家等の間でも認識されていたから,地元の登山家から情報収集を行うことなどによっても,同様の認識を持つことは可能であったというべきである。以上からすると,講師らは,本件事故当時,本件雪庇全体の大きさが少なくとも25m程度あることを予見することは可能であったというべきである。」
判決は、予見可能性についてこのように判断をしたうえで、過失について以下のように述べている。
「講師らは,大日岳山頂付近の雪庇の規模を1 0m程度と推測した上で,当該雪庇を避けるため,見かけの稜線上から十数m程度の距離をとって,登高ルート及び休憩場所の選定を行った。しかし,上記判断のとおり,講師らは,本件事故当時,大日岳山頂付近の雪庇の規模が25m程度あることを予見することは可能であったから,見かけの稜線上から少なくとも25m程度の距離をとって,登高ルート及び休憩場所の選定をすべきであり,講師らの登高ルート及び休憩場所の選定判断には過失があるというべきである。
ところで,前記当事者間に争いがない事実によれば,本件雪庇は全体の大きさが40m程度であり,先端から約15mの部分で破断し,崩落するに至ったものである。そうすると,講師らが,見かけの稜線上から25m程度の距離をとって登高ルート及び休憩場所の選定をしたとしても,研修生らが本件雪庇の上に進入すること自体は回避できなかったことになるけれども,研修生らが本件雪庇の少なくとも先端から約15mの部分を超えて進入することはなかったというべきである。したがって,仮に,調査報告書(乙2)が指摘するように,本件雪庇は,主として自重による曲げモーメント(下方に曲げようと作用する力)により,引っ張り強度を超える力がかかって,先端から約15mの部分で破断し,崩落するに至ったものであり,講師ら及び研修生らが本件雪庇上に進入したことによって崩落したものではないとしても,本件雪庇の崩落自体は発生したことになるけれども,研修生らが本件雪庇から転落することはなかったから,本件事故の発生は回避できたというべきである。
以上によれば,見かけの稜線上から十数m程度の距離をとって登高ルート及び休憩場所の選定を行った講師らの判断には過失があり,見かけの稜線上から25m程度の距離をとって登高ルート及び休憩場所の選定を行えば,本件事故は回避できたので,過失と本件事故発生との間に相当因果関係が認められる。」
判決は、大日岳山頂付近では、従来、少なくとも25~30mの雪庇が形成されていたこと等の事実から、講師は少なくとも25m程度の雪庇ができることは予見できたと事実認定をした。この事実認定によって研修生らが雪庇の先端から25m離れることが可能だったことになり、そうすれば、15mの部分で雪庇が崩壊したのだから、事故を回避することは可能だったという論理構成をとっている。
すなわち、判決は、
a.大日岳山頂付近では、従来、少なくとも25~30mの雪庇が形成されていた。
b.この点は地元登山家なども認識していた。
c.講師は少なくとも25m程度の雪庇ができることを予見でき、講師は雪庇の先端から25m以上離れるべきだった。
d.講師が注意義務を尽くせば、研修生らが雪庇の先端から25m離れることが可能であり、そのようにすれば雪庇の先端から15mの部分が崩壊しても事故を防ぐことができた。
という論理構成をとっている。
判決は、「従来、少なくとも25~30mの雪庇が形成されていた」ことから、「その年の事故のあった具体的な場所の雪庇が25m以上あること」について予見可能性を肯定した。
ここでは「大日岳の山頂付近では、過去に少なくとも25~30mの雪庇が形成されていた」という事実認定が決定的に重要な意味を持っている。
この判決の論理は、大日岳では「従来、少なくとも25~30mの雪庇が形成されていた」ことから、事故当時、25m以上の大きさの雪庇の予見可能性を認め、「雪庇の先端から25m以上離れるべきだった」とするもので、かなり形式的な論理になっている。この点について以下の問題点を指摘したい。
①、判決の形式的な論理
判決は、「本件雪庇の大きさを正確に把握することは不可能であるが、少なくとも25m程度の雪庇が形成されることを把握することは可能だった」とし、25m以上の大きさの雪庇の予見可能性を認めた。
しかし、雪庇は冬になると少しずつ、10m、20m、30mと成長していくが、その発達の仕方は年と時期と場所によって同一ではない。大日岳の山頂に限ってみても、雪庇の長さは均一ではなく、場所によって雪庇の大きさは微妙に異なるのであって、毎年、同じ場所にはほぼ同様の雪庇ができるとしても、「算数的な意味で」同じではない。したがって、「従来、少なくとも25~30mの雪庇が形成されていた」というのは、極めて大雑把な認識のレベルであり、それほど厳密さのある数字ではない。判決は、あたかも、冬には毎年同じ場所に一定規模の雪庇が固定的に形成されているかのような考え方をしており、その結果、判決は「雪庇の先端から25m以上離れるべき注意義務」という登山の実態からすれば奇異な注意義務を導き出してしまったのである。
雪庇に関する情報が大雑把なものだとすれば、それが講師の予見可能性の内容に影響をするとしても、それもまた大雑把なものとして理解されるべきである。すなわち、講師の認識は過去にその場所で25~30m程度の雪庇が形成されることが多いといった程度のものであり、その段階ではまだ抽象的な大雑把な予見可能性のレベルである。過去に25~30m程度の雪庇があったからといって、その年のある時期における当該場所での雪庇は23m程度かもしれないし、20m程度かもしれないし、正月頃はまだ15m程度の雪庇しかないかもしれない。過去のデータから雪庇の大きさを予測するとすれば、それは、雪庇は年によっては「最大で40mくらいあるかもしれない」といった程度のもので、「少なくとも25m以上はあるかもしれない」というのは机上で考え出された理屈である。25m以上の雪庇というのは、あくまで、一応の数字でしかなく、「25m」という数字に特別の意味があるわけではない。判決の論理では、予見すべき雪庇の大きさは25mではなく、20mでも、23mでもよかったのであり、たまたま、証人の誰かが「25m」という数字を言ったので、判決がそれを採用したのだが、その証人にしても、23mと言うか、25mと言うか、27mと言うかは、それほどの違いはないと考えているはずである。自然が作り出す現象を過去のデータだけから数字で予想することには無理がある。
ここで、重要なことは、「過去に、20m、30m、40mという雪庇が形成されていたことがある」という事実である。そして、この事実から、判決が言う「少なくとも25m程度の雪庇が形成されること」を予見できたかかどうかが問題なのではなく、「雪庇の先端から10数メートルの位置で休憩することの危険性」を予見できたという点が重要なのである。このように考えれば、講師が負う注意義務は、「雪庇の先端から10数mの位置で休憩してはならない」という内容になる。
「雪庇の先端から25m以上離れるべき注意義務」は注意義務の内容が明確であり、これに基づく判断も明確であるが、これは、交通事故で「時速50kmを遵守すべき注意義務」と考えるのと類似した発想である。しかし、登山では、雪庇という自然によって形成され、後で検証して初めて実態が明確になるような曖昧なものに対する予見可能性は、曖昧なものにならざるを得ないのである。曖昧なものは曖昧なものとして法的な予見可能性を考えるしかないのであって、「雪庇の先端から25m以上離れるべき注意義務」は内容が明確ではあるが、登山の実態からかけ離れた机上の理屈である。
過去の雪庇のデータはむろん重要であるが、それ以上に現場において、雪庇の大きさを把握し、予測することの方が重要な意味を持っている。損害賠償責任の要件としての予見可能性は具体的なものでなければならない。もし、予見可能性が抽象的なもので足りるとすれば、例えば、過去何度も雪崩が発生している場所だから雪崩を予見できたはずだとか、運転免許を取ったばかりの初心者が高速道路で運転すれば、事故を起こすことは容易に予見できるなどと、その抽象度を薄めていけば注意義務を課す範囲がどこまでも広がってしまう。過去に何度も雪崩が発生しているという事実だけから雪崩を予見できるとすれば、冬山のほとんどの斜面で雪崩が発生するので、ほとんど常に予見可能性が肯定されることになる。
また、予見可能性の対象は抽象的な事故一般ではなく、具体的に発生した当該事故を予見できたかということが予見可能性の問題であり(判決は、雪庇の規模の予見可能性=雪庇の崩落事故の予見可能性という前提で考えている)、この点からも、予見可能性や注意義務は具体的なものであることが要請される。なお、不法行為における注意義務は平均的な一般人を基準に考えることとされているが(この点で抽象的過失と呼ばれる)、このことと予見可能性の具体性は全く別の問題である。
過去のデータから雪庇の大きさを予見することは一般的抽象的であることを免れず、直ちに具体的なものを意味するわけではない。ここでの予見可能性は、実際の登山の現場における具体的な状況の中で、当該場所でどの程度の雪庇を予見し、雪庇の崩落を予見できたかという問題である。講師が雪庇の大きさを判断する際には、過去の雪庇の状況、山頂に至るまでの雪庇の大きさや発達状況、その年の降雪量、現場での積雪状況や地形、他の登山者からの情報等の諸事情を総合的に検討して判断すべきである。そして、これらの事情に基づいて、山頂に至るまでの間にどの程度の大きさの雪庇を予想できるかが、具体的な予見可能性の問題に他ならない。
しかし、判決は「従来、少なくとも25~30mの雪庇が形成されていた」という事実から、「25m以上の雪庇を予見できた」としており、その程度の認識は、登山に出発する前に机上で考えることができるレベルのものであって、具体的な予見可能性と呼ぶことはできない。
この事故については、判決は「雪庇の正確な大きさを把握することは不可能だった」とし、講師側も「雪庇の大きさを予見することは不可能だった」と主張しているが、仮に、そうだとすれば、それを前提にした結果回避義務を検討する必要がある。過去に巨大な雪庇が形成された事実を認識可能であり、かつ、現場で講師が雪庇の正確な大きさを把握できなかったのであれば、雪庇の先端から10数mといった中途半端な場所で休憩してはならないという注意義務が課されることになる。
過去のデータだけを根拠に予見可能性を判断するという極めて単純な考え方は、自然の複雑なメカニズムを単純な数字に置き換えて、それを論理の出発点にし、数字の算数的な操作によって結論を導くことを意味する。
さらに、25m以上の雪庇を予見できたとしても、それは吹き溜まり部分を含むから、吹き溜まり部分が崩壊することの予見可能性も必要である。吹き溜まり部分は雪が安定していなければ危険であるが、安定していればそれほど危険ではない。吹き溜まり部分の雪が安定しているかどうかは、事故後に研究者らが大がかりな調査でもしなければわからない。
判決の考え方は、雪庇の庇部分と吹きだまり部分の区別が容易でないことを前提に、吹きだまり部分に崩落の一般的な危険性があることから、吹きだまり部分に進入すること自体に雪庇崩落の具体的危険性があるというものである。判決は、雪庇崩落の具体的危険性や、事故の予見可能性の内容をかなり緩やかに判断している。
さらに判決は、雪庇の規模等の予見義務を講師らに課すことによって、予見可能性の判断を容易にしている。講師らは、当時の登山家の一般的レベルを超えて、高いレベルの予見義務を負っていると裁判所は判断したのであるが、、それは、国が主催し、冬山の初心者が参加する研修会だったからにほかならない。したがって、このような研修会では、よほど研修生に落ち度のある事故でない限り、事故が起きれば主催者に法的責任が生じる可能性が高いと言ってもよい。そして、雪崩や雪庇事故のように自然に起因する事故の場合には、被害者に落ち度がないのが通常である。登山に限らず、国や公共団体が危険性の高い行為を行う場合、国等は重い安全配慮義務を負うので、事故が起こった場合に、国等に法的責任が生じることが多い。
②、判決の論理の限界
この事故は、たまたま雪庇の先端から15mの地点で雪庇が崩落したので、判決は、「過去に25~30m程度の雪庇が形成されていた」という事実から「25mの雪庇の予見可能性」を認め、講師に過失があるとしたのだが、仮に、研修生が雪庇の先端から25mの位置で事故に巻き込まれたとすれば、判決の論理では講師に過失がないことになり、雪庇から20mの位置で事故が起きれば、過失があることになる。判決では、雪庇の先端から25m以上離れていたかどうかが、過失の有無を決することになるが、前記のように、「過去の25~30mの雪庇」という点はあくまで一応の目安程度に考えるべきであって、それを絶対視すべきではない。過去のデータ以外の諸事情も総合的に検討して、予見可能性の有無を判断すべきであり、仮に、雪庇の先端から25mの位置で事故が起こったとしても、状況によっては講師に法的責任が生じる可能性がある。
あくまで、自然とか登山の実態に則して考えれば、「従来、25~30mの雪庇が形成されていた」という事実以外に、その年の雪庇の発達状況、講師らが事故現場よりも手前の稜線で雪庇が10m程度であると考えたこと、その他の講師らの認識内容、山の地形、その年の降雪量、積雪状況、気象状況等を総合的に検討して、雪庇の先端から10数メートル離れた場所で休憩することの危険性について検討すべきだった。
過去のデータだけを基準に予見可能性を考えることの問題性は、過去のデータだけを基準に登山者に結果回避義務を課してはならないこと、すなわち過去のデータだけを基準に行為規範を考えてはならないという点にある。登山者は実際の山における具体的な状況に応じて、どのように行動すべきかを考えるべきであって、過去のデータだけから机上の理屈として行為規範を考えてはならないのである。
③、雪庇の大きさを把握すべき注意義務
判決は、原告らが主張する種々の雪庇の把握方法をすべて否定して、あっさりと「雪庇の正確な大きさを把握することは不可能だった」と述べている。そして、過去のデータから25m程度の雪庇を予見することが可能なのであるから、その他の争点について判断する必要がないと簡単に述べている。
しかし、研修会においては、実際の現場で雪庇の大きさを把握すること、雪庇の上に乗らないように正しいコースを設定すること、危険のない場所で休憩するよう指示することは講師の基本的な注意義務である。この義務を尽くしたかどうか、それが可能かどうかがこの裁判の最大の争点であり、判決が、講師の注意義務が尽くされたかどうかを詳細に検討することなくあっさりと「雪庇の正確な大きさを把握することは不可能だった」と判断した点は問題である。
確かに、そのように詳細な検討をしたとしても、判決が言うように現場で雪庇の正確な大きさを把握することが不可能だという場合がありうる。判決は、「雪庇の正確な大きさを把握することは不可能だった」との判断から、講師の行為規範として、過去のデータに基づいて「25m程度の雪庇を予想して行動すること」を定立したのだが、実はそのような行動は非常に危険なものである。仮に、雪庇が26mあれば、雪庇崩落に巻き込まれることになり、過去の25m以上の雪庇ということ自体が大雑把な情報でしかないので、それを直ちに登山活動の基準にしてはならない。吹き溜まり部分を含めて過去に大きな雪庇が形成され、そこに大きな雪庇があるかもしれないこと、雪庇の安定度がまったく不明の場合に、雪庇の大きさや安定度を把握しないまま登山を続けるこ自体が危険である。しかし、そのような危険があることがわかったうえで行動をするのが登山であり、登山から、危険性を完全に排除すれば、それは、危険性のない「危険な登山」という概念矛盾に陥る。
この事故では、講師は雪庇の大きさを10m程度と判断したのだが、それが吹きだまり部分を含むものかどうかわからない。そもそも、吹きだまり部分の規模は目視ではわからないはずである。講師らは事故現場よりもずっと手前の稜線の雪庇を10m程度と判断したのであるが、それはあまり正確とは言い難い遠方からの目測によるものある。それ自体が正確な判断ではないし、このことから事故現場である山頂付近の雪庇も同じとは限らない。
吹き溜まり部分の規模や安定度がわからないとすれば、雪庇の先端から10数mの位置で休憩することは非常に危険なことになる。吹きだまり部分の正確な大きさや安定度を把握できない以上、雪庇から可能な限り距離をとって行動すべきだった。この場合に、何m以上雪庇から離れれば安全かという基準はないが、雪庇の吹き溜まり部分の規模や安定度がわからないのだから、可能な限り雪庇から離れるしかない。そのようにした場合、逆に滑落などの危険が生じることがあるし、雪庇から可能な限り離れたつもりでも、それでも事故に遭うことがある。どのようにしても冬山は危険なのであり、どんなに注意していても、事故が起きれば、自己責任型の登山でない限り、結果的に法的責任が生じやすい。
また、山頂付近に大きな雪庇や吹き溜まりが形成されるような山は、雪庇からどの程度離れれば安全かが明確でなく、冬山初心者を含めた講習の場所としてはふさわしくない(危険性を承認した自主登山としての講習の対象とすべきである)。
雪庇から10数メートルの位置で休憩することは危険なことだったが、その位置で休憩することに危険を感じなかったのは、恐らく過去に危険な登山を何度も経験してきたという「油断」と「慢心」からだろう。登山家の登山技術と登山経験に対する過信が事故を招くことは珍しくない。人間の感覚は、慣れてくると麻痺するものだが、恐怖心も同じである。
過去のデータを参考にするだけではなく、実際の登山の現場において山頂の位置を確定したり、雪庇の大きさを把握する努力ことが必要であり、それを前提にして結果回避義務を考えなければならない。
判決は、以上のような義務が尽くされたかどうかを検討することなく、過去のデータから「25m程度の雪庇を予見できた」として一気に結果回避義務を導いているが、余りにも短絡的な論理だと言わざるを得ない。
なお、引率型の研修会(特に初心者を引率している場合)では講師に以上のような重い注意義務が課されるのであって、一般の登山において、雪庇の大きさを把握できない場合に、雪庇から可能な限り距離をとって行動すべき義務が生じるわけではない。
④、講師の過失
そもそも、「講師が雪庇の大きさを10m程度と判断し、雪庇の先端から10数メートル離れた位置で休憩した」と聞いた時、不安を感じる人がいるはずだ。ここでいう「10数m」は15m以内の者を含むから、算数的な意味でも10mとの差は僅かであるが、ここでは算数的な数値ではなく山での目測による距離が問題となっている。しかし、被告側の弁護士は、この点に何も疑問を感じなかったようで、それだからこそ被告側は、疑問を感じることなく、「講師は雪庇の大きさを10m程度と判断し、雪庇の先端から10数メートル離れた位置で休憩したのだから、講師には過失がない」という算数的な「理屈」を裁判で主張したのだろう。
しかし、10mの雪庇は十分に危険であること、ある場所で雪庇が10m程度あったということは、他の場所では雪庇が15m程度ある可能性があること、白一色での山での遠方からの目測による10mの距離の測定は、それほど正確なものではないこと、10mの雪庇は、吹き溜まりを含めればもっと大きなものになること、吹き溜まり部分も安定していなければ危険であることなどが予想できた。
山では同じ幅の雪庇がずっと続くことはありえず、雪庇の大きさは場所と時期によって絶えず変化する。山での「目測での10m程度」と「10数メートル」の差はほとんどないに等しい。また、すべてを目測で計測する山では、距離を測定するのは人間の感覚であり、実は、人間の感覚ほど当てにならないものはないのである。人間の視覚は何か物差しを基準に目測で距離を測定しているため、山での距離感はそれほど正確なものではない。
しばしば、人間の経験や感覚に頼る登山が批判され、科学的見地から安全性を確保すべきだとの主張がなされるが、機械や科学的手法を用いて正確な距離を測定できないことはないが、登山という一連の迅速な行動の中で絶えず距離を判断するとすれば、感覚に頼るのが現実である。登山における科学的知識は重要であるが、機械や科学的手法を最大限に利用すれば安全性は向上するが、おそらくそれは科学的活動であって登山ではなくなるだろう。人間の原始的、本性的、動物的な能力を使うことに登山の登山たる所以があるからである。
仮に、雪庇が10m程度にしか見えなかったとしても、目測による距離の判断は当てにならないこと、過去の情報などに照らし山頂の雪庇はもっと大きいかもしれないこと、したがって、その後の行動は念には念を入れて過剰なくらい慎重に行動する必要があると考えなければならなかった。
雪庇の危険性を理解するための思考や認識は論理的なものというよりも、むしろ感覚的なものと言ってもよい。人間は、後から冷静に考えれば、「どうしてそのような行動を取ったのかわからない」ということは、しばしばある。後で過失の有無を問題とする時には人間の行為に理屈を適用するのだが、人間がミスを犯す時は理屈に基づいて行動していないことが多い。人間が常に理屈に基づいて論理的に行動できればよいのだが、人間はなかなかそうはならない。
この事故は、天候の良さと集団的心理が「危険な登山慣れからくる油断」を加速させたのかもしれない。一部の班はまだ山頂に到着していなかったし、雪庇を認識して意識的に山側を歩いた講師もいるようだが、どういうルートをとるかは講師全員が意思統一すべきだった。事故は起こしてはならないのだが、確率的には人間はどこかでミスを犯すのであり、それだからこそ交通事故も含めて人間の事故がなくならない。したがって、このような危険な登山は引率登山ではなく危険を了解したうえでの登山(自主)登山として行うことが望ましい。
本件では、講師は雪庇を10数m程度と認識していたが、講師が雪庇の大きさや吹き溜まり部分の安定度を把握すべき注意義務を尽くしたとは言い難いか、あるいは、吹き溜まり部分がが巨大である可能性や、吹き溜まり部分が安定していない可能性もあったのだから、雪庇の先端から10数mの場所で休憩すべきではなかったことが過失の内容になる。
⑤予見可能性について
雪庇崩落を予見できたかどうかの議論は禅問答に近い。吹き溜まり部分を含めた雪庇の大きさを講師らは把握しておらず(その点は当時誰にもできなかっただろう)、その安定度も不明だった。
吹き溜まり部分の安定度を調べるためには、事故前に、大がかりな器具類を持ち込んで科学的な調査でもしない限りできなかっただろう。しかし、「決定版雪崩学」(山と渓谷社)の著者の1人である秋田谷英次氏(元北海道大学低温科学研究所長)は、この事故を聞いて、「雪庇のことはかなりわかっているつもりだったが、何もわかっていないことがわかった」と述べている(「北アルプス大日岳の事故と事件」ナカニシヤ出版)。それくらい、人間は自然についてわかっていないのだ。しかし、登山のように危険なことをする者にとって、「人間は自然についてわかっていないという事実」が「わかる」ことは非常に重要なことである。
「わからない」ことは登山の本質であり、未知の世界であるからこそ、人は登山を行うのである。吹き溜まりの大きさと安定度に関する情報が不足していることから、危険性を把握できなかったとも言えるが、逆に、情報が不足しているがゆえに危険性を予想できたはずだとも言える。吹き溜まり部分の危険性を知らなかったことを重視するか、吹き溜まり部分の安定度を知らなかったことを重視するか、その差は微妙だが、法的判断の結果は天と地ほど異なる。
講師らは吹き溜まり部分の崩落は予想すらしていなかったはずだが、安定していない雪は常に崩落の危険があるから、雪庇の崩落の危険を絶対に予見できなかったわけではない。もともと冬山は危険なものなので、ある程度の危険は予見可能なはずだが、現実の事故が予見可能かどうかの判断は禅問答になってしまうのである。
この判決は、単純化すれば、過去に巨大な雪庇(吹き溜まりを含む)ができることがわかっていたのだから、その年も巨大な雪庇(吹き溜まりを含む)ができることは予想でき、事故を回避できたはずだ、と述べているに過ぎない。判決のいう「25m」という基準は、判決文作成上のテクニックに過ぎないので、それほど意味を持たせるべきではない。
むしろ、その場所が安全であることが確認できていなければ、そのような場所で休憩すべきではなかったと言うべきであり、国が主催する研修会では、「安全性の程度がわからないこと」が国の責任になる面は否定できない。
6、若干のコメント
(1)裁判の結果を左右した事実認定
この種の裁判では、法律的な理屈ではなく、事実認定が重要であり、それによって、裁判の結論が決まると言ってもよい。
多くの人が山岳事故について議論する時、必ず一定の事実を元に議論をする。事実がすべて不明であれば、議論などできないからである。しかし、歴史的な事実を再現することはできないので、人の記憶、証言、録音、録画、写真などで歴史的な事実を推測するしかないが、それがしばしば真実だとは限らないのである。例えば、「事故現場の手前の稜線に10メートル程度の雪庇があった」かどうかを確かめようとした場合、目撃者の証言、事故の翌年に撮影した写真などから事実認定することになるが、これらはいずれも正確性は極めて低い。現実には「事故現場の手前の稜線に10メートル程度の雪庇があった」かどうかを確かめることは不可能であり、裁判所は、「事故現場の手前の稜線に10メートル程度の雪庇があると講師が判断した」という事実認定、すなわち、講師らの主観的認識の内容を事実認定している。主観的認識の内容の事実認定であれば、講師の証言から簡単に認定できる。しかし、客観的な事実の認定は、特に事故後に再現実験や正確な検証(もちろん、不正確な検証は可能である)等ができない山岳事故については、極めて難しいのである。
この裁判では、「冬山登山の経験がまったくない者が研修会に参加していた」という事実、「講師が指定した場所で休憩している時に起こった事故」という事実、「大日岳の山頂付近では、過去に少なくとも25~30mの雪庇が形成されていた」という事実認定によって、裁判所の判断が決定されたと言ってもよい。判決はそれほど重視していないが、講師が、山頂に至るまでの間に雪庇が10m程度だと認識していたという事実は重要である。
判決の論理の問題点については、以上に述べた通りであるが、判決が前提とした事実認定を前提とする限り、どのような論理構成をとっても裁判の結論に大きく影響しないように思われる。事故の関係者にとっては、裁判の結論が全てであり、判決の論理構成にほとんど関心がないことが多い。しかし、この判決が登山者に今後の行為規範として作用することを考えれば、判決がどのような考え方のもとにその結論を導き出したかという点は、登山者にとっては極めて重要である。
(2)危険の承認(危険の引受)
一般に、山岳事故の裁判では、危険の承認や自己責任の範囲が重要である。被告は、危険の承認を積極的な争点として主張していないが、恐らくそれは「冬山登山の経験がまったくない者が研修会に参加していた」という事故であり、講師が指定した場所で休憩していた時の事故だからだろう。
講習会と言えども参加者が危険を承認し、自己責任となる領域がある。この登山では、3月の北アルプスで通常予想される程度の危険性を受講生は承認しているとみなされるので、巨大な雪庇があることや、雪庇を踏み抜いたり、雪庇崩落の危険性を受講生は認識しておくべきである。しかし、そのような受講生の危険の承認は講師に安全配慮義務を前提としたものとなる。すなわち、受講生は講師が安全配慮義務を尽くすことを前提とし、それでもなお生じる冬山の危険は受講生の自己責任となる。
本件のような「冬山登山の経験がまったくない者」が参加する講習会では、講師の安全配慮義務の範囲は広く、講師は、受講生の登るコースなど受講生の行動の細部にまで指示をし、受講生はそれに従うことになる。このような講習会では休憩場所は講師が安全を確認したうえで指定をすることになるから、休憩場所の選定については講師に注意義務があり、受講生の自己責任が入る余地がない。
これに対し、一定レベル以上の受講生がある程度主体的に判断しながら行動をする形態の講習会では、先頭でラッセルをしていた受講生が雪庇を踏み抜いて遭難したような事故については、それが受講生の自己責任の範囲かどうか微妙な問題が生じる。ルートの選定が受講生の判断に委ねられている講習会なのか、講師がそのルートを指示したのか等によって微妙な判断になると思われる。たとえば、登山指導者を認定するための講習会、プロガイドを認定するための講習会、大学生のヒマラヤ遠征隊員のための講習会などでは、このようなルートの選定は参加者の自己責任に属すると考えるべきだろう。
(3)事故の原因について
講師は大日岳山頂付近では巨大な雪庇ができることは知っていたはずだが、具体的にイメージできず、自分の過去の経験と目視によって10m程度の雪庇を判断したものと思われる。恐らく、現地の状況から、吹き溜まり部分の雪が安定しているように感じ、雪の盛り上がり部分が山頂のような錯覚が生じたのだろう。これらはすべてその時の感覚とイメージと過去の経験から形成された判断であるが、前述したように、人間の感覚ほど当てにならないものはないのである。
仮に、過去に25m~30mの雪庇があることを知識として知っていたとしても、事故当時それを具体的にイメージできなければ、行動の基準にならない場合がある。山頂付近で、25mの雪庇をイメージできなければ、雪庇の先端から10数mの位置を、安全な距離だと勘違いすることもあるので、結局、実際の登山では、念には念を入れて最大限に慎重な行動が要求される。
また、講師らに過去何度も同じ場所で研修をしていることからくる油断があったと思われる。研修会では過去にも同じ場所で休憩していたようであり、今までは、たまたま雪庇が崩壊しなかっただけのことだろう。そういうことは危険な登山では珍しいことではなく、それで命を落とす人は多い。この事故のような雪庇崩壊は稀にしか起こらないかも知れないが、それでもそのような危険が絶対に予見できないということではない。ある程度の危険性を予見可能であれば、法的な予見可能性が肯定される可能性がある。今回のような雪庇崩壊の危険性はどの程度予見できたのかという議論は不毛な禅問答に近い。理屈のうえでは、事故は予見可能だとも言えるし、予見不可能だった言うことも可能であるが、この判決は多くの問題を含みつつ、「予見可能」と判断した。この種の裁判では、判決が正しいかどうかの問題は存在せず、裁判所がどのような価値判断を下すかという問題でしかない。国が主催する研修会では重い注意義務が課されること、危険な登山では事故が発生すれば予見可能性が容易に肯定されることから、この裁判では国に補償をさせるべきだという価値判断がなされたということである。
この種の登山のように危険な行動を引率して事故にが起きれば、引率者に重い責任が生じることは避けられない。したがって、参加者が危険を承認したうえで、自己責任のもとに参加すべきだった。しかし、今回の事故の被害者たちは、このような危険を覚悟のうえで、研修に参加したというわけではなかった点に問題がある。
(4)法的な意味の過失
山岳事故のほとんどは人間のミスに基づくものであるが、人間のミスのすべてが法的に過失になるのではない。人間のミスを過失と判断するかどうかは、法的見地からの価値判断である。
たとえば、判決の論理でいけば、仮に、講師らが25m以上雪庇の先端から離れていれば、事故に巻き込まれても過失はないことになるが、この判決の論理に問題があることは、前記のとおりである。その場合でも、事故が起これば講師に「雪庇を回避しなかった」ミスがあることは明らかであるが、判決が、「25m以上離れるべきだった」という理屈を前提とする以上、25m離れていれば、講師のミスは法的な過失ではないことになる。
このように過失があるかどうかは、法律論という理屈で決定されるが、前記のとおり、25m離れていれば十分ということではなく、登山者が安全のために守るべき注意義務は法的な注意義務とは別のところにある。
(5)人間は必ずミスを犯す。
「絶対に安全な登山はない」とか「人間は必ずミスを犯す」言うと、しばしば反発を受ける。しかし、「事故を起こしてはならない」ことと「絶対に安全な登山はない」ということは矛盾しない。
人間がなぜミスを犯すのかという点については、いろいろ研究がなされているが、ミスが減ることはあってもミスが無くなることは絶対にない。恐らく、人間の判断の過程は極めて複雑であり、同時に自然のメカニズムも複雑なので、その過程に合理的ではない要素が無数に存在するからだと思われる。判断の過程で存在する要素をすべて合理的なものにすればミスは生じないが、それでは人間ではなく機械になってしまうだろう。機械のように指示や命令通りに動くものは、故障することはあってもミスはありえない。人間が機械ではなく、自律的な判断に基づいて行動するという、まさにその点にミスが生じる原因があり、それは、人間を構成する細胞の1つ1つ、遺伝子の1つ1つにミスが生じる原因が存在することを意味する。人体の神秘はそのままミスが生じる神秘に繋がっているのだ。したがって、「なぜ、人間はミスを犯すのか」という問いに対しては、「それは、人間だからだ」と答えるしかない。
しかし、ミスが直ちに事故に繋がるものではなく、事故はいくつものミスが重なった時に起こる。いくつものミスが重なるかどうかは偶然による。そこで、人間がミスを犯すことを前提に、人間がミスを犯しても事故にならないようにすることが、事故の防止策になる。
したがって、講習会についても人間がミスを犯すことを前提に考えておく必要がある。
(6)講師の責任
法律上は、講師に過失がある場合に主催者である国が賠償責任を負う形をとり、原則として講師個人に損害賠償責任は生じない。
法的には講師に過失があったのだが、恐らく、多くの登山家が事故当時と同じコースをとった可能性があり(ほとんどの場合は雪庇の吹き溜まり部分は崩落しない)、講師は登山家として、少なくとも、現地ではそれなりに注意していた。登山では、一定の注意していても事故が起こることがあり、法的にはその程度の注意では不十分だという場合がある。
損害賠償の問題は損害を誰に負担させるかという問題であり、リスクの配分の問題だという面がある。国が主催する研修会であれば、この種の事故の損害は国が負担するのが妥当だという判断が裁判所にあり、それが予見可能性、結果回避義務という理屈をまとったと言えなくもない。この点が講師の刑事責任について嫌疑不十分で不起訴になったことに関係している。
(7)引率型の講習会は危険な登山に相応しくない。
本来登山は危険なものであり、危険な登山を引率型の講習として行って事故が起これば法的責任が問われる可能性が高い。
八ヶ岳の中岳道のように過去に雪崩事故のあった箇所が一般ルートになっている場合には、ここで引率型の講習中に雪崩事故が起これば、過去の雪崩事故を例に「雪崩は予見可能だった」とされる可能性が高い(実際に雪崩れているから雪崩の具体的危険性が存在しており、それを予見可能だったかどうかが主たる争点になる)。しかるに、北アルプスなどではルート上に過去に雪崩事故のないような山域はほとんどないのであって、引率型の講習は山麓の安全な場所で行うしかないように思われる。
私は、10年以上も前に、山岳連盟主催の冬山講習会の岩稜登攀の講師を務めたことがある。講習内容を企画し、受講生を募集したのは山岳連盟であり、講師は受講生の経歴や技術のレベルを知らされることなく、講師を依頼されただけだった。講習当日、講師は初めて受講生と顔を合わせた。その講習会では、岩稜の取り付きまでの雪壁をはい上がるのに手間取る受講生が1人おり、その受講生は取り付きから講師が1人付き添って下山した。その受講生を下山させたことは賢明な判断だった(その受講生は、翌年、同じ山域で雪壁登攀中に滑落死した)。講習会の参加者は、いずれも山岳連盟に所属する山岳会の会員なので、参加申し込みをさせた各山岳会の役員は、当然、参加者の登山歴や技術、体力などを十分把握しているが、講習会を担当する講師が事前に受講生の適格性を判断するわけではない。また、講習を企画する者と実際に講習を実施する講師が別人で、十分に連携がなされておらず、関係者の「あうんの呼吸」と、講習現場での講師の機転で何とか講習会が運営されているのが実情だった。このような講習会の運営方法を見ていると、いつ事故が起きても仕方ないように思える。もし、事故が起これば、講師が責任を問われることになる(もちろん、山岳連盟の責任も問われる)。
今回の事故について「このようなことで講師が責任を問われるのであれば、講師を引き受ける者がいなくなる」という声を聞くが、まさにその通りである。安全管理が不十分な講習会であれば、講師を務めることはやめた方が賢明だろう。
どんなに注意していても、人間はどこかでミスを犯すものであり、それは確率的に生じる問題である。事故の後で理屈で考えれば、「あのとき、こうすべきだった」と言うことは易しいが、人間はそのようにできないから、山岳事故がなくならない。今後も、山岳事故が0になることはありえない。
このように言えば、事故防止のために努力している人や事故の被害者から必ず反発を受ける。
事故の被害者の遺族はは、「防ぐことができた事故だった」と考えるが、それは間違いではない。「事故を防ぐことができる」ことと「必ず事故は起きる」ことは、矛盾しない。「人間は必ず事故を起こす」ことは、「事故を起こしても仕方ない」とか、「事故を起こしても許される」ということではない。そうではなく、「事故を絶対に起こしてはならない」し、「事故を起こしたことに過失があれば、重い責任を負う」のであるが、このことと「人間は必ず事故を起こす」ことは、矛盾しないのである。それでいいということではなく、あくまで、人間の実態がそうだということである。
逆説的に言えば、「人間は必ずミスを犯す」からこそ、刑事罰や損害賠償責任の制度があるともいえる。
日本は、あらゆる分野で組織や団体活動を通じて「個人の面倒を見る」という、いわば「お節介文化」が浸透しているので、山岳団体が危険性を伴う引率登山講習を行うのが当たり前になっているが、世界的には珍しいことではないかと思う。本来、危険な登山の技術は、例えば、仲間同士の登山のように、個人の自己責任においてレベルアップを図るべき領域であり、それを組織や団体で引率して世話をすれば、事故があった場合の責任を引き受けることになる。あるいはガイド登山であれば、ガイドは有償契約によって、事故の場合のガイドの法的責任というリスクを覚悟しておくことになる。
引率登山は登山技術のレベルアップのためには非常に効率が良いが、その効率の良さには以上のようなリスクが伴う。
仮に、危険な登山の引率講習を行うのであれば、予算、スタッフ、講師の資格や講師の養成システム、研修方法や研修のプログラム等を確立して事故が起こらないように万全の制度にすることが必要である。それでも、危険な登山をしていれば確率的に事故は必ず起こるので、事故が起こった場合の補償制度等を確立しておくことが必要になる。逆に言えば、そこまでの覚悟と体制がなければ、危険な登山の引率講習はできないように思われる。
日本では、多くの山岳連盟や山岳会が危険を伴う登山講習を実施しているが、ほとんどボランティアで、貧弱な体制のもとで行われることが多い。ほとんどの場合に、事故が起こることまで想定していないように思われるが、事故が起これば、たとえ受講生に免責同意書を提出させていても講師に損害賠償責任が生じる可能性が高い。
講師の法的責任については、今回の判決は、今までとは違った新しい考え方を下したのではなく、実はずっと以前から法律的にはそうだったのだが、今まではたまたま講習会での事故があっても裁判になることが稀だっただけのことである(自衛隊の訓練に伴う事故などについては、過去に何件も裁判になっている)。
引率型ではない講習であれば、参加者の自己責任を考えやすいが、それは例えば、ヒマラヤで行う高所登山学校だとか、ガイドを養成するための研修だとか、仲間同士の登山の延長としての講習であり、そこでは受講生が自分で危険性を判断してそれを回避できるだけのレベルにあるかどうかが重要である。
この裁判は、引率型の研修登山に関するものであって、自主登山に対しては何ら影響を与えるものではない。この判決に対し、登山文化を萎縮させるものだとの意見があるが、危険を覚悟のうえで行う本来の登山には何ら影響を与えない。
しかし、この判決が引率型の研修登山には一定の影響を与えることは間違いない。この裁判は危険性を伴う研修登山や講習会の従来のあり方に大きな問題提起をしている。
(8)リーダー冬山研修会安全検討会(2008年6月15日作成)
富山地方裁判所平成18年4月判決に対する控訴審(名古屋高等裁判所)で平成19年7月に和解が成立し、下記の和解条項に基づいて、登山研修所の大学山岳部リーダー冬山研修会に係る安全検討会が文部科学省に設置された。
(和解条項・抜粋)
5〈1〉 文部科学省は、本件訴訟において明らかとなった本件事故に関する事実関係を踏まえ、安全検討会(仮称)を設けて、そこにおいて、本件事故を教訓として、本件研修会を安全な形で再開することができるか、再開する場合には、安全対策の内容とそれをどう徹底していくかについて、十分検討するものとする。安全検討会(仮称)は、幅広い有識者から構成されることとなるよう配慮する。
私はこの安全検討会の委員に就任したが、それは、「山岳事故の危険性と安全性についてどのように考えるべきか」という問題意識に基づく。安全検討会は、和解条項にあるように、1審判決の判断を踏まえて研修会の安全対策のあり方を検討するとされている。
本来、事故を解明するためには、事故の原因や背景、事実経過、事故の態様、事故のメカニズム、雪庇の研究、事故回避方法(どうすれば事故を回避できたのか)、安全対策、研修所のあり方、海外の制度との比較、登山思想、登山者の意識などについて、総合的に検証することが必要である。しかし、安全検討会は、「本件訴訟において明らかとなった本件事故に関する事実関係」を前提として、もっぱら安全対策について検討することとされている。事故の原因については、和解条項にあるように、「本件訴訟において明らかとなった本件事故に関する事実関係」を前提とすることになり、遭難そのものを検証することになっていない。登山という観点から考えれば、裁判で事故の全容は解明されていない。もともと裁判は法的紛争を解決するだけなので、裁判で事実をすべて明らかにできるとは限らないが、裁判で一応、事実関係が明らかになったものとみなして、安全対策を検討しようというのがこの和解条項である。
私が安全検討会の委員になったのは、「山岳事故の危険性と安全性についてどのように考えるべきか」という問題意識からである。安全検討会は、雪庇事故に関する安全性だけではなく、研修会の安全性そのものを検討するのであり、すべての登山に共通することを検討する。
和解条項の「本件訴訟において明らかとなった本件事故に関する事実関係」とは、1審判決が認定した事実はこれに該当し、それ以外の事実は該当しないということになる。
裁判上の和解は、日常用語における仲直りという意味とは違って、事故の責任問題の追及を終わりにして法的紛争を終結させるという意味を持っている。和解が成立すれば、裁判上の争点は解決されたものと見なされ、紛争の蒸し返しが許されなくなる。安全検討会は法的紛争が終結したという前提のもとに成り立っており、和解条項に記載されていない責任の追及はできない。1審判決は講師に過失があったことを前提に国の代位責任を認定しており、これは和解条項も同じである。したがって、講師の過失を認めた前提である事故の経緯や事故の原因に関する事実を動かしたり補充することはできない。事故原因をさらに究明することは、1審判決が認定した事故の経緯や事故の原因に関する事実を再検討することになってしまう。再検討するということは、一審判決の事実認定を否定する可能性を持つが、それは和解条項により安全検討会の任務ではない。
安全検討会に対し、「遭難を検証すべきだ」という意見があるが、5年に及ぶ裁判は事故の検証の過程でもあった。したがって、安全検討会は裁判の結果を前提とするのである。もし、新たに事故原因等を調査した場合に、調査した結果が判決が認定した事実と異なる場合が、大問題なのである。検討会自体が、裁判の中で一審判決を前提としているのだから、それとは異なる調査はできないのではないか。あらかじめ一審判決の認定した事故原因を前提に事故原因等を踏査するのは、矛盾であり、科学の否定である。
もっとも、裁判によって事故が十分に検証されたかというとそうではない。例えば、1審判決では雪庇の規模が40メートル以上あったと認定しているが、これは裁判所が調査したうえでこのように認定したわけではない。原告、被告の双方が雪庇の規模が40メートル以上あったことを争わなかったから、裁判所がこのように事実認定をしたのである。裁判では争いのない事実について、裁判所がそれと異なる認定をすることはできないことになっている。したがって、雪庇の規模が40メートル以上あったかどうかは、本当は曖昧なのである。
したがって、事故の検証の必要性はあるが、それは、例えば、雪庇に関する実験や大日岳での雪庇調査、事故後の調査データの科学的分析、解明など裁判で行われなかった検証になる。裁判では大がかりな実験や検証、科学的な鑑定は行われていないが、これらも必要だろう。雪崩講習は各地で行われているが、雪庇に関する実践的な講習はほとんど行われていない。座学にとどまらない実践的な雪庇講習の方法はまだ日本では未開拓の分野である。これらの検証の結果、裁判では解明されていない事実や判断の不十分な点も明らかになるだろう。いずれにしても、そのためには、事故の事実関係、原因、雪庇の科学的解明、安全対策、登山技術、登山観等を検討する遭難検証委員会とでも呼ぶべきものを設置することが必要である。その場合の検証は、裁判所が認定した事実にとらわれることなく解明することになる。一定の事実や結論を前提に科学的な検証を行うことは科学の名に値しない。
「北アルプス大日岳遭難事故調査報告書」(北アルプス大日岳遭難事故調査委員会編)の内容が安全検討会で検討されていないという意見があるが、同報告書の内容の是非を論じることは、「本件訴訟において明らかとなった本件事故に関する事実関係」を踏まえた安全対策の検討のうえで必要ない。1審判決は同報告書の予見可能性に関する結論部分を否定したものと理解でき、1審判決で既に解決済みの問題である。現時点で、北アルプス大日岳遭難事故調査報告書の内容を子細に検討する意味はない。1審判決が同報告書を問題にしていないのは、同報告書の証拠価値が低いものと判断したからだと思われる。
判決は、関係者が判断してほしい点を判断するのではなく、法的解決のうえで論理的に必要なことしか判断しないので、関係者から見れば不満が残ることが多い。しかし、裁判所は国が紛争解決のために運営する機関なので、法的な紛争解決に必要ないことは判断しないという性格を持っている。その意味で、裁判所は最低限の判断しかしないのである。
安全検討会で上記報告書の内容を子細に検討したり、裁判所が判断しなかったことまで判断することは、裁判をやり直すことになり、それは安全検討会の役割ではない。
裁判の結果を踏まえれば、事故の原因は下記のようにまとめることができる。
(大日岳事故の原因)
①直接的要因
事故現場で、雪庇の吹き溜まり部分で休憩した講師の判断ミス
②間接的要因
イ、研修所の安全管理体制の問題
・事前の情報収集のシステムの欠如(過去の雪庇の規模、ルートのとり方など)
・組織的な安全管理体制の問題
・登山研修所の予算、スタッフの体制など
ロ、研修の対象となる時期やルートの危険性
・危険を伴う時期やルートの登山では、些細な判断ミスが大事故に直結しやすい。
ところで、事故の原因を考える時、人間の思考による追及は際限がないという性格がある。例えば、大日岳の雪庇の規模に関する研修所の情報収集が十分でなかったことについて、さらに、「情報収集が十分でなかった原因はなにか」、「講師に情報が伝わらなかったのは何故か」、「研修所に情報収集するシステムがなかった原因は何か」などを考えれば、際限のない原因追及が可能である。加害者が国であろうと私人であろうと、被害者の立場は変わらない。社会的・歴史的事実は人間の行為がもたらすものであり、あらゆる人間の行為について「理由」を問うことが可能である。しかし、「なぜ」という問いに対する解答が見つかるとは限らない。
人命にかかわる事故や事件が起きた場合、法的手続によって紛争の法的な解決はできるが、「紛争」そのものは解決されないことが多い。判決の宣告や裁判上の和解の成立によって、裁判所は「紛争は解決されました」と宣言するが、関係者は「加害者を赦すつもりはない」と考える場合が多い。事故や事件の関係者にとって紛争は簡単に解決できるものではない。
他方で、情報収集するシステムの欠如の原因を追及することと、今後情報収集するシステムをどうやって構築するかということは別のことである。従来の情報収集体制の不十分さを事細かに調査、追及しても、それによって、今後すぐれた制度ができることにはならない。従来の情報収集体制が不十分だったことは判決で明かであり、それを前提に今後の情報収集のシステムをどのように構築し、それをどのように指導の指針に盛り込むかという点が重要である。
安全対策を検討することは、言葉だけを取り上げれば、責任の所在を不問にしているように見えるが、そうではない。両者はいわば考える方向が逆なのである。安全対策を考えることは、過去に向かうのではなく、将来に向かうという点で、考える方向が異なる。事故の全容を解明することは、ある程度は安全対策のうえで必要であるが、事故の全容を解明しなければ、安全対策ができないということではない。「なぜ」ではなく、「今後、どうすべきか」を考えることが重要である。
「安全対策を記述した文書」は、逆に言えば、今までの研修会における安全対策の不十分な点の指摘である。ただし、安全対策の欠如=事故の原因ではない(事故の原因は1審判決記載のとおりである)。
安全対策は、裁判所が認定した事実と責任の所在を前提にして、情報収集のシステムの確立、安全指針の確立、それを文書化して情報の継承を図ること、座学を実技に生かす方策の検討等に左右される。
安全検討会の報告は、あくまで言葉で書かれたものでしかなく、それを実践できるかどうかは人間の行為にかかっている。
(9)登山研修所のあり方
①、大日岳事故以前の登山研修所は、登山家のほとんどボランティアに近い形で運営されてきた。この点は、事故後に、講師を非常勤職員とするなどの変更がなされた。
しかし、フランスの国立スキー登山学校やイギリスのMLTUKなどと較べると、予算、研修内容、スタッフ、施設、講師と研修生の待遇など雲泥の違いがある。国家が本気で登山リーダーの養成をしようとすれば、それくらいの体制が必要である。登山は危険を伴う行為なので、中途半端な制度で行うことはいろんな意味でリスクが伴う。しかし、フランスやイギリスのような充実した制度を作っても、絶対に事故がないというわけではない。
②、登山は本質的に危険な行為なので、絶対的な安全性を保証できない。この点で、例えば、電車の運行のように、安全管理を徹底すれば、少なくとも理論的には100パーセントの安全性が保証できる領域と異なる。登山が対象とする自然のメカニズムは完全に解明されていないので、登山では理論的にも100パーセントの安全性はありえない。
登山において、可能な限り安全性を高めようとすれば、実践的な登山研修をやめて、例えば、中央アルプス千畳敷カールでの雪上講習のように、安全管理の可能な場所での冬山研修にするしかない(その場合には、たぶん、99パ-セントくらいの安全性は可能だろう)。大日岳登頂をめざす実践的な登山研修と、中央アルプス千畳敷カールでの雪上講習の違いは、事前に講習場所の安全性をチェックできるかどうかという管理可能性の違いである。大日岳登頂をめざす登山研修でも、事前にルートをチェックして、20メートル間隔でルート上にポールを立て、山頂にも事前にポールを立て、事前に雪庇を掘り起こして崩落の危険性や規模をチェックすれば、危険性の管理が可能だが、そこまでして「実践的な登山研修」をする意味があるかどうか疑問である。
したがって、実践的な冬山登山研修は参加者がその危険性を承認したうえで行うことが必要であり、引率して行うことは望ましくない。
しかし、日本の登山研修所は引率型の登山研修を行う場であり、危険承認型の登山研修は、危険性の承認が一般化していない日本の文化の中ではかなり難しいように思われる。この問題は「個人」や「自己」に関する文化の違いが反映する。
従来、登山家の多くは危険承認型の登山の世界に住んでおり、引率型の登山の法的責任に不慣れ、ないし、反発をする傾向があった。雪庇の吹き溜まり部分が危険だとしてもそこをルートに使用することはありうることであって、その程度の危険は仕方ないというのが、これまでのほとんどの登山家の意識だっただろう。雪庇の吹き溜まり部分の危険性を気にするようであれば、冬山登山などできないというのが、従来の登山家の意識だったのではないか。そこには、「冬山ではある程度の危険は仕方ない」という危険性の承認の意識がある。しかし、自主登山であればそれでもよいが、安全配慮義務を負う引率登山ではそういうわけにはいかない。むろん、引率した講師は、「ある程度の危険は仕方ない」とは考えておらず、「安全であることに徹する」という自覚を持っていただろう。しかし、登山のスタイルは自分が育ってきた登山の世界から完全に無縁ではありえず、無意識のうちに従来のスタイルの登山をしてしまうことがある。雪庇の吹き溜まり部分の危険性を軽視したことや、山頂の位置を確定できないことをそれほど気にとめなかったのはそのあらわれだろう。私自身がこのような登山観の中で登山をしてきたので、この点はよくわかる。
私は、個人的には、危険性を承認したうえで行うのでなければ、実践的な冬山登山研修は廃止した方がよいという考えを持っていたが、安全検討会では、実践的な冬山登山研修を存続する意見が多数だったので、実践的な冬山登山研修を存続するさせるための条件を検討することになった。もともと100パーセントの安全管理のできないことを安全に行うことは、当然のことながら難しい。実践的な冬山登山研修の再開を望む声が大きくなければ、実践的な冬山登山研修を再開しないということも1つの選択肢であり、それは国民が選択することである。
もっとも、現実問題として、今後、文部科学省主催の冬山研修会の講師になる登山家がいないのではないかという問題がある。その理由から、今後の冬山研修会は中央アルプス千畳敷カールのようなゲレンデ的な場所での雪上講習しか実施できない可能性がある。危険な引率登山は、「どうしてもしなければならないもの」ではないので、それはそれでかまわない。
個人の尊厳の中でもっとも根元的な価値は生命の確保であるが、引率型の危険な登山は、自分の命を他人に預けることを意味する。危険な登山は自主登山を原則にすべきである。
|
![]() 「ルールのない危険なスポーツ」における危険の引受と民事上の注意義務
「ルールのない危険なスポーツ」における危険の引受と民事上の注意義務 ![]() 弘前大学医学部山岳部事故控訴審判決(名古屋高等裁判所平成15年 3月12日判決)について
弘前大学医学部山岳部事故控訴審判決(名古屋高等裁判所平成15年 3月12日判決)について![]() 「登山の法律学」、溝手康史、東京新聞出版局、2007年、定価1700円、電子書籍あり
「登山の法律学」、溝手康史、東京新聞出版局、2007年、定価1700円、電子書籍あり
![]() 「山岳事故の責任 登山の指針と紛争予防のために」、溝手康史、2015
「山岳事故の責任 登山の指針と紛争予防のために」、溝手康史、2015