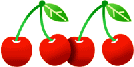| トップページ | 経 歴 | 文章1 | 文章2 | 文章3 | 真空断 熱HP |
団塊世代 HP |


のらくろ二等兵から大戦荒波を越え
自然から心に贈り物 その三
素直な心の持ち主なりて自然から受けるもの
全 編 項 目
殊更なる自然観の芽生え 一
文章は人に読んでもらうために書くもの
やっときた平和 大阪文学学校
文章は書くことに意義あり
自然から心に贈られしもの回顧
殊更なる自然観の芽生え 二
迷いの回顧
自然詩人ワーズワースの詩
森の学校と完成
自然を見つめさせる時、所
賢母と慈母 除かれたくない心
感性の受け渡し
野花から 心眼の芽生え
若人であってこそ 最もな心の糧
日本の故郷
里山の春
里の夏
里の夜空
里の秋
里の冬
里山、里の生業
抜き切り
柴切り
竹の子
能代
田隙
田植え
神を見た
段々畑 いちご畑
養蚕
小道 渓流 晩鐘
里の行事
お盆
秋祭り
運動会 手作りの醤油
実りの実感 取立ての味
大なべで炊いた飯 痩せの大食いの馬鹿力
里の学び 古道
吉野の慈母、心の湯浴み
サムエルウルマンの青春
市(いち)の町
ワーズワース、ゲーテの自然観
本物と似非者
世界遺産と土道、古道
弘法大師、山の上寺院の導き
南朝秘道秘史
隠れ熊野古道
賢母と慈母思考の始まり
心の湯浴み
馬方さんと少年倶楽部
殺生嫌いと前畑秀子
清水とH2O
日本の故郷
蘇る里、里山の夏
若人と若やぎ人
明らかに自然が人に勝る所
山 森 林
蘇る森林、抜き切り
吉野杉の性
トリプル授業教室の恩恵
吉野水の活用
綺麗な水で育った女性
綺麗な水辺で育つとき
綺麗な水は思わせる
大昔のこと
庄屋の家
蘇る里の暮らし
古ぼけ
高野猿とつり橋
高野槙風呂
吉野良水と高野豆腐
ほおの葉寿司
エビカニアレルギ
カールルイスと山火事
カラオケの露払い
里、里山、慈母、心の湯浴み談義
付随記 慈母は招く
自然詩
抜 書 き
春 夏 夜空 秋 冬
里山の春
春の訪れを待つのはひとしお
冬が訪れてくるとき
一夜のうちに雪が山々を覆い
秋の名残りを覚えさせず
だが 春の訪れは適う
雪は 山裾から消えはじめ
冬を名残り惜しませ
春を待ち焦がらせること幾日か
山頂だけを白くして春がくる
待っていた 里山に登れる時がきた
段々畑の上 林まで百メートルばかり
畑端の小道を登り 雑木林に入る
木蔭に まだ残っている雪を見て 冬の名残りを感じ
青空に向かって立つ木を仰ぎ 新芽をみつけ
冬 枯れたのではないかと もんでいた気が安らぎ
春だと より感じる、
雑木は良い
葉を落とした枝ぶりが良く
新緑になるときも
緑濃く茂るときも
紅葉したときも艮い
木の名を知らなくてもよい
なおなお
葉を落とした雑木に混じる松
常緑樹の緑はより濃く見えて良い
それに 山桜がくわわるとき なお良い
山一面に咲くも艮く
林の中 ただ一本咲くも良く
もっとも 春だ と感じるときだ
冬が長く寒かったとき 春は より良い
と感じながら坂を登り、立ち止まり、林の中を見渡し、また登り、立ち止ま
る。
る。
雑木の枝振りを見上げ、この時季しか見ることができない、良い眺めだと
見とれ、それに混じる山桜の枝を見つけ、去年咲いていた様を思い出し、
今年は、あと幾日で咲くのか、去年よりも多く花を咲かせるのか少ないの
か、などと思いながら急坂を登り続ける。
見とれ、それに混じる山桜の枝を見つけ、去年咲いていた様を思い出し、
今年は、あと幾日で咲くのか、去年よりも多く花を咲かせるのか少ないの
か、などと思いながら急坂を登り続ける。
道に敷き詰めている落ち葉を踏んで滑り、膝を付いたり木につかまり、あえ
ぎながら二百メートルばかり登ると三角形の草原に出る。
ぎながら二百メートルばかり登ると三角形の草原に出る。
この草原を三角原と呼び、それを囲んで、背くらべができるほどの雑木があ
り、更に、その外を囲んで大きい松や雑木が立ち並んでいて、森を抜け、
草原に出ると「ぽっかり」空いて空が見える。
り、更に、その外を囲んで大きい松や雑木が立ち並んでいて、森を抜け、
草原に出ると「ぽっかり」空いて空が見える。
村外れから三百メートルぐらいの所だが、ここから、家は見えず、一番、身
近で山の中を感じる所である。
近で山の中を感じる所である。
ここには雪はなく、この辺りの背丈ほどの木は芽吹き始めている。
木々の新芽は良い
芽吹く様が良く
活きが良く
彩りも艮い
木の名を知らなくてもよい
その新芽を、接ぎ木を見守るのと同じように手で触りながら見る。それは、
茶摘みのとき触れる新芽の感触と似ている。それを、また、日を経て見に
行って触れる。
茶摘みのとき触れる新芽の感触と似ている。それを、また、日を経て見に
行って触れる。
芽吹きから新緑になるまで、一春に幾度も行き、その度に手を触れ、次第
に固さを増していく新芽や新葉の感触を味わう。
に固さを増していく新芽や新葉の感触を味わう。
これを、新緑になるまで繰り返すのである
新緑は良い
日が透くような若葉が良く
まねができない色彩
山を覆い 花をしのぐのが良い
木の名を知らなくてもよい
このころは、とくに遊ぶことがなくてもよい。萌黄、浅緑、若葉をうまく描くに
は、どのような色合わせをすればよいのかと思案しながら眺めるだけでよ
い。
は、どのような色合わせをすればよいのかと思案しながら眺めるだけでよ
い。
それに、このころは、土の温もりを心地艮く感じる。
特に三角原は太陽を直に受けている。そこ
に、しばらく居ると確かな土の温もりが体に伝わってくる。
つい、土の上に腰を下ろしたくなり、座って、周りの潅木の新緑を見回し、
それを囲う林の木を見上げたり、遠くの山々の木々に目を向けたり。
それを囲う林の木を見上げたり、遠くの山々の木々に目を向けたり。
いずれも、萌え出た若葉に覆われている。その中に遅咲きの山桜が、ぽつ
んと立ち。ほんのわずかな花をつけている。山つつじも咲いている。山つつ
じの色は良いと、いつも、その色合いに見とれる。それは新緑の中に咲くか
ら余計にそう感じるのかも知れない。
んと立ち。ほんのわずかな花をつけている。山つつじも咲いている。山つつ
じの色は良いと、いつも、その色合いに見とれる。それは新緑の中に咲くか
ら余計にそう感じるのかも知れない。
ときに、長けた、うぐいすの音が山々を渡ってくる。
小鳥がさえずる。
つい十メートルばかり前の草原から山鳩が飛び立つ。
あの鳥も土の温もりを求めて居たのだろうか。
このころ、人も動物も、日当たりを特に求めるのではなく、かといって日陰を
恋うのでもないのが良い。
恋うのでもないのが良い。
と、この時季と新緑を、より恋うようになる。
でも また 夏の緑も艮い
より濃い茂りが良く
全山を覆うのも
活を覚えさせるのも
茂りの木蔭が涼しさを
より 感じさせるのが良い
木の名を知らなくてもよい
この季節には、好きな落ち葉の匂い違いがする木蔭を選んで寝床にし、
山肌に敷く落ち葉を敷物に、寝転んで漫画の本を読む。
山肌に敷く落ち葉を敷物に、寝転んで漫画の本を読む。
匂に飽きると、また、別の匂を求め、場所を寝転ぶ。
蝉が鳴きむせんでいる
小鳥が落ち葉をかいている
時々 小きい動物が走り去る
微風が渡ると梢の葉は触れ合ってぞよめく
木漏れ日が動く
葉が舞いながら散ってきて胸や膿にとまる
梢で茂りを増し 重なり合っていた枝が
風もないのに何かの弾みで「ザー」と離れ 生きている
なと感じさせる
枯れ枝が「ばりつ」と折れて落ちる
木に這い登っている蔦の先が枝を求めて動く
森を、ちょっと見ると静寂に見えるが、森の中に一人でしばらく、凝としてい
ると、森の動と性を感じ始め、「みしみし」と言うような音にならない音を感
じ、立ち並ぶ、四、五十センチの木が、より大きく見えだし、大樹の生気に
気押され、落ち着きを失いはじめて、
ると、森の動と性を感じ始め、「みしみし」と言うような音にならない音を感
じ、立ち並ぶ、四、五十センチの木が、より大きく見えだし、大樹の生気に
気押され、落ち着きを失いはじめて、
森を退屈凌ぎの遊び場とみくびっていたはずの自分が小さく見えだし、心も
となくなり、負けて逃げ出したくなる。
となくなり、負けて逃げ出したくなる。
だが、それでは自分が哀れに思える。
そのうちに、大樹の下で育っている潅木や茨に目が移る。
この木は 林の風情を増すためだけに育っているのではない
大樹の根元が
乾かないように
大雨に洗われないように
雪で冷えないようにしている
それは 真なのか否か分からない
だが そのように見ると、なお、ゆかしく感じると、潅木に心を和められ、大
樹から受ける圧迫を押しもどし、落ち着きを取り戻して、また、漫画を読む。
樹から受ける圧迫を押しもどし、落ち着きを取り戻して、また、漫画を読む。
このように木や山肌と接した後、我が家に居たりしているとき、雨が降る
と、雨を受けて清々している木や思い切り雨を吸っている山肌を頭に描き、
また、日照りが続くと雨を求めている木や山肌を頭に描くようになって、雨
上がりのあとや日照りが続いたあとには山肌や木を見に行きたくなる。
と、雨を受けて清々している木や思い切り雨を吸っている山肌を頭に描き、
また、日照りが続くと雨を求めている木や山肌を頭に描くようになって、雨
上がりのあとや日照りが続いたあとには山肌や木を見に行きたくなる。
そして、秋口から紅葉を待ち焦がれながら登る。
紅葉は良い
黄色も赤も茶も艮く
山を飾りおおいつくすのも良く
朝日夕日に映えるとき特に良い、
木の名を知らなくても良い
このころ、道には、色付いた落ち葉が敷いていて、匂が林の内に滞ってい
る。松の木の辺りでは、松特有の匂があり、木によって、それぞれ違い、そ
して秋が深まるに連れて人通りの少ない道は、色付いた落ち葉で覆われ、
匂もまた変わってゆく。
る。松の木の辺りでは、松特有の匂があり、木によって、それぞれ違い、そ
して秋が深まるに連れて人通りの少ない道は、色付いた落ち葉で覆われ、
匂もまた変わってゆく。
そこで 紅葉をふり仰ぎながら
グミを取る
栗を拾う
山梨を取る
茸を探す
山の中 紅葉の中 山の実りを求めて歩き回る
それが 秋の里山での遊びである
里の夏
朝
軒端の巣で育つ燕の子が
小さく力強く鳴く
深い眠りが覚める
親燕が餌を求め
大きく羽撃き 巣を飛び立って行く
竹どいを流れる水音が聞こえはじめ
浅い眠りが心地よく覚めてゆく
夏の一日が始まる
日はまだ 蝉もまだ鳴いていない静かな朝
庭先から山腹に点在する村を見下ろし
家々は小さくなったと感じる
田畑の茂りは建家を低く見せ
大柿の木は家より高く伸び
冬 幹だけのときに比べ
夏 大きい葉が茂った木は
その幾倍もの大きさを誇示するから
それらを 見えない朝霧が覆っている.
夏の朝なのだ
村を囲ってそびえる連峰は
いま盛んに茂る緑に覆われている
連峰に区切られた空は
まだ明けきっていない
連峰の頂には
雲なのか 霧なのかと見紛う 朝霧が棚引く
やがて 朝日は東峰の向こう側に登り
山頂に林立する木姿を浮き立たせる
そして 霧は山頂を越え 雲になる
朝日は西峰の頂を照らし始め
して 山面を照らし 東峰の影を写し
日当たりと日陰を明らかに分ける線を描く
その線は 朝日を待つ村へ向かい
でも 急がず
一面の茂りを
次々 照らしながら降りてくる
照り明かされゆく緑は鮮やか
目を外らさせず
村向うの丘を照らし
家々を照らし
続いて 大柿の木の葉を日射し、
漏れて 中の霧を証す
柿の葉に乗る露は
集まって葉から葉へ落ち
更に集まって水玉になり
朝日にきらめきながら落ちる
小芋の葉にのる露も
寄り集まって水玉になり
きらめきながら
そよ風に揺れる葉の上を転げ回る
やがて 太陽は東峰の上に すっかり登り
朝日を村に注ぐ
山々 田畑の茂りは いまから大きく葉を広げ
日光を存分に吸う
蝉の音が耳につきはじめる
小鳥の音も
昼
真昼の陽光は山や田畑に降り注ぐ
木々の葉は反り返って日光を吸う
稲や草々も背伸びをして太陽を恋う
蝉はうるさく鳴く
燕が飛び交う
蝶も蜂もまた
夕
蝉が鳴きくたびれるのでは
と気になるころ
あちこちの山に茂る草むらが
葉を裏返して波立ち
稲田も波立ち始める
そして 木々の葉も
葉の裏を見せてぞよめく
夕立の前ぶれか
東峰の南方を見つめる
雨が降りはじめるのは あそこだ
峰が煙り始めた 夕立だ
雨足は速く
東峰の山面に沿い 北へ走ってくる
山一面がけむり
向いの丘 氏神の森と煙りきて
大粒の雨が頬をたたく
四辺の山と空の境が消える
雨はどしや降り 一面の茂りをたたき
はじき返ってしぶく
稲妻が走り
雷音が四辺の山に鳴り渡る
稲は雨に打たれて踊り
大柿の木は
茂る葉に雨を受け たわみゆらぐ
屋根が受けた雨は といをあふれて注ぎ
庭を掘る
見る間に溝を追って流れ
坂道は川
― ― ―
数十分で夕立は止む
稲妻の閃光が薄れ
雷音は連峰の外にうつり 遠のく
雲間から日がもれ始め
虹が薄くかかり
次第に色を濃くして続く、
しばらーく
やがて 霧は虹を消しながら山を登り
頂上に棚引く
柿の葉から水玉がきらめきながら落ち続ける
巣で雨をしのいだ燕は
また 餌を求めて飛び立ち
蝉も また鳴きはじめる
夕焼け
夕立が去るのも 雪が去るのも見事
空は より青く 高い
日は西に大きく傾き
間も無く 西峰にしずみはじめ
峰の影を 向かう山々におとして一線を引く
その線は山面を陰らしながら登り
頂上を越え 空は焼けはじめる
雨後の夕焼けは特に美しい
焼け空のもと
山々は静かにたたずまい
雨に洗われた茂りは潤々しい
親燕は巣に帰って 子燕とならぶ
日暮らし蝉だけが
まだ一 二匹 ケタ ケタ鳴き続けている
やがて
西峰の上に 宵の明星が見え始め
星は 次第に数を増してゆく
里の夜
夜空の四季
山間の真夏
夕食後
肌を出すと寒いほど
晴れた夜
ぬれ縁に並んで腰を掛け.
夜空や夜景を見ながらの団らん
月が無い夜 星明かり
ほんのり見える 山や家
ときに 訪れて来た人々も くわわる団らん
間食は おかき お菓子
頬ばりながら
山腹の斜面に点在し
おぼろげに浮かぶ家々を眺める
夜道を明かりが通って行く
人影は見えない
明かりだけが動いて行く
あちらの家から こちらの家へ
明かりが一つの家に集まって行く
何かあったのかーーー
ときに 速く動く
それも気になる
そして 夜遅くなって動く
またまた気になる
明かりの動きがなくなり
谷間の蛍が目立つ
遠目に蛍をみつめると
目が闇に慣れてくる
いや
星が輝きを増したのか
教を増したのか
、
大柿の木が影のように見えてくる
氏神の森
向いの丘
連峰のたたずまいも
四辺の連邦が夜空を四辺形に区切る稜線は明らか
かすむ空のはてを隠し
よその空を隠し
わが夜空だけに焦点を絞る
それでこそわが夜空はよい.
澄み渡る空だけを
輝く星だけを
奥深くの星をともに
ありったけ見せてくれる
明日の天気もわかり
四季もわかる
わが夜空 高く 澄み 星は底光り
天の川がくつきり見えるとき 秋
その夜空 なお深く 黒く
星は沈み 底光るとき 冬
その夜空 やや・かすみ
星もやや のとき 春
それより 空は高く 澄み
星は空に浮いて輝くとき 夏
わが夜空だからこそ
違いがよく分かる
流れ星も鮮やか
夏 一夜に幾つも流れ ′・
数えるのが楽しい
夜の深まりとともに
奥深い星がくわわり
数を増し 輝きを増す
ぬれ緑に並ぶ人々 ひとしく
わが夜空を仰ぎ たたえること幾十分
そして 夜話をはじめる
「昔 南朝方が村向いの丘に城を築いた
そのときも星は輝いていたのだろうーー」
話す人の姿 顔は輪郭だけ
表情も 話しぶりも分からず
声は うす闇の中から聞えてくる
眺める山々 家々はおぼろげ
そこで星にさそわれながら話す人
より いにしえを思い 夢想を広げる
「幾度か戦って城は落ちた そのとき この
星明かりのもと城を逃れて行く人も居たのだろう」
ぬれ縁に並ぶ人すべて
ひととき いにしえに導かれ 夜空を仰ぎ
また 今にもどり 星をたたえ
明日の天気を推し生り
訪れ人はうす闇の中へ幻のように消えて行く
われ一人
わが夜空
この星
この夜景
残して寝るのがおしい
振り仰ぎ振り返り見ながら寝床に向かう
里の秋 大柿の木、蜂雀にかかる情
茅葺きの屋根に被さって立つ大柿の木
太さは一抱えばかり
高さ 広がりとも 十メートルほど
その下で育っていたころ 庭先から仰ぎ
木が新芽を出すと 春だと心がうき
白い花を咲かせると 初夏だと心若やぎ
茂りを増していく葉
次第に緑を濃くし 彩ってゆき
つれて 実も太り 色付いてゆくのを見て
季節を感じた木だ
この木の、地上一・五メートルぐらいのところから左右に大枝が張りだし、上
に伸びた大幹の、地上六メートルぐらいの所が、さらに、三つ叉になってい
て、この辺りが木のほぼ中ほどで、夏には、三つ叉を囲んで、大きく濃い緑
の葉が茂って空を隠し、ころ合の涼み場になった。
に伸びた大幹の、地上六メートルぐらいの所が、さらに、三つ叉になってい
て、この辺りが木のほぼ中ほどで、夏には、三つ叉を囲んで、大きく濃い緑
の葉が茂って空を隠し、ころ合の涼み場になった。
夏、晴れた日には、毎日のように涼みに登った。
ときに羽を休めていた、ひよ鳥が物音に驚き、大きく羽撃いて飛び去る。
鳴き咽んでいた蝉も声を潜め幾匹か飛び去り、蝶やとんぼも飛び立つ。
三つ叉の枝に股がり、幹に背をもたせて涼む。
蝉が舞い戻って来て、すぐ傍の手が届く枝に止まって鳴き始め、蝶やとん
ぼも、また、枝に戻って羽を休める。
ぼも、また、枝に戻って羽を休める。
ほかの枝々には、どこから上ってきたのか 雨蛙も居る。
くわが虫が居る。
かまきり、すいっちょ、いなごも。
蟻が木やに、に列をつくっている。
蜂の巣があり傷んだ柿に蜂が集まっている。
蜂だけは驚かず私を刺しにこないで
巣の子に餌を運び続けている
雀が茂りを潜り飛び込んで来て枝に止まり、
頭を傾げ傾げ
私を見つけたのか 見逃しているのか
餌を探し 枝々を渡り始める
蝶やとんぼも憩の場所を変えて飛び回り
ときに 枝と間違えて肩や腕に留まる
聞違えて留まったと分かっていている
でも 慕われていると思いたい
取りたくない
くもが巣を作っている
巣に柿の葉を千切って掛ける
くもは巣を破って葉を落とし
巣を前の通りに うまく繕う
今から巣を張るくもが糸を垂らしている
風にそよぐ糸の端が枝にくっ着くと
その糸を伝って次の糸を張り
それを また 伝って
傘の骨のように巣の骨組を造り
それに、網を張っていく
実に巧みに張る
見ていて退屈しない
巣が出来上がる
巣の真中で憩いながら餌を待つ
賢い 巧みだ 感心だ
嫌なくもなのだが いじめる気にならない
だが ときに 巣に蝶やとんぼが引っ掛かる
くもは素早く餌に向かう
とたんに くもが憎くなって叩き落とし
蝶やとんぼに絡まった糸を取ってやる
羽を傷めないように取り
逃がしてやって ほっとする
でも、嫌いな虫が巣にかかると
そのままにしておく
蝉が鳴き競べをしている
幾種類居るのか
ときに柿の葉が風にそよぐ
その音に驚き ひととき鳴き止み
また 鳴き咽ぶ
穀をかむった蝉の子も居る
殻から抜け出ようとして
枝に爪を立て 殻を割り 頭を出し
仰向けに反り返る
出てきた「みどり子」は
そのままじっとしている
やがて 空気に馴れ
次第に緑色を消し
蝉の色に変わり
強そうになり
羽を動かし
歩き始め
一人前の蝉になる
この蝉を取る気はしない
せわしいのは 雀
枝の上で跳ね跳ね 首を傾げ
枝々を飛び渡って餌を漁る
人が居るのに知ってか知らないのか
こちらも 素知らぬ振りで
見て居ようと思わせる
いそがしいのは 蜂
餌と巣の間だけを飽きずにき行き来する
人を無視しているようなのが
ちよつと 気にくわないが
健気だと思わせる
この雀や 蝉も、取ったり苛める気にはならず、そっとしておいて見ていた
い。
い。
他の木に、留まっている蝉を見ると、取ろうとし、蜂の巣を見つけると、その
場で叩き落すし、雀が止まっていると石を投げ付けるのだが。、
場で叩き落すし、雀が止まっていると石を投げ付けるのだが。、
そんなことを感じ、虫たちの生態を見ながら涼んでいるとき、蜂に何回か
刺され、ひととき、腹が立ったが、ほかで刺されたときと違って、あまり、蜂を
憎くいとは思わず、巣を叩き落とそうとはしなかった。
刺され、ひととき、腹が立ったが、ほかで刺されたときと違って、あまり、蜂を
憎くいとは思わず、巣を叩き落とそうとはしなかった。
このころ、我が家の離れの二階の軒下に、直径四十センチぐらいの「ぬっ
こ」蜂の巣があり、三年ばかり、そのままにしていた。
こ」蜂の巣があり、三年ばかり、そのままにしていた。
その間、初夏から秋にかけて、黒い蜂が「うんうん」うなりながら家の周りを
飛び交う。
飛び交う。
こうなると、我が家は家族七人に、飼っている、牛、兎、鶏、鯉。それに、
軒端の燕と蜂が加わり、更に、大柿の木で憩う鳥や虫たちを加えると、三
百人、頭、羽 匹を超す大家族になる。このような大家族になると、退屈な
どしている暇がなくなる。
軒端の燕と蜂が加わり、更に、大柿の木で憩う鳥や虫たちを加えると、三
百人、頭、羽 匹を超す大家族になる。このような大家族になると、退屈な
どしている暇がなくなる。
そのうちの「ぬっこ」蜂も心得ていてなのか、どうなのか分からないが、家
の者・家族を刺さない。
の者・家族を刺さない。
二階の縁で巣から二メートルばかりの所で昼寝をしていても刺さないので、
そのままにしていた。
そのままにしていた。
だが、三年ばかりたってから、他家の人を刺してしまったので退治しなけれ
ばならなくなったのである。
ばならなくなったのである。
それより前、大谷と言う家に、大梨の木があり、木の「すのこ」に、ぬっこ蜂
の巣があって、親指ぐらいの黒い蜂が飛びまわっていて怖く、私たちは、そ
この道を通れなかった。
の巣があって、親指ぐらいの黒い蜂が飛びまわっていて怖く、私たちは、そ
この道を通れなかった。
しかし、大谷の人は、
「この蜂は内の者を刺さんのや」
と平気で、飛び交う蜂の内を行き来していて、
「ここを通るときは内の者と一緒に通ると刺されない」
と私が通るときは、いつも傍に付いてくれていた。
そんなわけで、
「蜂が居るから梨を取られなくてよい」
と、何年かそのままにしていたのだが、大谷の人が、梨を取っていて、うっ
かり、梨を巣に落とし込んでしまった。
かり、梨を巣に落とし込んでしまった。
蜂は驚き、気が転倒し、木の持ち主である人を総攻撃で刺してしまったので
ある。
ある。
このとき、即座に蜂を退治した。
その経験者が今回の蜂退治に参加していたのである。
初秋の夜、蜂が静まるのを待って、攻め方は、目だけを残して体全体を厚
い布で覆い、竹竿の先に石油缶を取り付け、缶に綿を詰め、石油を浸ませ
て火を付け、これで巣を火攻めにして攻め落とした。
い布で覆い、竹竿の先に石油缶を取り付け、缶に綿を詰め、石油を浸ませ
て火を付け、これで巣を火攻めにして攻め落とした。
その夜、蜂の子飯を炊き、常に食べられる物ではないから近所の方々を招
いた。
いた。
皆は
「珍しい」
と喜んで食べていたが、我が家の者たちは、少々、箸をつけただけだった。
私は蜂の子を除けて食べた。
これより、ずっと前から、私の部屋は離れの二階で、その軒下に巣が有った
から、蜂のすぐ傍で毎日、蜂の生態を見つくしていた。
から、蜂のすぐ傍で毎日、蜂の生態を見つくしていた。
蜂の「うなり」を聞きながら昼寝をしていて、
「今日は、えらい静かやな」
と安心したり、
「あ、今日は、うなりがおかしい。巣に敵が近付いているな」
と察知し、鳥などの敵を追っ払ってやったり、敵に追われたり、迷って、部屋
に入って来た蜂を部屋に囲い、しばらくしてから、窓を開け放って逃がして
やったりしていた。
に入って来た蜂を部屋に囲い、しばらくしてから、窓を開け放って逃がして
やったりしていた。
部屋に入ってきた蜂は私を刺さないし、私は蜂を、一匹も殺さなかった。
、
、
そのようにしていたから火攻めに合った蝉に少々哀れを覚え、蜂の子飯
を気兼ねなく食べることができなかった。
を気兼ねなく食べることができなかった。
私だけではなく、我家の者はすべて同じ思いをしていたのではないだろう
か。
か。
人の情けとは不思議なもので、ちょっと考えられないような情けをおぼえる
ものである。
ものである。
それは、そのときどき、その人と相手によって違うようだ。
わが家では、燕の子が誤って庭に落ちると、大事に巣に戻してやって、そ
の子の様子を、家族、皆が気遣って見守るときが度々あった。
の子の様子を、家族、皆が気遣って見守るときが度々あった。
なのに、そこらあたりの餌を漁り回り、人を避けて逃げ去る雀を、わなにか
けたり、打ち落とした。
けたり、打ち落とした。
もし、雀が、わが家に来て、大柿の木でと同じように、はばかりなくしたり、
子を育てたりしたら、私たちは、燕にしてやるのと同じようしてやりたくなる
のではないだろうか。
子を育てたりしたら、私たちは、燕にしてやるのと同じようしてやりたくなる
のではないだろうか。
それから、私は都会に出て、ずっと後に家を持つことになった。
あちこち探しているうちに桜と、しゆろの木がある家にゆき当たった。桜の
木は、太さハ十センチ、高さ八メートルばかり、しゆろは、高さハメートルほ
どで大木のうちに入る。
木は、太さハ十センチ、高さ八メートルばかり、しゆろは、高さハメートルほ
どで大木のうちに入る。
都会では少ない。私は、大柿の木が念頭にあったから両木に惹かれて住ま
うことにした。
うことにした。
桜の木の梢に、ときどき雀がやってくる。だが、私が庭に出ると、いそぎ、
飛び去る。前の大柿の木でと同じようにできると良いと、雀の巣箱を造って
桜の木に取り付けてみたのだが、雀は、入らない。
飛び去る。前の大柿の木でと同じようにできると良いと、雀の巣箱を造って
桜の木に取り付けてみたのだが、雀は、入らない。
諦めてしまって、幾年か後、子供たちが成長し、小鳥を飼いたいと望みだし
たので、カナリヤを飼うことにした。
たので、カナリヤを飼うことにした。
鳥篭をときどき、縁先に吊しておくと、雀が近付いてきて、カナリヤが庭に落
とした餌を啄み始めた。
とした餌を啄み始めた。
そこで、パン屑を庭に撒いて置くと、桜の木にやってくる雀が数を増し、庭
に降りてくる雀も増えて来た。
に降りてくる雀も増えて来た。
このころ、小学五年生だった長男、三蔵ぐらいだった次男、それに、ワイフも
パン屑を撒いて雀を待つようになり、なお、数が増えできたので、米屋から
粉米をもらって撒くようにした。
パン屑を撒いて雀を待つようになり、なお、数が増えできたので、米屋から
粉米をもらって撒くようにした。
都会の真中にある住家の木に雀が群がってさえずり、朝早くには、寝床
の、つい、外の庭で餌を啄む。
の、つい、外の庭で餌を啄む。
山里の家に居たときにも無かったことである。嬉しい。
ワイフや子供たちも同じ思い。餌を撒き続けながら雀の様子を観察し始め、
「どれかが先に桜の木の梢に止まって、様子を見てから仲間を呼んでくる」
と言う。それほど賢くないと思ったが、よく見ると、そのようにしているようで
ある。
ある。
皆は、だんだん、興味を増して、細かく観察するようになり、
「桜の梢で監視しているのが居る」
「どれか、一羽が先に餌を啄み、それに従って啄む」
「どの雀は威張っている」
「あの雀は大人しい」
「あの雀は少しびっこを引いている、それをかばってやっているのも居る」
と、詳しく見ている。
そのうち、人に馴れ、庭から家の方に近づいてきて、テラスに置いてある
皿の餌を啄み、傍に居る人を恐れなくなり、終に居間に入ってきて食卓の
御飯粒を啄みはじめた。
皿の餌を啄み、傍に居る人を恐れなくなり、終に居間に入ってきて食卓の
御飯粒を啄みはじめた。
「今日は、どの部屋まで入ってきて、迷わずに出ていった」
と、ワイフは夕食時に報告し、皆は、雀が人を恐れなくなり、我が家にして
振る舞うのに興味を増していく。
振る舞うのに興味を増していく。
そうした、ある日曜日の午後、子供たちが、柱の陰から居間を覗いてい
る。
る。
見ると、雀が数羽、部屋に入ってきて、雀のために食卓の皿に入れてある
飯を啄んでいる。水を飲んでいる。そして、床を歩き回っているではない
か。
飯を啄んでいる。水を飲んでいる。そして、床を歩き回っているではない
か。
とうとう、三人は彼らをここまで手懐けて家族にしてしまった。そして、二十
羽を超す家族の生態を見て労わり、触れ合いを楽しんで退屈しない。
羽を超す家族の生態を見て労わり、触れ合いを楽しんで退屈しない。
この雀を追っ払うことはできない。
そのうえ、子供たちは、蝉取りが大好きな年ごろなのに、我が家の桜の木
に居る蝉を取らずに公園の木へ取りに行くし、桜の木の蜂の巣を見ている
だけで、落とそうとはしない。
に居る蝉を取らずに公園の木へ取りに行くし、桜の木の蜂の巣を見ている
だけで、落とそうとはしない。
これを見て、私が、若いきと昇った大柿の木でのことをつぶさに思い出し、
あの木のお陰で鳥や蝶、蜂とまでも無理なく付き合い、生態を見ながら育っ
た。
あの木のお陰で鳥や蝶、蜂とまでも無理なく付き合い、生態を見ながら育っ
た。
あの時は意識していなかったが、楽しい時代だったのだ。
それに、あの木のお陰で桜の木のもとに住まおうとし、雀を誘おうとし、子
供たちやワイフまでも誘い込んで、また、楽しい想いをすることができたの
だなと思い至った。
供たちやワイフまでも誘い込んで、また、楽しい想いをすることができたの
だなと思い至った。
そして、前に、三年間接していた「ぬっこ」蜂のことも思い出し、あのきと、火
攻めにあった蝉を哀れに思い、でも人に、
攻めにあった蝉を哀れに思い、でも人に、
「蜂が可哀相だ」
などと言ったら笑われるだろうと、蜂にまで情けを覚えることに割り切れな
いものを感じていたのだが、あれで良かったのだ、それが人なのだと思い、
それから、大柿の木で蜂に刺されたとき、
いものを感じていたのだが、あれで良かったのだ、それが人なのだと思い、
それから、大柿の木で蜂に刺されたとき、
「この蜂は、俺がこの木で共に居る人だということを知らないのだろう」
として、少々、腹が立っても、あまり、憎まなかったのだろうなどなどと思っ
た。
た。
その、大柿の木に登るのは「涼み」だけで
がなかった。
花が咲いたら見に。新緑のころには萌え出を見に。そして緑の中で涼み、
秋口から熟柿ができるのを待ち焦がれて取りに登った。
秋口から熟柿ができるのを待ち焦がれて取りに登った。
取り遅れると、雀や百舌たちに先取りされるから彼らと競り合いをしてい
た。
た。
秋祭りには、柿の葉寿司の葉を取りにも登ったから、蜂の巣作り、子育
て、蜂の子が産み付けられてから羽を出し、飛び立ち、空き巣になってゆく
のを総て見ていた。
て、蜂の子が産み付けられてから羽を出し、飛び立ち、空き巣になってゆく
のを総て見ていた。
それに、秋には、柿の葉が彩ってゆくのを見るのが楽しみだった。濃い緑
の葉に黄色い模様ができ始め、秋が深まるに連れて、黄、茶、赤と色を増
やしながら彩りを変えてゆく。
の葉に黄色い模様ができ始め、秋が深まるに連れて、黄、茶、赤と色を増
やしながら彩りを変えてゆく。
やがて、紅葉の内に居るようになり、日当たりの、ぷ厚い葉、日陰の薄い葉
とそれぞれ適って彩り、それを、長い間見蕩れていた。
とそれぞれ適って彩り、それを、長い間見蕩れていた。
更に秋が深まると、色付いた葉が、そっと枝を離れて舞いながら散り、微
風が渡ると降るように散って空を広く見せ、色付いた実が青空に絵を描き、
それに、木の下一面に散っている葉もまた、良い絵だった。
風が渡ると降るように散って空を広く見せ、色付いた実が青空に絵を描き、
それに、木の下一面に散っている葉もまた、良い絵だった。
そして、この柿の実は渋柿だったから、干し柿を作る柿取りに登った。実
が着いている枝を竹竿で折り取ると、蜂の空き巣が着いていて、巣立ちを
想わされながら柿を取った。
が着いている枝を竹竿で折り取ると、蜂の空き巣が着いていて、巣立ちを
想わされながら柿を取った。
この木と、木に住まう鳥や虫たちと十年以上付き合った。
なかなか忘れられず、木をもとにして起きたごとごとを、のちのち、残してお
くことも含めて記すことにした
くことも含めて記すことにした
里の雪降る正月
初冬の夜明け
雪が積もっている
と感じる夜明け
風のそよぎも 木の葉のそよぎも
雪に閉ざされている、
と感じるものしずけさ
障子を開ける白一色
昨日の緑の山々が
一夜の内に白い山に変わっている
この光景と急変に驚く
朝飯をかっこんで表に飛び出す
寒くない
新雪に足跡を付けながら歩き
立ち止まり
葉に雪をためてたわむ木々を仰ぎ
手をかざし 目を細め 白峰を眺めまわす
東 西 南 北にそびえる白峰は
標高 千メートルばかり
昨日は その緑峰の元に居た
今日は 白峰に囲まれている
この変わりばえ
この光景にふれられるのは幸せ
初雪が降った
暮れが迫った 大掃除
と言っても山里の家
周りに 雪を冠った木々や草々
南天があり さつき 山茶花があり
雪だまりがある
その雪すべてを除くは野暮ったい
暮れはさらに迫った
その日 朝 餅米を蒸しはじめ
せいろを四 五段積んで蒸す
湯気が勢いよく吹き出し
餅米特有の句をともない
家の内に立篭る
外は雪山
それで より家の中と人の温もりを感じ
餅を握る手から心へ伝わってくる温もりを心地よく感じる
餅つきが終った
正月は間近
女手は 豆腐やこんにゃくを作り
子供手は 雪山へ行き
松 竹 梅を切る
雪に清められた木だ
と感じながら切る
男手は 神棚の掃除
家の修理
注連縄を造り
正月の飾りつけ
暮れには家族 皆 忙しく立ち働く
この忙しさがあってこそ 心改まる迎春
大晦日の夜
正月の神火を迎えに氏神へ
神社を囲う大樹の森は雪を冠り
大屋根となって神域を覆っている
雪屋根のもと
たき火をしながら神火を待つ
十一時過ぎ
神主は服装を正し
松明を神前に奉り
祝詞を捧げる
人々はたき火を消し
手にしている明かりも消す
神前の灯明だけが額ずく神主の姿を照らす
祝詞は森に浸み入るように響き
人々の心は鎮まってゆく
神主は祝詞を終え
神前の灯明から松明に火を移す
神主が捧げる火は雪屋根の内を明るく照らし
雪の上に火の粉を降り注ぎながら
神前の石段を降りて来る .
社や大樹や石段は
より神聖な神域を現すごとくに見え
人々の心はより鎮まる
松明から神火をいただいて帰る道々
振り返る
家々へ 正月を運ぶ火が
点々と雪の上を動いていく
深夜
家中の火をすべて消し
家族は服装を正して神火を迎え
まず神棚の灯明に移して神を奉り
次に 整え直した かまどに移し
神火の移火で雑煮を煮る
家中の火をすべて神火で点し
暮れを越え元旦を迎える
零時過ぎ
外の 音なく降り積もる雪の
音を感じながらいただく雑煮は
このときだけの味
元旦の朝 わざわざ新雪を探し
足を埋め 身が清まるのを感じ
山々を より清らかな白だ
と眺めまわす
そうだ
正月には雪が積もっているもの
正月と雪を切り放しては考えられない
そこにいる私は幸せ
雪が少ない年
田畑や山にだけ残し
道々の雪が解けている年
この正月は雪がないようだ
と話していた大晦日の夜中から降り始め
元旦の朝 全く汚れのない新雪が山々を覆う
このような年は格別に
正月だ と感じる
大寒 水は肌を刺すように冷たく
氷は肌に凍てつく
庭も畑も凍る
木々の葉も草葉も
にわとりは鳴かず
鯉は動かず ′
雪は粉雪
根雪のかさを増してゆく
二月 暦の上では節分 立春
だが 山野は根雪に覆われたまま
その上に なお しんしんと雪が降る
氷は まだ堅い
田も畑も眠ったまま
木々も草葉も
梅はまだ
うぐいすもまだ
火だけを恋う ′
三月 節句の菱餅は柔らかい
餅が柔らかいのか
春を迎える心が柔らいでいるのか
氷も柔らぎ
雪はまばらで ぼた雪
竹の葉に積もると落ちない
竹は しわりながら耐えに耐え
力つきて割れる
その音が夜空に響くとき
竹を割ったようとの例えのとおり
いさぎよいと感じる音
そんな夜が幾夜
かあり
梅 桃が咲き始め
うぐいすが つたなく 鳴きはじめる