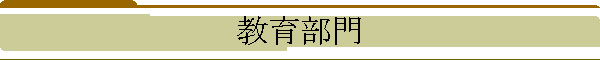『イリュージョン』リチャード・バック・著 村上龍・訳 集英社文庫
(1987年6月12日号)
リチャード・バックは不思議な作家である。彼が有名になったのは『かもめのジョナサン』という、はぐれ者のかもめがカモメの救世主になる物語であったが、彼はそれを、ある声に導かれて書いたという。『イリュージョン』は、救世主を廃業した救世主の物語であり、いわば『ジョナサン』の続編であるが、この作品もまたインスピレーションに満ちている。
冒頭でイントロダクションとして、ある救世主の覚醒と、彼の活躍、そして廃業までが簡単に紹介される。この救世主がドナルド・シモダ、愛称ドンである。物語は、リチャードという男の一人称形式で語られる。彼は、放浪の飛行機乗りであり、各地で客を飛行機に乗せて生活をしている。
リチャードが、旅先で、救世主廃業後、同じく旅回りの飛行機乗りをしているドンと出会うところから物語は始まる。やがてリチャードは、ドンの起こす奇蹟を自にし、彼が救世主であることを知り、弟子となる。ドンはリチャードに『救世主入門』というテキストを与えるとともに、風変わりな方法で教育を始める。ドンは、この世全てがイリュージョン(幻影)であることを説くのである。
リチャードは、旅を続ける中で、着実に学んでいく。ところが、ある町で、ドンがラジオに出演し、挑発的な発言をしたことから、物語は急転回する。ドンの発言に怒った人々が、二人を襲うのである。ドンがその力によって町を飛び立とうとした時、彼を守るはずの男に撃たれてしまうのである。そしてまたリチャードは一人になる。
この作品中に『救世主入門』の言葉が、引用されるのであるが、どの言葉も意味深く、一生かけて考える価値がある。一部を紹介しよう。「三歩先を見る能力を常に活用せよ。さもなくば、常に三歩後を歩むことになる。」「いかなる種類や程度のものであっても、困難は君達に何かを与える。君達は、言うなれば、困難さを捜しているのである。困難さが与えてくれるものには、価値があることを知っているからである。」いかがであろうか。『イリュージョン』を読んだら、『救世主入門』の言葉の意味を考えてほしい。そして君の考えを聞かせてほしい。その時、静かな爆発が君に起こるかもしれない。あるいは数年後、あるいは千年後。
『内村鑑三』鈴木範久・著 岩波新書 (1988年2月6日号)
内村鑑三は、新渡戸稲造、植村正久らと並ぶ日本近代の先覚者的キリスト者である。江戸時代の禁教政策で息の根を止められていたキリスト教は、これらの人々によって一躍世界の最高水準に達した。鑑三は高崎藩の儒学者の子として生まれ、儒学教育を受けて育つが、札幌農学校入学によりクラークの遺風を受けて、キリスト教信者となる。
鑑三の名を有名にしたのは、一高在職中の教育勅語への不敬事件と、日露戦時の非戦論であろう。これにより彼は非国民の汚名を着せられるが、彼ほど日本を愛した者もいない。イエスと日本(JESUSとJAPAN)という二つのJに彼の生涯は捧げられた。
新渡戸稲造は『武士道』を書いたが、この人達の精神は、キリストを主君と仰いだ武士道と言える。鑑三の門下には、キリスト者では無教会派の矢内原忠雄、塚本虎二、文学では、志賀直哉、有島武郎、小山内薫がいる。
『孔子』井上靖・著 新潮社 (1990年6月28日号)
孔子は五十歳を過ぎてから、故国魯を後にして、中原放浪という諸国歴訪の旅に出る。この旅に終始供をしたのが顔回、子路、子貢である。主人公の焉薑(えんきょう)は中原放浪の途中で一行に加わり、孔子の従者を務め、孔子の死後隠棲したという架空の人物である。全章彼の回想を中心として、中原放浪の思い出、天命論、孔子の言葉の解釈、三人の弟子の人物論などが語られる。
本の帯に「天命とは何かを問う」と副題が付されているが、作者が特に力を入れているのが、天と天命の解明である。これが孔子の原動力と見なされている。天命論においては、天命の存在については確信しながらも、天命と運命の関係について作者が悩んだ跡がうかがえる。作者は天命と運命を並列的に考えているようであるが、はたしてそうであろうか。孔子の力強い言葉を読む時、天命の前に運命無しと私には感じられるのである。
「ハーンの宗教意識」(「小泉八雲来日百年特集」より) (1990年10月27日号)
ギリシア・イギリス・フランス・アメリカ・日本とたどったハーンの旅は心の旅でもあり、彼は東西の宗教の実体験者であった。しかも彼の魂は詩人的側面と哲学者的側面を具有していたために、彼は宗教を心情面・哲理面等様々な局面から理解する力を持っていた。またアメリカでの新聞記者生活は、ハーンをイデオロギーから現実を解釈するのではなく、虚心に事実を受容することからその背後にあるものへと向かわせた。
ギリシア人を母にもったハーンにとって、ギリシア神話のような多神教的世界がもともと親しめる世界であったようだ。イギリス・フランスで受けたキリスト教教育、特にフランスでの厳格なローマ・カトリック教育はハーンには耐えがたいもので、ハーンをキリスト教から決定的に引き離した。しかし、このことはハーンが無神論者になったことを意味するものではない。ハーンは霊的に敏感な体質であったようで、幼年期に何度も幽霊を見ており、霊的世界への関心は人一倍強かった。加えて、ギリシア的世界を知っていたことがキリスト教への反発即無神論者という西洋人の不幸なパターンから彼を救った。
アメリカ時代にハーンの宗教意識は目覚め始める。この時代、仏教書を英訳と仏訳で数種類読んでおり、かなりの理解をしていたと思われる。また古事記の英訳を読み、ギリシア神話と同じ多神教世界を見出し、日本への関心を深めていた。一方、アメリカ時代のハーンの思想に大きな影響を与えたのが、イギリスのスペンサーの進化論哲学であり、ハーンの仏教解釈にその影響が大きい。
憧れの国日本にやってきたハーンが赴任したのは、神話の国出雲であり、このことがハーンの神道理解、日本理解を助けたのは言うまでもない。ハーンは西洋人の学者が神道を理解できないのは、記紀や注釈書の中に神道を求めるためであることを見抜き、神道の本当の姿は実は国民の心情の中にあり、「最も高い感情が宗教的に発現したものである」と看破している。この後もハーンの神道研究は進み、その根底に先祖崇拝があり、民族の先祖としての皇室崇拝と結びついているのを見る。また皇室は権力の中心ではなく、国民の心情的中心であり、宗教的な王朝は永続性に対する異常な力を持っているとしている。このことは太平洋戦争の敗戦時における皇室の存続にもあてはまるだろう。
儒教については孝道として日本の先祖崇拝と結びつき武士道は忠義の宗教としている。さらに仏教も民間信仰としては先祖崇拝があり、この点において神儒仏は実質上融合しているのである。加護と感謝の一種の日本教を見出している。
しかし、ハーンの仏教理解はさらに雛解な、大乗仏教の哲学へと及んでいる。ハーンはそれをスペンサーの進化論哲学と結びつけて理解している。人間が天界と地上を輪廻しながら涅槃(ねはん)に達していくことを、波状に進化する過程と見なしている。その点で仏教は一種の霊的進化説ある。西田幾太郎は、ハーンは自然科学的法則の裏に「永遠の過去より永遠の未来にわたる霊的進化の力が働いている」のを見ていると評している。また涅槃は窮極の絶対、一元的実在であるとしている。涅槃に達した諸仏が併存する状態は多元的一元論であるとしている。この一元は非人格的一神とも言えるから、このことは多神教と一神教の融合と言える。このように全てを包含する仏教をハーンは「許容の宗教」と呼んでいるが、仏教に多神的寛容性と一神的統一性の両面を見出したのである。
ハーンが日本の神道や、特に仏教にこのような傾倒を見せたのはなぜであろうか。ハーンは幼児期父母の離婚にあい、父には捨てられ、瞼の母を慕っていた。キリスト教の父なる神に見捨てられ、西洋文明の殺伐した合理主義、科学万能主義は、詩人的・宗教的魂を持つ彼にはなじめなかった。父性原理の強い宗教と文明に失望した彼は心の奥で母性原理の強い宗教と社会を求めていたと言えよう。ハーンはそれを日本に見出したのである。天照大神という女神を中心とする神道や、観音信仰等母性的包容性を持つ仏教とそれが生きている社会、そして何よりも出雲で妻となった女神セツは優しさと美の世界を求める彼に深い安らぎを与えたのである。
映像ライブラリーについて (1991年2月2日号)
二学期の12月17日・18日の両日、化学講義室・生物講義室を使って、映像ライブラリー『フィールド・オブ・ドリームズ』を上映した。修道杯とかさなり、どれくらいの参加者があるか、不安であったが、両日で、中学生を中心に70余名の参加者があり、盛会であった。
上映後、簡単なアンケートを行なった。結果を見ると、要望として、テスト終了のたびごと、もしくは一カ月に一回こういった催しを計画して欲しいというものが多く見られ、苦言としては、画面が小さくて、字幕が見にくかったという意見が寄せられた。今後の開催計画や作品選定に参考にしたいと思う。
映像ライブラリーは、これまで10月末から11月上旬の読書週間に行なってきたが、映像文化の著しい普及で、読書のきっかけが、映像からという人が増加しており、図書館としても、映像ライブラリーに積極的に取り組んでいこうと考えている。
今回の上映作品『フィールド・オブ・ドリームズ』の原作は、W・P・キンセラによる『シューレス・ジョー』(文春文庫刊)である。ぜひ一読して、映像との差などを楽しんでほしい。また、ぜひこんな作品を映像ライブラリーとして、上映してほしいというものがあれば、図書委員を通じて、もしくは「こえ」のポストなどを通じてどしどし申し出てほしい
「特集 環境問題」より (1991年10月28日号)
我々が環境問題を意識するようになったのはいつのころからだろうか。我が国で言えば、戦後昭和四十年代に公害問題が多発した。しかし、その時代は、一地域、一企業の問題という傾向が強かったように思う。昭和五十年代に入り有吉佐和子の『複合汚染』は全ての日本人が汚染にさらされていることを知らせた。昭和六十年代環境問題は世界的問題となった。この速度は今後十年が正念場であることを暗示するように思う。
「レイチェル・カーソンを読む」
現在人類が直面している環境問題にいちはやく気づき、綿密な調査と科学的資料に基づいて、化学物質による汚染問題を提起したのが、アメリカの女流作家、レイチェル・カーソン(一九○七〜一九六四)であった。彼女の著書『沈黙の春』は、ベストセラーとなりアメリカ中に大反響を巻き起こした。この著書がなかったら、人類が環境問題に気づくのは十年は遅れたであろうと言われている。ここでは彼女の業績を知るための基本的な書籍をいくつか紹介し、環境問題を考える入門としたい。
『レイチェル・カーソン 沈黙の春をこえて』
キャサリン・カドリンスキー・作 上遠恵子・訳 祐学社
彼女の伝記として最も読みやすい本と言えるのが本書である。レイチエル・カーソンはアメリカのペンシルベニア州の田舎に生まれた。小さい頃の彼女は、海へのあこがれと、作家になることへの夢とを合わせ持っていたが、十歳の時に雑誌の懸賞小説に応募し、受賞している。海へのあこがれを取るか、それとも作家になるか、この悩みは大学にまでつきまとうが、結果的には彼女は、両方を取ることになる。
大学では彼女は初めは英文学志望であったが、生物学を専攻し、海洋生物学者への道を歩み始める。彼女が初めて海を見たのは、大学を卒業した年であった。その時に見た銀色に輝くマボラの群れに彼女は感激しなぜか突然涙があふれてきたと述べている。科学者としての彼女の根底には、生命の美を感じる心と、生命への畏敬とが常にあったが、このでき事は、それを物語っているように思う。
大学院卒業後、漁業局に勤めた彼女は、勤務のかたわら、海を題材にした著作にとりかかる。こうして書かれた『われらをめぐる海』はベストセラーになり、彼女は漁業局をやめ著作に専念することとなるのである。
作家としての地位を固めた彼女のもとにやがてDDTを始めとする農薬の被害の情報が届き始め、彼女は問題の重要さに気づき、独自の調査を始める。彼女自身生物学者ではあったが、大量の専門知識を必要とするこの仕事は、彼女の体力を消耗させ、彼女はガンにかかってしまうのである。治療と並行して執筆された本は、四年の歳月をかけて一九六二年に出版された。『沈黙の春』である。出版されるや否や、この本はアメリカ中に大反響を巻き起こした。しかしガンは既に体中に転移し、彼女は二年後の一九六四年、五十六でその生涯を閉じることとなるのである。
『沈黙の春』レイチェルカーソン・著 青樹簗一・訳 新潮文庫
彼女の主著であり、生命をかけて書かれた本である。この本は科学者としての正確な知識に基づいて書かれているが、単なる知的な告発書ではなく、作家としての彼女の生命への姿勢がいたるところに表わされている。その意味では生命論の書とも言えるのである。冒頭部分の「明日のための寓話」は、この部分だけでも読んでほしいところである。アメリカのある田舎町、四季折々に野花の咲き乱れる美しい町であった。しかしある春のこと、暗い影がしのびよった。鳥はけいれんを起こし、鳴き声は消えた。沈黙の春であった。家のひさしやといには白い粉がたまっていた。それが沈黙の春をもたらしたのであった。即ちDDTを始めとする農薬である。一九六○年当時、アメリカ大陸のいたる所でDDTの空中散布が行われていた。その恐ろしさを初めて警告したのが本書である。
『われらをめぐる海』レイチェル・カーソン・著 日下実男・訳 早川文庫
『沈黙の春』を書く前、作家としての名声を確立し本である。現在文庫本で出版されており、手に入れやすい。海洋生物学者としての知識と、自らの経験とが活かされた本である。いたるところに散文詩的な美しい表現があり、単なる知識以上のものを与えてくれる。アメリカでベストセラーとなったのもうなずける。
全体として感じるのは母なる海のすばらしさである。海は単なる水たまりでもなく漁場でもない。生命のふるさとなのである。我々が海に感じるなつかしさはどこからくるのだろうか。
コラム「背表紙」(「特集 環境問題」より) (1991年10月28日号)
アメリカにおける環境問題の先駆者が、レイチェル・カーソンなら、日本におけるそれは田中正造と言える。田中正造(一八四一〜一九一三)は長い間忘れられた存在であった。彼が明治の人であり、人々の記憶から遠ざかったこともその一つであるが、自然を守り人民を守るために、敢然と政府に立ち向かい、天皇にまで直訴したというその行動が、一種の反逆者として異端視されたことが主な原因であろう。大戦前の雰囲気で言えば彼は正に非国民であったのである。日露戦争に反対した内村鑑三とともに、彼は黙殺されなければならない偉人であった。内村鑑三についての評語に「蹴倒された後に拝み倒される。」というのがあるが、正に田中正造をめぐる世間の評価もその通りであった。
足尾鉱毒事件は、古河市兵衛の経営する足尾銅山によって引き起こされた。足尾銅山は規模の拡大とともに銅山周辺の木を乱伐し、鉱毒を流し続けた。その結果、大洪水が起こり、渡良瀬川の流域住民五十万人が田畑や人体に被害をこうむった。しかし、政府は古河の味方をし、住民の声は無視された。政府にとって日清日露の戦争を遂行するために古河の銅は必需品だったのである。国栄えて人亡ぶ。富国強兵策の影の部分が足尾鉱毒事件であった。
田中正造は反対運動の先頭に立ったが、彼の期待は裏切られ続けた。憲政にのっとった順法的対策を彼は求め、暴力を一切禁止したが、運動は追いつめられ、被害の中心地谷中村は水没させられた。正造は水びたしの谷中村で残留住民と最後の抵抗をし、そこで亡くなった。晩年の彼の思想は政治、宗教、環境の全般にわたり、クリスチャンとして神無き時代の破壊的性格を鋭く指摘している。人々が生命の本質を見誤る時、いかに全てが狂ってくるか。世紀末の現在、彼の思想はますますその輝きを増しているように思う。
儒教の倫理(「特集 論語の世界」より) (1992年2月1日号)
昨年の十二月、山本七平氏が亡くなられた。氏は『日本人とユダヤ人』をはじめとする一連の著書で、聖書と古典の教養を背景にした山本学というべきものを開いた人である。氏は青山学院の出身で父親が内村鑑三の心酔者であったために聖書の理解が深いのだが、その氏に『論語の読み方』という著書がある。聖書と論語は一見結びつきそうもないものなのだが、中国学の大家であった吉川幸次郎と、聖書の大家であった内村鑑三がともに、論語と聖書を並行して読むと、両者の理解が進むと語っていたことが書かれている。
これは一見意外に感じられることだが興味深いことである。内村鑑三は不敬事件を起こした人なので、儒教の対極にある人物のように考えられるがそうではない。彼は幼少時代に漢学者であった父親のもとで儒学を深く学んでいる。江戸時代の儒学であるから、忠孝を中心としたものに違いないが、この儒家精神がそのまま青年期に接したキリスト教に受け継がれている。即ち忠孝の対象が、地上の君主から、天の主の神と救い主のイエスに代わったのである。彼の強さを支えていたのは実は儒教精神であったと思われる。儒教と武士道がかつてほどの力は持たない現代ではもはや鉄の人は現れないかもしれない。
儒教における忠孝とキリスト教における信仰は心理的には同一の現象であって、心の縦糸と言えるが、これに対する横糸は儒教における恕とキリスト教の隣人愛である。孔子は徳の根底に仁を置き、その縦の形を忠孝、横を恕、汎愛としたが、キリスト教の愛も縦に表せば信仰であり、横に表せば隣人愛であるから、両者は同一の心理構造を持っている。吉川幸次郎も内村鑑三もこの点に気づいていたように思われる。よき儒者はよきクリスチャンとなり、よきクリスチャンはよき儒者となる可能性を持っている。
そしてこのことと関連するのがキリスト教文化圏である西洋と儒教文化圏である東洋の現代文明における交代現象である。かつて両者は全く別のものとして考えられていた。キリスト教文化圏の職業倫理はプロテスタンティズムに代表されるが、それが勤勉な産業社会を支えてきた。東洋が産業面で西洋に遅れたのはそれがないからであると考えられていた。しかし実際には遅れはしたものの日本を皮切りとした東アジア諸国の産業面での展開はめざましく西洋人は考えを改めざるをえなくなったのである。東アジア人の勤勉さを支えるものは何なのか。そこに至って儒教に行きつかざるをえなかったのである。日本は明治維新によって、神道と儒教が結びつき、強力な文明開化が進められた。国家にしろ、会社にしろ、人間関係、組織作りの面や行動倫理に儒教は強い力を持つ。資本主義はキリスト教倫理から儒教倫理の国へ移りつつあり、そのような倫理を持たない共産主義は今や崩壊しようとしている。
しかし日本の発展を支えた儒教も教育現場では実学教育に押され軽視されている。教育の結果は数十年後に表れるから将来の日本は心配である。内面に倫理の欠如した生徒をただ利益や金銭欲だけで仕事にかりたてることができるのであろうか。資本主義社会は、一見個人の欲望追求だけで成り立っているように見えるが、実は倫理意識に基づく禁欲的な勤勉さから成り立っている。このことを忘れる時、社会は衰退の道を歩み始める。既に西洋社会がそうなりつつあるように。
儒教の仁義礼智信という徳目は、特別なものではない。逆を考えてみればよい。仁愛の逆は憎しみやエゴイズム、正義の逆は不義や悪、礼節の逆は無秩序や混乱、智恵の逆は愚かさや迷妄、信頼の逆は裏切りや不信。いったいどちらを我々は選ぼうとするのだろう。前者は天国への道であり後者は地獄への道である。地獄はあの世にあるだけとは限らない。我々の無自覚な行動が、周囲や社会に混乱の種をまくのである。そうなってしまった国がいかに多いことか。倫理は押しつけられるルールではなく、自らの内に輝く灯明である。それは天地を貫く普遍性にまで高まるものである。カン卜は「わが上なる星輝く空とわが内なる道徳律」と述べているが、孔子も同じ気持ちであったに違いない。
終わりに論語や儒教を知るための本をいくつか紹介しておきたい。
原典
『論語』金谷治・訳 岩波文庫
『論語』木村英一・訳 講談社文庫
解説書
『論語の読み方』 山本七平 祥伝社ノンブック
『儒教とは何か』 加地伸行 中公新書
小説
『論語物語』下村湖人 講談社学術文庫
『孔子』井上靖 新潮社
『弟子』中島敦 新潮文庫
コラム「背表紙」(「特集 論語の世界」より) (1992年2月1日号)
私のところに生命保険会社の人がよくやってくる。渡されるパンフレットには人生設計を考えましょうと書かれてある。生命保険は人の生き方を教えてくれるのかと思うとそうではない。高齢化社会を迎えて老後のことを考えましょうというわけである。確かにそれは必要なことだから今後ますます政府なども自分の老後を自分で考えることを奨励してくるに違いない。
私も、アリとキリギリスになるのは嫌なのでそれは考えなければならないが、問題は、人生をいかに生き延びるかではなくて、いかに生きるかである。人はパンのみにて生くるにあらずで、金はあっても、ゲートボールをしても人は満足しているとは限らない。
ここに一人の老人がいる。その眼差しは遙か彼方を見つめ深く刻まれたしわには叡智の刻印がある。長く伸びた白いひげには、時間を友とした者の持つ落ち着きと悠然としたゆとりが感じられる。それは美しさを越えて崇高さを感じさせる。彼はかつて若い時に老子を訪ねたことがある。老子に感嘆した彼は老子は龍のような人だと述べたが老子とは別の道を歩んだ。しかし今やこの人もまた老子のように雲に乗じて天に昇ろうとするかのようである。この老人の名を孔丘という。
死をまじかに控え静かに自分の人生を振り返った彼は、こう語った。「吾十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順う。七十にして心の欲する所に従いて矩を踰えず」(『論語』)これが孔子の一生である。東洋人は長い間この言葉を自らの人生の目標として生きてきた。この言葉から十五を志学、三十を而立(じりつ)、四十を不惑、五十を知命、六十を耳順、七十を従心と言う。美しい言葉ばかりである。諸君は志学の年齢の前後である。志はあるだろうか。伸びゆく命は何をめざすのだろうか。
『田中正造の生涯』林 竹二・著 講談社現代新書 (1992年2月1日号)
足尾銅山鉱毒事件の反対運動の先頭に立った田中正造についての評伝のうち、手に入りやすく、また一般にあまり知られていない晩年の思想が紹介されているのが本書である。
正造が政治家を志したのは三十八歳の時であり、自由民権運動に加わり、県会議員となる。当時の栃木県県令であった三島通庸の圧政に抵抗したことにより県民の支持を得る。国会開設とともに衆議院議員となるが、そのころ起こったのが渡良瀬川流域における鉱毒問題であった。
日本の公害第一号といわれるこの問題に、正造は一身をかけてとり組むこととなるが、銅山主の古河と結んだ政府の壁は厚く、被害の中心地谷中村は遊水池として水没させられる。正造は水びたしの谷中村に入り最後の抵抗をするのである。
この晩年の谷中村での生活を描いたものに城山三郎の『辛酸』(角川文庫)があるが、本書と合わせて読めば、一層理解が深まることと思う。
茂吉と白秋(「特集 短歌の世界」より) (1992年7月17日号)
近代の短歌は実に多くの優れた才能に恵まれた。正岡子規、島木赤彦、与謝野晶子、斎藤茂吉、北原白秋、若山牧水、石川啄木などである。おそらく唐代の漢詩人達にも匹敵するほどの人々であると思う。これらの歌人の中で、もし二人を選べと言われるなら、私は斎藤茂吉と北原白秋を選ぶ。 この二人は歌の質、量、歌壇の勢力、後世への影響などにおいて抜きんでているだけでなく、写実主義と浪漫主義、東北の山育ちと九州の水郷育ち、医学者と詩歌一筋など様々の面で対照的であり、しかも相互に互選歌集を出すなどして認めあっていた間柄であた。このような二人の歌を日本に生まれて日本語で鑑賞できることの喜びを私は思う。優れた詩歌というものは若い時代に一度覚えると後々にまで心の中に生きていて、何かにつけて思い出される。そして心の慰めとなるのである。二人の生涯と幾つかの歌を紹介したいと思う。
「死に近き母に添寝のしんしんと遠田のかはづ天に聞こゆる」斎藤茂吉は東北山形の蔵王のふもとで生まれた。生家は農家であったが、生来の頭脳の優秀さを認められ東京の親戚のもとにあずけられた。それが斎藤家であり、東京帝大の医学部を卒業後、同家の婿養子となる。その茂吉の生母「いく」が亡くなったのは茂吉が三十一歳の時のことであった。母危篤の報を受けた茂吉は母のもとにかけつける。その一連のでき事や心境が連作「死にたまふ母」であり、五十九首からなる大作である。茂吉の第一歌集『赤光』の中心をなしている。「死に近き」の歌は、母の死にまにあって、危篤の母に医者である茂吉が添い寝をしているときの情景を詠んだものである。夜がしんしんと更けてゆき目は冴えて眠れない。そのとき遠田の蛙の声が天にたち昇るように聞こえてくる。蛙の声というものは原始的で土から湧きあがるように聞こえる。私は中学生の時にこの歌を習って以来、蛙の声を聞くとこの歌を思い出す。都会の子は蛙の声を気持ち悪がるそうであるが、私には最も親しい声である。土に生きるもののこの野太い声はどこかユーモラスでしかも神秘的であり、あるいは一心に鳴いている様はもの悲しくもある。土に生き今昇天しようとする母に最もふさわしい声かもしれない。私には蛙が念仏しているようにも聞こえる。亡くなった母を火葬にした折の次の歌も忘れられない。「星のゐる夜ぞらのもとに赤赤とははそはの母は燃えゆきにけり」
「あかあかと一本の道とほりたりたまきはるわが命なりけり」これは第二歌集『あらたま』に収められている歌である。茂吉は島木赤彦とともに『アララギ』によって正岡子規以来の根岸短歌会を継承してアララギ派をなしていた。そして子規の写生説をさらに深め実相観入を説えた。その実相観入の根元にあるエネルギーが最もよく表われているのがこの歌であろう。皮相な写生ではなく対象の本質に迫ろうとする茂吉の心的エネルギーのすさまじさを感じさせる。芥川龍之介はこの歌をゴツホの絵を思わせると述べたが至言であると思う。
次に北原白秋について述べたい。白秋は九州の水郷柳川で生まれた。実家は酒造家で裕福な家庭に育った。中学生のころから詩歌に親しみ、早稲田大学の英文科に入学する。当時の浪漫主義の拠点であった与謝野鉄幹の『明星』を舞台に活躍する。詩と歌の両面にその才能を発揮していた。「春の鳥な鳴きそ鳴きそあかあかと外(と)の面(も)の草に日の入る夕(ゆうべ)」これは第一歌集の『桐の花』の銀笛哀慕調と題された一連の作の一つである。いかにも浪漫的な甘酸っぱいもの悲しさが伝わってくる。白秋の青春の繊細な感受性のあふれた歌である。しかしこの甘美な世界は突如破れることとなる。それが「桐の花事件」と呼ばれる人妻との恋愛事件であり、白秋は訴えられ投獄される。幸い示談が成立し釈放されたものの白秋の受けた痛手は大きく、白秋は死を決意して三浦半島に渡る。この闇の中から白秋に全く新しい光明法悦の世界が現れてくる。
「かうかうと今ぞこの世のものならぬ金柑(きんかん)の木に秋風ぞ吹く」秋の陽を受けて照り輝く金柑の実に、白秋はこの世ならぬ光を見ている。この歌は『雲母(きらら)集』に収められているが、この歌集は闇の底から、実在の光の中に跳入した白秋の法悦があふれ、濃厚な宗教的雰囲気をたたえている。まさに悪人正機の芸術版である。
中年期以降の白秋はさらに光と闇の対立を越えた幽玄の世界に入ってゆき、近代の「新幽玄体」を唱えるようになる。「行く水の目にとどまらぬ青水沫(あおみなわ)鶺鴒(せきれい)の尾は触れにたりけり」悠久の時間の流れに一瞬の青き軌跡を残した白秋自身を歌ったかのようである。晩年に発刊した短歌雑誌『多磨』は真の浪漫精神の復興を願ったものである。
参考図書 中公文庫 日本の詩歌8『斎藤茂吉』 日本の詩歌9『北原白秋』
コラム「背表紙」(「特集 短歌の世界」より) (1992年7月17日号)
白秋ほどその育った風土というものを感じさせる人は少ないであろう。水郷柳川は白秋を産み、柳川は白秋の街となった。白秋の死後まもなく出版された『水の構図』という写真集は、白秋の愛した柳川の戦前の風景を白黒写真で伝えてくれる。『思い出』の中で白秋は柳川を「静かな廃市」「水に浮いた灰色の柩(ひつぎ)」と呼んでいるが、この写真集をめくっていると、古き柳川の街の中を自分がさまよっているような気持ちになる。この写真集は現在、柳川の白秋生家保存会によって復刻されている。
今年の五月、私はあこがれの街柳川を、修学旅行団の一員として初めて訪れることができた。柳川の堀割は六キロ四方の市の中に、総延長四百七十キロにわたって張り巡らされている。まさに水郷である。舟下りは、どんこ舟と呼ばれる平底の十数名乗りの舟で行われる。水は堀の水らしく澄んではいないが、水草や岸辺の草花、水路に伸びている栴檀の枝に花が美しい。柳の木陰には、涼風が吹き抜け、老いさびた船頭の声を聞きながら舟はゆっくりと進んでゆく。「色にして老木の柳うちしだる我が柳川の水の豊けさ 白秋」
福永武彦に『廃市』という小説がある。柳川を念頭に置いて、廃れゆく旧家の美しい姉妹の織なす三角関係の破綻の悲劇を描いたものである。人々が善意によって生きながらも、相手を傷つけまいとして結局自らを傷つけてゆくのである。大林宣彦はこの作品を映画化しているが、冒頭では、白黒とセピア色の混じった画面を用いて、廃市のイメージを描き出していた。水辺に垂れた柳は女性の柔らかさと悲しみを思わせる。
水というものが人々に与える安らぎ、潤いというものは、はかりしれないものがある。老子は水の徳を讃え、それが道に近いと述べているが、柳川にいると自分も無為自然の流れの中にいるような気がしてくる。
芥川龍之介 その生涯(「生誕百年 特集 芥川龍之介」より)
(1992年10月27日号)
本年は芥川龍之介生誕百年である。芥川が東京に生まれたのは明治二五年(一八九二年)三月であった。日清戦争の起こる二年前である。芥川には三十五歳の死の二年前に書かれた『大導寺信輔の半生』という自伝的小説がある。少年時代から高等学校時代までを描いたものだが、作者の予定では、現在残されているものの三、四倍書かれるはずであったが、その死のため果たされなかった作品である。そこに退職官吏であった父のことが書かれているが、この父は芥川道章であり、彼の養父である。彼の実父は長州出身の新原敏三である。彼は東京で牛乳業を営んでいたが、彼と妻「ふく」の間の長男として生まれたのが龍之介である。ところが誕生の約八カ月後ふくは突然発狂する。龍之介は母の味を知らぬまま、ふくの実家である芥川家の養子となるのである。ふくが亡くなったのは芥川十歳の時であったが、実母の発狂という事実が芥川に投げかけた暗い影は否定できない。養家の芥川家は代々江戸城のお数寄屋坊主を勤めた旧家であり、文人趣味の濃厚な家であった。養父の道章は南画や俳句もよくし文学者としての芥川を育くむには恵まれた環境であったと言えよう。
頭脳の優秀さは幼時から際立ち、本好きの孤独な少年であった。『大導寺信輔の半生』によれば、本への情熱は小学校時代から始まっている。やがてそれは病的なまでの偏愛となる。彼はあらゆるものを本の中に学ぶ。「実際彼は人生を知る為に街頭の行人を眺めなかった。寧ろ行人を眺める為に本の中の人生を知ろうとした。」「この『本から現実へ』は常に信輔には真理だった。」このことは後の芥川の作風に如実に反映しているように思う。彼が短編を好んで書いたのは、彼の頭の中で計算しつくされた人物と筋を展開させるには長編よりも短編の方が好都合だったせいかもしれない。長編は漱石もしばしば経験しているように作者の予定外の展開を時として見せる。それは作中人物が活きて動き始めるからであり、それが長編の魅力でもあるのだが、芥川は全てを自らのコントロールの下に置きたかったに違いない。完全なる人工物の世界を彼は目ざしていたように思える。
芥川の文筆活動は早くも十歳の時に始まっている。友人達と発刊した回覧雑誌『日の世界』への執筆である。中学以後は校友会雑誌、東京帝大英文科では、『新思潮』を友人達と創刊している。在学中に書かれた『羅生門』は二十三歳の時の作品である。この年に芥川は漱石を訪れ、門下生の一人となっている。翌年『新思潮』に発表された『鼻』は漱石の賞賛を受ける。力量を認められた彼は、漱石の推薦で各誌に作品を発表するようになり新進作家としての地位を碓立してゆく。しかしその出発は師の漱石に比べて余りに早すぎたのではなかろうか。芥川が処女作『老年』を書いたのが二十二歳、死は三十五歳である。漱石の作家としての出発が三十八歳、死は五十歳である。ほぼ同じ十二、三年間であるが、作家として立つまでの教養、思索、人生経験の差は埋め難いものがあるように思う。漱石の友人正岡子規の創作期間が大学在学中から死の三十六歳までで、ほぼ芥川に符合するが、子規の死は肺病による。短詩型文学を続けることより小説を書き続けることの方がやはり精神的負担は大きかったに違いない。
大学卒業後の芥川は海軍機関学校の教官となり生活を支える一方で、旺盛な創作活動を続ける。二十七歳の時には教官を辞職し、漱石がそうであったように出勤義務のない新聞社の社員となって創作に打ちこむが一方精神の危機も近づけた。
彼の作品は従来次のように分類されている。説話集などに取材した王朝物、切支丹の殉教者を扱ったキリシタン物、江戸時代を扱った江戸物、明治の文明開化を扱った開化物、海外の作品に取材した異国物、「保吉(やすきち)」を主人公にして作者の私小説的傾向をもっ保吉物、児童文学として書かれた少年物などである。小中学生によく読まれるのは少年物、高校生によく読まれるのは王朝物であろう。
芥川の作風は理知派とも言われるように、意識的に計算された構成の上に、登場人物の心理を鋭く分析解剖する点にある。漱石に『坑夫』という心理分析を中心に書かれた中編小説があるが、芥川のそれは漱石よりも皮肉っぽく、冷笑的でつき放した感じがある。登場人物は芥川の掌の上で、思うように弄ばれたあげく捨てられてゆくのである。しかし一つだけ彼の思うようにはならなかったものがある。悪魔である。悪の書けない小説家は一人前ではない。芥川は『るしへる』において見事に悪魔の心情を描いている。が、柄にもなく彼は自ら描いたものに魅入られやがて魂まで奪われてしまう。下人の行方は彼にも分らなくなった。蜘蛛の糸は切れてしまった。「漠然とした不安」は自らの命を絶たせたのである。
コラム「背表紙」(「生誕百年 特集 芥川龍之介」より)(1992年10月27日号)
芥川龍之介の写真を見た人は一瞬にしてそのイメージと作品が重なって見えてくるに違いない。秀でた額、細く鋭いあご、暗さを帯びた瞳。これほど夭折の天才作家のイメージに合致するものはあるまい。それは芥川という一個の人物を通り越して、芸術家の典型にさえ感じられる。芸術の魔力、その魅力と恐ろしさを感じさせてくれる顔である。
芥川の写真はどんな文学史の本でも載っているが、私の学生時代、芥川を毎週思い起こさせてくれる顔があった。故芥川也寸志氏である。芥川龍之介には三人の息子がいた。比呂志、多加志、也寸志である。比呂志は俳優・演出家、也寸志が作曲家であった。二男の多加志は最も芥川に似ていた言われ、詩や小説を書いていたが学徒出障で戦死している。芸術一家である。
三男の也寸志が生まれたのは芥川三十三歳の時、二歳の時に既に父は自らこの世を去っていた。この宿命を不幸と言うべきか、幸と言うべきか私にはわからない。しかし毎週テレビの音楽番組で見る也寸志氏は実にかっこよかった。芥川を思わせる知的な細長い容貌は私の憧れであった。氏の曲については知らなかったが、その容貌は視聴者を納得させる音楽の顔であった。
その氏の音楽を聞いたのは、今年亡くなった松本清張原作の映画『砂の器』であった。監督は野村芳太郎であるが、脚本が橋本忍と山田洋次、音楽が芥川也寸志であった。私は映画の方が原作よりいいのではないかと思っているが、この作品における音楽の比重は主人公が不幸な過去を持つ青年作曲家ということもあり、他の作品よりも大きかったと思う。この映画に泣いた人の涙は多分に音楽に影響されていた。劇中主人公が自作自演するピアノ協奏曲『宿命』は芥川也寸志の指揮でレコードにもなった。秋の夜長にふさわしい映画であるが、それにしても偲ばれる人が増えたものだ。
王維(「特集 漢詩の世界」より) (1993年2月5日号)
「うれしい事に東洋の詩歌はそこを解脱したのがある。採菊東籬下(きくをとるとうりのもと)、悠然見南山(ゆうぜんとしてなんざんをみる)。ただそれぎりの裏(うち)に暑苦しい世の中をまるで忘れた光景が出てくる。……独坐幽篁裏(ひとりゆうこうのうちにざし)、弾琴復長嘯(きんをだんじてまたちょうしょうす)、深林人不知(しんりんひとしらず)、明月来相照(めいげつきたりてあいてらす)。ただ二十字のうちに優に別乾坤を建立している。この乾坤の功徳は『不如帰(ほととぎす)』や『金色夜叉』の功徳ではない。汽船、汽車、権利、義務、道徳、礼儀で疲れ果てた後、すべてを忘却してぐっすりと寝込むような功徳である。(『草枕』より)
漱石の『草枕』の冒頭にある、画工の独自の一部である。この冒頭の芸術論は非常に優れた文章だが、その中にそのまま引用されているのが王維の詩『竹里館(ちくりかん)』 ある。「採菊」というのは陶淵明の詩『飲酒』の一節である。王維の『竹里館』はこの時の画工の気持ちを表すのに最もふさわしかったのだろうし、漱石自身の最も愛唱する詩であったに違いない。王維は絵をよくし、文人画である南画の祖であると言われている。「詩中に画あり、画中に詩あり」とも言われる。俗世を離れて山中の温泉で美の世界にひたろうとする『草枕』の主人公の画工は王維をモデルにしているのかもしれない。それは漢詩を書き、俳句を作り、書も絵も描いていた漱石自身でもあろう。
竹里館とは王維の別荘であった?川(もうせん)荘の中の建物のひとつである。?川荘の中には幾つもの建物や庭園があり自然そのものに組み入れられた広大な別荘であった。現在よくある一戸建の別荘とは違う。一つの別世界がそこにあった。王維はそれを二十首の絶句に詠んで『?川集』を編んでいる。「空山人を見ず」で始まる『鹿柴(ろくさい)』もその中の一作品である。『竹里館』を読むと、月光の中に独り座し、琴を弾きながら詩を口ずさんでる王維の姿が彷彿としてくる。まさに漱石の言うように別乾坤・別天地の清浄に満ちており、超俗の人王維にしてはじめて作りうる詩であろう。
王維は深く仏教に帰依し、『維摩経』の主人公維摩詰(ゆいまきつ)から字(あざな)をとって摩詰を名のった。維摩詰は出家しない居士であったが、王維も一方では秀才として仕官をし、一方では?川に自適の世界を築いてそこに心を遊ばせていたのである。「半官半隠」と言われるが、凡人のなしうるものではない。王維は十代から既に詩人としての名をあげており、李白や社甫よりも早い。しかも絵や音楽も得意とする才人であった。唯一の不幸は晩年の安禄山の乱であったが、これとても彼の世界を崩すことはできなかっただろう。
漱石の漢詩(「特集 漢詩の世界」より) (1993年2月5日号)
漱石は英文学を学ぶ前、二松学舎で漢学を学んでおり、十代にして漢詩漢文を自ら書いた。帝国大学時代は、『木屑録(ぼくせつろく)』という漢文の紀行文を書き、また漢詩を作って友人の正岡子規に示している。漱石という号はもともと漢文を書く時の号である。「漱石枕流(そうせきちんりゅう)」という負けおしみの強い意を持つ語に由来するが、彼は漢学者にはならなかった。大学では英文学を学び英国に留学した。しかし英文学とは何かが彼にはわからなくなり深く悩む。漢文で培った文学の概念と英文学のそれとはあまりに違っていたからである。学者になることを彼はやめた。そして近代の自我という重いテーマを小説に描く。それはたしかに外国の対立と矛盾と葛藤の文学を知った故であろう。しかし一方で彼は漢詩、俳句、南画の世界に自らの魂を遊ばせ心の浄化をはかろうとした。王維のような世界が彼本来の文学の世界であった。王維は仏教に親しみ詩仏と呼ばれたが、漱石の禅への傾倒も有名である。
最晩年の漱石は『明暗』の執筆中、午前中小説を書き午後は漢詩を作っていた。彼の晩年の思想「則天去私」は『明暗』にわずかに表れるが『明暗』は未完となった。しかし漢詩には明らかにそれが表されている。吉川幸次郎の『漱石詩注』(岩波新書)によりその一つを書き下し文によって読んでみよう。
「真蹤(しんしょう)は寂寞として杳(はる)かに尋ね難く 虚懐を抱いて古今に歩まんと欲す 碧水碧山、何ぞ我有らん 蓋天蓋地、是れ無心 依稀たる暮色、月は草を離れ 錯落たる秋声、風は林に在り 眼耳双つながら忘れて身も亦た失い 空中に独り唱う白雲の吟」七言律詩であるが、拙訳をめげておく。
「真の道は寂寞として遙かに遠く行き難い しかし私は歩もう空っぽな心で時をも越えて 緑なす川にも山にも私心のありようはずはない 天も地もおおいてあるはただ無心 夕暮はおぼろに迫り月は草を離れて昇りゆく 秋風は入り乱れて声をたて、林の上を吹き過ぎてゆく 眼も耳もふたつながらに失われ、体も無しに我が心は 空中高く舞いあがる 独り白雲を吟じながら」
この詩を書いて二十日後に漱石は胃潰瘍の悪化のためにこの世を去った。この詩は自らの死を予言するかのようであり、自らの思いを記した遺言のようでもある。漱石は『草枕』の画工に語らしめているように東洋的閑寂の世界に憧れ続けた。小説やドラマというのは基本的には対立の世界であり天国的なものではない。しかし詩や絵なら俗世を離れた世界が表現できる。漱石にとり、俳句、書画、漢詩は心のバランスをとる上でなくてはならぬものだったのだろう。彼の高雅な魂がそれを求めていた。
白雲を吟じてゆかん月ととも則天去私の風に乗じて
コラム「背表紙」(「特集 漢詩の世界」より) (1993年2月5日号)
昨年の夏に私は大分県の日田市を訪れた。広瀬淡窓(たんそう)の私塾である咸宜園(かんぎえん)を訪れるのが目的であった。淡窓は十八世紀末から十九世紀前半の人で、頼山陽と同世代の人である。淡窓を慕って咸宜園の籍に上ったものは四千人と言われ、高野長英や大村益次郎が門下として名高い。淡窓の農兵論は益次郎の農兵徴募案につながったとも言われている。
咸宜園の前身を桂林荘と言う。淡窓の詩の中でも、その塾生に示した『桂林荘雑詠諸生に示す』は特に有名である。「道(い)ふを休(や)めよ他郷辛苦多しと 同袍友有り自ら相親しむ 柴扉(さいひ)暁(あかつき)に出づれば霜雪の如し 君は川流を汲め我は薪(たきぎ)を拾はん。」
原文は七言絶句。異郷にあり励ましあって学んでいる塾生の姿が目に浮かぶ。学問の喜びの前には多少の苦労は問題ではない。『論語』学而編の「朋有り、遠方より来たる亦楽しからずや」の世界がここにある。
淡窓を慕って遠方より来たのは塾生だけではない。江戸末期の多くの学者達がいる。頼山陽もその一人である。山陽は三十九歳の時一八一八年に九州一円を旅行している。大分の竹田で田能村竹田(たのむらちくでん)を訪ねた後、日田に広瀬淡窓を訪ねている。 私が日田で泊まったのは山陽がその時滞在した宿であり、玄関にそれを示す石碑が立っていた。私が広島から来たことを告げると宿の人はうれしそうに宿の由緒を語り碑の前で記念写真を撮ってくれた。
山陽が淡窓を訪れたのは桂林荘が手狭となって咸宜園に移ったばかりのころである。山陽は明治維新の端緒を開いたと言われる『日本外史』を著して既に十年を経ていた。竹の生い茂る咸宜園の一室で二人は何を語りあっただろう。維新はその半世紀後である。日田を北に下ると山陽自ら名づた耶馬渓があり、その下流に福沢諭吉の故郷中津がある。明治維新の源流は、この九州の山間の地にも確かに発していたのである。
『タゴール詩集 ギーターンジャリ』(「特集 アジアを知ろう」より)
タゴール・著 渡辺照宏・訳 岩波文庫 (1994年7月15日号)
二十世紀のインド人として日本人が思い浮かべるのは、インド独立の父ガンジーや、その後継者であるネールであろう。しかしインド人の心に大きな希望の灯をともし、影響を与えた人としてタゴールを忘れるわけにはいかない。タゴールの名声は、詩人としてアジア人初めてのノーベル文学賞を受賞したことにより、世界的なものとなったが、彼の活動は、詩作にとどまらず、小説・劇・思想・宗教と広汎にわたり、二十世紀のインド文化を代表すると言ってもよかろう。彼の父は実業家でありながら、宗教改革者として、しばしばヒマラヤ山中で瞑想生活を送っており、タゴールのもつ宗教性はこのような家庭環境の中で育まれた。家庭教師について学んだあと、十代の後半にはイギリスに渡りロンドン大学で英文学を学んでいる。タゴールの詩が、ヨーロッパで名声を得ることができたのは、彼自ら自作の詩を英訳したことにもよっている。
彼が、ノーベル文学賞を受賞したのは一九一三年のことであるが、当時日本では、アジア人初のノーベル賞ということで、これを喜び、一九一六年には新聞社が彼を招いている。「詩聖来たる」として彼は熱烈な歓迎を受けたのだが、日本での彼の講演は、第一次戦でしだいに軍国主義化する日本を批判する内容を含んでいたために、日本人の反応はしだいに冷たくなっていったと言われている。
タゴールはアメリカでもナショナリズムを批判する講演を行ったために、成功しなかったと言われる。しかし、彼の批判した両国のナショナリズムはやがて太平洋の覇権をめぐって対立することになるのであり、タゴールがいかに優れた眼力の持ち主であったかわかろう。
現在タゴールの著作で手に入れやすいのは、ノーベル賞の受賞理由となった詩集『ギーターンジャリ』(「合掌の歌」という意味)で、岩波文庫に収められている。東洋の哲人が歌う神への深い愛の普遍的価値は今も少しも減じていない。
『奥の細道』を辿る(「特集 芭蕉没後三百年」より) (1994年10月27日号)
芭蕉死して三百年。その句は一度耳にすれば忘れ難く、日本文化を代表する否、日本文化そのものを表しているように感じられる。特に『奥の細道』はその簡潔で力強い文と発句とが絶妙の調和をみせ、歌物語のような相乗効果をもつ。
芭蕉が『奥の細道』の旅をしたのは一六八九年のことであったが、この年は西行法師没後四百九十九年にあたり、仏教でいう五百回忌の年であった。今年は芭蕉没後三百年であるから、今年『奥の細道』をたどるのは、芭蕉が西行の跡を巡った動機に近いと言えよう。
『奥の細道』の旅は、三月下旬に江戸を発ってから、ほぼ五ヶ月に及び、その旅程は六百里(二千四百キロメートル)という当時としては大旅行であった。これを門人の曽良を連れて歩き通したのである。この旅は、風雅を求める旅であると同時に、古人の跡を慕う巡礼の旅であり、自然の中で心を浄化させてゆく宗教的な行の旅でもあった。それゆえ日本人の自然観を代表するような名句が、次々と生み出されてゆくのである。単なる物見遊山の旅ではない。それゆえ、現代においてもこの旅をなそうとする者は、巡礼者として、芭蕉とともにその跡を巡り、芭蕉の声を聞きつつ、自然の心に触れるのである。
できれば芭蕉と同じように歩いて巡るべきなのであろう。歩くリズムというのは、ものごとを考えたり、感じたりするリズムによく合うようである。俳句や短歌のような日本人の生得的リズムも、この歩くという生体のリズムと結びついているように感じられる。平泉や立石寺などでは、一〜二時間ゆっくり時間をかけて歩くとよい。
私はこの夏に、『奥の細道』の旅が北陸路に入る前までをたどってみたが、その主な点をあげておこう。東京の深川が出発点であるが、ここには現在芭蕉記念館があり、一訪をすすめる。日光には東照宮が建つが、おそらくこれは芭蕉の美意識と対極であろう。松島の風景は瀬戸内海の多島美を見慣れた者にはさほど珍しくはないだろう。
私が深く感じるものがあったのは平泉と山形の立石寺である。前者は歴史を知ることによって一層「あはれ」をかきたてられる。後者は今だに芭蕉の言う「清閑の地」である。わずか一時間でも岩上に立つ堂を巡れば、山岳修行者の気分になれる。「佳景寂寞(かけいじゃくまく)として心澄みゆくのみおぼゆ。」お堂に腰かけてしばし放心の時をもつがよい。
閑かさや岩にしみ入る蝉の声
最上川は日本三急流の一つと言われ、「五月雨を集めて早し最上川」と芭蕉に詠まれたが、その川下りは今も楽しめる。私はこの川下りで、蜩(ひぐらし)の鈴を振るような声を聞いた。立石寺で芭 蕉が聞いた蝉はニイニイ蝉説が有力だが、私は蜩だと思う。「心澄みゆくのみおぼゆ」は、蜩がふさわしい。
ヘルマン・ヘッセ 1946年受賞(「特集 ノーベル文学賞」より)
(1995年2月4日号)
ヘルマン・ヘッセの作品で中学生、高校生にもっともよく読まれているのは『車輪の下』であろう。この作品は、受験勉強や、管理教育にあえぐ日本の少年達から変わらぬ支持を集めている。ヘッセの神学校における体験に基づくと言われるこの作品はヘッセの精神遍歴の出発点をなしていると言ってよい。『車輪の下』の主人公は、その題名のとおり、目に見えない社会という車輪に押しつぶされて、若い命を失ってしまうのであるが、へッセにとってはその主人公の死は、苦悩の青少年期との訣別であった。へツセは、学校や社会の常識的価値観ではなく、自らの内面から湧きあがる真の価値観を生きようとしたのである。
第一次世界大戦の時に、へッセは、母国ドイツの戦争に反対して非戦論を唱えたために、裏切り者とみなされ苦境に陥る。スイスに移ったへッセが大戦後に発表したのが『シッダールタ』である。この作品は、シッダールタというインドの青年を主人公とするが、同名の釈迦のことではない。シッダールタは精神的遍歴の中、社会的に聖者と認められた釈迦に出会うが、彼の弟子にはなろうとせず、自ら探求する道を選ぶ。ここに、神学校を中退して自らの道を歩んだへッセの姿が重なる。一定の教義の信奉によって人が救われるとはヘッセは考えなかったのである。釈迦のもとを去ったシッダールタは川のほとりに住み、川の渡し守をしながら川から学ぶ。いつしか彼は人々から聖者と呼ばれるようになるのである。
社会の価値観と自らの価値観との相剋はへッセにとって大きなテーマであった。両者が調和した形で描かれる『ガラス玉演戯』は、理想の社会や教育を示すが、その実現は今後の人類の課題であろう。
戦争と文学(濫読のすすめ7) (1995年7月18日号)
戦争の実態というものは自分が被害者になるまでは本当にはわからないのだろう。しかし実際にその立場になると二度と思い出したくなかったり、あるいは語ってもとうてい伝えられないと思う。また死者には語りたくてもその方法がない。文学はその思いを代弁することによって声なき声を伝えてくれる。直接体験と間接体験の差は大きいが、すぐれた文学はその溝を埋めつつ、なおかつ悲劇を伝えるだけでなく、作者の精神を通すことによってそれを越えたものを提示してくれる。
広島に住む我々にとって原爆は避けては通れない課題である。原爆を題材とした文学作品の中で最も有名なのは井伏鱒二の『黒い雨』であろう。高校生の時にその一部を教科書で読み、更に全体を夏休みに読んだが、正直言って私には読み返すのに気が重い作品である。映画化された時に意を決して見に行ったが、白黒映画だからまだ救われたものの、それでもその後何度も夜中に目が覚めた。あの映画の中で被爆した中学生が街中で兄に出会い呼びかけるのに、兄は弟の変わり果てた姿に弟とわからず、名乗らせて確認する場面がある。あの場面が繰り返し現れるのである。私のおじが中学生で被爆し、変わり果てた姿で何度も自分の名を言いながら死んでいったことを母から聞かされたが、その話とあの場面が重なって他人事に思えないのである。小学校低学年の時に原爆資料館を見学し、その時受けた衝撃が心理的な傷になってしまっていることも関係しているのだろう。だから私は原爆のことを語りたがらない被爆者の気持ちがよくわかる。私の母も黒い雨を浴びた被爆者だが今は幸いにして元気である。しかし同じく被爆者であったおじやおばはここ数年六十代で次々と癌で亡くなっている。そこに被爆との因果関係があるのかどうかわからないが私の中のヒロシマは終わらない。
ヒロシマと並ぶナガサキの被爆を書いたもので私が最もよく読んだのは、『長崎の鐘』をはじめとする永井隆の著作である。歌謡曲の「長崎の鐘」は私の好きな曲の一つだが、あの歌のように永井隆の著作は悲劇が祈りの中に浄化されていて、私の神経でも何とか読める。氏の著作はカトリックの信仰に基づくものだが、宗派性に囚われる必要はない。悲劇とそれを乗り越えてゆく人間の精神の高貴さが氏の著作にはにじみ出ている。長崎に行って氏の住居であった如己堂のあまりの小ささに驚いたが、永井隆の存在は被爆地にまかれた一粒の麦であったと思う。
原爆以外では日本各地を襲った空襲が幾つもの作品に描かれている。中でも神戸空襲を描いた野坂昭如の『火垂(ほた)るの墓』は名作として評価が高い。独特の文体で一気に読ませる。被害者に、戦闘員と非戦闘員との区別がないのが近代戦の特徴だが、特に子供が被害者になる時に一層悲しみをそそられる。この話は野坂氏の実体験に基づく。今年一月の阪神大震災はあの悪夢を再び蘇らせた。炎の街に、空襲体験のある人は戦慄を覚えたと思う。私も小学生の時から夢の中で何度も空襲にうなされているのであの恐さがよくわかる。私の場合は目がさめれば終わりだが。
明治以降の歴史の流れの中で先の戦争を描いたものとしては北杜夫の『楡家(にれけ)の人びと』と芹沢光治良の『人間の運命』をあげたい。両者とも関東大震災も描かれている。北杜夫のユーモア精神は『楡家』でも活きているが、さすがに空襲の場面はそうはいかない。芹沢氏の作品はロマン・ロランの『ジャン・クリストフ』と並ぶ名作だと思うが、フランス留学体験を持つ自由主義者があの嵐の時代をどう生きたかが興味深い。十四巻にも及ぶ純文学としては稀に見る大作だが、その続編にあたるのが最晩年の『神の微笑(ほほえみ)』からの八部作である。それによって明治から平成までが描かれた。
国内の地上戦で住民が犠牲となった沖縄戦(「特集 終戦50年・歴史編」より)
(1995年10月27日号)
今年終戦五十周年にあたり、沖縄に「平和の礎(いしじ)」が建立された。沖縄戦の死者二十数万人の名を一人一人刻み込んだ碑である。海を見下ろす丘に屏風のような石碑が何列にもわたり並ぶ映像をニュース等で見た人も多いだろう。そこに刻まれた名は日本兵、米兵、沖縄県民、徴用された朝鮮人軍属など、立場を越え国境を越えて太平洋を横断している。沖縄戦はアジア・太平洋戦争の縮図であった。日本にとっては本土防衛の最後の防波堤であるとともに本土決戦に備える時間かせぎの場であった。アメリカにとって沖縄は本土攻撃の基地に予定されるとともに戦後の東アジア支配のための太平洋の要石(キー・ストーン)であった。戦後アメリカ領となった沖縄はベトナム戦時には北ベトナム爆撃の基地となるが、ベトナム戦争は沖縄戦の延長上にあったのである。「平和の礎」の前に立つ時にはアジア・太平洋戦争からベトナム戦争までに犠牲となった中国やベトナムを含む東アジアの人々の碑も心の目には補おう。その碑は海辺の丘に収まり切らず海を越えて続くかもしれないが、太平洋がその名の通り平和の海であることを祈って。
この美しい島が戦場となったのは太平洋上における位置が関係している。沖縄は民族的には日本人の住む島だが独立した琉球王国であった。しかしこの島を支配下に置きたいのは日本も中国も同じであった。十七世紀の薩摩藩による征服は中国には隠され、琉球は日清両国の属国となった。明治維新後沖縄県として日本に編入されたが、その後の日本の大陸進出を考えれば沖縄は朝鮮や台湾に先んじて征服された土地と言えよう。そして日本の敗戦後二十七年間アメリカ領となっていた。日本、中国、アメリカの大国主義に翻弄された歴史であった。沖縄がアジアの代弁者と言われる所以である。
沖縄戦の最大の特徴は民間人の犠牲者の多さである。民間人の死者十万はヒロシマやナガサキの各犠牲者数にほぼ匹敵する。ヒロシマを言うならオキナワを忘れてはならない。民間人の死者が多かった原因は、「鉄の暴風」と呼ばれた米軍の無差別砲撃や空爆とともに、降伏せず玉砕戦法をとった日本軍の戦い方にある。臨時に徴用された軍人軍属の死者も二万人を越えた。中でも学徒動員された鉄血勤皇隊や看護部隊のひめゆり部隊の悲劇が有名だ。香川京子氏の『ひめゆりたちの祈り』はこのテーマに四十年かかわり続けてきた厚みを感じさせる名著である。また鉄血勤皇隊員であった現沖縄県知事大田昌秀氏の『沖縄のこころ』も読んでほしい。最近の米兵暴行事件が象徴するように沖縄の戦後は終わっていない。
アジア・太平洋戦争(濫読のすすめ8) (1995年10月27日号)
アジア・太平洋戦争関係の文献はおびただしい数にのぼる。ここ三年ほど高三の小論文講座を担当しており、一学期の後半はディベート(討論会)をとり入れながら平和問題について考えてきた。生徒に資料を提供してゆく関係で一学期の後半は毎年のようにアジア・太平洋戦争に関する文献を読んできたが、まだまだ目を通していないものが多い。濫読と系統読書を組み合わせたような読み方になるのだが、ここではある程度整理して述べてみよう。
歴史を見る場合にどうしても問題となるのは歴史観である。歴史は書き換えられると言うが、見る人の視点によって全く別の見方ができてしまう。戦争中の日本人と戦後の日本人は全く別の史観の中を生きていると言ってよい。個々人や個々の国の利害を離れて、日本史でも東洋史でも西洋史でもない人類史を鳥瞰できるかどうかである。いわば地球を外から眺めつつ、三千年ならその百万回転を映画を見るように見つめていけるかということである。人類史を考えるなら、各文明圏の発生してゆく三千年から二千年の範囲で見なければならない。
この点ですぐれているのはトインビーの『歴史の研究』であろう。トインビーは大英帝国の生んだ最もすぐれたコスモポリタンの一人である。現在縮訳版が出ているので我々にも読みやすくなっている。トインビー史観の中で注目される点は一つの文明の盛衰に三拍半のサイクルを発見している点である。一つの文明が起こってから衰退するまでに「敗走―立ち直り」を三回燥り返した後に衰退するというものである。ことわざ.の「二度あることは三度ある」を法則化しているとも言えるが、現在の西洋文明を汎地球文明と見なすと、二つの世界大戦はトインビーサイクルの二回を終えたことになる。そうするともう一度世界大戦は起こるのか、起こってもそれを乗り越えて人類は立ち直れるのか。これが二十一世紀に向けての人類史上の私の関心事である。トインビーは予言者ではないからこれについて何も言ってはいない。
アジア・太平洋戦を局地的に見るには東京裁判関係の本を見るのがいい。一般によく読まれているのは朝日新聞記者団によるものであろう。裏話を含めて書かれていて興味深いのは児島嚢の中公新書版である。いずれも二巻本である。忘れてならないのは、ネールの依頼を受けて判事となったインド人パルの『パル判決書』であろう。インド版の『パル判決書』はヒロシマの原爆被害を冒頭に数ぺージにわたってのせているそうだが、日本の戦争犯罪だけを取り上げず連合国側のそれもとりあげている。パル判事は広島平和公園の碑文論争を巻き起こしたことでも有名だがパル判事の真意が曲解されている面がある。東京裁判の判事の中でパル判事が最も原爆に関心をもった人であることは確かである。『パル判決書』は現在講談社学術文庫から二巻本で出ている。
アジア・太平洋戦争は満州事変から日中戦争までを第一段階とし、真珠湾から敗戦までを第二段階とするのが一般的であろう。この第一段階の経緯を見る上で参考になるのは、清朝最後の皇帝溥儀の自伝『わが半生』と弟の溥傑と結婚した日本人愛新覚羅浩の『流転の王妃の昭和史』であり、満州国が何であったかをよく描いている。満州で忘れてはならないのは、関東軍内の七三一部隊であろう。森村誠一の『悪魔の飽食』が三部にわたって出されている。小中学生向けには、松谷みよ子の『屋根裏部屋の秘密』が刺激が少いだろうが、この事実に目をつぶることは許されまい。
私の読書歴(濫読のすすめ9) (1996年2月3日)
卒業生諸君、卒業おめでとう。ささやかなはなむとして、私の読書歴を語り、諸君の参考として提供したい。私の記憶にはっきりと残っている読書は小学校の三年生のころだった思う。もちろんそれまでにも童話やおとぎ話はずい分読んでいる。母が言うには字が読めないのに暗記していてページをめくりながらお経のようにすらすら言うのが不思議だったそうだからそれらの本が記憶の底に埋もれているのはまちがいあるまい。残念ながら今それを思い出すことはできず『舌切りすずめ』のさし絵の一部をかろうじて思い出す程度である。小学校三年生の時というのは、母が童話やおとぎ話以外のもので初めて買ってくれた本をよく覚えているからである。それは科学者のニュートンの伝記であり、小学生向けの偉人伝の中の一冊であった。これがたいそう気に入って伝記のおもしろさに熱中した。おそらく現実離れしたメルヘンの世界から現実の世界へと目が向き始めたころだったのだろう。
それからは家で買ってもらったり、あるいは学校の図書館にある伝記を次々と読んだが、私が好きになったのは、政治家のものよりも文学者の伝記だった。夏目漱石、石川啄木、北原白秋、宮沢賢治などは強く印象に残っている。政治家ではリンカーンや勝海舟は好きになったが、日本の戦国時代の武将は好きになれず、織田信長などは、はっきり言ってなぜこれが偉人伝に入るのか理解できなかった。おそらく子供心ながらに、偉大な仕事というのは人の心の糧となるものだという思いがあったのだろう。
とはいうものの、小学校五、六年生になると『三国志』とルパン全集にとりつかれてしまった。伝記とルパン物はほとんど全部読んでしまったから、これは濫読と同時に系統読書の始まりであったと言えよう。
この濫読の中で生涯忘れられない体験になったのは、夏目漱石の『こころ』であった。小学生の私はまず『坊ちゃん』を読んで気に入り、その延長のつもりで『こころ』を読んだのだが、これが『坊ちゃん』とは全く違った世界であった。しかし内容にひきずられて一気に読んでしまった。少年少女向けの文学全集はかなり読んだが、『こころ』ほど大きな感銘を受けたものはない。小学生にはたしてどの程度わかったのか定かではないが、読み終えたあとの不思議な感動にこれこそ文学だと思ったものだ。中学高校の時にはひきつづき漱石の他の作品も読んだが『こころ』に優るものはなかった。少年向け文学全集の中で好きになれなかったのは芥川龍之介の作品で、これはいまだにそうである。
中高時代は文学書も読んだが、しだいに哲学書を読むようになった。とはいってもいきなり原書は読めないので、新書で解説されたものである。仏教経典の解説書もよく読んだ。結局西洋哲学よりも東洋哲学の方がおもしろく感じられて、大学では東洋哲学を専攻することとなったが、中高時代の読書の結果である。
大学では専門書もよく読んだが文学書もよく読んだ 。特にひかれたのはへルマン・ヘツセであった。ヘッセの世界には東洋的なものが濃厚にあり、私の好みにぴったりだった。大学・ 大学院の時代は一番本が読めた時期で、一年に一本ずつ本棚がふえていき、大学院に入る時は本を置くために隣の部屋を追加して借りることになった。広島に帰る時、ほとんど持ち帰ったが、今や十三の本棚を四部屋に分けるはめになっている。五千冊を越えたろうが、阪神大震災以来家族に不安を与え続けて評判が悪い。本の下敷きになって死ぬのは本望とはまだ言えない。
『こころ』と「こころ」(濫読のすすめ10) (1996年7月15日号)
前回私の文学体験が夏目漱石の『こころ』に始まることを書いた。授業でも何年かに一度は扱うので、回数としては最も多く読んだ作品と言えるだろう。たまたま今年も『こころ』を授業で扱う年となったのだが、読み返す度に以前読んだ時には気づかなかったものに気づかされる。まるで生き物のように新しい面を見せてくれるのである。
私が昔読んでわからなかったのは「明治の精神に殉死する」ということであった。その後もこの問題を考え続けていてそれなりの結論を考えてはいるが、おそらくこのことは、漱石自身も読者には説明しにくいと思っていたようである。何となくわかるけれどもわからないところが残ってしまうという永遠の謎を感じさせる作品である。
「いじめ」が社会問題化して自殺が一種の流行のようになってしまう現代では、学生の自殺を扱った『こころ』のような作品は扱いにくい状況になってゆくかもしれない。まさか『こころ』を読んでこの作品が自殺を勧めているように受け取る者はいないと思うが、人間の生と死の非常に重要でデリケートな問題を含んでいることはたしかだろう。
たまたま授業で扱う前に『いじめと妬み』(渡部昇一・土居健郎・共著)を読んでいたところ、二人の話題に『こころ』が出てきたのに驚いた。そこで渡部昇一氏が大学時代に『こころ』を読んだ体験を述べている。「先生」の自殺の原因がよくわからないことと、その自殺が明治天皇の死をきっかけとするのはおかしいのではないかと思ったということだ。漱石の作品の中で一番おもしろいが、何がおもしろいのかよくわからない。それでもおもしろいという不思議な小説だと述べられている。この見方は私も同感である。渡部氏のこの話に対して、精神医学者である土居健郎氏が精神分析の立場から説明しているが、やはり説明しきっているという感じではない。この残る何かが文学では大事なのだと思う。
考えてみれば自分の「こころ」を説明しきれる人はいない。しかし説明できなくても我々は毎日考え、感じ、何かを表現し続けている。たまたま文章としてそれが残った時にその「こころ」が多くの人の目に触れるわけである。文学が鑑賞されるということは、この「こころ」が共有されることであり、説明しきれない不思議な何かをともに抱き、かみしめることだろう。
漱石の『こころ』は読書感想文によく取りあげられる作品だが、何かを書きたいという気持がわきおこる作品なのだと思う。「先生」が若い学生に自分の「こころ」を伝えたくなって、長大な遺書を書き送ったように。
「永訣の朝」から『銀河鉄道の夜』へ(濫読のすすめ11)
(1996年10月22日号)
私が文学者の個人全集で初めて買ったのが宮沢賢治全集であった。それをきっかけに賢治について考えたことを書いてみたいと思いながらもそのままになっていた。このたび生誕百年を機に研究書を読んでみると、私の考えたことは見当違いではなかったようだ。
賢治の文学作品の中で最も高い評価を得ているのは詩集では『春と修羅』、童話では『銀河鉄道の夜』であろう。『春と修羅』の中で特に注目されるのは「永訣の朝」に始まる一連の妹トシへの挽歌である。賢治にとってトシは、法華経への信仰を同じくする同志であり、精神的恋人でもあった。トシを失った衝撃は極めて大きく、賢治はその傷を癒そうと樺太まで旅に出る。失われたトシの魂を捜し求める旅であった。そして「青森挽歌」や「オホーツク挽歌」が生まれている。「青森挽歌」では「きしゃは銀河系の玲瓏レンズ 巨きな水素のりんごのなかをかけている」と歌っている。また「永訣の朝」をそのまま 童話にしたような『チュンセとポーセの手紙』という兄妹の話も書いている。
『銀河鉄道の夜』はこの兄妹関係を少年同士の友人関係に置き換えている。亡くなった友人カムパネルラが妹トシ、ジョバンニが賢治である。ジョバンニは牧場の丘でいつのまにかカムパネルラと汽車に乗っているのだが、実はこの時すでにカムパネルラは人を助けようとして川で溺れて死んでいたのである。「幻想第四次の銀河鉄道」の旅は異次元に向けてのいわば霊界旅行であり、この汽車の乗客はジョバンニ以外は死者なのである。タイタニック号の遭難者を思わせる姉弟がその典型で、この姉弟も賢治とトシを想起させる。
ジョバンニがこの汽車に乗ることができたのは天上のどこにでも行ける切符を持っていたからだが、この切符は賢治の信仰を象徴し、法華経や題目であろう。妹を失った悲しみを祈りに換え、妹への愛を人類愛にまで高め、みんなのために「ほんとうの幸福」を探すのがジョバンニである残された賢治の使命であった。
それは大乗仏教の菩薩道であり、その具体化が羅須地人協会を設立しての農民への献身であった。「雨ニモマケズ」の「デクノボー」とは法華経に言う「常不軽菩薩(じょうふぎょうぼさつ)」や「地涌の菩薩」であろう。
『銀河鉄道の夜』は最期まで手を加えられたために未完のままとなり、賢治は妹のもとへと旅立った。チュンセとポーセの「双子の星」は今も銀河に輝いている。
濫読の「山」(濫読のすすめ12) (1997年1月31日号)
昨年の夏に私は二種類の原稿を書いていた。一つは学園の研究紀要に載せるためのもので『歎異抄』について書いたものである。こちらの方は前年度の紀要の仕事が終わった昨年の冬から夏にかけて準備をし、何冊もの本を読んできたが、その読書は系統読書であった。普通テーマが決まっていればいくら多くの本を読んでも系統読書である。ところがもう一つの仕事にとりかかってみて、テーマが決まっていても系統読書にならず、濫読になる場合があることがわかった。こちらのテーマは中国四国地方の山の伝説を百集めるというものであった。まず高い山をリストアップしようと思い登山の本にあたったのだが、これはほとんど役に立たなかった。高い山は山岳信仰の対象となる場合は別として人とのかかわりが薄いのである。高い山だから伝説があるわけではない。伝説を生むのは山でなく人である。
このことに気づいてから、ようやく糸口がつかめたように思った。本当のテーマは、「山」ではなく、むしろ「人」であったのである。しかしそれはテーマとしては大きすぎる。役に立ったのは歴史紀行、文学紀行というたぐいのものだったが、百冊ぐらいの本を手あたりしだいに調べることになってしまった。
伝説とは歴史と文学のはざまに位置するものであろうが、伝説を生み出すのは歴史的事実よりもむしろ人の思いなのである。例えば安徳天皇は源平の合戦で壇ノ浦に入水したことになっている。ところが屋島から四国に逃げて生き延びたという伝説もあるのである。高知県の御在所山と横倉山にその御陵伝説が伝わる。この伝承により横倉山は明治時代に宮内省から、安徳天皇の御陵参考地に指定されている。この場合は作り話とは言い切れないかもしれない。
それに対して動物が登場する伝説は完全な作り話であることは明らかだが、それだけに人々の思いがよくわかる。今年の大河ドラマの主人公毛利元就にも山にまつわる伝説がある。宿敵尼子との戦いは武田対上杉の中国版とも言うべきもので幾つかの伝説を残すが、その一つに森山狐の伝説がある。郡山の北に美しい狐がおり猟師がこれをねらっていたが、元就はおふれを出して捕獲を禁じた。尼子の大軍が郡山城を包囲した時にこの狐は自分の家来を兵に化けさせて城を守り、さんざんに尼子を苦しめた。そのおかげでついに戦は元就の勝利に終わった。元就が吉田の人々を城にかくまったことがこの伝説を生んだのだろう。
知覧(濫読のすすめ13) (1997年7月18日号)
この春に私は鹿児島県の知覧を訪れた。薩摩半島の南に位置するこの町に戦争中陸軍の特攻基地があった。鹿児島県内には幾つかの特攻基地があったが、中でも陸軍の知覧と、大隅半島にある海軍の鹿屋がその中心であった。いずれも沖縄戦の米艦隊に突撃している。
私が知覧のことを知ったのは二十数年前の十代前半の時のことである。当時学研から出ていた高木俊朗の『知覧』を読んだことによる。筆者は戦争中に陸軍報道班員として知覧におり、戦後に取材を加えてこの本を書いている。書名は現在『特攻基地知覧』と変わり角川文庫に入っている。
知覧には特攻隊員の手紙や遺品を集めた特攻平和会館がある。私が訪れた日、薩摩地方の桜はすでに満開だった。特攻平和会館の前にはみごとな桜並木があったが、折からの雨に打たれて散り始めていた。出撃する兵士達は奉仕の女学生の振る桜の小枝に見送られて飛び立って行ったという。兵士の戦死を意味する「散華」という言葉の激しさと痛ましさを知らせようとするかのような強い雨と散り敷く桜の花びらであった。その雨の中をバスから降りた観光客や修学旅行生が小走りに館へと急いでいく。
多くの人々を吸い込んだにもかかわらず、館内は意外と静かであった。展示室の壁には展示品のすきまを縫うように千羽鶴が吊りさげられている。修学旅行生が持参したものである。館内の不思議な静けさは遺書や遺品に心打たれた人々の発する厳粛な雰囲気のせいであった。ほとんど全員のものが並べてあるのではないかと思われるほどの白黒写真の遺影の列。収納しきれないほどの手紙は引き出して見ることができる。その幾つかに目を通すうちに観光気分は確実に消えていく。特攻隊員の思い出を語る当時の軍用旅館の女将の証言ビデオの前は大変な人だかりだが、私語一つない。その口から特攻隊員を涙して見送った当時の知覧が蘇る。
高木俊朗が書いているように戦争中特攻隊員は美化されすぎていた。たしかに少年飛行兵には何一つ疑うことなく沖縄の海に散っていった者も多かったろう。しかし年輩の隊員や学徒出身の隊員の胸の内にはまた別の苦悩があったことが読み取れた。年輩の隊員が子供にあてた手紙にはことに胸を打たれるものがあった。高木俊朗の本には、恋人との別れ、妻との別れ、また郷里に飛び親の前で畑に激突した者がいたことも書かれている。
あっというまに時がたち、外に出ると雨はすでに小止みになっていた。
炎(濫読のすすめ14) (1997年10月29日)
山のキャンプ場の朝は夏でも寒い。焚火でもしようと思って始めたところ、子供がおもしろがるので暖をとるよりも焚火そのものが目的になってしまった。子供が次々と木を拾い集めてくる。親子でその炎のゆらめきを見詰めていると、太古の魂が呼びさまされるようなあやしい気分になる。
この夏に私は二度上京したが、二度目の時に上野の国立博物館に寄った。浄土教の原稿を書き終えた後で、仏像を見るつもりだった。ところが全く予期していなかったものに心を奪われた。それは縄文土器である。陶芸室の一角で他を圧倒する存在感があった。炎を模したと思われる土器上部のうねりを見ていると、何か血が騒ぐのを覚えた。そして夏の初めにキャンプで焚火を見詰めていた時を思いだし、縄文人と心が通じたように思った。
考えてみれば土器は火で燃やして作るのだ。火の中で生まれるものを火の形にするのは当然の発想だろう。縄文人は炎の力を自分の命としたかったのかもしれない。焚火が窯に代わり、この発想は忘れられたのだろうか。私は青磁や白磁が好きだが滑らかな肌には炎の生命感はない。かえって洗練の果ての危うさがある。
縄文土器の美を発見したのは岡本太郎だろうが、『日本の伝統』という本で縄文土器を「民族の生命力」として語っている。「芸術は爆発だ」と叫んだ彼の顔が土器に重なる。それまでは縄文土器のイメージはグロテスクなものというのが一般だった。
同じ夏の一度目の上京の時、私は両国の江戸東京博物館に行った。東京大空襲の展示を見るためだった。展示品の一つに劇場の屋根裏で発見された鉄骨があった。火災の熱で曲がったものだが、炎の中でくねったその姿は抽象彫刻のようで力強い美しさがあった。一緒にいた友人の子供には「恐いね」と言ったのだが、あやしいものが残った。
この心情を破壊を喜ぶ心情かと思ったが縄文土器を見て納得した。炎の芸術があるのだ。炎には創造性の美と力がある。その一方で炎の破壊性は文明によって制御されたかに見えてむしろ増幅される。平山郁夫の「広島生変図」は炎のこの両面を描くようだが破壊を創造へと転ずる祈りがある。あの鉄骨も一種の焼物として期せずして生まれた「東京生変図」なのだ。
天の火を人に与えたプロメテウスはゼウスに罰されたという。人は創造の火を破壊の火に変えてしまう。炎のもつ生命感を失った現代人はかえって凶暴になってはいまいか。現代人は縄文人ほどに炎を我が命として美に昇華しえているだろうか。
いつか結婚する卒業生諸君へ 松井博文詩集『フミとユウ』(濫読のすすめ15)
(1998年2月7日号)
昨年の八月に本校英語科の松井博文先生の第三詩集『フミとユウ』が文藝書房から刊行された。中国新聞にも紹介記事が掲載されたので、見た人もいるだろう。松井先生は日頃から二つの同人誌に詩を発表されているが、『フミとユウ』に収められている詩で私が同人誌で読んだのは一編だけだった。先生に尋ねたところ、私の記憶は間違いではなく、その一編を除いて、すべて未発表の詩であるとのことだった。十数年間にわたってひそかに書き綴られた家族の肖像がここにある。
副題に「結婚するあなたへ」とあり、表紙には、幼い女児と男児の姿が写っている。先生の子供さんだが、男女両方の子供がいることが作品の幅を広げ共感を呼ぶ。先生自作の宣伝文は次のように言う。「子育てとは理屈ではないことを理屈で歌ったホロ苦くもユーモラスな詩集 あなたには結婚する喜びを、結婚した人には子育ての勇気を与えてくれる心暖まる物語」少子化に悩む現代に向けられた言葉だろう。自分の作品を客観的に見ることは難しいが、先生の場合は非常に的確である。十数年という長い時間にわたって書き続けられたことも距離を置いて見るのに好都合だったのかもしれない。それ以上に感じるのは、詩心と同時に哲学する心があって、それを非常に長い時間をかけて成熟させてきたために、一本の芯ができあがっていることだ。その哲学する目が自らの作品を冷静に、しかもいとおしんで見つめている。
その哲学とは若者がよく陥りがちな観念だけの構築物ではなく、体験と思索が交互に反復しながら織り込まれてゆく種類のものである。一人の彫刻家が作品と語り合いながらじっくりと作品を彫りあげてゆく姿、あるいは、山奥で育つ一本の木が、幾星霜を経て大樹に育つ姿、そういったものに含まれる一貫した何かを哲学と呼んでよいのなら、先生の哲学とはそういう種類のものである。
この詩集には成長する我が子の姿の上に、それとひきかえのように衰えてゆく自分の姿と、自分を産み育て亡くなる父の姿が重っている。旧い港町の尾道という背景もよく合う。東洋の家族観は家を一筋の生命の流れのように捉えてきた。あるいは枝分かれしてゆく大樹のように見てきた。命は時間を必要とする。その重みを歴史と呼ぶ。個人中心の家族観のため命を産む家族が、ひいては個人までも崩壊する現代を先生の「イノチ」は静かに諭している。松井先生に教わった卒業生諸君はこの詩集を理解してくれる人と結婚するといい。
記録と記憶(濫読のすすめ16) (1998年7月17日号)
市内のデパートでピュリツアー賞の写真展が開かれていたので子供連れで出かけた。日曜日のせいだったためもあろうが、かなりの人出で、入口付近では人の肩越しに写真を見る盛況だった。テレビ主流の時代に報道写真が人々の関心をそれほど集めるとは思っていなかったので少々意外だった。
この写真展は二十世紀後半の人類史と重なっている。私にとって特に印象的だったのは戦争写真であった。硫黄島に米軍兵士が星条旗を立てる場面の写真は非常に有名であるが、言うまでもなくそれはアメリカ側から見た戦争の終結と勝利を象徴する英雄的な写真である。日本人にとって戦争の終結を意味する写真は、ここにはなかったが、焼跡に立つ原爆ドームの写真や、宮城前にひれ伏して泣く人々の写真であろう。アメリカ人にとっては大きな代償を払ったものの、輝かしい勝利を収めたこの戦争を象徴するモニュメント的写真であった。
しかしベトナム戦争となると輝かしい勝利は消えて、影の部分が顔を出す。私の記憶に残っているのはここからである。この写真展を見に来た人々は、報道写真を通して自分の歩んできた二十世紀を振り返ろうとしていたのかもしれない。二十世紀文明の中心であり、戦後は日本の同盟国となったアメリカの報道写真は、日本人の時代の記憶と重なる。ベトナム戦争の写真は太平洋戦争の場合と違い、日本人の目と重なりやすいだろう。
「戦死」したと言うべき日本人写真家沢田教一のベトナム戦争の写真はその点でも意味深く印象的である。ベトナム人母子四人が、幼子は抱かれて、泳いで川を渡る写真は「安全への逃避」と名づけられているが、一連の戦争の写真の中に置かれていなければこれが戦争の場面とは気付きにくいかもしれない。しかし同じ時代を生き、少し前には空襲の中を逃げまどった日本人にとっては、同じアジア人の母子の姿は自分達の記憶と重なったはずである。さらにこの写真は空襲の記憶をもたないアメリカの人々の心をも捕えた。普通の戦争写真は事実を撮ることに徹するが、沢田の写真は心を撮っている。アメリカ人写真家の撮った、退役した車イスの黒人兵士が幼子を抱いて軍のパレードを見守る写真も印象的だ。我々はまだ二十世紀の記録と記憶に囲まれている。やがて沢田の写真のように記録が記憶を呼びさましたり、また新たな記憶を作るだろうか。写真を見た私の子供は頭が痛くなったと言った。かわいそうなことをしたが、彼のこの記憶は二十一世紀をどう造るだろうか。
「ノーマライゼーション」を越えて(濫読のすすめ17) (1998年10月27日号)
七月の初めの市民球場でのこと。私達の後ろの席がいやににぎやかだ。私の子供も耳が痛くなるくらい大声で応援しているが、それを圧倒するほどだ。しばらくしてそれが視覚障害者のグループらしいことがわかった。そのうちの一人がラジオを手にフェンスの前に来て応援を始めた。後ろからはまずいプレーがあると、「障害者でも取れるぞー」と障害者からヤジが飛ぶ。
試合は野村のホームランでカープが阪神に勝ったが、この日の出来事は私の心を軽くさせた。というのはその夏に私は校外の研究会で障害者問題について発表することになっていたが、障害者との接触が限られたものだったために、観念だけで固めたようなぎこちない発表になりそうだったからだ。自らの障害を隠そうともせず、見えないはずの野球をスタンドの人々と一緒になって応援する障害者の姿は何ともさわやかだった。川を前にして渡れそうにないと悩んでいるこちらに、向こうからじゃぶじゃぶと足を踏み入れて渡ってきてくれたようだった。
長野オリンピックの後のパラリンピックは多くの人々に感動を与えた。障害者はスポーツに無縁だと思う人はもういないだろう。しかしそこにはまだ困難を克服して超人的プレーを見せる障害者という障害者を聖人視する空気が漂っているように思う。オリンピックは元来が神聖な祭典だからそれはかまわないが、障害者との接触の少ない人々には障害者の生き方に先入観を与える面があるだろう。ヘレン・ケラーや星野富弘氏の生き方は素晴らしく、人間の尊厳を示しているが、障害者聖人観は健常者の押し付けとして障害者との間に壁を作っていないだろうか。
そういう障害者観から抜け出せない人に薦めたいのが障害者プロレスを描いた北島行徳・著『無敵のハンディキャップ』である。自ら障害をさらして戦う彼らは決して「清く正しく美しい」障害者ではない。酒癖、女癖が悪く、女装癖を持つ者もいる。そもそもこの発想は障害者同士が女性をめぐり取っ組み合いを演じたことから生まれた。試合はすべて真剣勝負。障害者同士の対戦がメインで、水着姿の女子プロレスまであるが、驚くのは障害者対健常者の対戦があることだ。彼らと戦うボランティアの悪役健常者レスラーは「福祉の仮面をかぶった悪魔、今世紀最大の偽善者」を名乗り容赦なく攻撃し、「ノーマライゼーション」を 越えた「アブノーマライゼーション」?が展開される。この本を読むあなたを障害者はリングの上に引きずり出すだろう。
『いいたかことのいっぱいあっと』(濫読のすすめ18) (1999年2月6日号)
昨年の六月に「ヒロシマ・ナガサキの修学旅行を手伝う会」を主宰しておられた江口保先生が亡くなられた。私は数日前に先生の著書である『いいたかことのいつぱいあっと』の出版記念会の案内状をいただいていたので、突然の計報に驚いた。先生が病気療養されていたことは手紙で知っていたが、回復したとの知らせを受けていたばかりであった。地元の新聞でもこのことは報じられたので知っている人はいるだろう。
江口先生は東京での中学教師生活を定年前にやめられて広島に単身赴任され、修学旅行生に被爆者の体験を語ってもらう橋渡しをされていた。全くのボランティアで十年近く活動された。先生が広島での生活を終えられることを知った私が、本校での講演をお願いしようとしたところ、ちょうど先生は東京に引き揚げられたあとで、私は東京に行って先生にお会いし、講演を引き受けていただいた。それ以来のおつきあいだった。先生にはすでに『碑に誓う』という著書があり、その中に本校のことが紹介されていた。先生は長崎での被爆者であったが、 長年平和教育に打ち込んでこられた体験を語っていただいた。『いいたかことのいっぱいあっと』には前著ではあまり語られなかった御自身のことが詳しく語られ、自叙伝の趣きを見せている。
この本の中に東京での中学教師時代に、生徒を引率して広島に修学旅行に来ていた時代のことが書かれている。栗原貞子さんの「生ましめんかな」という詩に感動した女子生徒と栗原さんの出会いがそこに描かれている。本校の近くにあった千田町の貯金局の地下で被爆者がうめいている中で、一人の妊婦が産気づいた。赤ん坊が産まれるぞという声に、人々は自分の苦しみを忘れて心配する。その時負傷していた一人の女性が産婆であることを名乗り出て、そのお産を手伝う。赤ん坊が生まれてまもなくその産婆は息を引き取った。「生ましめんかな己が命捨つとも」この詩の最後の一句である。平和公園で生徒と出会った栗原さんはこの詩の説明をする中で、この時産まれた赤ん坊は「ヒロシマという世界へ向かって平和を要求する赤ん坊」なのだと語っている。江口先生が長年に渡って続けられた仕事も、若くみずみずしい生徒の心の中にこの「赤ん坊」を産み出す仕事であった。ソクラテスにならっていえば、「平和の産婆術」が先生のお仕事だった。「生ましめんかな己が命捨つとも」は先生にも捧げるべき言葉だろう。
怨念と恐怖のリング(濫読のすすめ19) (1999年7月2日号)
『歎異抄を読む』(洛西書院)を出版してからまもなくのこと、あるところから鈴木光司の『リング』についてのコメントを求められた。一種の心霊現象を扱った作品だから、 宗教に関心を持 つ人間として、あるいは教育の場に身を置く人間としてどう思うかということである。
『リング』は生徒の読書ノートに登場するので内容はほぼわかっていたが、恐そうなので自分で読もうという気は起こらなかった。読んでみると確かに恐い。ホラー推理とでも言うのだろうか。殺された女の怨念がビデオに映り、それを見た人間はそのビデオを他人に見せない限り死ぬ。怨念の現象化とその増殖がこの小説の鍵であろう。怨念の現象化は昔から崇りとして知られるものだが、この小説ではさらにそれが人の恐怖心によって伝染し増殖するものとしている。
文学の中に昔から怪談はあったが、現代という文脈の中では昔とは意味が異るだろう。科学の発達でこの世の秘密はなくなり、SFでさえ人々は飽きてしまう。退屈した人々の興味を満たすものの一つが未知の心霊現象なのだろう。オカルトブームの延長で考えればよいのだろうが、その結果が某教団の殺人事件や神戸の小学生殺人事件ではなかったのか。某教祖も自分の怨念を信者の恐怖心を使って増殖させたのだろう。
怨念の現象化は霊的法則の裏面であろうが、自然科学の法則を利用して殺人兵器ができるのと同じようなものだ。自然科学の法則も霊的法則もそれを統べる高度な意識がなければ危険なものとなる。その意識とは神仏と呼ばれてきたものである。とめどなく進行する合理主義とその裏面としての心霊現象への興味は表裏一体のものであろう。
二十世紀の人類の歩んできた道は、物質面と心理面が相関していたように思う。怨念の増殖は世界大戦を引き起こし、大量殺人兵器を生んだ。民衆の支配階級への怨念は革命を引き起こし、理論武装した恐怖の支配の後、自壊した。貧困への恐怖と表裏一体となっている欲望は市場原理の名の下でコントロールがきかなくなり、破産の恐怖から逃れようと人々は必死である。自己責任の美名の下で破産した人に怨念は残らないのか。ユーゴでは民族対立に端を発した戦争が起こった。怨念が戦争を生み、誤爆によって関係なかった国にも怨念が飛び火する。怨念と恐怖のリングを止めるものは何か。例えば親鸞はそれを「安心」と呼んだ。
岡本太郎ワールド(濫読のすすめ20) (1999年10月27日号)
亡くなってから、いっそうその存在感が大きくなるということはよくあることだ。芸術家の場合は生存中よりもむしろ没後の評価の方が重要かもしれない。作品そのものの価値については素人にはなかなかわからないが、心に残るか残らないかは 誰にでもわかる簡単な基 準である。
岡本太郎が万博公園に立てた「太陽の塔」は評価はさまざまだったが、万博時の建物が取り壊された中で唯一残っている。とりわけ関西の子供に強く支持されていたという。鳥にも人にも木にも見える不思議な存在である。
九六年に岡本太郎が亡くなった時に、意外な感じがした。テレビコマーシャルで「芸術は爆発だ」と叫んでいた頃、すでに七十歳代だったはずだが、老いるとか、ふけるということはこの人には無縁のことと思われた。活火山のように噴き上げ続ける永遠の青年というイメージであった。
岡本太郎が亡くなった翌年、私は縄文土器を見て強く感じるものがあり、それ以来、岡本太郎の書いたものに強く引かれるようになった。絵画、彫刻といった造形作家であるばかりでなく、彼は立派な思想家である。その岡本太郎の本は絶版になったものが多く、手に入りにくかったが、私と同じように岡本太郎の本を読みたい人間が増えたせいだろうか、みすず書房から「岡本太郎の本」として、次々と復刊されだした。またこれに先立って、岡本太郎の秘書であり、養女であった岡本敏子の『岡本太郎に乾杯』が新潮社から出版された。岡本太郎を見るだけでなく、読むことが可能になったのである。
特に岡本敏子の語る、『岡本太郎に乾杯』は岡本太郎という存在の魅力を見事に描き出している。岡本太郎への恋文と言っていいかもしれない。これを読むと岡本太郎の作品を見たことのない人でも岡本太郎のファンになってしまうのではなかろうか。 その岡本太郎の自宅兼アトリエが、岡本太郎記念館として現在一般公開されている。東京の青山にあるが、通りから奥に入った閑静な場所にある。一歩中に入ると、庭からすでに岡本太郎ワールドである。座ることを拒否する椅子があるかと思えば、角をはやした釣り鐘がぶら下がっていてたたくことができる。館内では意外に小柄な岡本太郎人形が出迎えてくれ、画室では未完成の絵が鮮やかな原色を発している。太陽の塔はここで生まれた。彼のエネルギーと時代のエネルギーがここでぶつかり合ったのである。
太郎と敏子(濫読のすすめ21) (2000年2月5日号)
前回、岡本敏子の『岡本太郎に乾杯』について書いたが、岡本敏子による岡本太郎の本が次々と刊行されている。一九九九年に、『芸術は爆発だ・ 岡本太郎痛快語録』、『岡本太郎が、いる』、『太郎神話 岡本太郎という宇宙をめぐって』とたて続けに出された。前二者は 岡本敏子の自著であり、後一者は岡本敏子による編書で、さまざまな人々の書いた岡本太郎についての文章を年代に区切ってまとめたものである。どの本も興味深く、岡本太郎が何を考え、何をしたのか、何をしようとしていたのかを伝えてくれる。
『岡本太郎に乾杯』でもそうだったが、岡本太郎にとって、岡本敏子という存在がいかに重要だ ったかが、これらの本を読むとよくわかる。岡本太郎には、群れを作らない一匹狼の芸術家というイメージがあり、まさに太陽のように、虚空に向かって、一人で爆発し、一人で輝き続けるという明るい孤独者という印象があった。「太陽の塔」は、そういう彼の自画像のようにそそり立っていた。
その印象は間違っていたとは思わないが、岡本太郎は自らは公言しなかったが、岡本敏子という存在が、常に彼のそばにあり、その芸術、著作、あるいは旅行、遊びといった生活のすべての場面にともに参加していたのである。その参加のしかたというのは、秘書とか、養女という立場で考えられる以上のものであったようだ。精神的な夫婦、あるいは恋人のようなものと言ってよいのかもしれないが、それとも少し違う。パートナーはパートナーなのだが、芸術家のパートナーとして、彼女のような存在は、あるいは、この二人のような関係は珍しいのではないだろうか。
昨年末に広島でダリの展覧会があったが、ダリにはガラという妻がいた。ダリはガラを美の女神として、自分の芸術創作の原泉はガラであると常々語っていた。またしばしば、ガラをモデルにして絵を描いている。そのガラの存在に比べれば、岡本敏子の存在の何とつつましやかなことだろう。岡本太郎と親交のあった人は別として、私のように、作品を通してしか、あるいは著作を通してしか岡本太郎を知らなかった者は、岡本敏子の存在について知らないのが普通だったろう。岡本太郎の絵画や著作には彼女は登場しないのである。ところが彼女は、描かれる側ではなく、ともに描き、ともに書く側に立っていた。そして、太郎の死後もそれを続けているのである。
太郎の鯉のぼり(濫読のすすめ22) (2000年6月30日号)
今年は鯉幟(以下「鯉昇り」と書かせてもらう)を揚げなかった。二人目の子が小学校に入学し、昼間にいないのに揚げてもしかたがないという話になった。子どもも、もう揚げなくていいという。なんだか寂しくなった。 その前の年も一番揚げたいのはお父さんだろうと冷やかされた。 男の子が生まれてうれしかったのは、キャッチボールができることと鯉昇りを揚げられることだった。キャッチボールは生まれてすぐには無理だが、鯉昇りは一年目から揚げられる。初めて鯉昇りを揚げた年、自分の子どもは何もわからないのだが、近所の子どもが大勢集まってきた。マンションやアパート住まいの子が多いのだが、ベランダの小さい鯉昇りではもの足りなかったのだろう。ある子などは町中の鯉昇りを見て回って家で報告するので、「鯉昇り評論家」と呼ばれたという。勝手に揚げ降ろしまでされるので閉口したが、揚げてよかったと思った。それ以来十年近く揚げ続けた。 東京の青山にある岡太太郎記念館に行ったときのこと、展示作品の中に鯉昇りがあるのを見つけて、妙にうれしくなった。ああやっぱり岡本太郎も鯉昇りが好きだったんだと思った。目ん玉がやたらに大きくて、そこから何本もの炎のような筋が放射されていて威勢がいい。これはぜひ空を泳いでいるところを見てみたいと思った。広島市民球場にも揚げてみたい。
昨年の十一月に刊行された『芸術は爆発だ!岡本太郎痛快語録』(小学館文庫)を読んでいたら、鯉昇りについて語った言葉があった。「鯉のぼり、いいねえ。あんな大きな魚が空を泳ぐんだよ。凄いイマジネーションじゃないか。それも、一人の芸術家の創作じゃない。普通の民衆がみんなで自然に持ってるイメージなんだ。世界中にひろめたいな」そう言われれば芸術家が鯉昇りを初めて作ったのではない。生活の必要から生まれたものでもない。民衆の中に生まれ、それぞれが持っているイメージで泳がしてきたのだ。初夏になると日本中のいたるところで若葉の風に吹かれて鯉昇りが泳ぐのである。これは芸術であり祭りである。この精神はまた「太陽の塔」にも共通するものでもあろう。みんなで自然に持っている太陽のイメージ。それを彼は祭りの場に建てたのだ。鯉を空に泳がせることに比べればはるかにまともな発想だ。そして子どもたちが喜んだ。太陽の塔も空を泳ぐ彼の鯉昇りだろう。
最後のストライク(濫読のすすめ23) (2000年10月27日号)
秋風とともに野球シーズンが終わりを迎えた。セ・リーグは巨人が圧倒的な戦力で独走し、ほとんど見せ場のないままに 九月中に優勝が決まってしまった。広島カープは江藤の巨人への移籍と、主力選手の相次ぐ故障で不本意な成績に終わった。開幕の東京ドームでの対巨人戦の勝ち越しと、九月の広島市民球場で巨人の胴上げを阻止したのがせめてもの慰めである。
今年のカープはストッパーの不在に泣かされ続けた。九回までリードしながら逆転負け、サヨナラ負けをする姿に歯ぎしりしたファンは多いだろう。カープが優勝を争う時には名ストッパーがいた。初優勝の年の宮本、日本シリーズ制覇の年の江夏。その後の大野豊。そして何よりもファンの目に焼き付いているのは「炎のストッパー」と呼ばれた津田恒美だろう。津田が亡くなって今年で七年になるが、七月に津田を主人公にしたテレビドラマ「最後のストライク」が放映された。夏休み中だったので見た人も多いだろう。
津田が亡くなった翌年にはNHKで津田を描いたドキュメンタリー「もう一度、投げたかった」が放送された。私はこの番組で津田の闘病生活を知ったが、今回のドラマは津田の活躍の時代よりも闘病から死に至るまでに重点を置いたものだった。
津田が常に手にし、今は妻の晃代さんの手元に残されたボールには「弱気は最大の敵」と書かれている。津田は球はめっぽう速いものの、気が優しく「ノミの心臓」と呼ばれた高校球児だった。その津田にこの言葉を教えたのはコーチとして招かれた早稲田のエース道方康友だった。私の大学時代、道方は後に巨人のエースとなった法政の江川卓と投げ合っていた。道方は津田が自分の言葉を支えに投げ抜いたのを番組で知って胸が熱くなったという。
新人王を取り、抑えに転向後は躍り上がるようなフォームで一五〇キロのストレートを投げ込んだ津田。しかしその津田を脳腫瘍という病魔が襲う。病名を知って子供のように泣きじゃくる津田に妻の晃代は絶対に治ると言い聞かせる。そして食事療法を中心にした東洋医学を自ら学び、献身的な看病を続ける。道方の言葉は妻の晃代にも受け継がれたのである。
歩くことさえできなかった津田は奇跡の回復をしトレーニングジムに通うまでになる。津田はよく歌の「愛は勝つ」を口ずさんだという。しかしついに最後の時が訪れる。二人の軌跡は今番組と同名の本に収められている。
二十世紀の歎異抄(濫読のすすめ24) (2001年2月3日号)
二〇〇〇年の十二月三十一日にこの原稿を書いている。二十世紀もあと数時間で終わりである。「二十一世紀に遺したい本」というのが今号のテーマだということで、私にとって何にあたるか考えた。二十世紀の間に書かれた本ということなら少しは限られてくるが、それ以前のものを含めて考えれば大変な数になる。いわゆる古典というものは数百年、あるいは千年、二千年と読み継がれたものだから、当然二十一世紀にも読み継がれるだろう。二十世紀に書かれたものの中から、今後古典として何百年も読まれるものを見つけるのはなかなか難しい。
そう考えているうちに一つ思い至ったものがある。すでに古典であったにも関わらず二十世紀になって再発見されたものである。それは『歎異抄』である。鎌倉新仏教の親鸞の説明で、必ずといっていいほど引用されるものなので、これが二十世紀になって発見されたというと驚かれるかもしれない。
『歎異抄』は親鸞の没後に、親鸞の弟子であった唯円が書いたと言われる親鸞の語録である。そうであれば当然教団内で聖典扱いされてしかるべきなのだが、室町時代の真宗中興の祖であった蓮如によって一種の禁書の扱いを受けてしまった。『歎異抄』の奥書には「右この聖教は当流大事の聖教となすなり。宿善の機無きにおいては、左右無くこれを許すべからざるものなり」(原漢文)と書かれ、蓮如の署名がある。
この奥書の「宿善の機無きにおいては」という書き方からすると、いわゆる悪人正機説の誤解を恐れてのことだったのかもしれない。宗門の者にとってこの封印を解くことは並々ならぬ勇気を要する。それをなしたのが真宗大谷派(東本願寺)において宗門改革を押し進め、一度は除名にあった清沢満之を中心とする人々だった。一九〇〇年(明治三十三年)、東京の清沢のもとに「浩々洞」と呼ばれた同志が集まり、翌一九〇一年(三十四年)『精神界』という雑誌を発行する。
このころ清沢が愛読したのが『歎異抄』であった。この『精神界』から暁烏敏、曽我量深、金子大栄といった『歎異抄』の語り手が輩出する。『歎異抄』は二十世紀の古典なのである。それが提起した人間と悪の問題は戦争の世紀と呼ばれた二十世紀の人々の心を捕えた。二十一世紀の人々にとってこの問題は二十世紀の特殊な問題で済んでいるだろうか。
童謡を聴く時(濫読のすすめ25) (2001年6月29日号)
人がその一生で童謡に耳を傾けるのは、どのような時だろう。
第一は幼少時代。童謡は子供のために作られているのだからこれは当然 だろう。その時代に子供がその意味を本当にわかっているかと言えば、それはどうかわからない。 文語調の曲の場合は詞がわかっていないこともあるだろうし、口語の歌詞であっても、何となく聞いて、うれしくなったり、しんみりしたりしていたのだろう。しかしそれがその後の基礎となる。
第二は親になってから。子供が生まれると、あるいは気の早い人は胎教のために子供が生まれる前から、子供にどんな曲を聴かせればいいか考える。その中にクラシックの名曲もあるだろうし、α波ミュージックもあるだろうが、童謡も当然のように入るだろう。
私もそうで、長男が生まれる時にひととおり買いそろえた。中でもダ・カーポの歌った「抒情歌ファンタジーおもいでの贈りもの」という二枚組のCDは名盤だった。
ここまで童謡と書いてきたが、唱歌も含めて抒情歌と言う方が適切かもしれない。童謡という言い方は対象者を示す言い方だが、抒情歌という言い方は、対象者を限定せず、曲のあり方を示している。童謡だと思って聞いているものは実は抒情歌なのだろう。
親となって聞いた童謡は子供のためよりも、むしろ自分のためになってしまった。童謡の再発見である。子供の頃には気 がつかなかったものがそこにはいっぱいつまっていた。
北原白秋の再発見もその一つだった。ダ・カーポのCDには四十曲の抒情歌が入っていたが、そのうち北原白秋作詞の曲 が四曲ある。「まちぼうけ」、「この道」、「砂山」、「からたちの花」である。このうち三曲が山田耕筰の作曲である。私がこの中で特に好きなのは「この道」と「からたちの花」である。北原白秋は言葉の魔術師と言われたが、先にあげた四曲の詞はいずれも口語で平易に書かれていて、耳で聞いてすぐわかる。しかしそこにこもっている思いの深さは言いしれぬものがある。
まもなく九三年の本校の『研究紀要』に『北原白秋を読む』を百ぺージほど書いたが、昨年度までおられた音楽の山本先生がたいそうほめて下さった。求めているものが重なっていたのだろう。
童謡を聴く第三の時は年代を超えた時である。昔に戻るという意味ではなく子供に返るとき。人が本当に子供に返るのは魂の親と出会う時である。
里の秋(濫読のすすめ26) (2001年11月16日号)
秋祭りが近くなったある日曜日の朝にラジオを聴いていると、童謡歌手の川田正子さんのインタビユーが放送された。八歳でデビューして歌手生活六十年になるという。
現在活躍中の歌手で、はたして六十年歌手活動を続けられる人がどれほどいるだろうか。若者向きの歌を歌っている人にはまず無理だろう。川田さんの歌手としての力も当然のことながら、童謡というジャンルに負うところが大きいと思う。子供のころに聴いた歌が忘れられなくて、それこそ「三つ子の魂百までも」であって、一生聴き続ける。しかもその聴き方が年とともに変化してくる。川田さんの歌を聴いてきた人は川田さんとともに戦中戦後の苦難の時代を過ごし、今定年後の穏やかな時を向かえている、そんな人が多いのではなかろうか。
六十周年記念コンサートが近いという川田さんの歌がインタビューの後に放送された。歌は作詞が斎藤信夫、作曲が海沼実の『里の秋』であった。秋の夜の曲だが、朝聴いてもしみじみとしたものがあった。私は特に一番の歌詞が好きである。 「しずかな しずかな 里の秋 お背戸に木の実の 落ちる夜は ああ かあさんと ただ二人 栗の実 煮てます いろりばた」
この歌詞が子供のころの自分の生活と重なるのである。私が幼いころ、 父は夜勤があったので、母と二人で夜を過ごすことが多かった。秋や冬の夜になると世の中全体が静まりかえる中、風の音だけが響いて、ストーブの上でやかんが音をたてているということがよくあった。時にはやかんのかわりに煮物のなべがコトコトと鳴っていた。
私が小学校の後半になると父は転勤があり、単身赴任となった。どうして一家転住とならなかったのかよくわからないが、 家と畑があったので人手に任すわけにいかなかったのだろう。それまで以上に母と二人の夜になった。正確に言うと弟が生まれていたので母と子の三人の生活になった。
この曲を聴くとそのころのことを思い出す。こんな生活をしている人は 多いのだろうなと思っていた。ただ「いろりばた」 が出てくるので、どこか東北の山里で、父親は都会に出かせぎに出ているのかと思っていた。
ところがそれは全くの誤解であった。今から六十年前の一九四一年の十二月下旬にこの歌の歌詞は作られたのだった。一九三七年に日中戦争が始まり、一九四一年十二月八日に太平洋戦争が始まった。作詞者の斎藤信夫は戦時色一色の中で好きな童謡を作ることができず悶々としていた。そんな時、戦地にいる父への慰問文形式の歌を考えついた。一番は父にあてた家庭の現況報告なのである。戦後になってこの歌は日の目を見るが、その時には復員兵を待つ歌に書き換えられた。三番は船に揺られて帰る父の無事を祈る歌詞である。このことを私は『唱歌・童謡ものがたり』(一九九九年岩波書店)で知った。私は幸せな誤解者だった。
この歌詞が生まれて六十年。歌として還暦を迎えた。そして今自衛隊が海外に出ようとしている。この歌を誤解なしに聴く子がこの日本にまた生まれるのだろうか。
読み続けてきた本 四半世紀を越えて( 特集「卒業生におくる一冊の本」より)
(2002年2月2日号)
私が長年関心を持ち続けてきた本は、いずれも高校生の時に授業で習ったものである。一つは親鸞の『歎異抄』、もう一つが芭蕉の『奥の細道』である。『歎異抄』は、私見を述べた本を出し、今も雑誌に『歎異抄』をテーマにした連載を続けている。
『奥の細道』は授業で扱うことが多く、その行程を何回かに分けて回っている。研究紀要にも書いた。主なところはほぽ回ったが、すべてを見るにはまだ時間がかかりそうだ。同じ場所でも、もう一度行ってみたい。
この他にも『古事記』『方丈記』など、何回も読み返し、今だに関心を持ち続けているものがある。いずれも、高校のころ初めて読み、大学入学後に本格的に勉強をしたものである。『古事記』についてはこの春に本にまとめる予定である。
これらの本とのつきあいは四半世紀を越えた。諸君にもそういう本に出会ってほしい。
『奥の細道』時の旅人(濫読のすすめ27) (2002年2月2日号)
「卒業生におくる本」の中に『奥の細道』をあげた。その旅程を何度かに分けて回っている。大学のころから部分的には行っていたが、全旅程を回ってみようという気になったのは教員になってからである。授業で教える際に、行ったことがない場所をさも見てきたように言うのは気がひけた。また芭蕉の文体が簡潔で省略が多いので実地を見ないとよくわからないという面もあった。
しかし何よりも文章と発句の魅力が、それが作られた土地に行ってみたいという気持ちを起こさせる最大の要因だろう。
「月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。」この書き出しはあまりにも有名だが、『平家物詩』の冒頭や『方丈記』の冒頭と並ぶすぐれた書き出しだと思う。いずれも無常観が述べられているが、日本文学における無常観の重要性を思う。「無常」と「あはれ」を抜いてしまうと、日本文学らしさはなくなってしまうかもしれない。「無常」と「あはれ」は深く結びついていて、季節の移り変わりの中で詠まれる俳句はその典型だろう。紀行は旅だから自らを進んで無常の中に投げ入れることである。そうして自らを投げ入れながらも、その流れに流されるだけではない。自ずとその流れから浮かび上がって輝き出してくるものがある。『奥の細道』はその絶妙の組み合わせなのである。何度か足を運ぶうちに、芭蕉が見たものの中で、時の流れの前に崩れ去ったものも、あるいは生き残ったものも見てきた。『奥の細道』のハイライトと言っていい平泉の中尊寺の金色堂、山形の立石寺、出羽三山の月山、湯殿山などは、芭蕉が見た状態にかなり近いから芭蕉が感じたものを追体験することができる。
その一方で、まったく様相を変えてしまい、跡かたも残っていない所も多い。そもそも芭蕉の旅は、東北、北陸の各地に散らばる歌枕を見ようとする旅であった。ところが歌だけ残って歌枕はすでに消えているということが芭蕉の当時でもあった。「むかしよりよみ置る歌枕、おほく語伝ふといへども、山崩、川流て、道あらたまり、石は埋て土にかくれ、木は老て若木にかはれば、時移り代変じて、其の跡たしかならぬ事のみ」と書いている通りである。芭蕉の旅から三百年して我々が回れば、残っている方が奇跡なのかもしれない。
芭蕉が見たものの中で、それ以後に最も劇的な変化を遂げたのは秋田の象潟であろう。象潟は日本海側にあるが、太平洋側にある松島と好対照をなしており、芭蕉の旅の重要な目的地である。「松嶋は笑ふが如く、象潟はうらむがごとし。寂しさに悲しみをくはえて、地勢魂をなやますに似たり。」と芭蕉は書いた。繊細な多島美をはかなげな美女にたとえている。
その印象通りと言うべきか、その後象潟は大地震で海底が隆起し、湾に浮かんでいた小島は地上の丘になってしまった。名勝は一日にして消えてしまったのである。
しかしまだ丘は残っている。そこには松もはえている。当時の面影をしのべなくはない。残ったものと消えたものと。芭蕉とともにしばし時の旅人となる。
『大漢和辞典』(大修館)( 特集「座右の辞書・事典」より)(2002年6月28日号)
我々は辞書があるのが当たり前と思っているが、辞書が本格的に作られ普及したのは明治時代に学校制度が始まってからだろう。私は親鸞の著作をよく読むが、鎌倉時代は辞書がないから、親鸞は頭の中の辞書で膨大な漢語の仏教用語を一語一語吟味しながら著作をしている。その形跡が本人による語注という形で著作中に残っており、時には独創的な語釈もある。こういった先人の苦労の上に、さらにそれを集大成する学者の苦労があり、現在の辞書がある。
どの辞書にもその苦労は宿っているが、とりわけそれを感じるのは『大漢和辞典』(大修館)である。諸橋轍次という大学者と鈴木一平というたたきあげの出版人の二人三脚で、戦災による原版消失という苦難を乗り越えてこの辞書は生まれた。親字五万、熟語五十万を収録する漢字文化の大百科である。いずれ電子化されるかもしれないが、全十五巻の重みを感じたい。諸君も一度は手にとってほしい。
玉(ぎょく) (アートらんだむ1) (2002年6月28日号)
昨年世界四大文明展が日本各地で開かれ、広島ではそのうち中国文明展が開かれた。それから一年して、それとは別の企画で古代エジプト文明展が広島で開かれた。内容的には昨年のものと遜色なかったのではなかろうか。一年の間隔を開けて、両方を見ることができた。
文明展では必ずといっていいほど一番の見所が宣伝に使われる。今年のエジプト文明展ではプスセンネス一世の黄金のマスクだった。王のミイラにかぶせられていたというもので、ツタンカーメン王のマスクと並ぶ名品と言われている。会場では特別に一室が設けられてこのマスクが陳列されていた。照明を落とした室内でまさに永遠の輝きを放ち、王の威厳と魂の不死を示していた。
エジプト文明は黄金文明とも言われるが、まさにそれを象徴する作品である。黄金の魅力は今も昔もかわらないし、世界のどこに行っても通用するものだろう。家に帰ってから書いた子どもの日記を見るとこのマスクが精巧に表情をもって描かれていて感心した。
一年前の中国文明展を思い起こすと、そのときの目玉は玉(ぎょく)の棺だった。正確に言うと、死者の身体をすっぽりと覆う玉の衣である。正方形の青緑の玉片を二千枚以上、銀の糸で一枚ずつ結び合わせて作られたものである。中国人がいかに玉を愛していたかがよくわかる。
エジプト展の黄金のマスクと比べた場合は黄金のマスクの方が見栄えはするだろう。中国人も黄金を軽視したわけではない。中国文明展でも黄金の品はあり、日本の志賀島で発見された「漢委奴国王」の金印とよく似た漢王の金印があった。しかし金と玉とどちらをとるかと言われたらおそらく古代中国人は玉を選んだに違いない。自分の魂を包むのは玉なのである。
私が心惹かれたのは白玉杯である。玉は大きく分けて青緑色のものと白色のものがあるが、中国文明展の白玉杯は名品だった。何の飾りもなく、ただ磨き上げただけで、生地の魅力を引き出している。見つめるほどに引き込まれていく。
黄金の力はそこから出てきて人をひれ伏させるものがある。発散し圧倒する。玉の力は人を引き込む力である。虜の仕方が違う。その虜になるのは中国人やその影響を受けた漢字文化圏の人だけなのだろうか。玉杯は静かに光を納めていた。
『土佐日記』(特集「旅へのいざない」より) (2002年11月13日号 )
高二の諸君は古典の授業で『土佐日記』を読んだが、授業で読んだのは冒頭の「門出」と結びの「帰京」だけだった。肝心の船旅の部分が抜けてしまったので、もし時間があれば現代語訳でよいから読んでもらいたい。
私もあちこち出歩いて紀行文のまねごとのようなものを書いてきたが、日本での紀行文のはしりが『土佐日記』と言ってよい。旅の中で見聞する新しい景物はもちろん紀行文の中心だが、そこに描かれる昔の人々の心情が興味深い。
この夏に私は近畿に行ったが、そのときに大阪の住吉大社に立ち寄った。住吉大社は海の神として有名で、昔は海辺に面して、難波江の入り口に当たる場所にあった。難波は浪速とも書くが、航海の難所であったようだ。河口が近く潮の流れが複雑だったのだろう。
『土佐日記』によると、一行を乗せた船が住吉のあたりに近づくと、突然海が荒れた。そこでまず神に幣を奉るのだが効果がなく、ますます波風が強くなる。そこでもっと神が喜びそうなものを奉れという船頭のすすめで、一つしかない大事な鏡を海に投げ入れる。すると突然海は鏡の面のように鎮まったと言う。
卑弥呼が鏡を好んだと言われるが、鏡が呪力を持ち、神と人を結ぶ重要な捧げ物だったことがこの記事からもわかる。卑弥呼が魏に送った使いも海に鏡を投げ入れながらやっとのことで荒海を渡ったのだろうか。その時代から続くものが『土佐日記』にも見えるようだ。
『月光』(アートらんだむ4) (2003年6月27日号 )
「I am God's child この腐敗した世界に堕とされた How do I live on a such a field」『月光』(作詞作曲・鬼束ちひろ)という曲の歌い出しである。このフレーズの「God's child(神の子)」は印象的である。自分を「神の子」と呼ぶのはキリスト教徒にとっては憚かられるだろう。汎神教的考え方が強いと言われている日本人でも正面きって言うのはためらうのではあるまいか。
自分が「神の子」という自覚を持てばどうなるのだろう。この自覚が本物ならばこの世界も「神の国」になるはずである。しかしこの曲ではこの世界は「腐敗した世界」であり、「こんな場所でどうやって生きろというの」と続く。自分が「神の子」であると自覚し始めた、あるいはそういう予感をもったときの、この世界との違和感を歌っているのだろう。
「神の子」とまでは言えないまでも、自分の中の純粋性を自覚したとき、この世界にいることが耐えられないという感覚は多くの若者の中にあるはずである。その感覚とどう付き合うか。それによってその人の人生は大きく変わるだろう。ある人は一時の気の迷いだと思ってできるだけそれを忘れようとするかもしれない。あるいは世界はこんなものだと思い、何とか折り合いをつけようとするかもしれない。人によっては自分の正しさを信じて「腐敗した世界」を変えようとしようとするかもしれない。あるいは自分の心の中にだけはその世界を維持しようとして芸術や宗教に関わっていくかもしれない。
この歌では「貴方なら救いだして 私を 静寂から」とこの感覚を得たことによる苦しみとそこからの救いの希求が歌われる。この「貴方」が神ならばキリスト教で言う「神の沈黙」が破れるのを待たなければならない。あるいは「貴方」は魅力的な異性やあるいは真実を知った覚者なのか。この「貴方」が何かによって救いの内容は変わるが、究極的には「愛」になるはずである。どれを選ぶかは「あなた」次第である。
『平家物語』(特集「歴史と文学」より) (2006年7月18日号)
『平家物語』は国民文学として中学の国語教科書に採られる数少ない古典作品の一つである。二年生の教科書に入ることが多く、現在本校で使っている教科書ではその冒頭部分と「敦盛の最期」が載せられている。
その有名な冒頭は「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。」で始まる。『平家物語』はこの「鐘の声」に象徴される「無常の響き」が主調音を奏でていると言われる。この読み方には異論もあり、小林秀雄はその戦闘場面の鮮やかな描写から健康的な「肉体の文学」として読むという見方を提示している。私も若い頃はその見方にうなずくものがあった。源義経の活躍に喝采を送りたくなる気持ちはよくわかる。
しかししだいに年齢のせいか、武士達の血湧き肉躍る戦いも、義経の常人離れした活躍も、すべては滅びの序章にすぎないと感じるようになった。彼らは滅びるからこそ一瞬の輝きを放つのである。
「敦盛の最期」は一ノ谷の合戦で功を立てようとした熊谷直実が、海上に逃れる平家一門の中から将軍とおぼしき武者に組み付き、首を取る場面である。刀を立てようとした武者は歳わずか十六、七の美少年、敦盛だった。その姿は直実自身の息子の姿と重なり、直実は命を助けようとする。
しかし早く首を取れという若武者の声と背後に迫る味方の軍勢の声に押され、泣く泣くその首を取る。「あはれ、弓矢取る身ほど口惜しかりけるものはなし。」と嘆いた直実はその後出家して法然上人の弟子となり、蓮生と名乗ったという。
岡山の誕生寺はその熊谷直実が法然の生誕地に建てた寺である。私はこの春そこを訪れた。寺には法然像と熊谷直実の像がある。法然像は普段は見ることができないが、直実の像は見ることができる。いかにも坂東武者らしい、いかつい顔である。このいかつい顔が敦盛の首を取るときの苦しい表情が目に浮かぶ。
敦盛は自らの命と引き替えに僧蓮生を生み、その蓮生がこの寺を建てた。直実は敦盛に自らその菩提を弔うことを誓っている。ここには勝者も敗者もない。私が直実の像を拝して境内に出ると、時の鐘が鳴り始めた。その鐘の音は静かに山里に響きわたり、余韻を残して再び時の中に消え去った。
コラム「背表紙」(特集「歴史と文学」より) (2006年7月18日号)
厳島神社は平清盛の造営によって現在の姿になったと言われている。その平家一門が神社に納めた『平家納経』は『法華経』を筆写したものだ。
以前、広島県立美術館で『平家納経』の展覧会が開かれた時に実物を見ることができたが、経文を写す紙の装飾に見えるきらびやかさは平家一門の栄華そのものだった。
ただそのきらびやかさと経文の内容の間にかなりの隔たりがある。平家は写経の功徳により栄華の存続を祈ったのだろうが、その祈りは無常の風の前に虚しく潰え去った。
今年の連休のはじめに私は厳島神社を見下ろす高台にある千畳閣で「平曲」を聞いた。「平曲」はかつて琵琶法師が『平家物語』を演じたもので、現在これを伝えている人はごくわずかである。そのうちの一人、荒尾努氏がその日の演者だった。
演目の中でひときわ私の心を揺さぶったのは、平家が壇ノ浦で滅ぶ「先帝御入水」の場面である。ちょうどその日はなぜかその時間に風が強く、目を閉じて聞いていると波が高かったというその日の壇ノ浦にいるような臨場感がある。堂内を吹き抜ける風の中に平家一門の嘆きの声が混じっているかのようだ。壇ノ浦に臨む寺で「平曲」を演じたという「耳なし芳一」の姿が荒尾氏と重なる。
私は荒尾氏演奏の「平曲」のCDをもっているが、そこにはこの風はない。吹き抜ける風の中でこの物語が今も生き続けていることを実感したひとときだった。
『出口のない海』横山秀夫・原作(特集「観てから読む?読んでから観る?映画と原作」より)
(2007年3月1日号)
私が特攻のことを正確に知ったのは小学生の時に読んだ『知覧』という本を通してだ。鹿児島の知覧に陸軍の飛行機特攻基地があった。今そこに知覧特攻平和会館がある。そのそばにミュージアム知覧という博物館がある。ここに「隠れ念仏」の展示がある。江戸時代に薩摩藩は浄土真宗を禁じた。そのため「隠れ切支丹」と同様に信者が迫害を受け殉教者が出た。この二つの殉難は性質は違うが、知覧は私にとっては忘れられない地だ。
日本軍は飛行機による特攻の他に戦局の悪化に伴い数々の特攻を行った。戦艦大和の洋上特攻もその一つ。私が知覧を知るころに知ったものに陸軍暁部隊のモーターボートに爆弾を積んで敵艦に体当たりする特攻がある。この特攻を知る人は少ないだろう。実は私の伯父がその特攻隊員で、少し終戦が遅かったら自分はここにはいないとよく聞かされた。その伯父もすでにこの世の人ではない。
『出口のない海』は魚雷に人間が乗り込み操縦する日本海軍の人間魚雷「回天」による特攻を描く。回天の実物は広島では呉の大和ミュージアムで見ることができる。
主人公は甲子園の優勝投手で大学進学後に肩を痛めた並木浩二。肩を痛めても投げることができる魔球を編み出そうと努力するが完成しないうちに学徒動員で海軍に入る。
回天への搭乗員になることが決まり、死ぬための猛訓練を重ね自分の死と向き合って生きる日々。一方で生きていることの証のように魔球完成への情熱を燃やす。もう一つ彼の生の証は彼を幼い時から慕う恋人の存在。しかし回天の搭乗員は絶対に自分の配属先や出撃を明かすことは許されない。夜毎の特訓が実り魔球が完成したかに思えた時、ついに出撃の命令が下る。
回天は潜水艦の甲板に固定されて外洋に出て、敵艦発見後に体当たりする。映画はこの潜水艦内の場面から始まる。回想を交えながら刻一刻と出撃と目前の死に向かって緊迫した場面が展開する。同僚が出撃し爆音とともに命を散らし、そしていよいよ自分も出撃という時、思わぬ事態が起こる
助かったかに見えた並木を別の運命が待ち受ける。確かに彼の海に出口はなかった。しかし恋人への遺書は一編の詩。最後の一球は彼女の胸にしっかりと受け止められた。
コラム「背表紙」(特集「観てから読む?読んでから観る?映画と原作」より)
(2007年3月1日号)
文学作品が映画化されたり、アニメやドラマになることでより多くの読者を獲得することがある。また先に文学作品を読み、これは映画でも見たいなという作品もある。
もっとも原作とは別の作品になってしまうこともあるから要注意。昨年夏に公開の『日本沈没』は昔原作を読み、前回映画化されたものも見たので今回も期待したが、あまりに原作と違う作品となっていてとまどった。
紹介する『かはたれ』と『たそかれ』は河童が主人公の二部作。児童文学だが三世代で読みたい作品だ。挿絵が多いのでそれも映画化された時の想像をかきたてる。以前はファンタジーは実写映画では難しかったが、今はコンピュータ・グラフィックの発達で何でも表現できる。原作に忠実に映画化してほしい作品だ。
いずれも舞台は古都鎌倉だが、『たそかれ』には戦争での空襲の場面がある。広島の人が読めばこれは広島が舞台なのではないかと思うだろう。実は作者の朽木祥は広島出身の被爆二世。そのことがこの作品の背景にある。平和を願う作者の思いがファンタジーを通し見事に表されている。
クライマックスは「耳に聞こえない音楽」を人、河童、犬が心を一つにして聞き合う場面。そういうものがあることを信じさせてくれる作品だ。
川端康成『美しい日本の私』(特集「ノーベル賞をめざす君へ」より) (2009年3月7日号)
二○○八年のノーベル賞の発表で驚いたのは南部陽一郎の物理学賞受賞である。一九九○年に私は彼のことを授業で紹介したことがある。教科書にタイムマシンについて述べた教材があった。その関連で最新の物理学理論を調べた際に彼のことを知った。私はある本に彼の名を書いたので今回その名を聞いて驚いた。
南部陽一郎の話をしたのは国語の授業でのことだが、国語教師として私が深く関わったのは、一九六八年に日本人で初めてノーベル文学賞を受賞した川端康成である。
その『伊豆の踊子』は長らく高校教科書の定番作品となっていた。高校の国語教材の中で私が特に好きな作品の一つだった。『伊豆の踊子』は何度も映画化され、読みやすい作品なので、中学生、高校生にはぜひその全編を読んでもらいたい。
それとともに読んでもらいたいのは彼のノーベル賞受賞記念講演である『美しい日本の私』である。川端がノーベル文学賞を受賞した時に私はまだ十歳だったので、その記念講演を本で読んだのは後のことだ。そこに書かれた世界のことは、みな私の好むものだった。驚いたのは、文学者である彼が多くの日本人僧侶の言葉や和歌を紹介し、それらが自分の作品の背景となっていることを語っていたことである。
道元、明恵、良寛、一休、親鸞、西行と、まるで日本仏教の紹介のようだ。特に明恵の歌の紹介には多くがさかれ、そこに「元仁元年(一二二四年)」の詞書きをもつ月の歌が紹介されている。「山の端にわれも入りなむ月も入れ夜な夜なごとにまた友とせむ」
元仁元年は親鸞の『教行信証』に縁が深く、浄土真宗ではこの年を立教開宗の年としている。明恵と親鸞は同じ年に生まれ、明恵は華厳宗、親鸞は浄土真宗と宗派は異なるが、二人の人生の間には深い相関関係がある。
川端が紹介した明恵の月の歌には元仁元年の歌とともに、「あかあかやあかあかあかやあかあかやあかやあかあかあかあかや月」という歌がある。
親鸞の『教行信証』には「月愛三昧」(がつあいざんまい)という美しい言葉がある。苦しむ者を救おうと如来が光を放つ三昧の境地を表すものだ。仏教を知らなくてもそのイメージが湧く。親鸞も明恵と同じ月を眺めていたに違いない。
『引き出しの中の家』 朽木祥・著(「旬の本だな」より) (2010年7月3日号)
「花明かり」って何でしょう。心の中の引き出しにどうぞ。
『八月の光』 朽木祥・著(「旬の本だな」より) (2013年3月2日号)
広島で「八月の光」と言うと太陽よりももっと強烈な光がありますが、それだけではありません。
 コラム背表紙「たそかれ」
コラム背表紙「たそかれ」
(2007年3月号 特集 観てから読む?読んでから観る?映画と原作)
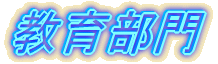
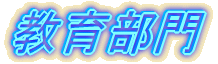

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()