

このページの内容
2013年12月30日版「宗教と平和」
『アジア・太平洋戦争を考える視点』の紹介
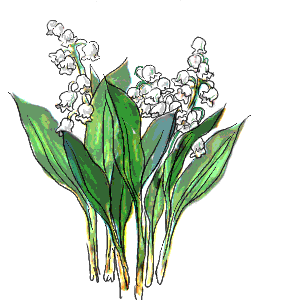
2013年12月30日版
「宗教と平和」
『和の光 文学と平和』(2015年刊に収録)
![]()
『流光』(修道中高等学校発行 被爆50周年記念誌 1995年11月4日発行)より p145〜p150
心の被爆者
『和の光 文学と平和』(2015年刊に収録)
修道中学高等学校教諭 渡辺郁夫
終戦五十周年の夏が終わろうとしている。原爆記念日のころ内外の訪問者で異常なにぎわいをみせた平和公園
は、再びいつもの静けさを取り戻している。今年の盛り上がりはいったい何だったのだろう。半世紀を過ぎて老いた
被爆者やその関係者にとっては、今年は自分達の思いを伝える最後の夏だったのかもしれない。五十周年まで
は何とか続けたいという思いは被爆者のみならず、先の戦争被災者や遺族に共通した思いだったかもしれな
い。特に年老いた母親にとっては。毎年蝉しぐれを聞くと私は夏の訪れとともに原爆とその被災者のことを思
うが、蝉はいつまでも鳴き続けるわけではない。やがてばったりと声の途切れる時が来る。この夏の盛り上が
りは、秋が近づくにつれてかえって祭の後のような虚しさを残しはしないか。八月も終わりに近づいた今、私は
秘かにそれを恐れている。そうしてこれから鳴き続けなければならないのは、たとえそれがひそやかな声であ
ったとしても、その声を上げ続けなければならないのは、我々第二世代なのだということを思わずにはいられな
い。
私の母は黒い雨を浴びた被爆者だが、今は大きな病気もなく五十代の終わりを過ごしている。しかし私の
親類で被爆者だったものは、ほとんど六十代に癌で亡くなっている。それも発病の直前までは非常に元気だっ
たにもかかわらず突然癌が発見され、手術のかいもなく亡くなっている。この数年何回もそれを経験した。
私が井伏鱒二の『黒い雨』を読み返す気にならないのは、主人公の女性が外傷はないのに黒い雨を浴びただ
けで発病してゆくことが、半世紀を経て私の親類に起こっていることと共通しているように思えてならないか
らだ。私は母に長く元気でいてほしい。
私の親類の被爆者は、この黒い雨を浴びた人達と、旧市内で披爆し亡くなった人とに分かれる。私の母方
の実家である大平家の伯父と伯母が後者である。伯父は当時旧制中学生であったが、学徒動員で建物疎開に
出ていて被爆した。一週間後に救護所となっていた寺で、うわ言のように自分の名前を言い続けているところ
を、捜していた兄弟に発見された。顔は黒く焼けただれ本人と識別出来ないが、目だけが光り、本人の名乗
りと焼け残った服の胸元に縫いつけられた名札で本人と確認したという。戸板に乗せられ変わり果てた姿で
帰宅した。治療と言えば赤チンを塗るだけで、
もはや死を待つばかりであった。それでも一週間ほど生き、
時計の鐘が鳴ると学校に行くと言って起き上がり、廊下に倒れたり、うわ言で同級生に号令をかけたり点乎
をとったこともあった。最期におはぎを食べたいというので祖母が作り、喜んで食べたが、まもなく亡くなったという。
私はおはぎを食べるとこの話を思い出す。また平山郁夫氏の修道中学時代の被爆体験を聞いた時にはこの伯
父のことを思った。三年前放映された平山氏の修道中学時代のことを描いたドキュメンタリードラマ『炎の
絵』にほんのわずか出演させてもらった時もこの伯父のことが頭をよぎった。そして、学校は異なるけれど
も本校の慰霊碑の儀牲者の中に私は伯父を見る思いがする。同じく学徒動員による建物疎開中の被爆であっ
た。夫を早く失った祖母にとってこの息子
への期待は大きかったようだ。この伯父の名を勝(まさる)と言ったが、
私も祖母から「勝が生きていたら」という言葉を聞い
たことがある。母はよく祖母から、子供が勉強したがった
らさせてやれと言われたというが、それは祖母の念頭にこの学業半ばで亡くなった伯父のことが常にあったからだ
ろう。子供にしたいだけ勉強をさせてやりたかったという思いはおそらく修道中学儀牲者の遺族にも共通する思
いであ ろう。
もう一人の犠牲者である伯母の名をハツネと言い、看護婦であったが即死に近かったらしい。堺町一丁目
にあった伊藤病院の看護婦であったが、病院の全員が死亡し、焼け跡の焼死体の中から金歯の位置で推測
し、それらしい死体の骨を兄弟が持ち帰ったという。伯母は非常時には本川小学校に集合するように言われ
ていたということだが、堺町も本川小学校も、爆心地に非常に近いから助かる見込みはなかっただろう。爆
心地と言われる島病院の御子息がかつて私のクラスの生徒だったが、島病院の前を通ると私はこの伯母を思
う。香川京子さんが『ひめゆりたちの祈り』の
中に沖縄戦で亡くなった日本のナイチンゲールと呼ばれる
上原貴美子さんのことを書いておられる。非常に感動的な話だが、香川さんが苦労して発見された上原看護
婦の写真の昔風の白衣姿を見ると、私の伯母もあのような姿で戦時下の広島で働いていたのだろうかと思
う。あの八月六日の 朝までは。
これらの話はいずれも母や祖母から聞いたものだが、祖母は三年前に亡くなった。大平家の跡取りである
従兄は、被爆死した伯父に似たのか優秀で東京で大学教師となったために、広島の家は今空き家のまま閉ざされ
ている。病床の祖母を見舞ってはよく話をしたことがなつかしい。祖母は九十歳を過ぎてからも驚くほど記
憶カがよく、おかげで貴重な話を聞くことができた。祖母は熱心な真宗の信者だったが、亡くなる何年か前
に長年愛用していた経文を全て私にくれた。自分はもう覚えてしまったからいらないと言っていた。読み続
けて傷んだのを糸でかがって修復してあっ
た。この経文と耳の底に残る話し声が今では祖母の形見で
ある。それは同時に祖母の心に生き続けた伯父や伯母の形
見でもある。
以上は聞き伝えの被爆体験だが、私にとってはこれ以上に大きい被爆体験がある。それは心理的被爆体験
と呼ぶべきものであり、ほとんど私の一生を決定づけたと言ってもよいものである。小学校の一、二年生の
時のことだったと思うが、私は父に連れられて市内に遊びに出かけた。可部線の沿線に住んでいた私にとっ
て中心部に出かけることは、「街に行く」と呼んでこの上もない楽しみだった。当時デパートは福屋と天満
屋しかなかったが、そこの屋上遊園地で遊ぶのが楽しみだった。その日もそういう楽しい日の一つで終わる
はずだったのだが、時間が余ったのだろう、父
が平和公園に連れて行ってくれた。そこで私は何を思った
のか、原爆資料館に入りたいと言ったのだった。おそらく空中に浮かぶような資料館の建物に幼い好奇心を
そそられ
たのだろう。父は気が乗らないようすだったが、私がせが
むので連れて入ってくれた。
しかし建物の中は、その美しい外見とは全く正反対の地獄図の世界であった。幼い私にはその体験はあま
りに衝撃が強かった。その日家に帰ってから私は泣いた。泣き続けて父や母を困惑させた。時間の観念が充
分に確立していなかった少年にとってそれは過去の出来事ではなく、今にもいつ起こるかわからないことに
思えた。私は恐怖の中に突き落とされた。戦争が起きたらどうすると言って私は泣いた。父が自分が守って
やるから心配するなと言ってくれた
のを覚えている。しかしそれが気休めにしかすぎないこと
は私にもわかった。
そうしたことがあってから、私は安心を求めて毎晩仏壇
にお参りするようになった。戦争が起きませんように。世
界が平和でありますように。原爆が落ちませんように。私は熱心に祈った。この心理的被爆体験は戦争の恐
怖にとどまらず、死の恐怖、さらに言えば、戦争をする人間への不信、外界への恐怖、存在の不安と結びつ
き私は心底からものごとを楽しめない人間になってしまった。夜寝るのも怖かった。そのまま死ぬのではな
いかという恐れとともに、空襲の夢をよく見てうなされたからである。いつ死ぬかもわからないのにどうし
て人は平然と生き、他の子供達は楽しそうなのだろう。不思議だった。自分はどうしてこんな暗い世界に生
まれたのか。自分はどうして広島のような恐
ろしいところに生まれたのか。少年の疑問はとどまるとこ
ろがなかった。あれほど楽しみだった「街に行く」ことも楽しみに不安が入り混じるのだった。可部線の電車が横川
鉄橋を越えて中心部に近づくと私は言いようのない不安に襲われ、帰りに電車が横川鉄橋を越えるとほっと
一安心するのだった。今にして思えばこれらの問いは幼いながらも、きわめて正統的な哲学的、宗教的疑問
であり、後の私の進
路を決定づける問いだった。
私は何年も祈り続けた。時折祖母がやって来て、数日間滞在した。祖母の名はマサノと言ったが私はこの祖
母が大好きだった。好きなだけでなく、熱心に念仏する祖母は最も尊敬すべき、あるいは信頼すべき、唯一
と言ってもよい大人であった。それはこの祖母が私と同じ問いをかつて有した人であったことを私が感じた
せいかもしれない。私は、家族や、友人達が自分と同じような問いを抱いて生きているように見えなかっ
た。私は孤独だった。私は祈り続
けた。しかし不安は解消しなかった。
高校生になったころ私は思った。自分はいつも恐怖心から祈っているがそれでいいのだろうか。恐怖心か
ら祈るからいつまでたっても不安は解消しないのではないか。全く別のあり方があるのではないか。私はよく本を
読んだが、文学、哲学、宗教が結局は私の関心事だった。私はよく念仏したが、念仏して行くという極楽浄
土の世界に、自分のような恐怖と不安の塊が行けるのだろうかという思いにとらわれた。極楽には恐怖はな
いはずだからだ。全く別のものが湧き上がってそれが新しい生を創るのではないのか。平和な世界も恐怖、
不安、悲しみ、憎しみ、恨みからは生まれないはずだ。憎悪の入り混じったような政治的平和運動に私は疑
問を感じた。真の平和はそこから生まれないと
思った。
この解決は大学生活に持ち越された。私は上京して大学に入り東洋哲学を学び、また仏教青年会に入ったが、
それは自分の疑問を解き、真の安心と平和への道を求めたからである。私がようやく本当の安心を得たのは
二十歳の時のことだったが、そのことについては二十歳の時に書いた『十三番目の冥想』に述べてある。あ
る師との運命的出会いがあった。師との冥想中、天地が裂けた。私は世界が愛に包まれていることを知っ
て、はじめて平和というものの正体を見た。最近、この師の亡くなられた七回忌にあたり、師との出会いの
思い出となる『十三番目の冥想』を活字にすることができた。図書館に寄贈したので詳しくはそちらに譲る
が、あの被爆体験以来、十数年かかってようやく私は、真の平和の入り口にたどりついたのだった。それ以
降はそれを深めるとともに、自分の見出したものを人に説明できるように勉強し、さらには、文明・文化の
方向を平和に向けていかにすべきかを考えるようになった。それが大学、大学院と続いた二十代の私の営み
だった。完全なる平和がすでにある。それが私の平和論の出発点だった。二十代の終わりに私は広島に帰っ
たが、研究紀要に書いたアジア・太平洋戦争論はこの延長線上にある。これからもヒロシマから考える平和
論を書いていきたい。
しかし今思い返すにつけ、少年期のあの体験はあまりに強烈であった。私は自分の苦しみを思うと小さい子供を
原爆資料館に連れて行くのは賛成できない。父が私にせがまれてとまどったのも無理はない。子供の心に心
理的外傷(トラウマ)を作る恐れがある。小学校時代私は原爆関係の写真には拒絶反応を示した。級友にそ
のことを知られてしまい、意地の悪い一人に、ある本の中の被爆者の写真を無理やり見せられたことがあ
る。小学校三年生の時のことだ。外傷はほとんどなく、防空頭巾をかぶり血痕のついた顔で、何かを訴えか
けるような眼差しの少年の写真だった。私は目をそむけたが、自分と同年代のその少年の姿、その眼差しは
私の目の底に焼き付いて忘れられなくなった。被
爆した自分の姿のように思えた。私が原爆のことを思うと
き、見たことのない伯父や伯母に代わって、あの少年の眼
差しが浮かぶのだった。
そして、三十年近くたった去年のこと、私はある写真展
で全く思いがけなくその少年に再会した。それは「ファミ
リー・オブ・マン」という写真展だった。人類を一つの家
族に見なして、その生から死へのドラマが世界各地で撮ら
れたおびただしい数の写真を用いて展開されていた。一つの壮大なドラマを見るような写真展だった。その終わり
の方の一枚に私はこの忘れられない写真を見出したのである。突然の再会に驚いたが、確かに彼だった。も
はやかつてのように目をそむけることはなく私はその少年に再会した。心理的被爆者であった少年の日の私
に再会したような気分だった。胸元に縫いつけられている名札の字が読み取れそうなので目を近づけた。そ
の字は「山田郁二」と読めた。「郁夫」である私は自分の分身のようなその「郁二」という名に驚くととも
に、写真につけられた説明で少年が長崎の被爆者と知ってさらに驚いた。私は少年が広島の被爆者だと思っ
ていたからである。よく考えてみると、自分は級
友に写真を見せられたときに、その写真の説明もその本も
読んではいないのだった。広島の被爆少年というのは私の勝手な思いこみに過ぎなかった。しかし不思議な
ことに私は広島に生まれながらも原爆関係の本で最もよく読んだのは『長崎の鐘』で知られる永井隆の著作
であり、私は自分と長崎とのつながりを深く感じていたのであった。私の中ではいつの間にか「広島−真宗
安芸門徒−祖母」と「長時ーキリスト教カトリックー永井隆」という構図ができていて、自分はどちら側に
も立てるように思っていた。この少
年の目が私の目を長崎に向けさせていたのかも知れない。
この写真はこの夏の中国新聞の夕刊に、被爆の写真の一つとして掲載され、そこで、「おにぎりを持つ母
子」という題が付いていることも知った。思えば私の平和の探求はこの少年の眼差しとともに続けられたよ
うなものだ。被爆二世の心理的被爆少年と、実際の被爆少年は、広島と長崎とに別れて、同じ名を共有しつ
つ生きてきたはずであった。山田少年のその後のことは記事にはなかった。私は生きていると信じたかっ
た。長崎の電話番号で調べてみたいという思いにも駆られた。しかし、もし生きておられたら私とその人の
年齢は二十歳ほど離れているはずである。あの写
真のために迷惑されたこともあったかも知れないし、私に
は想像もつかないような苦難の戦後を歩まれたかも知れない。そう思うと私は調べる勇気がなくなった。そ
うして新聞からその写真を切り取って形見として保存しておくこととした。心に被爆した少年の日の私の形
見として。その人
の無事を祈りつつ。(一九九五年八月二十八日)
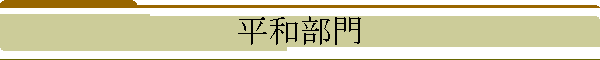
先頭へ