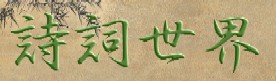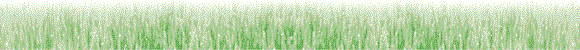@@
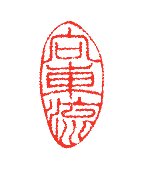
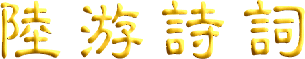
¿ ¤ú¥@@@èª
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìv@¤à
|
èª\VJC áméÒû¾B ç·è vÌû¸C OXN¿ÜÉsB äêámשC jZÂnulûB åånvÅ´íC æ¯áwsº°B ¶§aeÅÂC ÎçràãPAÓã³B é¾¾õäC ñ ~³DêB  |