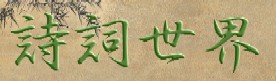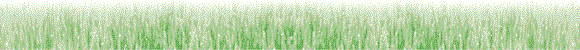|
|||
| @ | ÒMÒÌ |
||
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@k©E¯Ì
| äZªÉC ìûòRºB ¡äÒ´MC ¢ä@ç¹B û¡Vºé_C HƳ±B OO\öC gÀÂÛB ¦r¹C H°B ß¹èàÈC ]ÐáÆVB À¾`jZC à³årB ø´Ç°ñC ´dB |
 |