|
◎寒天製造に向く自然条件(H17.2.4)
|
|
今日は立春である。日中、昼の時間がかなり長くなってきているのが実感される。
今回は天然寒天の気象条件についてまとめてみる。
まず、第1に冷えること。ところてんが凍るところが肝心であり、寒天の名前の由来でもある。夜間から朝方にかけて−5℃から−10℃までくらいが適当である。(寒天の命名は宇治、黄檗山万福寺建立の隠元禅師)
次には製品が仕上がるためには融解、乾燥しなければならないので、昼間は晴れることが重要である。しかも風が強くないこと。
このような条件にあった代表地域が、岐阜県の東美濃、恵那市山岡地区である。他には長野県伊那地区、京都府亀岡地区などもあげられる。
1月20日の大寒から今日まで−5℃〜−7℃と冷え、日中は晴れて製造には好条件であった。
角(棒)寒天の産地の長野県茅野地区では、糸寒天製造地域より夜間温度がさらに下がる。
ところで年々温暖化が進み、岐阜地区では20年ほど前は90日ほど操業できたのが、ここ2〜3年は75日〜80日程度になっている。
写真は1月30日に撮影、恵那市山岡町からみた恵那山である。
恵那山は中央アルプス最南端に位置する標高2191mの美濃随一の名山である。日本百名山の76番にあげられている。
この写真では山頂に雪をみることができ、この雪がある間は夜間の冷えが期待できる。
この山の雪の有無をみては寒天の製造期の目安にもしている。
|
 |

|
|
◎てんぐさ(寒天原料)の種類(H13.12.2)
天然細寒天では各種てんぐさを配合してそれぞれの特徴を活かしながら寒天製品にする。当社では国内てんぐさの伊豆、三重、和歌山、徳島、高知産を中心に配合、製造している。
ゲル化したゼリー強度が適当に高く、しかも粘りのある寒天ができる。和菓子原料には最適な天然細寒天になる。 |
|
◎寒天の炊き込み(H16.1.6)
|
右の写真は夕方、沸騰してきた釜に草を投入しているところである。
口径135cmの鉄釜(内容量1,740リットル)の上に檜製の胴をのせ釜全体の容積を確保している。この胴はコシキと呼んでいて、およそ上部の直径は210cmほどある。そこへ水で洗浄、タンクで3日間水漬けしてアク出しをした原藻のてんぐさを逐次投入していく。てんぐさの仕込み量は240kg前後が多い。
その後、バーナーで一旦さがった釜温を沸騰するまで約40分ほど炊き込み、吹きこぼれる直前で火止めする。おおよそ午後5時ごろである。そのまま放置して翌朝6時ごろから釜から煮えて出たところてん液をくみ出し絞る工程に入る。
ここまでの原藻の煮かたで寒天製品の品質のポイントゼリー強度と歩止まりが決まるので重要である。
釜を炊く人を頭領といっているが長年やっていても気にいった炊き方ができるのは、常にというわけにはいかない。それほど勘と経験がいる作業である。 |
 |


|
|
◎凍結と融解、乾燥(H15.12.19)
|
朝、ところてん状に突き出された生の寒天は夜間にかけて凍り始める。晴れていれば午後6時ごろには1℃程に温度が下がり、凍りはじめる。
夜の間、晴れていると放射冷却で朝まで零下でいき、日の出直前では零下5から8℃までさがる。3日ほどで下まで凍ると次は融解、乾燥工程にはいる。
日中は太陽の光線が充分あたるように寒天の載ったスを傾斜させ、乾燥させる。この間水分の除去は融解のみならず昇華にもよって水分が減っていく。この繰り返しで約2週間ほどで乾燥して製品となる。
ポイントは夜間凍ること、昼間に天気がよく乾燥すること。雪が多いところは湿気があり、乾燥もあまり進まず適地とはいえない。この天候条件にあったところが天然寒天の製造条件である。岐阜県の東濃地区、山岡町はその最適地である。 |
 |


|
|
◎寒天の野上げ作業(H16.2.19)
|
今年の天然寒天の製造も終わりに近づいてきた。今日は朝の最低気温は零下7℃であったが日中は15℃ほどまで上昇した。この陽気で寒天の乾燥は順調に進み干しあがった寒天の野上げ作業に追われている。棚場には空きがおおくなってきている。
毎回、ゼリー強度試験の為、サンプル取りをするが今日時点でサンプルがとれずに残っている数は7日分と少なくなっている。最終込み日はこれからの天気次第であるが早い工場で21日、普通のところで23日か24日くらいを考えている。操業日は77日から80日近くなるものと思われる。
当初、12月には暖かくて1週間ほど遅れて製造開始されたが、その後は順調にきたほうである。
写真の手前に積んであるのはローラーである。この上に糊の入った重さ50kg以上ある小舟を棚場へ滑らせ入れていく。 |
 |

|
|
◎寒天の生産量(H16.2.2)
|
平成16年1月28日の日本食糧新聞記事から抜粋する。それによると寒天総供給量が国内品1000トン、輸入品1500トン計2500トン。国内品の内訳は天然の角寒天(主産地、長野県茅野市)で150トン、岐阜県の糸寒天の冬期純天然品が70トン、冬期以外の冷蔵庫利用で冷凍、自然乾燥して製造する冷凍寒天が80トンの計、糸寒天150トン。残りの700トンが粉末寒天の生産量と推測される。
今年の天然糸寒天製造工場数は14工場である。
ちなみに今から36年前の昭和42年(1967年)では岐阜県の製造工場数93工場、113釜、糸寒天生産量が550トンであった。(岐阜県寒天協会発行「岐阜寒天の50年史」による)
工場数で85%減、生産量で73%減である。 |
 |

|
|
◎寒天製造の釜(H16.2.26)
|
25日の朝に寒天液をくみ出しして、今日26日に外の天場へ突き出しをした。工場内ではこれで終了となり、26日の午後、この冬炊き続けた釜を上げる。
鉄製もしくはステンレス製で口径135cm、4尺5寸(内容量は1,740リットル)ある。通称尺5(シャクゴ)の釜と呼んでいる。
この写真の釜は鉄製である。釜の内部は腐食を防ぐためにカシューを塗布して来年に備える。 |
 |

|
|
◎天草の洗浄(H16.12.25)
|
写真は天草を洗う回転式の天草洗浄機である。
タンクに天草を2日間、水浸して汐とあくを抜きその後、洗浄機で洗って釜に投入する。この洗浄工程はいつも均一に十分おこなうことが重要である。
十分洗うことは寒天の仕上がりの色に影響してくるし、いつも均一に洗うことは釜の中の煮熟状態が一定になり製品の安定につながってくる。
ところてんの製造の場合でもどうようなことがいえ、ところてんの光沢のよし悪しにかかわってくる。
洗浄機械はこの六角型回転式のものから、コンクリートミキサー車を改造したもの、タンクの中を流していく流水式とあるが、基本的なことは均一、十分に洗うことを要点とする。 |
 |

|
|
◎新寒天…天日漂白(h18.1.5)
|
|
予報より良くなって、今日の天気は久しぶりに11時ごろから晴れ間がのぞいた。いっせいに乾し場の寒天をひろげ乾燥を進ませる。(写真上)
棚詰まりに加え正月もあって、ここ2週間は釜を休める日が9日もできてしまった。この天気を生かして少しでも製品を仕上げ、乾し場を確保する。
今日ようやく新寒天ができあがってきた。(写真下)
雪が多かったおかげで色は白く、良く晒されて仕上がった。水分を含んだ状態で日光にさらすと紫外線のおかげで漂白がどんどん進む。
手触りの感じもしっかりしていて上等である。
例年は、12月ごろ仕込んだものは1月の寒中仕込み品に比べ見栄えが落ちるものであるが、今年の20年ぶりの寒さと雪で、仕事は大変苦労してきたものの、製品は特上品となり満足である。
今日は寒の入りであるが、日の長さは長くなってくるので、それを期待して順調に凍結、融解、乾燥が進むことを願うばかりである。
|
 |


|
|
◎寒天物性試験 ゼリー強度試験と融点(h18.1.12)
|
|
あいかわらず低温が続く毎日である。
今日は、岐阜県恵那市山岡町にある岐阜県寒天研究室の物性試験の様子を報告する。
ここでは、組合員の毎日の寒天製品の物性試験ほか、開発の為の依頼試験などおこなってくれる。
寒天の物性としてゼリー強度と粘度、それに融点を重要視しているが、今回はゼリー強度と融点をとりあげてみる。
ゼリー強度数値は日寒水式が多く用いられている。20℃、1.5%濃度の寒天ゲル1平方センチメートルあたりの20秒間耐えうるグラム数をgcで表している。通常、糸寒天は350gcから550gc程度であり、用途によっては高い500gc以上のものが必要とされたり、逆に400gc程度のものでよかったりする。
写真上はその寒天を溶解しているところである。この過程でも、煮溶けの良否がチェックされる。
また、融点試験(写真下)は1.5%濃度ゲルの試験管を逆さにして過熱し、何度で溶解し始めてそのゲルが離れるかをチェックする。ゼリー強度の高い方が融点も高くなるが、使用原料によっても差が生じる。糸寒天はてんぐさを原料としていて、450gcの強度で概ね91℃〜92℃程度である。一方、オゴノリ原料の粉寒天は、ゼリー強度700gcで88℃〜89℃である。
融点が高いと、みつ豆寒天などの製品にしてから加熱殺菌しても角が丸くならないので有利である。また、糸寒天の製造途中で生天の融点を測定することによって、2週間後に仕上がる寒天のゼリー強度も推定できるので、その点でも融点測定の利用価値がある。
また、粘度も重要である。センチポイズで表しているが、これも高い方が有用である。
ゼリー強度、融点、粘度は、てんぐさ原料でも品種、産地による差が生じ、また、製造中の火の入れ加減でも差がでてくる。このあたりも製造のおもしろいところである。
他にも透明度、残渣の有無など様々なチェック項目があり、それぞれの利用目的に適合した寒天を製造、提供していくのである。
|
 |


|
|
◎寒天物性試験2 寒天粘度数値(h18.1.20)
|
|
前回、物性試験でゼリー強度試験と融点の測定方法を報告したが、今回は強度と同様重要なファクターである粘度数値について記す。
粘度はcpセンチポイズで表しているが、該当のゾルの回転軸に対する抵抗値で表している。
岐阜県寒天研究室の粘度計は、EMILA回転粘度計(Denmark)で寒天ゾルの60℃と50℃の抵抗数値で表す。写真上は、ゾルを一定温度に保つ保温バットと回転軸受け筒と表示を表す板を写している。写真下は部分を拡大したもの。
今回、天草産地による寒天特性を調べるため、研究室へ依頼試験した。そのうち、外国産(A国)天草だけの寒天と外国産(B国)天草だけの寒天、それに現在製造中の当社天然糸寒天(原料は国内産天草が主)のそれぞれのゼリー強度試験と粘度試験の結果を比較してみる。
・外国産(A国)天草だけの寒天 430gc、 2.0cp
・外国産(B国)天草だけの寒天 450gc、 6.4cp
・国内産天草主体での寒天 460gc、14.0cp
(強度は日寒水式、粘度はEMILA粘度計使用、ゾル50℃)
同じくらいのゼリー強度でも、粘度ではかなりの差が産地により違いが出ているのは興味深い。
EMILA型のほか、B型回転粘度計も多く使用されている。使用する粘度計で数値は異なってくるので、どんな粘度計での数値かチェックが必要である。EMILA粘度計の数値はB型回転粘度計の約55%の値となっている。
ちなみにB型回転粘度計数値(当社販売のトコロテン用粉末寒天1000gc)80cpのものはEMILA型では44cpのデータがある。
|
 |


|
|
◎煮熟条件の検討(酸と粘度/弾力の関係)(h19.1.17)
|
|
今日は煮熟の条件をかえて生天のゼリー強度や粘度、絞り具合、かえり等を調整することにした。実施することは酸の度合いの調整であり、酸が低い場合は生天のネバリが強くなり、高い場合はネバリが弱くなる。変更した条件が適切かどうかは、生天を割ってみることで判断する。割ったときにジワリといった感じで割れる場合は低く、一方でパリンと気持ちよく割れると良い生天といえるのである。ただし、度合いが強すぎても、生天のネバリがなくなる為、その量が良質な生天を作るポイントとなる。
理化学的な点からみれば、寒天は小分子(単糖:D-ガラクトースと3,6-アンヒドローα-Lガラクトース)が多数結合した巨大分子(多糖類)である。寒天の凝固作用はこの巨大分子同士が絡みあって現れる。しかし、酸により巨大分子の分解が行われ始めると(加水分解)、分子が小さくなっていく。分子が小さくなると絡み合いが巨大分子の時よりは少なくなり、結果的に寒天はネバリが低下していく。粘度の低下はこの機構が作用していると考えられている。一方で酸は原藻の外皮の成分を分解して内部に存在する寒天質を多く抽出してくる(*、**)。この為、酸量が過多であると寒天質は多く抽出されるが小分子となってしまい、ネバリがなくなってしまうので、酸量が良質な生天を作るポイントとなる。
今回はこれまでより若干高くしたところ、釜の内部の原藻のかえりはよく、釜から勢いよく湯気がでていった。出た湯気は天井一杯に広がり、その後工場の外へと出て行った。適切な度合いであった。
(報告/森田 尚宏)
* 寒天ハンドブック 農学博士 林金雄 岡崎彰夫 光琳書院 1970,(252-272)
** 海藻利用の科学 山田信夫 成山堂書店 2000(120)
|
 |

勢いの良いかえり
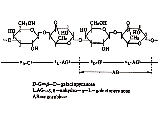
寒天の分子構造
|
|
◎おいしさの数値化(ゼリー強度試験)(h19.1.22)
|
|
一年の内で一番寒い大寒の割にここ数日暖かい日々が続き、正月明けに積もった雪も全て溶けてしまった。ただ、寒天の製造に関しては本日まで晴天が多かった為、寒天は順調に仕上がっている。また、凍てがのっていない生天も少々あるが、一度冷え込んで凍てがのれば、後は冷凍/乾燥の繰り返しの為、寒天の製造は順調に仕上がると期待できる。
生天に関しては、先週酸の度合いを検討したことが功を奏したらしく、パリンと気持ちよく割れた。良い生天ができた証拠である。
寒天の美味しさの目安であるゼリー強度であるが、日寒水式の方法が広く採用されており基本的な考えとしては '1.5%寒天溶液を作成し20℃で15時間放置凝固せしめたゲルについて、その表面1平方cm当たり20秒間耐えうる最大重量(g数)とする'
となっている。
寒天研究室では1.5%寒天溶液を作成して(寒天6gに脱イオン水400ml添加後、逆流冷却器により15分間加熱溶解)、20秒で破壊される時のオモリの重さをゼリー強度としている(凝固条件は温度20℃・湿度98%)。当方法は上記基本に則った正確な方法であるが、加重前に寒天の感触から大凡のゼリー強度を判断せねばならず、長年の経験が必要である。
一方、弊社の方法は凝固した1.5%寒天にオモリをのせ、寒天が破壊した時間とオモリの重さを記録し、計算式から算出する方式をとっている。この計算式は寒天ハンドブックに記載されており、この方法で算出しても寒天研究室の試験結果と大きく異なることはない。この為、弊社では当方法を用いることにしている。こういった方法を用いて寒天の美味しさを客観的に数値化させ、更に外観の形状で最終的に良否を判断している。
(報告/森田 尚宏)
|
 |

順調に仕上がっていく寒天

逆流冷却器を用いたゼリー強度試験
|