| 序 章 |
|
 古来から人間は喜怒哀楽を歌にして心の浄化をはかってきた。大衆の喜怒哀楽をレジスタンスの一手法として演説の代わりに歌で演じたのが明治の演歌師でありる。大正期のレコードは街で歌わわれている曲を録音して売っていた昭和3年、レコード会社は作詩、作曲家、歌手を専属として抱え、新曲作って流行させようと企て、ヒット第一弾「君恋し」が出た。 古来から人間は喜怒哀楽を歌にして心の浄化をはかってきた。大衆の喜怒哀楽をレジスタンスの一手法として演説の代わりに歌で演じたのが明治の演歌師でありる。大正期のレコードは街で歌わわれている曲を録音して売っていた昭和3年、レコード会社は作詩、作曲家、歌手を専属として抱え、新曲作って流行させようと企て、ヒット第一弾「君恋し」が出た。
「東京行進曲」で西条八十は聴いてすぐ覚えられるよう、都都逸二つを繋ぎ合わせた一節四行の歌詞を書き、中山晋平は西洋楽器のオーケストラで伴奏する和様折衷の新しい歌を作った。明治、大正の演歌とは似ても似つかぬ歌謡曲の誕生だ。マイクロフォンの高性能化は甘い声をキャッチし「酒は涙か溜息か」を生んだ。「赤城の子守唄」「旅の夜風」など映画とレコードが映画主題歌が次々とヒットし、歌謡界は代もあった。
|
 スター歌手百花繚乱 スター歌手百花繚乱
|
戦後大流行した「リンゴの歌」(昭和21年)は大衆に明るさと希望を取り戻させ、祖国再建の心のよりどころとなった。それまで禁止されていた米英の音楽がどっと流れ込み、その影響を受けた「東京の花売り娘」「東京ブギウギ」などの歌謡曲が巷に流れた。美空ひばりの出現と岡晴夫、田端義男、春日八郎などスター歌手が百花繚乱、大衆はそれぞれの贔屓を(ひいき)を声援した。この風潮に拍車をかけたのが民放と芸能雑誌だ。更にテレビ放送(昭和28年2月1日NHKテレビ本放送開始)の普及によりアイドル歌手、グループサウンズなど歌唱力より眺めて格好の良いタレントに人気が集中した。 |
 ニューミューシックの台頭 ニューミューシックの台頭
|
昭和40年代(1965)に入るとビートルズなどの影響を受け、フォークやロックが現れ、歌謡曲という言葉ではくくりきれなけなり、ニューミュージックなる言葉を生んだ。45年春「演歌の星」のキャッチフレーズで藤圭子がデビューした。「新宿の女」や「圭子の夢は夜ひらく」がヒットした。作家の五木寛之はこの新人を評して「演歌、艶歌、援歌など呼び方はあるが彼女の歌は怨歌がふさわしい」と絶賛した。演歌とニューミュージックは対峙する時流を作った。 |
 国民総歌手時代の到来 国民総歌手時代の到来
|
昭和50年(1975)に入るとカラオケが普及し始め、聴く時代から自らが歌う時代へと変貌し「歌い手ごっこ」のカラオケは国民的レジャーとして定着していった。また、自分が作って歌うというシンガーソングライターが多くなり、電子音楽の多彩なハーモニーとビート感溢れるリズムにより、日本の大衆音楽は大きな様変わりを遂げた。
また、テレビCMから生まれるヒット曲は寿命がすこぶるる短く、歌手の露出度もそれに伴う。一方、演歌の詩にはポエムが無く、曲も大衆に迎合するあまりパターン化して新鮮味を失いCDやテープの売り上げは低迷を余儀なくされている。歌から大衆の喜怒哀楽をスポイルした結果だ |
 |
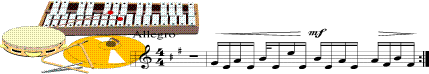 |
 |

