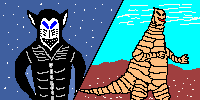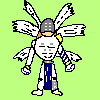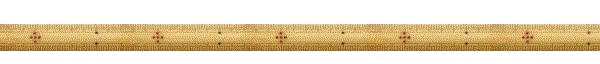本日の授業 第3日
◆ 甥の言葉、老いと言葉 ◆
今、私の家にはもうすぐ4歳になる甥(おい)がいます。
姉の息子なんですが、これがまたかわいい。
姉は昔から憎ったらしかったんですが、この子のかわいさったら
いまだ一人身の私に「この子に老後の面倒を見てもらおうかな」などと思わせるほど。
なんせ自分の息子ではないので、無責任にかわいがれるのがまた良い。
やはり「自分の子でない身内の子」ってのがかわいがるには一番ですなあ。
などという話はさておき、この子がよく私のところに本を持ってきては質問します。
「ねえ、これはなあに?」
「ああ、これはメフィラス星人だよ」
「めひなすせえじん?」
「め、ふぃ、ら、す、せいじん」
「めーひーらーすーせーじん。め、ひ、ら、す、せーじん。めひらすせーじん。めひらす……」
ひたすらブツブツつぶやいているのです。そのうち、
「じゃあねえ、これは?」
「これはレッドキングだよ、れっどきんぐ」
「れ、っ、ど、き、ん、ぐ。れっどきんぐ。れっどきんぐ。れっどきんぐ……」
やがて今度は別の本を取り出し
「ねえねえ、これはなあに?」
「これはね、えーと、エンジェモンだって」
「えんねもん?」
「え、ん、じぇ、も、ん」
「えんじぇもん。えんじぇもん。えんじぇもん。えんじぇもん……」
そのうち、ママがやってきました。
「ままー、これはね、めひらすせいじんっていうの。あとね、こっちはね、れっどきんぐ」
「へー、そうなんだー、すごいねー」
「あのね、あのね、こっちはね、えんじぇもん」
「ふーん、よく知ってるわねえ」
そう、よく知っているのです。よく覚えているのです。
ひたすら声に出し、繰り返す。繰り返す。それで覚えてしまうのです。
子どもの新しい言語、新たなボキャブラリーはそんなふうにして増えていくようです。
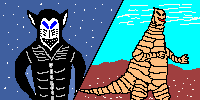
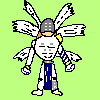
左図:メフィラス星人/レッドキング 右図:エンジェモン 〈イメージ図〉
ひるがえって、塾。
英語の授業では、教科書の新出単語や本文は必ず声に出して読みの練習をするのですが、
(少なくともうちの塾の)中学生たちはあまり声をださない。しっかり発音しない。
もちろん本文などはちゃんと目で追って読んではいるのですが、
まさに文字どおり「黙読」なのです。黙〜って読んでいる。
勝手な印象では、英語を苦手とする生徒ほど声を出していないように思います。
なぜなんでしょうか。
仲間のいるなかで声を出して練習するといったことに、多少なりとも「照れ」があるのでしょうか。
もしみんなが声を出せば「みんなが出してるから私もちゃんと出そう」と思うのでしょうか。
それとも逆に「みんなが出してるから私は出さなくたっていいや」と思うのでしょうか。
その辺りの対応は人それぞれなんでしょうが、いずれにせよ
新たな言語を習得しようという姿勢では、
4歳に満たない子どもに中学生は劣っています。
しかし、そんな中学生を我々はあれこれ言っていられるのでしょうか。
もっと歳を取った自分の身に照らし合わせてみても、
何か事を行うときについ周りの目を気にしてしまうということが多少なりともあるような気がします。
それはあるいは、歳を取っていくとともに、いやむしろ
歳を取っていくからこそ湧き上がってくる感覚なのかもしれません。
4歳の子の、ひたすらに何かを求めていく態度。
大人になっていく人間が社会性と引き換えに消し去っていくものとは、
もしかしたらそんな態度なのかもしれません。
老いていくのは、体ではなく、心の態度なのか。
話がちょっと大きくなってしまいましたが、少なくとも
新たな言葉を習得するためにはひたすら声に出して繰り返す。それしかないでしょう。
「言葉」とは「言の葉」。一葉一葉、声に出して言ってみて初めて「言葉」と成り得るものです。
人間が文字を発明する遥か以前から、そんなことは分かっていたはずなんですけどね。
とはいっても、4歳にとってのウルトラ怪獣やデジモンと、中学生にとっての教科としての英語とでは
興味の対象が雲泥の差だというのもまた事実。
それでは、ひたすら繰り返すのも酷ってもんかしら?
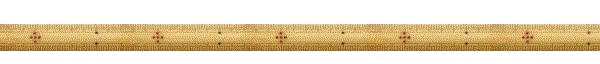
◆ 本日の問題 ◆
それぞれの言葉の、対義語(反対の意味の言葉、対になった言葉)を考えてみましょう。
漢字と英語、両方答えられますか? 答えは下にあります。
1.甥(nephew) 2.答える(answer)
3.深い(deep) 4.具体的な(concrete)
←前日の授業へ 本日の授業メインページ 翌日の授業へ→
有悩講師陣HOME MANIAってます! プロフィール?