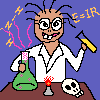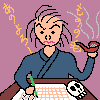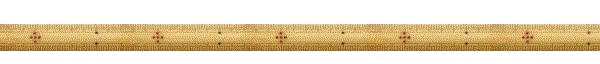本日の授業 第4日
◆ What's the
world made of ? ◆
(世界は何でできているか)
私は塾での専門は国語なのですが、その他にもいろいろと手を出しています。
この前は数学で「因数分解」をやりました。
中学時代がはるか昔の方々、覚えてますか?
x2+9x+20=(x+5)(x+4)、とかいうあれですね。
この場合は、かけて20、足して9になる数〈+5と+4〉を探す、ってやつでした。
しかし毎度の事ながら、これが生徒たちにはあまり実感できない様子。
いやもちろん、やり方としてはちゃんと分かるし答えも出せるんですが、意味があまり分からない。
(x+5)(x+4)を計算せよ、とかいう問題も嫌いだったけど、このほうがまだ納得がいく。
それをなんでわざわざ逆の作業をやるのか、なんのためにそんなことをするのか、と。
たしかに感覚としてはおっしゃる通りですわね。
私は国語担当というだけあって、やはり学生の頃から国語は好きでした。
特に古文、あのちょっと分かりづらい文章を動詞だ名詞だなどと品詞ごとに分けていき、
助動詞の意味なんかを一つ一つ見極めながら文の内容を把握していく、というのは
ある意味でパズルを解いていくような面白さがあったように記憶しています。
分かりづらいものをバラしていって言いたいことを考えていく、という。
バラしていけばその意味が分かっていくんですね。
さて、その後私は一時期化学系の友人たち(薬学部とかですね)と多く接する時期がありました。
私などはあの化学式だとかの意味合いがあまり実感として持てず
自分の人生にゃ関係ねーや、と思っていた頃もあったので、
彼らの化学への興味がどこからくるのか皆目見当がつかなかったのですが、
彼らに言わせれば私の好む品詞の分解の方がよっぽど分からんと言います。
あんなことのどこが面白いんだ、と。
そんな人々と接してみて気づいたこと、それは
彼らの場合は分子や原子という次元での話であり
私の場合は文法的、言語的な面からのアプローチでありましたが、
結局はどちらも物事の本質を見極めようとする姿だったのではないか、ということ。
たまたまその興味の方向が化学か文学かという違いがあるだけで、
目的としては同じなのではないか、ということです。
世界がどういうふうにできているのか。
それを探る方法として、たとえば化学があり、たとえば文学がある。
もちろんそのほかにも、人間の思考の数だけアプローチの方法があるでしょうが、基本的には
すべては世界の作られ方を分解してみるための方法ではないか、と思ったりしたのでした。
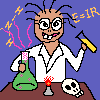
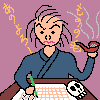
マッド・サイエンティスト vs.
マッド・リタレリスト(造語)
もっと身近な例で考えてみると、
たとえばどこかのホームページからエロ画像なんかをダウンロードして
プリントアウトしてみようとしたりする。
今のプリンターはほんとに高性能なんで、肌の微妙な色合いまでも忠実に再現してくれるでしょう。
しかしご存知の通り、プリンターのインクは3色、多くてもせいぜい5、6色ぐらいしか使っていないのです。
どんなにきれいなグラデーションも、赤・青・黄の3原色によって作られている。
これが複雑な色の世界を形作っている要素なのです。
世界は全てこの3色に分解できる(光の3原色はまた違うらしいですが)、これが本質です。
またもっと簡単な話では、
今日のカレーは美味かったなあ、材料は何使ってるんだろ?
牛肉、じゃがいも、にんじん、ヨーグルトでマイルドになったね、、
へえ、かくし味にチョコレートひとかけ入れたんだぁ、なんてことがあるかもしれません。
これもまさに、分解です。
味を追求するために、料理を材料のレベルにまで分解してみる。
混沌とした複雑な世界を、それを構成する要素に分解していけば
その本質が見えてくるということは往々にしてあることです。
さて、もうおわかりですね。
因数分解。字のごとく、もととなる数に分解してみるのがこれなのです。
いわば料理の世界の「数バージョン」。
『x2+9x+20』っていう料理は何でできてるのかなあ?
へー、材料は(x+5)と(x+4)だったんだあ、この二つを使って作ったんだぁ。
ってなことですね。
たまたま数字を使ったわけですが、これは結局
世界の本質を追求するための頭の訓練なのです。
ほら、数字を使えば分かりやすいでしょ、字が読めなくてもOKだし。
そんな考えで数学に接すれば、将来いつかきっと応用がきくことでしょう。
学校の勉強というのも要は、いろいろな考え方をするための練習です、練習。
余談ですが、数学者というのは
世の中を全て数字で解明できると考えている、と聞いたことがあります。
ですがある意味「○学者」と呼ばれる方々というのは皆そうかもしれませんね。
自分がそう信じる道で世界を追求し、解明していく。
しかし、いろいろと解明されていけばいくほど
中学生が勉強しなくちゃならない内容は増えていくばかり。
世界の解明は、うれしい悲鳴? それとも悲しい悲鳴?
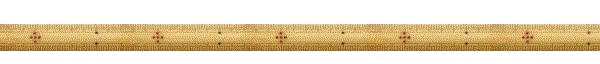
◆ 本日の問題 ◆
長寿を祝って使う言葉というのが古くからあります。
たとえば「還暦」とは60歳のことですね
(中国の干支は正しくは60種類ありますので、
60年経って生まれた干支、暦に還ってくる、という意味でしょう)。
では、次の言葉は、何歳のことを言っているでしょうか。
ちなみにテーマは「分解」です。
1. 米寿 2. 白寿
3. 茶寿 4. 皇寿
←前日の授業へ 本日の授業メインページ 翌日の授業へ→
有悩講師陣HOME MANIAってます! プロフィール?