仏像彫刻、私の作品Ⅲ![]()
| 「作品名の一覧」、及び「個々の作品へ」は、目次付作品一覧 からどうぞ! その他、仏像彫刻の全項目に関しては、”仏像彫刻へ”からもどうぞ! |
||||
| R2t | ||||
| 18.わらべ三兄弟(尊)!? | ||||
 |
||||
| 知人が入院。 で、気晴らしになればと、私なりの”わらべ薬師”を作り、お見舞いとしました。 作って見て思いつき! ”わらべ三兄弟(尊)?!”へと拡大してみました。 ・健康祈願⇒わらべ薬師 ・早く治りますように⇒わらべ地蔵 ・滅入ってはダメ!⇒わらべ不動、の意を込め!! |
||||
| 大きさは手で握れるサイズ(45mm角、高さ90~105mm)、材種はヒバ(あすなろ→明日は檜になろう!):わらべ尊にピッタリ!? | ||||
| こうしてみると、もう一つ 天部のわらべを作れば、”如来・菩薩・明王・天の一セットわらべ”になるかなぁ~など とも思えてきました!! その内作ってみようかと...(H26.6) |
||||
| 参考(童顔について) 元(近況)に戻る | ||||
| 19.愛染明王坐像 | |||
 |
↓回転します↓  |
||
| 1)完成:H26.10 2)材料: 榧(カヤ) 3)寸法: 仏像;8寸(坐4寸) ・像高・16.5cm ・巾 ・13.5cm ・奥行: 9.6cm ・全高;35cm ・全幅;19.5cm |
彫ってみました! 愛染明王 !! | ||
| ・憧れの「榧」材で。 檜に比べ堅く、粘り もあって、上手く彫れません。 そして、 榧のつやのある良さを引き出せず! もっと刀をこまめに研ぎ、仕上げるべき でした。(大いに反省(-_-メ) ) ・6臂。各手の接合に四→6苦八苦! 微妙な角度取りで像容が変る! 良い経験でした! ・眼は玉眼風!としました。 |
|||
| 東博で、神護寺や東博所蔵の愛染明王を何度か観ているのですが、観ると彫るでは大違い! 何を観ていたのか! との反省しきり。 とは云へ、本作を京都・作品展に出展後、奈良・西大寺で御開帳中であった「愛染明王」(善円作) や、京都・千本釈迦堂での快慶作「十大弟子」などを拝観し、”彫る”など忘れさせられ、”名作に感動”する心地良さを 実感・再確認しました。 これも、彫る経験を多少なりともしてきたからこそ、より深い感動に浸れたのではと思います。 |
|||
| 元(方法-連弁)に戻る 元(近況)に戻る | |||
| 20.十二神将の内の 波夷羅大将と伐折羅大将 | |||
| 20-1.波夷羅(ハイラ)大将 | 制作時期、寸法 等 | 彫ってみて... | |
 |
1)完成年月: H27.6 末 2)材料: 楠(クス) 3)寸法: 仏像;6寸 ・像高:20.7cm ・巾 :11cm ・奥行: 8cm ・全高;24.2cm  ↑動きます↓ 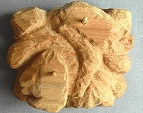 岩座の上面視ハイラ |
「興福寺・東金堂の木造十二神将像」 (鎌倉・13世紀;国宝) の内の、 波夷羅大将・伐折羅大将。 共に 動きが大きい動態に魅せられ、東博資料館等 で数視点の写真資料を見つけ、”ならば!”と 挑んでみたのですが.. 先ずは、波夷羅(ハイラ)大将: 左掲の作品写真(8視点)でも明らかですが、 特に左腰の構えが何とも整わず!、 少ない実写資料、後は想像で立体化!と覚 悟の上での挑戦でしたが、それでも ”ここは、どうなっている??”、”成る程、ここ はこうすれば!”と彫り進める内に解ってくる 事だらけ! 結果、彫り過ぎでボリュウム感が 今一つのスリムな体形になってしまいました。 そんな中、岩座では、上から見ると”ハイラ”! (ヤケ気味で遊ぶ!?しか能も無く) |
|
| 本格的に模すには、疑問ある毎に本物を観、更に、 まず粘土で見本を作る等がベストなのでしょうが.. そこまでの情熱、精神的・金銭的余裕も無く.. |
|||
| 出来てみれば、これはこれでマアマアかな~ (自分で褒めねば前へ進めない..?!) 次は、伐折羅!! 8月中には..。 |
|||
| 元(電動木彫機)に戻る 元(近況)に戻る | |||
| 20-2.伐折羅(バサラ)大将 | 制作時期、寸法 等 | 彫ってみて... | |
 |
1)完成年月: H27.9 末 2)材料: 楠(クス) 3)寸法: 仏像;6寸 ・像高:22.5cm ・巾 :11.5cm ・奥行: 8.5cm ・全高;25.5cm   |
資料写真は波夷羅大将よりは正面を向き、 彫り様も容易かと思ったのですが..。 |
|
| 中々形が掴めない!”激しい動態で、破綻を 示している”と評される右側面や、左腕を低く 構える背部など上体の捻り様。 右上腕部の 大袖・鰭袖の反し形状等など、彫りようもなく 中断、そして暫し嘆息!息抜きへ..の繰り返 し。 とは云へ、彫らねば前へ進めず!と居直 って、その分、彫りの過不足やバランスを欠き ながらも何とか完成・と・しました。 |
|||
| 二像とも実像(写真)とは、比べようもありませ が、これも今の実力。 "知足”し前へ! とする しか有りません! (PPKへの秘訣!) |
|||
| それにしても、動きの大きいこの二像。 本物(像高120cm前後)は、腰部で体部を 上下に分けるなど体勢に応じた木寄せとの事 ですが、顔や手・脚部など角度の微妙な調整 など、迫力を増すための工夫や彫像技法を 駆使しているのでは?とも思われます。 両像の仏師の技量の高さ、苦労と努力を、更 には完成後の達成感と感慨!が偲ばれます。 |
|||
| 20-3.両雄を飾る | |||
| 柿渋を塗った(後に渋味がより増す)飾り台を作り、両雄を並べてみました。 二像を並べてみると不出来個所も余り 目立たなくなり(見る眼が分散!?)...まあまあかなぁ~(出来たて直後は、いつもフムフムなのですが..) 十二神将はこの二体だけと思っていましたが、この際!もう少し作ってみるのもいいかなぁ~などとも思えて来ました。 |
|||
| 追記:飾り様の変化を楽しむ!? | |||
| 二像は、飾り台上で夫々回転出来る様にしています。 で、時には、二像の相対位置を変えるなどして、飾り様の変化 を楽しんでいます。(良かったら、その様子もどうぞ! →ここをクリック) |
|||
| 元(近況)に戻る | |||
| 21.《番外編》聖母子像 (レリーフ) | 制作時期、寸法 等 | 彫ってみて... | |
 |
1)完成年月: 2015(H27).10 中 2)材料: 松 3)寸法: 木の外形 ・全高:14cm ・巾 :7.5cm ・奥行:5.5cm ベルギー・ブルージュ 聖母教会の聖母子像  |
従姉夫妻宅にあった”松”の木が枯れ、切り落と した枝が保管されていました。 年輪を刻みながら、家と家族の成長を見守って きた思い出深い”木”。 記念に何かという事で、挑戦してみました。 従姉はクリスチャン!! で、 彫る像が仏像という訳にもいかず... |
|
| 思い浮かんだのが、ベルギーにいた頃に見た ”ブルージュの聖母教会”に祀られた ミケランジェロ作の「聖母子像」。 大理石の等身大の全身坐像で、厳かな大聖堂 の中で、ひときは輝きを放ち、息を呑む程に美し くも清楚で、それでいて堂々とした像でした。 |
|||
| その上体部を浮彫りの形で、彫ってみました。 出来映えは別!として、”思い出の木”として喜 んでいただけました! (←小写真。本当は無掲載に? 見比べられるし!..) |
|||
| 元(近況48.内)に戻る | |||
| 22.菩薩立像 (↓回転します) | 制作時期、寸法 等 | 彫ってみて... | |
 |
1)完成年月: H30.(2018)3初 2)材料: 檜 3)寸法: 仏像 1尺 ・像高:35cm ・巾 :19cm(台座) ・奥行:18cm( 〃) ・全高:49cm ↓踏割り蓮華(回転します) 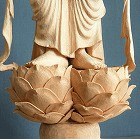 ↓三段框座上面視  |
下記を模してみました、[像高は、本物の約1/3の1尺] ・「菩薩立像」(鎌倉13世紀・重文、東博所蔵 [本像については、別記参照下さい。] |
|
| 東博所蔵で時折、通常館で展示され写真撮影も可。 で、遭遇!?する度に魅せられ、遂には模したくなり.. 初めての1尺立像で彫ってみたのですが.. |
|||
| 前作までの小像、荒い動態の「天や明王」に取り組んだ 身には”彫りの勝手違い”ばかりを感じつつ、また、 細かい所を含め”ここはどうなっている!?"で中断の多 い作像でした。 特にお顔や捻った腰の線の表現など彫り きれず!の不満が残る作像とはなりました。 そんな中、”踏割り蓮華座”は、まあまあその雰囲気はで たかな~と!蓮弁72枚!コツコツ地道に彫り、連肉に 貼り付け仕上げました!! |
|||
| それにしても模する過程を通して、あらためて本物の 奥深さの要素にも触れた思いで、その良さを再認識させ られました。(→表現要素の一部は) |
|||
| なお、実像の調査中に、”三段框座の最下段の後方は、 円形でなく、二段目の円形框と接する楕円(右写真は幣作) になっている”事を知りました。 祀る上で奥行に制限が あってこのような形にしたと思われます。 (台座の奥側を扁平にするのは本像に限らない方法の様です) |
|||
| 仏像彫刻TOPへ | |||
| 23.阿修羅立像 | 制作時期、寸法 等 | 彫ってみて | |
↓回転します |
1)完成年月: R1(2019).9初 2)材料 :檜 3)寸法: 仏像5.7寸 ・像高 :19cm ・巾 :13.5cm ・奥行 : 5cm ・全高 ;21.5cm ↓回転します   |
興福寺の八部衆(脱活乾漆像・奈良(天平)8世紀・国宝) の内の「阿修羅像」 |
|
| いつか模したいと思いつつも、あの名品の雰囲気を、 憂いを含んだ表情などを彫り出せるのか!で、躊躇し 続け..が、歳も歳の我が身!?どんなものか!と 先ずは小像でトライ!!し経験してみようと..。 |
|||
| 像輪郭は「魅惑の仏像・阿修羅(毎日新聞社刊)」の 前後左右の4面写真から作成。 材は6寸聖観音用 材を利用し、輪郭図作成では下記などに留意した 1)第一合掌手が左手側に少し寄っており?、6寸像 高では材に納まらないない為、5.7寸の採寸とした。 2)側面写真では足位置がやや前方に思え、作像で は後方に倒れる?と、輪郭を後方に数ミリずらした。 (→結果、作像はギリギリ倒れずであったが、 写真撮影角度のズレ?か、実像は体内に芯棒が 台座まで通り、後方に倒れない?不明)。 3)木取りは第二・三手や台座も同材から採った |
|||
| 彫る過程で、上半身部は合掌手との間が狭すぎ彫り 切れない為(合掌手を両臂釧部で繋ぐのも難しい為)何と! 両前腕の肘近くで折り(→その後接着で目立たない!?) 仕上げた。(小像での苦肉の策であったが、前面に手 が無い事で、下半身や頭部が彫り易くも有りました) |
|||
| 裳の動きのある合わせ目、淡い表現の衣文、ウエストのライン出し等々、彫り始めて気付く微妙さ、逆目などでの彫りの難しさ!! 最大の課題の三面顔部は、写真を倍尺にして顔面各部位置を採寸し、何とか実像の表情に近づけ様と.. 小像でもあり彫り難く、今の実力では”マッ!こんなものか”で妥協(-_-;)し、完成”と”しました。 今後、この経験で判った事を作像資料にも反映させ、もっと大きい作像をする機会に備えようと思います!! |
|||
| R2 | 仏像彫刻TOPへ | ||
| 私の作品を ご覧いただき 有難うございました <(_ _)> 今後も、新しい作品が出来ましたら掲載いたします。 その節、また ご覧いただければ 幸いです (^^♪ よろしければ、次ページ・彫刻の方法へ |
|
| 作品一覧の最初に戻る 仏像彫刻TOPに戻る 本HPのTOPへ戻る | |
| a |