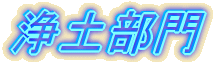
浄土部門 INDEXへ 新聞掲載記事等へ  戻る 進む
戻る 進む

このページの内容
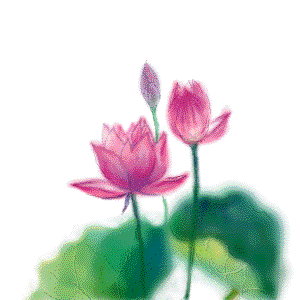 講演要旨 浄土の因果
講演要旨 浄土の因果
講演要旨 日本人の死生観―浄土教を中心として―
講演要旨 女性と若者の心をつかむもの―「本願寺展」より―
講演要旨 発掘・『歎異抄』
講演要旨 二河白道を生きる
講演要旨 真宗学寮報恩講「連続無窮」
講演要旨 善徳寺原爆逮夜法座
 講演要旨 唯説弥陀本願海
講演要旨 唯説弥陀本願海
講演要旨 妙好人に聞く
講演要旨 法然上人と親鸞
講演要旨 母の国・真宗
『歎異抄を読む-悪人正機の時代を生きる』の紹介
鬼束ちひろの「月光」について(中国新聞掲載記事と元のコメント)
講演要旨 浄土の歌(京都光華女子大の宗教講座での講演レジュメ
)
講演要旨 二十一世紀の『歎異抄』
講演要旨 現代と宗教
以下の新聞掲載記事は次のページにあります。
新聞掲載記事等へ
「光る海」(中国新聞掲載記事 文化欄緑地帯連載)
鬼束ちひろの「月光」について(中国新聞掲載記事の全文)
「春奈ちゃん事件に見る現代と宗教」(中国新聞掲載記事)
「心が浄土に遊ぶとき」(中国新聞掲載記事)
「歎異抄を読む」紹介記事(中国新聞掲載記事)

浄土の因果
2008.7.7広島別院・安芸北組仏教婦人会にて 渡辺郁夫
一 親鸞浄土教に至るまで (午前の部)
1「因果の法」
仏教の説く法の基本にあるのは「因果(縁起)の法」と言われる。これを詳しく説いたのが「十二縁起」であり、「無明、行、識、名色、六処、触、受、愛、取、有、生、老死」からなる。これをまとめて、「惑(縁)、業(因)、苦(果)」とする。これが「過去世、現世、来世」の「三世」に渡って展開する「三世の因果」となる。そこにあるのがいたずらに「生死」を繰り返す「業報(因果応報)」の連鎖である「輪廻」である。この「苦」からの解放(解脱)を説くのが仏教である。そこから完全に解放されたのが「涅槃」の世界である。苦である「輪廻」の世界を「此岸」とし、「涅槃」の世界を「彼岸」とする。仏陀とは此岸から彼岸に渡った人であり、その代表者が歴史的存在としての釈尊である。
釈尊においてはすでに在世中に涅槃に達していたが、「涅槃像」や「涅槃図」があるように、その死もまた涅槃として表された。涅槃が悟りでもあり、死でもあることがここから始まる。ここがまた浄土教の出発点でもあり、涅槃の世界が悟りの世界でもあり、死後の世界でもある。「此岸」と「彼岸」が「迷い」と「悟り」に対応するとともにこの世界と浄土にも対応する。いわゆる「あの世」はその中間的世界だが、「六道輪廻」として「迷い」、「此岸」に属するものである。「この世とかの世をともに捨てる」のが仏教である。
仏教はしばしばいわゆる「霊魂」を否定すると言われるが、それは「六道輪廻」を繰り返しているものが「霊魂」と言われるもので仮の存在に過ぎないからである。大乗仏教では「唯識」で説く「阿頼耶識(あらやしき)」と言われるものが、過去の自分を「種子」として記憶し生死を繰り返すものなので、「霊魂」に近いだろう。仏教はそれを越えることを目指している。霊魂と区別して「仏性」を説くのはそのためである。鈴木大拙は「霊性」という言い方もしているが、仏教はあの世や霊的知識を説くことに主眼があるのではない。それは現象の説明の一部である。仏や菩薩といった聖衆はいわゆる霊魂ではなく、仏性を体現したものを、仮に人間の形で表しているに過ぎない。「惑、業、苦」という「業報」の「三世の因果」からいかにして脱するかが問題である。「苦」からの解放をもたらすのが真実の認識であり、仏教はそのための方法論である修道論を説く。仏教が知識でも学問でもないのは、結局この苦からの解放を求めて修行する実践の宗教であるからである。これが仏道である。この実践の修道論も「因果の法」を基本とする。ここで説かれるのが「四諦」と「八正道」である。大乗仏教ではこれが「四諦」と「六波羅蜜」となる。「六波羅蜜」は「八正道」の内容を含んでそれを発展させたものである。
2「四諦」
「四諦」は「苦、集、滅、道」の各諦である。「苦諦」は詳しくは「四苦(生、老、病、死)八苦(四苦に加えて、愛別離苦、怨憎会苦、求不求得苦、五盛陰苦)」であり、現実の「苦」という「果」である。その「因」が「集諦」である。「苦」をもたらすのは人間が起こす様々な煩悩によるが、それは様々な因がより集まったものであり、その実体はないことからこう言われる。「滅諦」が修行の「果」である「涅槃」である。「道諦」が「滅諦」の「因」となる修行方法であり、「八正道」や「六波羅蜜」として説かれる。「四諦」を「因果」で表すと「苦」(果)、「集」(因)、「滅」(果)、「道」(因)となり、「因果の法」の展開であることがわかる。現在の苦しみという果には因があり、その因を滅するために、修道の仏道を歩むのが仏教である。これが実践の宗教であるということだ。因果の理法を基にした自業自得なので裁きの宗教でもない。「因果の法」は客観的な説明だが、それは何よりも衆生を実践に誘うためにある。その実践を「因」として苦からの解放という「果」に向かう。「因果の法」は決して現実を説明してあきらめさせるためにあるのではない。
ところが封建社会においては、仏教の説く「三世の因果」が悪用され、現実の身分社会の肯定に使われたという面がある。そのために「因果の法」そのものが悪しき思想のように思われることがあるが、それは全くの誤解である。江戸時代の仏教が御用宗教として、同じく御用学問として使われた儒教とともに封建社会維持のために使われたことが、現在の日本社会における仏教への人々の意識に影響していると思われ、甚だ残念なことだ。
3「道諦」
仏教を学ぶことはこうして実践である「道諦」へと進むことであるが、そこで説かれる「八正道」や「六波羅蜜」の修行について簡単に述べる。「八正道」が「正見、正思、正語、正業、正命、正精進、正念、正定」、大乗仏教の「六波羅蜜」が「布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧」となる。「八正道」も「六波羅蜜」もさらにこれをまとめて「戒、定、慧」の「三学」と言われ、現代でも通用している修道論である。この「因」を修めることで「滅諦」の涅槃という苦からの解脱の「果」がある。この考え方は、迷いの世界である「此岸」から悟りの世界である「彼岸」へ、衆生である自分が修行して渡るものであり、「因」はすべて自分の側にあり、その「果」を自分で受けるものである。いい意味での「自業自得」である。これがいわゆる「自力」の世界、「聖道門」仏教の世界である。
「因果の法」に基づくこの方法論自体には何の問題もない。すでに釈尊によって証明されている。この因果を信じることは仏教の原点である。しかしいくらそれを信じてもその修行ができなければ我々は永久に苦の世界から逃れられない。大乗仏教は一切衆生が「悉有仏性」で成仏すると言いながら、現実には「聖道門」の修行から我々は閉め出されているのを知らされる。これが「機」の「深信」に当たる。「機」の「深信」が無始以来流転し続ける罪悪生死の凡夫という自覚に至るのは、現在の迷いと苦が過去の因の果なら、過去も迷いと苦にあったことになり、また現在の迷いと苦がもし今生でそこから解脱できないなら、また将来の因となって迷いと苦という生死流転の果をもたらすからである。これが此岸の衆生の因果の信がもたらすものである。因果の起点を此岸の衆生に置く限り、自ら解脱しなければこれが当然の帰結である。果たして衆生の側の「因」しか「仏果」をもたらさないのか。これが比叡山で行き詰まった法然、親鸞の問題意識だったはずである。
4浄土教
ここに全く別の発想による救いの仏教が求められる。こうして生まれたのが「浄土門」仏教である。親鸞浄土教はこの問題に答えたものである。そこでは因果の起点を此岸の衆生から浄土の如来に転換する。まず「因」は衆生の側にいきなりあるのではなく、それに先だって如来の側にある。衆生を救おうとする如来の「本願」が「因」となり、如来から衆生に「信心と名号」が「果」として与えられる。即ち「如来廻向」である。衆生の側の「因果」ではなく、まず如来の「因」が衆生の「果」となる。「如来廻向」という「因果」である。次いで此岸の衆生に与えられたこの「信心と名号」を「因」として、彼岸での「往生成仏」という「果」がある。親鸞が聖道門と違い成仏を浄土に置くのは、因も果も浄土の側、如来の側に置くからである。この流れは如来から出たものが如来に還っているのであり、如来の「因」が如来の「果」となっている。聖道門の此岸の衆生の「因果」から、浄土の如来の「因果」へという発想の転換である。これが「他力」という救いの世界である。こうして「聖道門」仏教から漏れた者も「浄土門」仏教によってすべて救われることになり、大乗仏教が完成する。「大乗至極」の教えと言われる所以である。
ただしそれは聖道門の此岸の因果を無視したものではない。むしろその上に立ってそれを補完している。なぜなら、阿弥陀仏となる前の法蔵菩薩は誓願(本願)をたてて願行具足の聖道門的修行をしているからである。「無漏善」の「道諦」と「滅諦」の因と果を修めた結果、成仏して今浄土にあり、救済活動を展開しているのである。因位の法蔵菩薩の誓願が果位の阿弥陀仏の本願として成就して、今働いている。これは聖道門の此岸の因果の上に立って、浄土門の彼岸の因果を展開しているのである。釈尊の聖道門仏教の延長上にあり、聖道門の此岸の因果に加えて、彼岸の浄土の因果を補足しているのである。こうして仏教の因果の世界が完結する。なお浄土門的立場から言うと、この因位の法蔵菩薩も久遠実成の阿弥陀仏(無上仏)が衆生済度のために仮に姿を表したものであり(従果降因)、その点では因果の主系列は一貫して浄土の側にある。
二つの因果を時間との関係で比較しよう。衆生の側の「因果」では、無常の中にある衆生は時間の流れの中にある「因」を何年、何十年、あるいは何生と重ねてその「果」を受ける。無常の中から常住へ向かう。因と果が時間的にずれるのは出発点が無常の中にあるからだ。一般的には「因」が前で「果」が後になるのが「因果」である。
ところが浄土の「因果」は常住の世界にある「因」が無常の世界にある衆生を巡って常住の世界に戻る「果」となる。常住の世界での「因果」であり時間の流れが関係無い「因果」である。それで一念の信心をいただく時に往生が即時に定まる「即得往生」となる。
此土で信心をいただいて「正定聚」となることも本願の果(十八願「至心信楽の願」前半と十一願「必至滅度の願」前半の成就)であるし、称名念仏することも本願の果(十七願「諸仏称名の願」)であるし、また彼土に往生し成仏することも本願の果(「至心信楽の願」後半と「必至滅度の願」後半の成就)である。「行」を説く十七願では、浄土の諸仏の称名が此土の衆生の称名となり、彼土と此土が一体の願成就である。また「信」を説く十八願と、「証」を説く十一願は、ともに一つの本願の前半が此土での成就で、後半が彼土での成就である。このように「行・信・証」のいずれも此土・彼土一体の本願成就である。それで我々が信心をいただいて此土で「正定聚」となることが彼土の「如来と等し」と言われる。ただしそれを浄土での成仏と全く同じにしないのは、すでに述べたように親鸞が因も果も浄土・如来の側におき、こちら側で因果を完結させるからである。しかし信心も成仏も同じく本願の果としての等質性、一体性をもつ。それで信心は仏性と言われる。
このように彼土と此土のように異なるレベルのものが一体となる様相を大乗仏教では「相即」と言う。『般若心経』の「色即是空、空即是色」の「即」である。「相即」は同時因果とも言うべきもので本願成就を表す「即得往生」も「相即」の要素を含むと言える。
時間を越えた浄土の因果では、浄土の如来の「本願」がそのまま「本願成就」となる。無常という時間の流れの中の、此岸の衆生の欲望の世界とは異なり、「願い」がそのまま成就する、時間を越えた世界の「因果」がここにある。欲望のように成就した瞬間に虚しさに襲われ、その虚しさを消すために次の欲望に走るものではない。それが欲望の連鎖である輪廻である。本願の因果と欲望・輪廻の因果の違いがここにある。本願の因果は時間を超えた「横超」の「因果」である。臨終を待って往生が定まるのではないし、多念を重ねた果として往生があるのでもない。多念は発想としては聖道門の因果と似ている。信心決定した一念の相続も、外から見れば多念に見えるかもしれないが、中身が違う。この一念の「即得往生」に安心がある。「平生業成」である。
さらに往生後も原始仏教にはない本願(二十二願「還相廻向」の願」)を因とした還相廻向という果がある。因果の起点を此岸から浄土に転換するとこれが当然の帰結となる。過去どのように迷っていようとも自分の本来の居場所が浄土にあることを知れば起点が此岸から浄土に移り、ここに新たな生が展開する。次の生における還相廻向だけでなく今生においては「自信教人信」が可能になる。浄土往生がしばしば浄土に還ると表現されるのも、如来を御親とも呼ぶのも、自分の本来の居場所が浄土にあることを知り、起点、原点が此岸から浄土に移るからである。浄土教は浄土と如来を起点、原点とする。このように親鸞浄土教は「因果の法」に基づきながら発想を大きく転換させたものである。『教行信証』は「浄土の因果」に基づいて「真実」の救いを説きそれが「本願念仏」に集約される。
ここに何とも言えない「ありがたさ」があり、浄土門に出会えた喜びがある。「法」の「深信」である。法然と出会った親鸞の喜びである。浄土門に至る前書きが長くなったが、この前段階がないと浄土門のありがたさはわかりにくい。親鸞のように二十年かける必要は全くないが、この前段階を思うことは仏門にある者として時に必要なことだろう。親鸞の歩みは千年、二千年(『教行信証』では二千百七十三年)の仏教の歴史の凝縮であり、我々はそれを今「本願念仏」としていただいている。そのありがたさをかみしめたい。
『教行信証』の「四法」
*「教」(仏因)=本願・『無量寿経』(『教行信証』「教巻」本願を宗とし名号を体。)
*「行」(衆生の果・生因)=念仏・十七願「諸仏称名の願」(『教行信証』「行巻」の願)
「たとひわれ仏を得たらんに、十方世界の無量の諸仏、ことごとく咨嗟して、わが名を称せずは、正覚を取らじ。」
*「信」(衆生の果・生因)=信心・十八願「至心信楽の願」(『教行信証』「信巻」の願)
「たとひわれ仏を得たらんに、十方の衆生、至心信楽してわが国に生ぜんと欲ひて、乃至十念せん。(前半)、(後半)もし生ぜずは、正覚を取らじ。〜」
*「証」(仏果)=往生成仏・十一願「必至滅度の願」(『教行信証』「証巻」の願)
「たとひわれ仏を得たらんに、国中の人・天、定聚に住し(前半)、(後半)かならず滅度に至らずは、正覚を取らじ。」
二 究極の因果へ (午後の部)
1「善悪」の因果
仏教の「因果の法」は仏教という宗教を離れてもいわゆる「因果律」として成立するものである。この因果律は科学を成り立たせているものでもあり、そういう点では合理性がある。その意味での「因果の法」を否定する人は誰もいないだろう。ところが仏教の基本をなしているこの「因果の法」が、科学の面では受け容れられても、道徳や宗教の話となると急に旗色が悪くなる。科学の因果律と道徳・宗教の因果律は別物である、あるいは因果律は科学においてだけ成立し、それ以外では成立しないと思っている人が増えているようである。それが皮肉なことに因果律を基盤とする科学が幅を効かせた結果であるようだ。
しかしそれは浅はかな考え方であって、現代の科学が明らかにしているのは、現象の世界のほんの一部であるに過ぎない。その目に見えない世界を含めて「因果の法」は成立している。「因果律」を認めながら、自分だけその外にあり、何をしてもかまわないというのはむしがよすぎる。「因果の法」を信じることは仏教の出発点であって、この点において仏教の果たすべき役割はいささかも失われるものではないと思う。現代社会の様々な病理現象を見ると、かつて人々の心の中に確たる地位を占めていた「因果の法」が見失われているのだろうと思う。これが末法と言われることの一つの姿なのだろう。この因果の信は、浄土門の信から言えば、わざわざ「信」という言葉を使うほどでもなく、知的なものでもあり、少しものがわかればわかりそうなものだと思う。すでに述べたように科学的なものなのである。しかしそれさえ信じられないのなら、そこから説かなければいけない時代になったのだろう。この「因果の法」を説くだけでも充分宗教として成立する。
この「因果の法」の実際的な適用として、かつては誰もが信じ、知っていたことが 「善因善果」、「悪因悪果」であった。これが「三世の因果」として、この世のことだけではなく、この世を去った後にもつながっている。仏教本来としてはすでに述べたように、六道輪廻を越えた世界に至るための「因果の法」が、「道諦」(因)と「滅諦」(果)として説かれ、それを実践修道するのが仏教だった。しかしそこにまで至らなくても、六道輪廻の中だけでもこの「因果の法」は成立する。その範囲では、善をなせば「天」に至り、悪をなせば悪道に落ちる。「地獄、餓鬼、畜生、修羅」の世界である。六道輪廻から衆生が脱することが難しいのは、この範囲の因果さえ信じず無視するからだと言えよう。だからさらにその世界を越えた次の段階の因果に至らないのは当然かもしれない。高次の善である「無漏善」の因果としての「道諦」(因)と「滅諦」(果)にまで至らないのである。
しかし生死からの出離を求めてそこまで進んだとして、この次のレベルの因果である、この「道諦」(因)と「滅諦」(果)を修めようとしたとたんに、より高いレベルの善である煩悩の交じらない「無漏善」をなすことの難しさに襲われるのが修行者の常である。「道諦」の「八正道」や「六波羅蜜」を修することの難しさは、例えば「八正道」の「正見」、「正思」をとってもわかるし、「六波羅蜜」の「布施」や「持戒」をとってもわかる。あるいは「戒、定、慧」の「三学」もそれを修めようとしたとたんに壁に当たるだろう。ここが知識や学問ではない実践の道である仏道としての仏教の難しさである。
この因果を信じた結果、行き着くのが「悪業」だけを積み重ね出離の「善業」をなしえない「地獄必定」の我が身である。「機の深信」である。既に述べたようにここにおいて別の因果の法が要請され、浄土門の如来の本願を因とするもう一つの因果が説かれる。
2「信疑」の因果
因果を衆生の側ではなく如来の側の因果で捉えるのが浄土門であると述べたが、このことを衆生の側で見ると、如来より廻向された「信心」を因として救われ往生することになる。ここで衆生においては「善因善果」と「悪因悪果」、さらに高次の善を修める「道諦」(因)と「滅諦」(果)の「善悪」の因果に代わり、「信疑」の因果が成立する。『正信偈』の「還来生死輪転家 決以疑情為所止 速入寂静無為楽 必以信心為能入」(生死輪転の家に還来ることは、決するに疑情をもって所止とす。すみやかに寂静無為の楽に入ることは、かならず信心をもって能入とすといえり。)という「疑情所止、信心能入」である。
このように親鸞浄土教の因果論は、「如来廻向」の因果と「信疑」の因果から成り立っている。信心は如来廻向のものなので中心は「如来廻向」の因果であることは言うまでもない。『教行信証』では「それ真宗の教行信証を案ずれば、如来の大悲廻向の利益なり。ゆゑに、もしは因、もしは果、一事として阿弥陀如来の清浄願心の廻向成就したまへるところにあらざることあることなし。因、浄なるがゆゑに果また浄なり。」(証巻)と述べられている。『正信偈』では「本願名号正定業 至心信楽願為因 成等覚証大涅槃 必至滅度願成就」(本願の名号は正定の業なり。至心信楽の願(十八願)を因とす。等覚を成り大涅槃を証することは、必至滅度の願(十一願)成就なり。)、また同じく『正信偈』では「報土因果顕誓願 往還廻向由他力 正定之因唯信心」(報土の因果誓願に顕す。往還の廻向は他力による。正定の因はただ信心なり。)と述べられる。我々の信も証も如来の本願が因となり果となるものである。私の因果ではなく如来の因果である。私のものは何一つとしてない。それが浄土門である。そしてただ信心だけがある。それが仏性である。
ところが我々衆生の側においては、疑いが晴れ、信一つになることの難しさという大きな問題がある。これが浄土教が易行道と言われながらも、「難中の難これに過ぎたるは無し」と言われる所以である。『正信偈』に「弥陀仏本願念仏 邪見驕慢悪衆生 信楽受持甚以難 難中之難無過斯」(弥陀仏の本願念仏は、邪見驕慢の悪衆生、信楽受持することはなはだもって難し。難の中の難これに過ぎたるはなし。)という通りである。また浄土門に帰したかに見えながら、信じきれずいつのまにか疑いが頭をもたげる。『教行信証』に「化身土巻」がたてられて、疑いが晴れきれなかった者の往く「疑城胎宮」が説かれている通りである。聖道門の因果も信じて修行することができず、浄土門の因果も信じられないという人はいったいどうすればいいのだろう。そして特に現代人がそうなのである。
せっかく聖道門においては難しいと見えた道が、浄土門においていったん開かれたかに見えながら、再び門が閉じられるように見える。この壁をさらに乗り越えさせようとするところに浄土門の祖師方のご苦労がある。親鸞の「悪人正機」が本当に意味を持つのはそれが最後の救いの言葉であるからだ。通常は「善悪」の因果によって出離がかなわぬ悪人を救おうとするのが「悪人正機」であって、それが信じられるなら、それだけで充分である。ところがそれが信じられないのが現代人である。教育程度が高くなり、分別の知恵が付き、みんな賢くなってしまい、信じるというごく単純なことができなくなってしまっている。この人々の意識の変化が一つある。
それとともにもう一つ原因が考えられる。それは『歎異抄』が有名になり、「悪人正機」が教科書にも載るようになり、言葉として有名になりすぎたことである。その弊害とも言えるものがある。「悪人正機」は本来は「口伝」であり、救いを求める人への最後の切り札だった。劇薬的な特効薬という面があった。それが人口に膾炙してしまうと、新鮮味がなくなってしまうのである。かつてそれを初めて聞いた人々の心を捉えたような感動、ありがたみがなくなってしまうのである。『歎異抄』の著者である唯円と同じ立場に現代人は立てなくなっているのである。
私自身は「信心正因」でいっこうに問題はない。しかしそれが成立しにくくなっているのが現代の問題である。それが信と救いの宗教である真宗を襲っている困難である。これまでに述べてきた経緯を理解していただければ、親鸞浄土教が救いの宗教として、行き着くところまで行き着いた宗教であることがわかると思う。さらにそれを端的に表したのが「悪人正機」だった。しかしそれが通じないならば、次々と新たな表現をしていくしかない。私が「悪人正機」の拡大解釈をしていくのはその試みであって、どこか一つでよいから心に触れるものがあればと思っている。
「悪人」とは善悪の「悪」を犯した者というだけではなく、無明と無常という監獄の中に閉じこめられている我々人間の代名詞である。無明と無常の囚人の自覚である。それなくして真実の救いはない。その中でわかりやすいのが善悪であるから、「悪人」と言っているだけである。無明と無常に繋縛された人間の姿は様々であり、いわゆる「悪」をしていないから「悪人」ではないというわけでもなく、「悪人正機」も関係ないわけではない。
3「逆縁」の因果
この無明と無常の中に閉じこめられ、つながれている人間を、逆にそれを縁として真実へと導くのも浄土教の役目である。ここで同じく「因果」でありながら、通常の因果とは全く逆に見える「因果」がある。それが「逆縁」という「逆説的因果」である。
聖道門の発想は基本的には、通常の順当の因果である「順縁」の発想である。「善因善果」を重ねれば六道輪廻の中では「天」に行き着く。さらにそこから次の段階として無漏善を重ねて声聞、縁覚に至り、菩薩、仏と段階を踏んでいく。修道の階梯を一歩ずつ無理なく歩んでいくものである。これは誰も異を唱えることのできない順当の因果である。
そこからはずれた人間を救うのが浄土門である。ここにあるのは「逆縁」であり、本来は悟りへの障碍となるものの中にいる人間を救うのである。この逆縁を成り立たせているのも実は「如来廻向」である。すでに「衆生の因果」に代わり「如来の因果」という形でこの廻向を述べたが、その際の「廻向」は信心を与える「廻施」の意味が中心となる。これも廻向の重要な働きだが、私はまた「廻向」には「向きを廻らす」、「廻転」、「方向転換」、「翻す」意味があると思っている。「ものの逃ぐるを追はへ取るなり」と言われるものである。自力の心を翻えさし偽りに沈む人間を根本的にひっくり返す真実の力がある。
親鸞が好んで書き与えた聖覚の『唯信抄』では「信謗ともに因として、みなまさに浄土に生まるべし。」と言う。信じる者が往生するのは当然として、謗っていた者までそれを逆縁として往生するのである。「五逆誹謗正法」という「五逆罪」(殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出仏身血)の者も、正法を謗っていた者も、それを逆縁として往生する。
衆生の側においてはこれが「回心」として経験される。善悪の因果に漏れ、信疑の因果にも漏れた者の最後のよりどころがここにある。「畢竟依」である。「逆説的因果」と述べたが、もはやそれは通常の「因果」を越えたものと言った方がよく、むしろ奇蹟と呼んだ方がいいのかもしれない。それが浄土教においては働いているのである。信仰の奇蹟である。浄土教は「転」の宗教である。その結果、「悪」さえも「転悪成善」として「善」となり、結果的には出発点にあった「善悪」の因果にも適うことになる。
4「自然法爾」
しかし結局これもやはり「因果」として言えば「如来廻向の因果」となる。浄土の因果はこれも含めて、「廻施」も「廻転」も含めての、「自ずから然らしむ」という「自然」の因果である。如来という根本因の働きの結果である。これが「自然法爾」である。法が因となり、法が果となる究極の因果である。因も果もともに法なのだから、あえて因と果に分ける必要もない「無分別の因果」である。如来にとっては本来の姿に戻すだけのごく当たり前のことでも、人にはそれが奇蹟に見える。奇蹟とは「自然」の別名なのである。
さらにその「自然」の基には如来のあるがままの「無為自然」がある。親鸞が「無上仏とまふすはかたちもなくまします、かたちのましまさぬゆへに自然とはまふすなり。」(『末灯抄』)と述べる如来の「自然」である。この自利の「自ずから然り」を因として利他の「自ずから然らしむ」果の働きが生まれる。仮に自利と利他を因と果に分けたが本当は如来にとっては自他や因果の区別も利や損得の分別もない。「如来廻向の因果」とは「自然法爾」という「真実の因果」、「無分別の因果」である。これが究極の浄土の因果である。
こうして浄土の因果をたどると根本因の如来に行き着く。従って果から因に還るのが浄土教である。「法性のみやこへかえる」(『唯信抄文意』)と言われる。心情的には「懐かしさ」「思い出す」ことが鍵になる。懐かしい我が家、ふるさとを思い出しそこに還る。如来にも衆生にもごく自然ななりゆきである。我々の無意識にそこに戻る力が潜んでいる。
これまでに述べたことを基に「自然」を整理しよう。まず一つは「業道自然」である。此岸の因果として述べた衆生の業因による「善因善果、悪因悪果」の因果である。因果の法の基本である。次が「願力自然」であり、ここに衆生に信心を与え、往生成仏させる、如来廻向の浄土の因果の基本の働きがある。ここには「逆縁」摂取の「逆説的因果」である、衆生に劇的転換をもたらす如来廻向も含む。廻施の廻向も廻転の廻向も含んだ「願力自然」である。「願力自然」はいずれも如来を根本因とする如来廻向の浄土の因果である。如来の利他力である他力と言われるものの中心である。そしてさらにその如来の有様が『無量寿経』に成仏の相として説かれる「自然虚無の身、無極の体」の「自然」である。涅槃の別名として使われる「無為」と同じ「自然」で合わせて「無為自然」と言われる。この自利が如来の「自然」の原点であり、ここから利他のあらゆる働きの「自然」が生まれる。
このように「自然」は因果としても説明できるが、意識の上ではむしろ因と果に分けたり利を考える分析的、分別的発想を越えたところにあると言えるだろう。従って意識というよりむしろ無意識のものになる。こうなると「因果」より「自然」と言う方がふさわしくなってくる。晩年の親鸞が「自然」を言うのはそのためだろう。如来の働きも「自然」であるし、また衆生に信心が起こるのも「自然」である。「金剛の信心をうるゆゑに憶念自然なるなり。」(『唯信抄文意』)我々の計らいのない「無義」に「自然」は表れる。「無義」や「自然」には自他や因果の分別や利の分別を忘れることが入っているのだろう。親鸞の歩みは、聖道の因果からその上に立った浄土の因果へ、さらにその意識さえ越えた無分別、無意識の「自然法爾」へと進んだと言えよう。最終的には「自然」でいいが、因果のわきまえがないと、ただのなりゆきまかせや「造悪無碍」に陥るので注意すべきである。
ここで補足しておきたいことがある。中国仏教では仏教が中国に入ってくる前から道家思想において「無為自然」が説かれており、これに対して仏教の「因果の法」が説かれたという歴史的経緯がある。しかし道家思想のもっていた奥深さ、玄妙さは否定できるものではなく、『無量寿経』においても「自然」や「無為」という多くの道家思想の用語が用いられている。「因果の法」と「無為自然」はいずれも世界の有様を説くものとして中国仏教で融合したと言っていいだろう。これはインドでの仏教のあり方とは異なる展開である。浄土教もその展開の上にある。中国浄土教の祖師である曇鸞においても道家思想の影響があり、さらに曇鸞の影響を大きく受けている親鸞も同様であると言われる。これは実は聖道門である禅でも同様で、禅が仏教の「空」よりも、道家思想でよく用いられた「無」を多用するのはその表れと言える。鈴木大拙のような禅家が浄土教に深い関心を寄せるのも、いずれの教えも「自然」の表れであるからだろう。近代日本での老子道の大家だった伊福部隆彦は「無為」を「為す無し」と「無の為き(はたらき)」の両方で使っている。禅、浄、道の三家の一致はこのレベルで起こる。東洋思想はここに行き着くのだろう。
以上の三つの「自然」を含んだ「自然」だが、浄土教の中心は、如来の利他の働きを表す「願力自然」と、さらにその根本にある如来の自利の有様を表す「無為自然」である。「業道自然」は「自然」の中では最も周辺部にあるものだが、ここにも如来の働きは及んでいる。それが「尽十方無碍光如来」と呼ばれる所以である。私達は信じようが信じまいが、その「無碍光」の「自然」のただ中にある。いつか必ずその働きに気付くときがくる。
ここにおいてこの「無碍光」ということの本当の意味がわかる。何ものもこの働きを妨げることはできないということである。「善悪」も「信疑」も越えて、我々を救う真実の働きがここにある。我々が信じようとして信じるのでもなく、帰命しようとして帰命するのでもない。あれほど疑っていた私が気が付いてみたら救いの御手のただ中にいる。そこに感動がある。そこに信心がある。そこに働いているのはただ「自然」なのである。
人々が信じないから浄土教はもうだめだと言うのは嘘である。自己都合の言い訳にすぎない。それは無我の信ではない。如来より賜る「自然法爾」の信ではない。これは私自身の自戒である。真実の働きはそのようなものではない。我々にできることはただ自分の信を語ることだけかもしれない。賢い人には愚かに見えるかもしれない。それでも我らに語らせるものがある限り、この真実の救いを語っていきたい。それが親鸞の歩んだ「自信教人信」の道である。後に続く我々もまた「全員聞法、全員伝道」の道を歩むだけである。

日本人の死生観―浄土教を中心として―
2008.6.1広島市西区民文化センターにて 渡辺郁夫
1 日本人の他界観と仏教
一 古代日本人の他界観と仏教流入以後
古来日本人は多様な他界観をもっていた。これは日本人のルーツが多様であったことと関係しているのだろう。『古事記』、『日本書紀』においても幾つかの他界が語られている。「高天原」、「常世」、「黄泉の国」、「根の国」、「底の国」、「妣の国(母の国)」などである。これと対応するように神々も天津神の系統と国津神の系統とがあり、それぞれ伊勢神宮と出雲大社を中心に一つの世界を形成している。国譲り神話により、顕界を司るのは伊勢神宮を中心とする高天原の神、幽界を司るのは出雲大社の神であるオオクニヌシである。
これに加えて仏教が日本に入り、六道輪廻の世界(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天)とそれを越えた聖者の世界(声聞、縁覚、菩薩、仏)とが加えられた。特にその中の地獄はそれまでの他界にはっきりとこれに対応するものがなかったために大きな衝撃を日本人に与えたと思われる。記紀神話の世界では死は「かんあがる」と言われ、死ねば皆神になるというのが基本的な考えだった。かなり楽天的は他界観だったと言ってよいだろう。例えばスサノオは高天原を追放されているが、出雲に下り、国津神となっている。正邪や善悪の面ではかなり寛容で、罪を犯しても禊ぎ、祓いをすればそれは消せるものだった。
仏教は真理としての因果の道理を基本とするので、善因善果、悪因悪果であり、これは人間が勝手に変えられるものではなく、因果、業報の理法に基づくものだった。これがそのまま他界に反映するので他界も善因善果、悪因悪果に基づいて分かれることになる。理法なので、恣意的な裁きもない代わり、救いもない。この他界は古代日本人の並列的他界の多様さとは異なり、善悪による階層分化である。最下層に地獄があり、六道輪廻の中では天が最上層となる。
しかしここまではまだ迷いの世界で、人間自我にとらわれた「我執」の世界であり、「有」の中にある。それでここの最上部が「有頂天」と呼ばれる。人間的幸福を追求する欲の世界であり、人間的幸福への執着を越えた「無我」の「空」の世界ではない。 それでこれを越えようとする人間に対してはそれを邪魔し、引き留めようとするものがそこにあり、これが「六欲天の魔王」などと呼ばれる。悪魔的存在が地獄だけにあるのではなく、実は人間的幸福のさなかにあるというのは、この天も捨てさせてそれを越えたものを求めさせようとするからである。これを越えたのが仏教を学び悟る声聞から先の世界である。その基本は出家して世俗を捨てた上で真理を求めるものだった。ここからが輪廻を越えた聖者の世界だった。これがいわゆる「彼岸」であり、その前の迷いの世界が、この世界と他界の天から下を含めた「此岸」である。浄土はこの「彼岸」の側の他界である。六道輪廻の世界は今述べたように他界であってもこの世とともに「此岸」の側になる。
そこまで認識が進まないとしてもとりあえずは地獄に落ちるのは何としても避けたいので様々な功徳を積み、少しでも上の世界を求め、またこの世界に生まれ変わったときには少しでもいい暮らしをしたいという人々が仏教を知った貴族階級を中心に増えてくる。浄土教的な考え方の始まりである。やがてさらに平安末の混乱とともに末法思想の影響で浄土教熱が高まることになる。その中から後述する法然、親鸞の浄土教が生まれる。
二 明治時代以降の他界観
時代を飛ばして明治以降に進めて考えると、明治時代から正式にキリスト教が入り、ここに「天国」という他界が入ってくる。これを仏教的他界観と比べると、キリスト教の天国は本来そこに生まれれば、そこで永遠の生命を得て、この世に還ってくる必要のない世界であり、仏教の六道輪廻の世界を越えた浄土と同等のものだったと思われる。しかし、仏教の六道輪廻の中の「天」と混同され、地獄ではない、あの世の中の比較的いい世界くらいの感覚で受け止められ、「天国」は急速に日本に定着していったようだ。マスコミ等での表現を見ても「天国と地獄」という形での対になった他界観が現代の一般的な他界観の代表だろうと思う。
明治以降のその他の表現では仏教者でありながら、科学者、教育者、文学者でもあった宮沢賢治はアインシュタインの理論にいち早く接し、これを取り入れた「四次元」を他界に転用している。『銀河鉄道の夜』は亡くなった友人とともにする一種の霊界旅行と言うべきものだが、そこでも「四次元」の考え方を応用している。仏教の他界がもっていた階層構造を次元として捉えたものである。
他に鈴木大拙が紹介し、今でも読者を持つスウェーデンボルグの霊界は階層構造があるだけではなく、地球外の宇宙までも視野に入れた壮大なもので、宮沢賢治の他界観もこれと通じるものがある。
このように時代に応じて他界観も変遷しているが、私はただ階層構造をもつだけではなく、「迷い」と「悟り」、「有」と「空」、「我執」と「無我」と言った区分を入れた仏教の他界観は真実を生きる上で優れたものだと思う。単純な言葉ではすでに述べた「彼岸」と「此岸」である。これはキリスト教の場合も元来は同様だったと思われる。
2 浄土教の死生観
一 法然、親鸞の浄土教
浄土教は仏教の一部として生まれたので当然仏教の他界観をそのまま受けている。問題は「彼岸」である浄土にどのようにして往くかであった。仏教の他界観の基本は善因善果、悪因悪果の因果、業報の理法によって決まると述べたが、これは浄土教の側から「浄土門」に対して「聖道門」呼ばれる、天台や禅宗の仏教ではその通りである。
平安末に浄土教熱が高まったことを述べたが、貴族にとっての浄土教は、本来の彼岸としての浄土に行くものと言うよりは、実質的には「天」への再生を望むものだったと言えよう。これは本当の意味での永遠の生命を得ることではなく、ただ個生命の継続に過ぎず、本来は迷いの側の生に入れられるのだが、その道理がわからない人にとっては「天」で充分だったのだろう。
しかし、天台の僧だった法然や親鸞にとってはそうではなかった。彼らは聖道門仏教を学んでいるので仏教の基本は充分に承知している。しかし聖道門での修行と因果、業報の理法だけは自分がとうていその彼岸としての浄土に行けないことを自覚した。ここに彼らの苦しみがあり、また革命的仏教が生まれる素地がある。
これを法然は一切経を五度読み返し、ついに中国の善導の『観無量寿経疏』の「一心専念弥陀名号」で始まる一節と出会って「本願念仏」に開眼し、彼にとってのこの問題を解決した。聖道門の修行をなしえない凡夫、さらには地獄必定の悪人も、阿弥陀仏の本願を信じて称名念仏すれば浄土往生できるという革命的な仏教だった。善悪の因果の理法を越えた本願の救いの仏教を提示したのである。
これを受け継ぎ、さらに法然の口伝だったと言われる「悪人正機」を強調するとともに、自らの行や善を積んで浄土往生するのが基本だったものを、それに代えて本願を信じるという「信」によって往生することを強調したのが親鸞だった。それまでの仏教の「善悪」を対とする因果に代えて、「信疑」を対とする因果を打ち出した。「信心正因」と言われる、「本願」と相応する「信心」という「本願と信」の因果、「救い」の理法を見出したのである。本願という如来の根本因と衆生の信心という因の相応するところに、衆生の往生と成仏という「果」が得られるとした。だから親鸞にとって信心は仏性だった。「悟り」の仏教に対して「救い」の仏教がここに生まれた。
もともと大乗仏教では、釈迦仏だけでなく複数の仏がいて、それぞれの仏が自分の浄土を持っていた。大乗仏教はこの部分では、古代日本の他界観と似た並列的で多様な他界観をもっていた。それぞれの仏が自分の浄土に往生できる条件を満たす者をそこに往生させるという考え方である。法然、親鸞は阿弥陀仏の浄土はその本願を信じて念仏する者が往生できるとしたのである。他の仏の浄土のことまで言ったわけではない。
しかし阿弥陀仏の浄土は古来非常に人気があり、そこへの往生を願う人々が多く、経典の解釈も積み上げられたものがあった。天台でも阿弥陀仏の浄土を願う人々は多く、天台浄土教が生まれていた。いくら独自の浄土と独自の条件と言っても、通仏教の理法である、善悪の因果、業報の理法を無視したものは聖道門の人々には仏教には見えず、邪教にしか見えなかった。
結局法然教団は弾圧を被り、法然、親鸞は流罪となった。法然は赦免後まもなくなく亡くなるが、親鸞は越後に流罪となり、赦免後は関東で布教を続けた。しかしやがて彼らの唱えた「本願念仏」の救いの浄土教は、浄土教の大きな潮流となり現代に至っている。
二 親鸞の「還相」
親鸞の浄土教の特色の一つで、死生観に大きく関係するものとして、浄土往生する「往相」だけではなく、そこからこの世界に再び還ってくる「還相」を重視したことがあげられる。これは浄土が本来輪廻の世界を離れたものであり、この世界に生まれる必要がない世界であることを考えると大胆な説である。即ち親鸞の言う浄土は輪廻の中の天と同じでないのか、本当の浄土ではないのではないかと受け取られるおそれがあるということである。凡夫が往生できるというのもそのせいではないかと思われるかもしれない。
しかし決してそうではなく、親鸞にとって最も大事なのは「本願」であり、本願の働きのままに生きるのが彼の生き方だった。自分の説くことがいかに誤解を生みやすいかは、比叡山で学んだ彼にとって分かり切ったことである。しかし本願によって救われた自分はただそれが自分に説けと命じるものを説くだけだった。その働きはこの世を去った後も続き、その中に人々に救いを伝えるためにこの世界に戻ることも含まれていた。それは我執による輪廻の生ではない。自己保存の欲望によって生まれ変わり死に変わることとは決定的に違っている。自分のためにするのではない。本願のまま、生きてよし、死んでよしの浄土教だった。
三 親鸞の「自然法爾」と妙好人
この本願の働きのままに生きるのが彼にとっての「自然」だった。彼にとっての「自然」はそれ自体が偉大な理法であり仏法だった。彼が説いたのは確かに新しい仏教だったが、彼はただ「自然の理」に従っただけだった。それが「自然法爾」である。
この言葉は彼の浄土教理解を語ったものだが、そこにある「自然」は言葉自体は「じねん」という仏教語として使われているが、古来日本人の心をとらえてきたものだったろう。宗教の枠を越えて共感を呼ぶものがある。芭蕉や良寛の生き方を見ても彼らがみな自分なりの道で「自然法爾」を生きていたように見える。良寛は禅家だが、実際念仏者でもあった。もともと自力を否定し他力を説く浄土教は、人為を否定し無為を説く老子の「無為自然」と通じるものがある。浄土経典は中国で翻訳されるときに、老荘思想の「道家思想」を取り込んでいるし、浄土教も中国で発展したので、「自然法爾」も「無為自然」と通じる東洋人の発想だろうと思う。
親鸞の開いた真宗は後に妙好人という篤信者を多く輩出するが、彼らの生き方もみなこの「自然法爾」の中にあるように見える。
その妙好人の一人に江戸時代末期から昭和時代まで生きた「因幡の源左」がいる。彼は一生農業に生き、田畑を耕しながら、農閑期には請われるままに法話をして歩いた人である。この源左には墓がない。彼の檀那寺、鳥取市山根の願正寺には名号の刻まれた石碑があり、昔からこの村の人はその石の下の空洞に自分の骨を入れる。個人の墓はない。これがこの村の風習だった。自然に還るような源左の生き方にふさわしいあり方だと思う。
同じく妙好人として知られた「讃岐の庄松」は、死んだら墓を建ててあげようと言う同行に対して「おれは石の下には居らぬぞ」と言っている。彼らにならえば、本当の納骨とは自分を本来の居場所である浄土に還すことだろう。

女性と若者の心をつかむもの―「本願寺展」より―
2008.5.24浄土真宗・永光寺にて 渡辺郁夫
一 「本願寺展」に寄せて(中国新聞記事「女性と若者をつかんだもの」より)
仏教に三尊像と呼ばれる仏像がある。釈迦三尊は釈迦仏に文殊菩薩と普賢菩薩、阿弥陀三尊は阿弥陀仏に観音菩薩と勢至菩薩を配する。親鸞の妻、恵信尼は親鸞が観音菩薩、法然が勢至菩薩だと告げられる夢を見ている。
この夢は恵信尼筆の「恵信尼消息」に書かれ、一九二一年に本願寺で発見された。今回この書状と恵信尼像が出展される。親鸞は妻帯を公言した初めての僧だが、その夫婦の姿がこの手紙に明かされる。親鸞没後に書かれたこの手紙は亡き夫へあてた恋文に見える。
いつの時代でも女性の心をつかんだ宗教は発展する。真宗の出発点にそれがあった。念珠を繰る恵信尼像の朱に染まる口元に上るのは、亡き夫への尽きせぬ思いと称名念仏だ。
恵信尼が見た夢と呼応するような夢が親鸞にもある。比叡山で行き詰まった親鸞が一二○一年に京都の六角堂にこもり、そこで聖徳太子から受けた、「観音があなたの妻になる」という夢告である。その経緯も「恵信尼消息」に書かれている。それにより親鸞は法然に帰し、妻帯した。この夢告を右上に記した親鸞像が今回出展される「熊皮御影」である。
この親鸞像も念珠を繰る。その前には念仏聖が用いた途中が二股になった鹿杖が置かれている。本願念仏を伝える人生の出発点にあったのがこの夢告である。それはまた恵信尼とともに歩んだ旅路だった。二股が一本となる鹿杖は二人の旅を象徴するかのようだ。
恵信尼像を左に、親鸞像を右に、中央に「名号本尊」を置くと私の三尊像が完成する。こう並べれば、二人が向き合ってともに念仏しているように見える。
親鸞が書いた名号は「南無阿弥陀仏」の六字名号の他に「南無不可思議光仏」の八字名号、「帰命尽十方無碍光如来」の十字名号がある。名号を本尊とするのは親鸞から始まると言われる。
親鸞が名号を本尊としたのは彼にとっての念仏が偶像崇拝ではなかったことをよく示している。しばしば宗教は偶像崇拝に過ぎないと批判される。しかし親鸞にとっての念仏は「本願」という世界の根本精神による「真実」の救いの表れだった。「本願と名号」という御心と御名の、世界に通じる普遍的宗教がここにある。「四海のうちみな兄弟」、「四海同胞」の宗教である。
その親鸞の言葉は悩める青年唯円の心を捕えた。唯円がその感動を記した『歎異抄』の蓮如本が出展される。
いつの時代でも若者の心をつかんだ宗教は発展する。『歎異抄』が若者を中心に一般に読まれ始めたのは二十世紀になってからだ。新たな種はまかれたばかりである。
二 「本願寺展」を見て
1 親鸞御影と恵信尼像
私が本願寺展に行った日は、龍谷大学の岡村喜史先生の「本願寺の歴史と美術」という講演会がある日だった。会場は私の行った時間には満杯で、地階のロビーにモニターが置かれていたがその前もいっぱいだった。私は階段の上から講演を音声で聞かせてもらった。これだけの人が講演に集まるということは、まだまだ安芸門徒の力があるということだろう。会場に入れなかったのは残念だったが、多くの人が集まるのはありがたいことだと思った。
講演が終わった後で展覧会場に入ったので、当然人が多く、また熱心に見入っている人が多かった。会場に入ってすぐのところに親鸞の御影が二種類と恵信尼像が並べてかけてあった。これは私が紹介記事に書いたものに近い形であり、二人が向かい合い語り合っているような雰囲気があった。その恵信尼像の前に、恵信尼が親鸞から聞いた言葉を記した「恵信尼書状」が並べられていた。古筆の仮名書きの文は慣れていないと読みにくいが、幸いに対照して読めるように活字にしたものも置いてあり、それを見ると内容がわかる。実際に親鸞と恵信尼の肖像の前でそれを読むと、今目の前で親鸞が彼女に語りかけているかのようだった。『歎異抄』と同様に親鸞の肉声が聞こえてくる「親鸞ライブ」の趣があり、貴重な体験だった。
一九二一年に西本願寺でこの書状が見つからなければ、現代人の知る親鸞像はなかったと言っていい。親鸞が比叡山を出て六角堂にこもり、「後世をいのらせたまひけるに」、九十五日目の暁に聖徳太子の示現を得て法然上人に帰したことがそこに書かれている。「恵信尼書状」は青年親鸞の求道のさまが描かれた実に貴重な資料であり、大きな発見だった。「恵信尼書状」により親鸞の比叡山下山の理由は「生死出づべき道」を求め、「後世」を祈るという仏道上の問題であったことがよくわかる。親鸞が法然に帰したのは『教行信証』に書かれているように一二○一年のことである。これまで何度か書いてきたが、「恵信尼書状」が発見された一九二一年は一二○一年と同じく六十年に一度巡る干支が「辛酉」の年である。中国で革命の年と言われた辛酉の年に日本で初めに注目したのは、その在世中に六○一年の辛酉の年を経験した聖徳太子(五七四〜六二二)だろう。一九二一年は一二○一年と同じ辛酉の年であるとともに、また聖徳太子千三百回忌の記念すべき年でもあった。私は聖徳太子の導きが今も続いているのだと思っている。
またこの「恵信尼書状」には、親鸞が聖徳太子の示現を得て「後世のたすからんずる縁にあひまゐらせんとたづねまゐらせて」、法然上人のもとを訪れても、その場ですぐに弟子になったのではなく、またそこから百日間、雨の日も晴れの日も、来る日も来る日も法然上人の言葉を聞いて、やっと納得して法然上人に帰依したことが記されている。「また百か日、降るにも照るにも、いかなる大事にもまゐりてありしに、ただ後世のことは、よき人にもあしきにも、おなじやうに生死出づべき道をば、ただ一すぢに仰せられ候ひしを、うけたまはりさだめて候ひしかば、上人のわたらせたまはんところには、人はいかにも申せ、たとひ悪道にわららせたまふべしと申すとも、世々生々にも迷いければこそありけめとまで思ひまゐらする身なれば」(『恵信尼消息一』)
こうして百九十五日かけて、半年以上かかってやっと法然上人にどこまでもついていくという決意を固めたのである。おそらくはこれまで学んだ比叡山での聖道門の仏教に照らして法然の教えを考えるとともに、最後は分別を捨てて法然を信じるしかないという気持ちだったのだろう。親鸞の慎重な性格と思索、そして最後はただ信じるというあり方はここにもよく表れている。親鸞の著作を見ると思索とそこからの飛躍が見事に組み合わされているが、本当の思索というものはそういうものだろうと思う。分別知から無分別智へと飛躍するのである。
2 「恵信尼書状」に見る「聖道から浄土へ」
この「恵信尼書状」に記された親鸞の言葉から、親鸞の聖道門から浄土門への転向の過程が見えてくる。それは聖道門の教えが間違っていたということではない。その教えが自分にもたらすものを知った結果、次の道を求めざるをえなかったのである。聖道門を下敷きにしながら次の段階に進んでいるのである。やがて『教行信証』として結実する道のりがここから始まっている。それを仏教の根幹をなす「因果の法」を中心に見てみよう。
釈尊の説いた原始仏教は元来理知的な宗教で「因果(縁起)の法」(因果律)を中心としている。ただし単純な因果律だけなら、同じく因果律を基礎とする科学と同様に、理知的に受容するだけで済むだろうが、それが過去世、現世、来世に渡る「三世の因果」となると信が必要となる。それを信じないものにとっては何の価値もないものだろう。それどころか欲望の赴くままに生きたい人間にとってはかえって邪魔に見えるものだろう。残念なことに現代においてはこの因果の法を無視することがまかり通っている。まずこの因果の法を知ることから始めなければならい時代である。「信解脱」は原始仏教の中にもあり、親鸞浄土教ほどではないが、釈尊の言葉を信じることから仏教は始まる。因果の法について言えば、「善因善果、悪因悪果」が中心である。
そう言いながらも、実際にはこの世界では悪徳が栄えるように見えることがある。これについてはすでに釈尊在世中から疑問を持つ者がいたようであり、また現代でも因果の法を語るときには反論されることだろう。釈尊も因果の表れる時間的なずれは認めた上で、時間的にずれることはあっても必ずこの因果は表れ、特にこの世を去ったときにはっきりとそれがわかるとしている。「悪いことをしても、その業は、刀剣のように直ぐに斬ることは無い。しかし、来世におもむいてから、悪い行いをした人々の行きつく先を知るのである。のちに、その報いを受けるときに、劇しい苦しみが起こる。」(『感興の言葉(ウダーナ・ヴァルガ)』)天上から地獄までの悪趣を含めた世界があることは釈尊の言葉にはっきりと説かれている。
こうしてこの世のことだけではなく「三世の因果」が説かれる。その上でさらにそれを越えて「この世とかの世をともに捨てた」彼岸の涅槃の世界が説かれている。「奔り流れる妄執の水流を涸らし尽くして余すことのない修行者は、この世とかの世とをともに捨てる。あたかも蛇が旧い皮を脱皮して捨てるようなものである」(『スッタニ・パータ(ブッダの言葉)』)。親鸞が「生死出づべき道」を求め、「後世」を祈るというのは、「三世の因果」を信じた上で、六道輪廻の中の最高所である天上世界に生まれたいのではなく、仏教が目指した六道輪廻を越えた世界に至ろうとしたからである。
そこに至るのもまた因果の理法による。「苦(果)、集(因)、滅(果)、道(因)」の「四諦」を観じ実践することで可能になる。「道諦」がその実践で、原始仏教では「八正道(正見、正思、正語、正業、正命、正精進、正念、正定)」、大乗仏教では「六波羅蜜(布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧)」が説かれる。その実践を因として煩悩を断じ尽くせばこの世で彼岸に至る。
では現世で煩悩が滅し尽くさなかったら迷いの生死輪廻の中にとどまるかというとそうではない。現世で解脱できなかったとしてもあきらめる必要はなく、釈尊は仮に煩悩が残ったとしても四諦を観じて行じた者は迷いの生存には戻らないと説いている。道諦の因はこの世だけで滅諦の果をもたらすわけでなく、死後にも迷いの生死を離れるという滅諦の果を生じる。これは先に述べた、時間的にずれることはあっても必ず因果は表れ、特にこの世を去ったときにはっきりとそれがわかるとしたことの延長上にあり、「苦(果)、集(因)、滅(果)、道(因)」の「四諦」の因果と「三世の因果」を組み合わせたものである。
「どんな苦しみが生ずるのでも、すべて素因に縁って起こるのであるというのが、一つの観察である。しかしながら素因を残りなく止滅するならば、苦しみの生ずることがないというのが第二の観察である。修行僧らよ、このように二種を正しく観じて、怠らず、つとめ励んで、専心している修行僧にとっては、二つの果報のうちのいずれか一つの果報が期待され得る。すなわち現世における証智か、或いは煩悩の残りがあるならば、この迷いの生存に戻らないこである」(『スッタニ・パータ(ブッダの言葉)』)同様の言葉が十六回繰り返されている。
即ち親鸞の「現生正定聚」「往生成仏」と同様のことが説かれている。釈尊においては自分がそうであるように「此土得聖」が中心だっただろうが、それだけではなく浄土教の「彼土入聖」に当たるものもすでに説かれている。浄土教の原点は確かに原始仏教にある。浄土教はしばしば聖道門から仏教ではないと批判される。それはこれから述べるように聖道門の因果の法の上にさらに浄土の因果の法を説いたからだが、仏教の基本からはずれてはいない。原始仏教の延長上にあり、むしろ浄土門が開かれたことで仏教は完成した面がある。
問題はこの因果の理法が、原始仏教においては此岸の衆生を出発点とし、そこから解脱するか、解脱せず生死の迷いを繰り返すかの、此岸から此岸へか、此岸から彼岸への一方通行の因果であることだ。この因果に基づくと現在の苦の果は過去の迷いの因の結果であり、また現在の苦と迷いが因となって来世の苦をもたらす。この連鎖の中にあることを知らされる。もし過去世において解脱していればもはやこの生に還ってくることはないので、この生があることは過去世で解脱していなかったことを示している。何よりも現世を苦と感じる限りは過去世で解脱があったとは思えない。過去世の迷いが現世の苦となっていると受け取られるのである。
そのため釈尊であっても、自分はこれまで幾生となく無益に生死の苦しみを経巡ってきたと述懐するのである。「わたくしは幾多の生涯にわたって生死の流れを無益に経めぐって来た、〜あの生涯、この生涯とくりかえすのは苦しいことである。」(『真理の言葉(ダンマ・パダ=法句経の原典)』)親鸞もまた「世々生々にも迷いければこそありけめとまで思ひまゐらする身なれば」と言うが、これは聖道の因果を信じた結果である。これが実は此岸の衆生を起点とする「聖道の因果」の特徴の一つである。釈尊は実際には還相の如来・菩薩だったはずだが、自ら説いた此岸を起点とするこの因果に基づくとこのように言わざるをえないのである。
これがこの後に述べる浄土を起点とする「浄土の因果」になると違ってくる。法然はこの度の往生は三度目だが、今回はことに往生を遂げやすいと述べるし、また自ら還相の菩薩であることを述べるのである。「命終その期ちかづきて 本師源空のたまはく 往生みたびになりぬるに このたびことにとげやすし」(親鸞『高僧和讃』)、「われ、もと極楽にありし身なれば、さだめてかへりゆくべし」(『法然上人行状絵図三十七』)。
これは因果の起点が此土から浄土に転換したことによる。「此岸の因果」では此岸を出発点とするので、その因果によって生死を繰り返し此岸に留まり続けるか彼岸に至るかのどちらかで、生死輪廻か往相かである。「浄土の因果」となると浄土の如来を出発点としてその廻向である往相と還相の両方向が出てくる。真実が循環する因果の法である。往相はどちらにもあるので、還相があるのが「浄土の因果」の特徴である。もし釈尊を還相の如来・菩薩として受け取るなら結果的に浄土の因果を認めることになる。聖道門でも大乗仏教では「久遠実成の釈迦仏」を説き、釈尊はその化現とする。これは浄土教の還相と同様の方向であり、浄土の因果を認めたのも同然だろう。結局仏教、特に大乗仏教としては往相、還相の両相があるのが望ましいのである。このように親鸞浄土教は仏教の因果の完成という意味をもっている。
話を元に戻し、自力の修行で煩悩を絶ち迷いと苦の因果の連鎖を乗り越えることができるなら、生死を越えて涅槃に至り再び生死に戻ることはない。しかしそれができないとなると、生死を繰り返すしかない。この此土の衆生を起点とする「聖道の因果」を信じることは仏教の基本だが、その因果を信じた結果もたらされるが、聖者の場合は出離だが、我々凡夫にとっては出離不能である。これが「機の深信」である。欲望人間にとっての因果の信である。この因果は逃れがたい業の連鎖として、過去も現在も未来も三世に渡り我々にのしかかってくる。今この苦界にいることがその因果が働いている何よりの証しである。
「聖道の因果」は元来因果律というものの理知的な理解を中心として、「生死輪廻」の生命の連続性という三世の生を信じることを組み合わせたものなので、「機の深信」は自分を深く見つめた結果もたらされる理知的な自覚でもある。ただしそれは分別知である。
ここにおいてもう一つの因果が要請される。それはすでに浄土にある如来を起点とする因果である「浄土の因果」である。浄土の如来の本願を因として此土の衆生がここで信心を得て救われる果がもたらされ、さらにそれをまた因として浄土への往生成仏という果がもたらされる。如来を起点、出発点とする如来廻向の因果である。これを信じるのが「法の深信」である。ここでの法は「浄土の因果の法」、「如来廻向の因果の法」である。これが他力の世界である。この信は知に対応させれば無分別智でもある。これが「信心の智慧」である。「二種深信」は聖道の因果の信と浄土の因果の信を組み合わせたものである。「二種一具の信」と言われるが、そこには仏教の因果である「二種一具の因果」があり、それを信じるものだ。聖道門の因果を無視してはこの信はなりたたず、「造悪無碍」に陥るのはそのことがわかっていないからである。
この「浄土の因果の法」は、浄土の祖師から始まるが、この時代では法然がその端緒を開き、親鸞の『教行信証』によって完成されたと言っていいだろう。これにより仏教の因果の法が完成したと言える。往相、還相の両相をもった仏教となる。今我々はありがたいことに、すでに法然、親鸞によって完成されたものを受け取ることから始まっているが、これまでにないものを説くことの難しさは想像を絶するものがあるだろう。親鸞はしばしば経典の読み替えを行うが、「浄土の因果の法」を完成させる営みがそこにある。
そのように後に完成した立場から見れば法然の教えを受け取ることは容易だろうが、親鸞は長年比叡山で聖道門の修行をした人間であり、聖道門の因果が身にしみ込んでいる。それから見れば浄土の因果の世界へ進むのは、次の段階といいながらも大転換である。親鸞が六角堂にこもってから法然の弟子になるまでの百九十五日間がその難しさをよく表している。「恵信尼書状」を読みながら感慨深いものがあった。
また六角堂で受けた夢告は観音があなたの妻になるというものだったと考えられている。その夢告を記したのが「熊皮御影」である。これも出展(後期)されている。親鸞の悩みとその解決、その後の親鸞と恵信尼の出会いもここにある。青年の悩みと男女の出会い。その背後に見えるのが法然と阿弥陀仏の存在である。
3 靉光の絵と真実を求める青春群像
この他にも見るべきものは多々あるが、本願寺展を見た後、私は常設展も見たので先にそのことに触れておく。そこで見た絵に、親鸞と恵信尼像と重なるものがあった。それは靉光の天を仰ぐような自画像と、「コミサ」という俯いて祈るような女性像である。これが出会う前の親鸞と恵信尼の姿に重なって見えてくる。靉光(一九○七〜一九四六)は広島県(北広島町壬生)出身の画家で、昨年二○○七年が生誕百年に当たり、それを記念する展覧会が東京国立近代美術館他、広島でも開かれた。その際にもこの絵を見たが、今回特に印象に残った。昨年はまた一二○七年の「承元(建永)の法難」から八百年の年だったが奇縁である。
靉光の自画像は三種類あるが、広島県立美術館所蔵のものは「帽子をかむる自画像」である。この自画像は戦争中に描かれたもので、そのどこか天の一角を仰ぐような姿は苦難の時代の中で真実の美を求めてあがいている姿のようにも、また救いを求めている姿のようにも見える。年齢的には三十代半ばのものだが、真実を求め苦しむ青年の自画像と言っていいだろう。この時代の多くの若者が同じような気持ちだったかもしれない。美を求める画家は誰よりも敏感に困難な時代の中で真実を求めようとしていたように見える。その姿に比叡山時代の親鸞と重なるものを感じる。親鸞も比叡山で真実を求めながらしばしば天を仰ぐことがあったのではなかろうか。キリスト教に「神の沈黙」といわれるものがある。求めても祈っても神は沈黙したままであることを表すものだ。仏教でこれを言えば「如来の沈黙」ということになるだろう。求めても得られないものをなお求めざるをえない人間の姿がここにある。これが法然と出会う前、本願と出会う前の、後世を祈っていた親鸞の姿だろうと思う。人がいつか一度は通る道である。
もう一つの「コミサ」は靉光二十代の作品である。傘に寄りかかって目を閉じた少女は俯いて祈っているように見える。題名は作者の妹の名を取ったものだが、その雰囲気がキリスト教の「ミサ」を連想させる。少女の祈りに救いを求めるものを感じる。この作品は作者が傾倒したルオーの影響が強く出ていると言われる。ルオーはキリスト教の宗教画家としてよく知られ、この作品もルオーのもつ宗教性を引き継いでいるように見える。
私にはこれが親鸞と出会う前の恵信尼の姿と重なるように見える。彼女は晩婚で親鸞との出会いの経緯ははっきりしないが、彼女もただ自分の幸せを祈るということだけではなく、親鸞同様に後世を祈る気持ちが強かったのではあるまいか。そうでなくただ幸せな結婚を望むだけなら、当時はありえなかった僧侶との結婚に踏み切るはずがない。二人がどこで結ばれたかははっきりしないが、同じく法然の教えを聞いた縁があったと考える方が自然に思える。だからまた親鸞も法然に出会うまでの自分のことを彼女に語ったのだと思う。靉光の作品は、妹の結婚を機にその結婚前にこの作品を描いたと言われる。妹は自分のこれからの幸を祈っていたのだろうか。あるいは靉光は自分の気持ちを妹に投影したのかもしれないし、また妹を自分の理解者として自分の気持ちを代弁させたのかもしれない。この仰ぐ像と俯く像が、やがて真実において出会うとき、親鸞と恵信尼の像のように向かい合う像になるように見えるのである。
親鸞と恵信尼の出会い以来、青春と浄土教の縁は深い。それは二十世紀においても顕著である。『歎異抄』が青年を中心に一般に読まれ始めたのは清沢満之(一八六三〜一九○三)とその門下の影響が大きい。清沢満之が『精神界』を発行したのが一九○一年で二十世紀の初めの年である。広島県庄原市出身の倉田百三(一八九一〜一九四三)が『歎異抄』を下敷きにして書いた『出家とその弟子』は一九一六年に発表され、ベストセラーとなった。『出家とその弟子』は青春の宗教文学である。またすでに述べたように、『歎異抄』と同様に、親鸞の言葉を実際にその場で聞いた「親鸞ライブ」としてそれを記した恵信尼の「恵信尼書状」が西本願寺で発見されたのは一九二一年のことだ。そこには青年親鸞の姿と恵信尼の姿が記されている。これが発見されるまで恵信尼の存在は今のように大きくはなかったはずだ。当時の『歎異抄』や「恵信尼書状」は古典というよりも、新しく発見された書物として青年の心を捕らえたのだと思う。
また先に述べた靉光は二十世紀前半を生きた画家であり、ここにも同じく二十世紀前半の青春がある。靉光の自画像と「コミサ」は二十世紀の青春群像を代表するかのようだ。『歎異抄』や「恵信尼書状」を受け入れたのも、靉光の絵を受け入れたのも、彼ら二十世紀前半の青春群像だったのだろう。親鸞と恵信尼の物語は二十世紀前半を生きた若者の青春と呼応するものを宿した永遠の青春と言うべきものがあったのだと思う。これは単なるロマンティシズムではない。青春の真剣な真実と愛を求める姿がそこにある。親鸞と恵信尼の存在は「無量寿」に照らし出された青春であり、二人なのである。そこに惹かれた若者はそれを一つの理想像としたのだろう。
この秋から作家の五木寛之の「親鸞」が新聞に連載されるそうである。五木寛之は自身の体験を描くことを含めて、青春小説の名手である。おそらく親鸞の比叡山下山から法然、恵信尼との出会いまでは、作品の一つの山場になるだろう。「青春の門 親鸞編」になるのではあるまいか。また親鸞晩年の唯円とのやりとりも、青年唯円と親鸞自身の青春とが重ねて描かれることだろう。作者は『出家とその弟子』を越える作品を目指すはずであり、楽しみである。
4 その他の展示
もう一度「本願寺展」の会場に戻ろう。本願寺は大寺院として朝廷との関係をもつようになるが、その結びつきの結果もたらされたものの中に興味深い展示品がある。後鳥羽上皇の「熊野懐紙」である。後鳥羽上皇が度々行った熊野詣での際に詠まれた上皇と側近の歌を記したものだ。後鳥羽上皇と言えばその熊野参詣の折に起こった女房(松虫、鈴虫)の落飾事件が院の逆鱗に触れ、一二○七年の法然教団の法難である「承元(建永)の法難」を招いたことで知られる。この「熊野懐紙」はその事件以前の一二○○年の参詣の折のものだが、法然、親鸞が流罪となったことと関係のある上皇の熊野参詣の歌となると、これが本願寺に贈られて所蔵されているのは不思議な縁である。後に後鳥羽上皇は「承久の変」で鎌倉幕府に反乱を起こしたために自身も隠岐流罪となった。そこで作られたという「無常講式」は「存覚法語」に引用され、さらに蓮如の『白骨の御文章』に引用されて今も真宗で盛んに読まれている。この縁を思うと後鳥羽上皇は『観無量寿経』の阿闍世と同様に「逆謗摂取」の役回りを演じたのかもしれないと思わせられる。
また「本願寺の至宝」の部屋にはきらびやかな障壁画や欄間が展示されている。こういった「花鳥風月」も浄土教と必ずしも無縁ではない。浄土の荘厳を表すものとも言えるし、何よりも一切衆生がみな阿弥陀仏の本願の中に生かされていることを感じている念仏者の感性と一致する。現在も本願寺発行の「大乗」誌には昆虫や植物の連載があるが、これが念仏者にとっての「自然(じねん)」である。特に欄間には尾長鶏が舞い飛ぶ姿が透かし彫りにされており、私たちの心をしばし浄土に運んでくれる。親鸞の名が鳥の名を含んでいることからも縁を感じる逸品である。

発掘・『歎異抄』
2008.5.17京都光華女子大にて 渡辺郁夫
1 はじめに 『発掘歎異抄 親鸞を読み解く百話』について
一九九九年に『歎異抄を読む―悪人正機の時代を生きる―』を発行後、ある月刊誌に「発掘歎異抄」と名付けた連載を始めた。この連載は八十六回まで続いたが、その後も私のウェッブサイトに連載を続け、二○○八年二月号までで百回に達したのでそれを単行本にまとめた。足かけ九年かかり、ほぼ私の四十代がここに収まっている。母体となっているのは前述の『歎異抄を読む―悪人正機の時代を生きる―』だが、できるだけ読者に読みやすいように、読み物となるように心がけたつもりである。『歎異抄』の精神、また浄土教の精神を中心にしたエッセイと言えるだろう。
私の頭にモデルとしてあったのは、親鸞の『末灯抄』などの和文の消息類や、その流れを引く蓮如の『御文』である。漢文中心だった仏教が和文で表現されていくということが、鎌倉新仏教以降の流れとしてあり、これは大事なことだと思っている。蓮如の布教は行動力とともに、大量の『御文』による文書伝道と名号本尊を書き与えることによっていると言えるだろう。『御文』は親鸞の和文の消息類に基があり、名号本尊も親鸞の独創で親鸞から始まると言われる。親鸞にとっても蓮如にとっても、消息や『御文』を書くことと、名号本尊を書くことは、その一つ一つがともに「本願念仏」を伝えることだったのだと思う。私の一話一話もそうありたいと思って書いたものである。
親鸞の名号本尊は、誰でも本尊を持てるものである。これは仏教を貴族文化から一般民衆に解放したという面で大きな意味がある。寺や仏像は貴族しか持てないが、名号本尊があれば、家がそのまま道場となるのである。在家仏教という面ではこれは大きな意味をもつ。もう一つ仏像や仏画はそれを拝むことにより偶像崇拝に陥りやすいという問題がある。名号本尊はそこに表れた、ある精神そのものを直接受け取るものであり、親鸞の念仏が何であったかをよく表している。つまり親鸞による偶像崇拝の否定という面があり、私は現代においてはその意味をあらためて受け取り直す必要があると思っている。偶像崇拝ではない「真実」の宗教としての真宗がここにある。このようにある精神をそのまま伝えていくということが宗教伝道の中心であり、親鸞はそのためだけに生きたと言えるだろう。その純粋さが『歎異抄』を支えているものである。
現代では宗教はしばしば偶像崇拝や現世利益に過ぎないと批判される。崇拝の対象は物体やカリスマとして外にあるものだけとは限らない。我々は心の中に観念としてそれを作り出し、結果的に自我の補強を行っていることが多い。宗教紛争の基はここにあり、偶像崇拝の問題を解決するだけでも宗教はわかると言ってもいいくらいである。自我の補強手段である偶像崇拝でもなく、この世に人々を縛り付ける現世利益でもないのが、親鸞の伝えようとした「真実」である「本願念仏」の精神である。
人々の心から見失われた「真実」を、あらためて現代の文章の中に込めて、世の人々に伝えたいというのが私の願いであり、この世界に「本願念仏」の精神を伝えることは、「全員聞法、全員伝道」を基本とする「非僧非俗」の同朋教団として、親鸞の後継者である真宗門徒の等しくなすべきことだろう。本書は一念仏者による、その一つの試みである。
2 現代における宗教の伝え方
宗教の伝え方はその人が宗教をどう受け取っているかによって変わってくるので人それぞれである。真宗では先に述べた文書伝道と名号本尊とともに、『歎異抄』に見られるように、説法と聴聞が重視された。『歎異抄』は親鸞の語録を基にして当時の異義を批判するという形をとっているが、『歎異抄』が広く読まれるようになったのは親鸞の語録、特にその対機説法の魅力によるところが大きい。直に親鸞に接した人が書いた「親鸞ライブ」という面がある。これは先に述べた「本願念仏」の精神の体現者の自由自在に語る姿を写し出しているからである。これが教条主義的な真宗理解を越えたものをよく表している。親鸞がただの思想家、イデオローグではないことをよく表している。唯円の「歎異」の異義批判の部分には、まだ教条主義を脱し切れていない部分が感じられる。
親鸞その人の表したこの自由度は「自然法爾」という言葉によく表れているが、現代において新たに表現をしようとするときは、親鸞の書いたものを教条主義的に受け取ることを越えないとできないという面がある。浄土教の近代化、現代化を進めようとするとしばしばこの壁に突き当たる。教条主義的、原理主義的な親鸞浄土教の受け取り方との溝がどうしても生じる。二十世紀初頭に始まった清沢満之の改革もその壁との戦いだったと言えるだろう。こういった新たなものを生み出すエネルギーが教団内部のことで消耗されてしまうのははなはだ惜しむべきことだと思う。
そもそも『歎異抄』が青年を中心に一般に読まれ始めたのは二十世紀になってからのことだ。また『歎異抄』と同様に、親鸞の言葉を実際にその場で聞いた「親鸞ライブ」として、それを記した恵信尼の『恵信尼消息』が西本願寺で発見されたのは一九二一年のことだ。そこには青年親鸞の姿が記されている。『歎異抄』や『恵信尼消息』は新しい書物として青年の心を捕らえたのだと思う。それは親鸞再発見という面があった。しかし新しさは有名になればなるほどその力は減じてしまうという面がある。
そうこうしている間に、宗教を巡る世のあり方は激変している。私自身の経験でも真宗を巡る環境はこの十年ほどで相当変わったと言える。二十世紀から二十一世紀にかけての世紀の変わり目に、世代交代の波とともに変化が押し寄せているのだろう。戦後に育った人は戦後教育の影響や繁栄する物質文明の中で育った環境のせいか、概して宗教に無関心である。真宗の法座もお参りする人がかなり減っている。私がよく聴聞に行く広島で明治時代から続く「闡教部」という門徒による自主的な講があるが、そこでその変化を実感している。内部で異義だ、異端だ、異安心だと、言い争っている間に真宗そのものが衰退の危機に瀕しているというのが実態だろうと思う。連綿として伝えられてきた「本願念仏」の精神が伝わらなくなることは大変な事態である。私はそれを様々な表現を通してもう一度伝えたいと思っている。
その際に人々から敬遠されつつある宗教を宗教そのものとして語るだけではなく、その精神の表れを様々な事象や文化を通して語ることも必要だと思っている。宗教の偉大さは、それがこの世界だけではなく、全世界大の大きさで、全てを包含していることにある。私の目には宗教から漏れるものは何一つとしてないように見える。それが見えなくなった現代というのは異常な時代に見えるし、人々がそれで平気で生きているのはおかしいのではないかとさえ思う。しかし本当は人々の心の中は相当すさんでいるのだろう。日本での年間三万人という自殺者の数もそのことをよく表しているだろう。
私が宗教を伝えるに当たって重視しているものに、芸術と哲学がある。いずれも宗教の精神がそのまま表れやすい領域であり、宗教芸術、宗教哲学というものもある。浄土教の浄土も「本願」という根本精神の芸術的表現と言っていいものである。芸術と哲学は、宗教の具象的表現と抽象的表現、あるいは感性的、情緒的表現と知的表現という面がある。阿弥陀三尊は阿弥陀仏を中心に観音菩薩と勢至菩薩からなり、これは観音が阿弥陀仏の慈悲を、勢至が阿弥陀仏の智慧を表すと言われる。これは宗教を中心において芸術と哲学が言わば三尊を形成していることと対応していると思う。観音に当たるのが芸術、勢至に当たるのが哲学である。また、仏教全体、さらには宗教全体としては、三尊は慈悲の宗教である浄土教と智慧の宗教である禅の役目にも対応していると思う。鈴木大拙もそのように浄土教と禅を理解していたのだろう。それで私もこの三尊的な表現で浄土教を語ることをしてきている。名付けようのないある世界の根本精神の表れを、私はそれを仮に「本願」と語っているのだが、「本願」を「本願」として語るとともに、さらにその表れとして、芸術と哲学、具体的表現と抽象的表現、慈悲や愛と智慧の他の宗教を語る形である。
他の宗教も語るというのは、愛の宗教としてのキリスト教がその典型となる。私の語るキリスト教は現在ある正統的なキリスト教とは表面的には違うかもしれないが、私にはキリスト教が伝えようとしたものがよくわかるので、それをしばしば文章に取り入れている。キリスト教が世界宗教なら同じく浄土教も世界宗教である。真宗が日本だけの宗教であるのは本来のあり方ではないし、世界の人々に語っていくときに必要な表現を供えるべきだと思っている。『発掘歎異抄 親鸞を読み解く百話』はその一つの試みでもある。
3 「悪人正機」について
『歎異抄』に表れた浄土教の精神の一つがいわゆる「悪人正機」である。これはもとは法然の口伝にあったと思われ、真宗側ではそのように伝承されてきた。浄土宗の側では必ずしもそうではなかったようだが、これについては梶村昇氏の詳しい論考があり、「悪人正機」は親鸞や源智といった限られた門弟に語られた口伝だったと考えて間違いないだろう。法然はその影響の大きさからこれを誤解する可能性のない限られた門弟に語ったようで、これとは別の表現も伝わっているが、親鸞はこれこそ浄土教の中心精神と考え、語ったと思われる。それで真宗の側ではこれを公開して伝道したわけである。
その結果が、おそらくは法然もおそれた「造悪無碍」となって表れるのであり、「真実」を伝えることの難しさがここによく表れている。しかしこの壁の前で立ちすくんでは道徳と変わらない宗教になる。それを乗り越えて進んだのが親鸞の歩みだった。『歎異抄』はその親鸞の姿を実によく捉えている。私もその精神を現代に伝えていきたいと思っている。『歎異抄を読む―悪人正機の時代を生きる―』という本の副題もその気持ちを込めているし、『発掘歎異抄 親鸞を読み解く百話』でも多くの回を「悪人正機」を語ることに当てている。
先に宗教の三尊について述べ、慈悲、愛の宗教としての浄土教と、智慧の宗教としての禅ということを述べたが、これは言葉を換えれば「救い」の宗教と「悟り」の宗教と言ってもいいものであり、私は宗教の二大原理を「救い」と「悟り」、救済と覚醒だと思っている。他に加える原理としては創造原理だろうと思っている。浄土教の中心は「救い」を語ることにあり、自分の役目もそれにあると思っている。その上で結果的にそこで語られることは、「悟り」の宗教や「創造」の宗教で語られることとも合致すると思っている。
そのように受け取っているので「救い」の究極的表現とも言える「悪人正機」はこれを語らずして救いは成就しないものであり、「本願成就」の証しこそが、この私が救われる「悪人正機」なのである。「悪人正機」なくして「本願」なしというのが私の立場であり、それを語るのが親鸞の役目だった。それが招く誤解は『歎異抄』に語られている通りである。私もそれを語る以上は誤解と非難は覚悟している。
しかしできれば誤解を避け、その「真実」を受け取ってもらいたいと思い、あらゆる角度からこれを捉えている。言わば「真実」の門として「悪人正機」を語るという形をとっている。『歎異抄』を知り、「悪人正機」を知った人の多くがその門の前で立ち止まってしまっている。夏目漱石が『門』で、禅を取り上げて同様のことを語っているが、せっかく門の前まで来ながらそこで立ち止まり、結局は常識、あるいは良識に留まって虚しくこの人生を終わる人の何と多いことか。禅と同じく「百尺竿頭」に一歩を進めなければ「真実」の門は開かれない。これが親鸞にとっては「悪人」の自覚であり、それとともに起こる「信」だった。その一歩を踏み出したときに救いは表れるのであり、自分の側に踏みとどまったまま、自分にしがみついたまま救いを求めてもそれは救いようがない。
そしてその自覚は必ずしも「悪」だけとは限らない。「悪」というのは、如来と自分を「善悪」の軸で語るものだが、如来と自分の軸は無数と言っていいほどあり、その捉え方は人それぞれである。仮にそれを古来宗教でよく語られてきた「善悪」の軸で語っているのである。別の言い方では仏教で言ってきた、「無明」と「無常」の自覚でも同じである。阿弥陀仏は人間の「無明」に対しては「無限の光明」である「無量光」として、「無常」に対しては「永遠の命」である「無量寿」として語られている。「無明」と「無常」に閉じ込められた人間の解放者が「無量光」、「無量寿」である阿弥陀仏である。そこから我々を解放しようとするのが「本願」であり、「本願念仏」が全ての人に与えられたその解放の鍵なのである。「二種深信」が「二種一具」として語られているように、「法の深信」と「機の深信」、「救い」を受け取ることと「無明」、「無常」の自覚はセットであり、何の自覚もなくただ「無明」、「無常」の側に腰をおろしたまま救われることはありえない。
釈尊の説いた「因果(縁起)の法」は此岸の衆生を出発点とし彼岸へ至る因果だが、このわかりやすい因果をまず信じることが仏教の主発点である。聖道門仏教がそうであるようにこの修行が可能ならこれだけもかまわない。しかしまたその因果を信じるだけでは無始以来流転し続ける自分の愚かさを知らされるだけという人もいる。これが「機の深信」に当たるが、そこに浄土の如来を出発点とするもう一つの因果である「浄土の因果」が説かれるとき救いの門が開かれる。これが「法の深信」である。二つの因果は同じく因果の法である。この因果が展開していることに人は気付こうとしない。せめて此岸の因果だけでも信じることがなければ出離はない。そこに人間の愚かさがよく表れている。因果の中にある自分の自覚を促すとともにそこに表れる救いを語るのが親鸞のやり方である。
親鸞の場合はしばしばこれを「悪」の自覚として語るが、それは親鸞が本来極めて倫理観の強い人間だからであり、微細なことも「罪」として感じるからである。「悪」の方で語るのは、「無明」の側で自覚と救いを語ることと同じである。蓮如は主として「無常」の側でこの救いを語っている。親鸞と語り方は違っても「無常」の自覚を促すともにそこからの「救い」を語っている。私もこの伝統を受け継ぎつつ、「無明」と「無常」の自覚を語り、それとともにそこからの解放を「救い」として語っている。
これらはできるだけ具体的に語る方が自分の身近に感じられるだろうと思い、自分自身の身辺に取材したことや、あるいは芸術作品を通して語っている。「発掘歎異抄」は今も続編を書いているが、最近のこととしてはミュージカルの『美女と野獣』を通してこの救いを語っている。魔法によって道具や野獣に変えられてしまった人間が真実の愛によって人間に戻るという展開に浄土教と通じるものを感じるからである。人間が、現代の物質文明が、自らかかってしまったこの魔法を解く鍵が「本願念仏」にあるからである。
最近私は広島で「本願寺展」を見たが、同時に見た常設展で、広島出身の画家の靉光の天を仰ぐ自画像と、「コミサ」という俯いて祈るような女性像を見た。これが出会う前の親鸞と恵信尼の姿に重なって見えた。美を求める人の姿は真実を求める人の姿と重なるものがあり、これも「悪人正機」と通じるものがある。靉光は二十世紀前半を生きた画家で彼の人生と『歎異抄』の紹介や『恵信尼消息』の発見は同じく二十世紀前半で重なっている。二十世紀の青春がこれらのものを受け入れたのだと思う。
また私は哲学的でも語れるものは語ろうと思っている。これについては先に挙げた清沢満之の宗教哲学の教学によく表れている。私はそれを踏まえつつ、特に「悪人正機」を一種の「弁証法」として語っている。「正・反・合」と進み、矛盾からより高次の統合に至る「弁証法」のあり方が、善の希求から悪人の自覚へ進み、そこに人間の善悪を越えた救いの表れる「悪人正機」と同様の構造をもっていることを感じるからである。私はヘーゲルの哲学や、プラトンの「イデア論」は浄土教と同じレベルのことを語っていると思っている。私の表現にはしばしば両者に通じるものがあると思うが、キリスト教の場合もそうだが、意図的にしているよりも、今述べたように元々同レベルのものを語っているので自ずからそうなっているのだろうと思う。これも世界宗教として浄土教を語る一環である。

渡辺郁夫 2008.2.3元浄寺
(午前の部)
1 私と二河白道
私と二河白道をつなぐ最初のものは、私の祖母の部屋にかけてあった二河白道図である。祖母の部屋は二階にあり、仏壇は一階にあった。晩年足が不自由だった祖母にとってはこの図は本尊の代わりにもなっていたのだろう。子どものころは私はこの図を二河白道図とは知らなかったので、地獄と極楽を描いたものかと思っていた。旅人に襲いかかる群賊悪獣、火と水は子ども心には地獄の様を描いているように見えたものだ。自分の宗教的イメージの形成にとってこの絵は大きな役割を果たしたのだろうと思う。
昨年の夏に境港市にある水木しげる記念館を訪れたが、その展示に地獄極楽図の複製があった。これは水木しげるが子ども時代に家に手伝いに来ていた、のんのん婆というおばあさんに連れられていっていた寺にあったものの複製である。のんのん婆の家は境港市の対岸の島根半島にあり、のんのん婆は民間宗教者だったということだ。小泉八雲は松江に来て島根半島のもつ不思議な魅力にとりつかれた人だが、小泉八雲と水木しげるの世界は重なるものがある。小泉八雲には民俗学者としての面があるが、水木しげるも同様で水木しげる記念館にはその展示もある。水木しげるが異界に関心を抱いたのは、島根半島の近くに育ったことや、このおばあさんや地獄極楽図の影響が大きいのだろう。そのことは安芸門徒の地に生まれ、熱心な念仏者だった祖母に親しみ、二河白道図を見て育った私の人生と重なるものがある。
私が子どものころ二河白道図を見てこれを水木しげるが見たような地獄極楽図のように思ったのは正確に言えば間違いだが、強ち間違いとは言い切れない。少なくとも極楽図の部分は重なっている。また水火の難と群賊悪獣はこの世界のものだが、それは自分の心の中に起こる煩悩として地獄に通じるものをもっている。親鸞聖人の「地獄は一定すみかぞかし」であり、自分の心の中の地獄が描かれていると取ることができる。
またこの世界で起こる、人間のもつ貪欲、瞋恚の表れである戦争や、水害といった災難を考えれば、この世の地獄はいくらでもある。私の祖母は太平洋戦争を経験し、原爆で子ども二人を失い、自身も被爆者だったが、戦争を経験した人にとっては、水火の難と群賊悪獣は、戦難でもあり、また敵兵でもあっただろう。これは群賊悪獣に武士の姿が描かれることがあることからもよくわかる。戦乱の時代を生きた人々にとって敵に追われ、火に追われということが実際にあったのである。それはほんの数十年前までは日本の現実としてあったことだ。
また現代でも、戦難は今も海外では起こっている。水の難、火の難としては、地震や台風といった自然災害がある。さらに環境破壊の結果として温暖化現象があり、それによって台風の大規模化、洪水の多発、低地の浸水、猛暑、干ばつといったものが人類を襲っている。今後ますますその程度が大きくなるかもしれない。これも元をただせば、人間のもつ貪欲の表れである。
このように言えば、まるでそれは平安鎌倉時代の人々がもった末法意識と同様ではないかと思われるかもしれない。一面においてそれはその通りだと思う。それは人間の煩悩、無明といったものはいつの時代でも変わらずあり、少なくともそれは人が自分の心の中をのぞいて見ればわかることである。また文明の進歩によって目に見える形ではこの世界はよくなっているように見えるが、世界全体としてはまだまだであるし、その文明の進歩が地球規模での環境破壊を招いているという現実がある。要するに見る目次第では人間とこの世界は無明の中にあるという意味で常に末法なのである。
しかし同時にその人間世界の無明を照らしだし、闇を破る光明も常にある。それが無量光であり無量寿である阿弥陀仏である。阿弥陀仏は無明と無常からの解放者である。この光が消えることはなく、その光が我々を照らしだし導くことは常に変わらない。見る目さえあれば常に正法でもある。従って末法とは一面において正しいがそれはまだ認識の半ばに過ぎない。「二種深信」の「機の深信(心)」が末法の自覚に当たり、「法の深信」が正法の認識に当たる。「二種深信」も「二河白道」も善導が唱えたものなので両者は対応しているはずである。浄土教は正法・像法・末法の「正・像・末」三時通説で、なおかつ法滅後も続く教法であるが、道を歩むものの実感としては自分の中の末法と如来の正法の認識が中心となる。
このように二河白道図は地獄図ではない。無明の世界から光明の世界に通じる道、無常の世界から永遠の命の世界に通じる道を指し示すものである。光明の世界、永遠の命の世界から言えば、無明の世界、無常の世界は仮のものに過ぎない。本当にあるのは浄土教が阿弥陀仏として語ってきた、無量光、無量寿だけである。無限の光、永遠の命である。人生はそれを発見する旅であると言える。そしてそれに目覚めさせようとする願いと働きが常に我々に臨んでいる。それが本願であり、本願力である。我々を真実に生かそうとする願いと働きである。真実願と真実力である。そのことに目覚めたときに、人生という道は「無碍の一道」となる。これが「信心」という「白道」である。信心の白道を歩む我々の人生は、本願成就の人生であり、我々一人ひとりが本願成就文である。「地獄は一定すみかぞかし」から出発し「無碍の一道」を説く『歎異抄』の世界も、一つの二河白道図である。
この信心という「白道」はもはや水にあって溺れることなく、火にあって焼けることのない、水火の難を逃れた「安心」の道である。群賊悪獣はここに立ち入ることはできない。その信心がもはや無明と無常の私ではない本当の私であり、永遠の命である。その永遠の命である信心がそのまま浄土に往生する。往生するのは信心である。信心の往くところが浄土である。「信心すなはち仏性なり」という、仏性である信心が浄土に往生する。「如来より賜る信心」が如来のもとに還るのである。「如来より賜る信心」は如来の分身であり、それが本体である如来のもとに還る。永遠の命が永遠の命の世界に還るのである。私が往生するのではない。自己執着の対象である自我としての私が往くのなら、それはまだ六道輪廻の世界である。「如来より賜る信心」という、もはや私のものではない私が往生する。それで輪廻の有の生と区別して、浄土往生を「無生の生」と言う。
確かに信心をいただいても、この世で肉体としての私の中に信心がある限りは、ある程度は肉体の制約を受けるように見えるかもしれない。二河白道図で水火の煩悩の中に信心の白道があるように見えるように。また「病」はその制約としては誰しも逃れ難いものだろう。次いで「老」があり、さらにその先に「死」がある。こうして肉体の制約がどんどん厳しくなっていくように見える。ところが最後に解放が起こる。ただしこの解放が機能するには、それ以前に肉体の制約を超えたもの、永遠の命である仏性に目覚めている必要がある。それが平生業成である。それがあると肉体を失うことでもはや肉体の制約を受けることは全くなく、仏性が常に全面的に開顕する。これが往生成仏である。こうして我々は肉体の制約を逆縁として肉体を越えたもの、信心という永遠の命、仏性に目覚めていくのである。
そもそも束縛に満ちたこの世界、此土は、束縛の全くない順縁の浄土に対しては逆縁として存在しているのだとも言える。無明と無常は、その対極にある光明と常住、永遠の命を知らせる逆縁なのである。悪人正機もこの世界と人間の逆縁的構造を端的に表現したものと言うことができる。
しかし肉体を制約の面だけで捉えるのは一面的である。肉体を持っていることは如来から見れば仏性としての信心をこの世界に留めることでもある。それは如来に本願の働き場、活躍の舞台を提供することである。この意味で肉体を持つことは極めて重要なことであり、本願にかなうことである。生き急ぐ必要は全くない。むしろ先に救われた者こそ最後までこの世界に留まり、全ての人を彼岸に渡していく浄土の渡し守となるのである。たとえ群賊悪獣に囲まれても。それが信心をいただいた者の役目である。東岸の釈尊の役目と同じである。『涅槃経』の「阿闍世王の為に涅槃に入らず」、「阿闍世の為に無量億劫に涅槃に入らず」という釈尊の精神である。本願の「設我得仏、不取正覚」の精神である。この生でそれが終わらなければまた還ってきて続ける。こうして我々は肉体を持っても失っても、本願を生き続けるのである。
私はこのように考えるので、自分が、あるいは世界が、今も二河白道図の中にあると思っている。浄土教の提示する人生地図として、あるいは世界地図として、二河白道図は今も生きていると思うし、また現代の二河白道図が次々と生まれているのではないかと思う。人間の深層意識の中では依然として人生の生と死の軸として東西軸は活きており、その上でこれを道として歩む二河白道図は活きているのだと思う。またそのことを意識できた人の人生は、それに気付かないまま、確かな目的もなく欲望のおもくままにさまよったあげくに、無常の風の前に虚しく死を迎える人の人生と大きく変わるはずである。欲望の人生と本願の人生は全く異なるのである。後に仏教の心理学である「唯識」との関連であらためてそのことを考えたい。
2 「平山郁夫展」より
昨年十一月から十二月に広島県立美術館で開かれた「平山郁夫展」で、平山郁夫の絵を見ながら、これも現代の二河白道図ではないかと思った。平山郁夫の絵の人気の秘密もその要素があるのではないかと感じた。芸術の中には無意識の表象という要素がかなりあり、その中に二河白道図の要素が入っているように思ったのである。
今回の展覧会は平山郁夫の画業六十年を記念したものである。私は名前が同じで、また同じ学園の同窓生ということもあり、平山郁夫に縁を感じている。私は職場への出勤の途中に毎日のように朝日を浴びた二葉山の仏舎利塔を見、また安芸の小富士である似の島を見ている。似の島は白島通りで白島電停を過ぎたあたりから八丁堀にかけてビルの谷間によく見える。私の学校の校歌は「安芸の小富士にあかねさし 希望の光輝けば」と始まる。この校歌から題を採った「希望の光 安芸の小富士」という絵が平山郁夫によって描かれている。これが陶板画となって同窓会によって寄贈されて本校の本館ロビーを飾っている。かなり大きな絵で吹き抜けの壁一面を飾っている。この絵が私の最も親しんだ平山郁夫の絵で、この絵はかつての仏教がもっていた「須弥山」の世界を感じさせるものがある。
平山郁夫の世界は大きく言えば仏教絵画、昔で言う仏画の世界であり、それがシルクロードによって東西を結んだ世界的な東西軸の上に展開している。平山郁夫の絵画の一つの原点は広島での被爆体験である。これが絵になったのはかなり後のことで一九七九年に「広島生変図」として描かれ広島県立美術館に所蔵されている。焼けただれる原爆ドームの空を一面に覆う紅蓮の炎と、その炎の中に不動明王を配したもので、人間の作り出した業火とそれを鎮めようとする不動明王を描いた一種の仏画となっている。
私はこの絵を見ると芥川龍之介の描いた『地獄変』のモデルとなった『宇治拾遺物語』の「絵仏師良秀」の話を思い出す。絵仏師という仏画を描いていた良秀という絵師が、自分の家が焼けたときにそれを見て初めて不動明王の火炎の描き方がわかり、それ以来良秀の描く不動明王は「よじり不動」として有り難がられたという話である。
この炎の記憶は平山郁夫にとっては忘れようにも忘れられないものだろう。これが二河白道図の炎と重なる。そしてまたこのときの広島の川は炎から逃れる人々で溢れたという。その人々は水によっても亡くなっていったのである。八月六日の広島は二河白道図の中にあったのである。平山郁夫も修道中学での学徒動員中に被爆し、危うくこの難を逃れた。しかし戦後も長く原爆症の後遺症に苦しみ、これが仏画を描く動機となったと言われている。幸いにしてそれが認められ、やがてさらに仏教伝来のルートとしてシルクロードを描き、国民的な人気作家となっていった。
その画業も展示も明らかに東西軸をもっているのだが、その西の端というべき所に位置し、また時間的には仏陀の時代を過去の始点に置くと、現代に最も近いところに位置する作品に一九九六年「平和の祈り―サラエボ戦跡」という作品がある。シルクロードも砂漠地帯で日本画の画題としては描きにくいと思うが、この戦場跡も本来が花鳥風月を得意とする通常の日本画からはかなり離れたもので、描きにくい作品だろうと思う。この作品は瓦礫の山の前に八人の子どもが立ち、その後ろによく見ると瓦礫の山を縫うように白い道が続いている。子どもたちの中心に立つのは赤い服に黒いズボンの少女であり、その右横に白いシャツの男の子、その後ろに白いヘアバンド、白いシャツ、白いズボンという白ずくめの少女が立っている。この二人の後ろから白い道が延びているように見える。子どもたちの表情は戦場跡に立つ者としては明るい。微笑をたたえているようにも見え、絶望の表情ではない。
私はこのに絵にたいそう心を動かされ、ヒロシマから出発した平山郁夫がヒロシマの焼け跡とサラエボの焼け跡を、また自分の青少年時代と現地の少年少女を重ねて描いているのだろうと思った。この絵の配色や構図は二河白道図と重なるものがあると思う。また少年少女の八人という数はヒロシマの八月の「八」と重なっているのだろうか。また私は仏画を描いてきたこの人にとって「八」は法輪図の「八」の矢とも重なっているのだろうと思う。
「転法輪」とは法輪を回すことだが、またこれは法輪に転ずるとも読める。欲望と業の結果としてあるこの世界の輪廻の悲惨を法輪に転ずるのが仏道である。「怨みに報いるに怨みを以てしたならば、ついに怨みの息むことがない。」(法句経)、憎しみに対するのに憎しみを以てすれば憎しみのやむことはない。これが平和の教えとしての仏教の根本にある。怨み、憎しみをも逆縁として法輪に転ずるのが仏教である。『観無量寿経』の阿闍世の非道もそうである。私はこの八人の子どもたちにそれが託されているように感じた。二河白道図で言えば、もし旅人が後ろから迫る群賊悪獣と戦ったら彼はどうなっただろう。輪廻から逃れることはできなかったはずである。被爆の後遺症に苦しみながら仏画を描いた平山郁夫の心にはこの仏陀の教えが響いていたのではあるまいか。戦後の自らの歩みとこの絵は重なり、そしてまたこれからの世界を担う次の世代へとその願いは託されている。このメッセージを多くの人にまた青少年に受け取ってもらいたいと思う。
平山郁夫の画業が仏陀の時代から現代を結び、しかも東西軸をもって世界的な規模で展開していることは、この展覧会を見た多くの人々の心に焼き付いたことだろう。この中間にシルクロードのシリーズがあるのだが、次にそれについて述べたい。
平山郁夫の初期の画業は仏陀の時代を描いていた。広島県立美術館にある「受胎霊夢」は釈迦が摩耶夫人に宿る際に摩耶夫人が見たという霊夢の伝説に基づく。キリスト教で言えば「受胎告知」に相当するものである。金色の光に包まれた白い象の穏やかな表情とあずまやに座り静かにそれを受け入れようとする摩耶夫人の姿が闇の中に浮かび上がる。この白い象を受け入れる摩耶夫人の姿に信心が見える。広島県立美術館にあるのでこれまでも何度も見てきたが私の好きな絵である。この白い象から「白道」が始まったのだと思う。
仏伝に基づくこのシリーズに続くのが、玄奘三蔵が歩んだ仏教伝来のシルクロードのシリーズである。初期の仏伝を描いていた時代は平山郁夫はインドには行っておらず、想像で描いていたという。そのためか空想的なロマンティシズムが画面から感じられ、それはそれで一つの魅力になっている。それがシルクロードのシリーズになると現場に立ち実景を見て描いているために、かなり画風が変わったのではないかと思える面がある。ロマンティシズムよりリアリズムが前面に出てくる感じがする。乾ききった砂漠や荒野の風景は、伝統的な日本画が得意とする緑豊かな花鳥風月の情緒の世界とは異質な世界に見える。
しかし法を求めてインドに旅した玄奘三蔵の旅の中に、人々は自分ではなしえないことを成し遂げた人物の壮大なロマンを見てきた。玄奘三蔵自身が残した『大唐西域記』(六四六年)と、その旅行に着想を得た『西遊記』は仏教の枠を越えて人々のまだ見ぬ世界へのロマンをかき立ててきた。日本で『西遊記』が繰り返しドラマ化されているように、それは今も続いている。こうしてシルクロードのシリーズには画題そのものがロマンティシズムをもっていてそれがリアリズム的な画面によって描かれている。ロマンティシズムとリアリズムの融合がここにある。これもまた二河白道図の要素である。二河白道図はそもそも幻想的で空想の世界だが、極めてリアルでもある。
この玄奘三蔵(六○二〜六六四)の時代は善導(六一三〜六八一)の時代と重なっている。ともに長安にいた。玄奘帰国の年(貞観十九年六四五年、日本では大化の改新の年)は善導の師、道綽が八十四歳で没した年であり、善導は三十三歳で、長安での教化を始めた。善導も『大唐西域記』を読んだだろう。善導の二河白道は荒野を行く旅人が忽然として現れた幻を見るもので、この旅は玄奘三蔵の西域の旅が念頭にあるかもしれない。また当時の漢詩にも西域はよく描かれ人々のロマンをかき立てた。長安の都では西域から来た人々の体験談がよく聞かれたことだろう。僧侶にも西域出身の人達が多くいたことだろう。そのような人々の語る体験談がこの話の基にあるように思う。
二河白道の旅の中に求法の旅が重なっていたとしておかしくない。むしろその方が話の展開としては自然だろうと思う。求道心のある人物が主人公でなければこの話は成り立たない。また求道心があれば、たとえ西域、さらにインドまで行くことはできなくても、自分の置かれた立場を自覚しさえすれば、今ここで安心を得ることができるのが浄土教であるという立場がここにある。なお一般的には二河白道の旅は善導が長安と終南山を往復する経験が基になったのだろうと言われている(塚本善隆)。確かにそれもあるだろう。ただ終南山はその名の通り長安の南にあり、南北に行くことになり、方向が合わない。この南北を東西に置き換える時に、玄奘三蔵のことが意識に上るだろうと思う。
玄奘三蔵は自身の仏教的立場としては唯識を宣揚し、弥勒信仰をもっていた。その門下の慈恩大師窺基(基)が唯識を説く法相宗の祖である。法相宗は日本では興福寺、薬師寺、法隆寺(現在は聖徳宗を名乗る)の宗教で奈良仏教の中心だった。玄奘は浄土教に対しては阿弥陀仏の浄土に凡夫が往生できるはずはないと批判していたと言われる(道世・編『諸経要集』)。善導の二河白道はそれに対する反論という意味も込められているように思う。
善導が玄奘三蔵の旅と思想を念頭に置いたとすれば、二河白道はそこから着想を得たとも言えるし、またその旅に対して浄土教の立ち場を新たに示したものだとも言えるだろう。着想としては、西への求法の旅という面がまず共通点としてある。もう一つは玄奘が専門とした唯識の立場を応用あるいは転用していることが考えられる。二河白道はイメージの世界として『観無量寿経』の観想念仏に通じるものがあるが、観想念仏で観想するのは浄土と仏なので二河白道では西の岸が対応する。二河白道は『観経疏』で語られているので当然関係が考えられる。それとともに私は唯識とも関係するのではないかと思う。
唯識は唯心論的な思想だが、二河白道の世界もすべて旅人の心の中で起こったできごとであり、唯心所現の世界である。唯識は存在を、迷いとしての遍計所執性、迷いと真実の中間的存在として依他起性、真実としての円成実性の三つに分けるが、この三区分は二河白道が迷いとしての東岸と中間の河、真実としての西岸から成ることに対応する。唯識の依他起性は縁起によって迷いにも真実にもどちらにもなりうるものだが、浄土教ではその中間に当たるところに真実の白道を置いていることで、唯識を越える立ち場を示していると思う。また玄奘の求法が常人にはできない旅であったのに対して心さえあれば誰でも歩むことができるというものである。即ち難行に対して易行の立場である。その易行は信心を得たことによって易行となるのである。問題は心の問題である。心に信心を生じるかどうかという内的な問題であって、何をするか、どこに行くかいった外的な問題ではなくなる。
こうして、玄奘三蔵の旅は人々が憧れながらも彼にしかできなかったものだが、二河白道の旅は信心さえあれば誰にでも歩めるものになったのである。ただ心さえあれば誰にでも可能であり、ただ信心さえあれば歩めるものとなる。玄奘の旅とその教えの矛盾点を突いているように見える。確かに西天インドは遠いが、西方浄土の十万億土に比べれば比較にならない。しかしそのとてつもない距離はただ信心一つで縮まるのである。旅という面でも、心という面でも浄土教は玄奘以上のことを誰にでも可能にしている。浄土教こそ人の心の奥底を見つめて誰にでも歩める道を示したものであるという立ち場である。これは唯識のお株を奪っているのではないかと思える。唯信によって唯識という唯心を越えているのである。
またこの善導と玄奘の関係は浄土門仏教と聖道門仏教の関係として捉えると、日本での法然門下の浄土教と聖道門の関係とよく対応している。法相宗の興福寺が「興福寺奏状」によって、「偏依善導」を標榜する法然浄土教を批判したのもこの流れから言えば必然だったのだろう。
このシルクロードの旅を描いたものとして平山郁夫に「絲綢之路天空」がある。天山山脈の火焔山の前に広がる砂漠をラクダのキャラバンが進んで行く。画面の右から左に進むその旅が二河白道の旅と重なるのである。そして、大画面のせいか、画家の力量のせいか、それまでに見て来た仏教伝来の旅の影響か、自分もそのラクダの歩みの中に入って進んでいるような錯覚に陥る。その列が今も歩み続けているように思えるのである。
会場ではその先に「西方浄土須弥山」が置かれていた。これは白い雪を頂いたヒマラヤ山脈を三枚の大画面に描いたものである。西方浄土と須弥山は本来は別物だが、平山郁夫の中では重なっていたのだろう。中国人が西方浄土を思う時にはヒマラヤ山脈と須弥山に重なっているのかもしれない。本当の旅の目的地はこの山の向こうにあるはずなのだが、この山が目的地になっている印象を受ける。それでいいのだろうと思う。この絵は二○○七年となっているので、私が親しんできた「希望の光 安芸の小富士」の絵が先に描かれているのだが、私が「希望の光 安芸の小富士」に須弥山を感じたのは間違ってはいなかったのだと思う。画家の中で仏教的世界観があり、それが現実の風景の中に投影されてきたのだろう。「絲綢之路天空」と「西方浄土須弥山」を続けて見ると、ここに二河白道図が見えてくるのである。
また平山郁夫の絵にはしばしば太陽が描かれているが、なぜかこれが夕日に見えるのである。実際に夕日を描いたものが多いが、「明けゆく長安大雁塔」という作品がある。これは題名を見れば朝日を描いていることは明らかだが、私にはこれが夕日に見えた。仏塔と夕日が浄土信仰の出発点にあったのだろうと私は思う。実は「希望の光 安芸の小富士」も校歌の内容から言えば朝日を描いているはずなのだが、これも夕日を描いているように見える。私はそれでいいと思っているのだが、平山郁夫の中には夕日のイメージが強くあるのではないかと思っている。これは画家の感性に関係するのだろうが、浄土教が夕日を重んじてきたこととも関係するように思う。
このようにして私は平山郁夫の人生にも画業にも二河白道図を感じるのである。これだけ大画面の大量の作品を見る機会はそうはないかもしれないので、貴重な経験をさせてもらった。平山郁夫の作品は大画面のものが多いが、これはその必然性があることが実物を見てわかる。絵の中に引き込まれるような感覚は写真では難しく、この大画面を前にしないと味わえないように思う。
(午後の部)
3 善導の「二河白道の譬喩」
善導の「二河白道の譬喩」は『観経疏』「散善義」に説かれたもので、かなり長いものだが、要約すると次のようになる。人が西に向かって百千里を行こうとするが、その前に忽然として二つの河が現れた。火の河が南に、水の河が北にある。それぞれ河幅は百歩、深くて底が無く、また南北に果てしなく続く。その水火の河の中間に白い道がある。広さが四五寸で道の長さは河幅と同じく百歩である。その道には水と火が絶えず襲いかかって休むことがない。見渡す限りの荒野には頼ることのできる者はなく、それどころか群賊と悪獣がこの人が一人であるのを見て殺そうと競って迫って来る。引き返しても死、立ち止まっても死、進んでも死である(三定死)。この人はどうやっても死を免れないならこの白道を行こうとする。そのとき東の岸に声があり、「この道を決定して行け」と勧め、西の岸にも声があり、「一心正念にして直ちに来たれ、汝を護らん」という呼び声がする。この人が白道を歩み始めると東の岸の群賊と悪獣は「この道は険悪で死ぬに違いないないから帰ってこい、自分達には悪心はない
」と言う。しかし人はこの声に耳を貸さず道を進むとたちまちにして西の岸に着き、永く諸々の難を逃れ、善友と相まみえて喜びあった。
この譬喩は善導自身によってこの後に解説されている。東の岸が娑婆の火宅の世界、西の岸が極楽浄土。群賊と悪獣は衆生の六根、六識、六塵、五陰、四大。無人の荒野は悪友のみいて善知識のいないこと。水の河が貪愛、火の河が瞋憎という煩悩。白道が衆生に生じた清浄の浄土願生心。東の岸の発遣の声が釈迦の教法、西の岸の招喚の声が阿弥陀仏の衆生を呼ぶ声である。
この譬喩の舞台となるのは、西域に想定された無人の荒野だろう。そこを行く旅人が主人公である。忽然と現れる幻は砂漠での幻覚を思わせる。この幻覚は衆生の心に生じたものだが、迷い、無明によって生じたものと、真実、光明によって生じたものとがある。群賊と悪獣という衆生の六根、六識、六塵、五陰、四大。無人の荒野という悪友のみいて善知識のいないこと。水の河である貪愛、火の河である瞋憎という煩悩。これらはいずれも無明の側に属する幻であり、本来は無いものである。それが人を迷わし、人はそれに惑わされるのである。これに対して、白道である衆生に生じた清浄の浄土願生心。東の岸の発遣の声である釈迦の教法。西の岸の招喚の声である阿弥陀仏の衆生を呼ぶ声。これらはいずれも光明の側に属し、これが本来あるものである。
そもそもこの旅を求法の旅とすれば、初めから教えも行き着く先も道もあったのである。すでに古人によって歩まれた一貫した道があった。それが幻によって隠されようとしている。幻が消えれば道も法もある。玄奘三蔵の旅がそうであったように。これがこの旅の基本である。
またこの道はただ一人歩むものである。それは人が一人生まれ、一人死す存在だからだ。この白道は一人で渡るものだ。狭く見えるのは自分一人の道であることを示している。そして回りを見渡しても誰もいないということがわかったとき道は一人で歩むものだとわかる。きょろきょろしている間はまだ自分の道が見えていないということだ。そして本願の道はその一人ひとりに対応している。必ず備えられた道である。渡り始めればそれが大道だとわかるものだ。そうして人にその道の存在を示すことができる。もちろんそれはその人のために備えられた本願の道である。
ここで考えたいことがある。この白道はこの世、此土、此岸に属するものなのか、それとも浄土、彼岸に属するものなのかということである。二つの岸の中間にあるのだから、どちらでもないというのも一つの答えだろうし、どちらかというのもあるだろう。また中間にあるのだから両方に属するというのもあるだろう。両方に属する場合でも無量光の世界はこの有量の世界を包含していてそれで両方に属するように見えるという答えもあるだろう。浄土にたどり着くまでは水火に襲われるのだから此土、此岸に属するという答えもるだろうし、信心は如来廻向のもので、群賊悪獣はそこに立ち入れないので、浄土、彼岸に属するという答えもあるだろう。
これを数学の集合論で使うような二つの円の関係で考えてみよう。そうすると次のようになる。(一)まず二つの円が離れていると考えるもの。確かに「西方十万億土」という言い方ははてしない隔たりを感じさせる。次に二つの円が接していて、(二)此岸の側にあると考えるもの、(三)両方にあると考えるもの、(四)彼岸の側と考えるもの。(五)二つの円が部分的に重なっていると考えるもの。(六)二つの円の片方が一つの円の中にあると考えるもの。この六種類が考えられるだろう。(七)またそれに加えて、これは歩むにつれて変わるのだという答えもあるだろう。此岸の要素が減っていき、彼岸の要素が増えていくという考え方で、これも出発点をどうするかで変わるが、これも一つの種類に入れよう。この七つめの考え方は前の六つを含めることもできる。そうすると七種類の考え方がありそうだ。私はこれは一種の公案として成立しうると思う。その答えはその人の受け取り方、立場、心境によって変わってくるだろう。
ここでこれを考える一つの手がかりを出したい。それは陰陽五行説との関係である。私はこの譬喩で南に火の河、北に水の河があるのは、陰陽五行説によるのだと思う。陰陽五行説では「木、火、土、金、水」の五行をそれぞれ方位の「東、南、中央、西、北」に配当する。またこれには色があり、「青、朱(赤)、黄、白、玄(黒)」となる。南に火と赤、北に水と黒、西に金と白となる。西の浄土が清浄の白で阿弥陀仏は金色だろう。この配当だと中央の土が中間の道になるのはいいのだが、色としては黄になりそうなものだ。実際昔は道の色は土の色だった。それが白になるのはこれが西への道だからだろう。また西に属する道として西から延ばされてきた道ととることもできる。私はこの道はこの世で無明煩悩に沈もうとする衆生に、浄土から延ばされた救いの道として感じるので、この世にありながらも浄土の側に属するものだと思う。中央の「土」がそのまま「浄土」の「土」の表れになるのだと思う。だから水火が襲ってもこの道を消すことはできないし、群賊悪獣はここに立ち入ることはできない。この白道は我々を往生させようとする如来の「願生心」の表れである。それが我々の「願生心」となる。この如来廻向の信心が白道であり、「即得往生」の道である。この道を通して、我々の信心として、浄土はこの世界に進出しようとしている。その意味では浄土は拡張する世界である。二河白道を陰陽五行説と対応させると白道が浄土の側に属することがよりはっきりすると思う。二河白道は中国伝統の世界観の上に仏教、浄土教の世界観を重ねたものだろうと思う。
この考え方から先の二つの円の関係を考えると、私は二つの円が離れているという受け取り方は「百千里」を行こうとする出発点ではあるかもしれないが、信心をいただいた後は、接しているという受け取り方、部分的に重なっているという受け取り方、二つの円の片方が一つの円の中にあるという受け取り方のどれかだろうと思う。またこれが心境に応じて変化していくと考えると、初めは離れていたものが、接点を持ち重なってきてやがて包含され(摂取)、最後は片方つまり浄土の円だけが残る(往生成仏)のだと思う。これが如来廻向のあり方だと思う。なお聖道門ではこれがよく悟りの世界が円相で示されるように、初めから一つの円しか問題にしないだろう。浄土門はこれを二つの円の関係で考えるのだと思う。また天台には「十界互具」という考え方があり、これは今の円で示すと円が重なっている受け取り方や、包含されている受け取り方と近いのだろうと思う。
また、この浄土の位置づけと関連して思うことがある。先に善導の「二河白道の譬喩」は玄奘三蔵の旅を念頭に置いたのかもしれないと述べたが、玄奘三蔵はインドから多数の仏典を持ち帰った。このように仏典を持ち来たることを「将来」すると言う。動詞としての使い方である。普通我々が「将来」という言葉で思い浮かべるのは時間的にこれからやって来るもの、「将に来たらんとするもの」という意味で未来と同じような意味の、時間に付けられた名詞としての将来である。我々にとって浄土は将来そこに行く世界であるが、それに先だって浄土がこちらに自らを将来するのだと思う。さらに言えば、持ち来たるの「将来」だけでもよい。ここに浄土が持ち来たらされ、また我々が浄土に持ち来たらされる。我々のところに浄土が将来され、また我々が浄土に将来されるのである。白道が浄土に属するものであるということをこれに当てはめると、白道は浄土から自らを将来し、またそれによって将来の浄土に我々を運ぶもの、我々を将来するものでもある。これが自力ではない如来廻向の世界である。
このように私は「将来」という言葉に如来廻向を感じる。「即得往生」、「平生業成」、「常来迎」、「正定聚」がそこにある。自力的な浄土観では時間的な将来しか見えないだろうと思う。一般的には将来が未来とほぼ同じ意味で使われるが、「未来」とは「未だ来たらず」であり、まだ来ていないことである。肯定的に言えば将来、否定的に言えば未来である。普通の将来の裏にはこの未確定で否定的なものが潜んでいて、期待の裏に不安が隠れている。期待という自力の裏に不安が隠れている。前に時間の壁がまだ立ちはだかっているのである。それに対して白道の信心をいただいた我々は、如来廻向のすでにここに将来された浄土を生きている。如来の側ですでにこの時間の壁を打ち破ってくださっているからである。すでに御手の内にあるのである。ここに本当の安心がある。このような意味でも私は白道は西の側、浄土の側に属するものだとも思う。
また「如来」という言葉も「如より来たる」ものであるとともに「如に来たる」ものでもある。如来の原語である「タターガター」には両方の意味があると言う。この働きは真如から我々のところに来たるものでもあり、我々を真如の世界に連れて行くものでもある。この働きと如来廻向は重なっている。親鸞聖人が如来というものを実感したときに自ずと出てきたのが如来廻向という表現だったのだろうと思う。私は「将来」という言葉にもしばしばそれを感じるのである。
4 親鸞聖人と「二河白道の譬喩」
親鸞聖人は『教行信証』「信巻」に「二河白道の譬喩」を引用される。ここでは親鸞聖人の解釈を引用する。「まことに知んぬ、二河の譬喩の中に「白道四五寸」といふは、白道とは、白の言は黒に対するなり。白はすなはちこれ選択摂取の白業、往相廻向の浄業なり。黒はすなはちこれ無明煩悩の黒業、二乗・人・天の雑善なり。道の言は路に対せるなり。道はすなはちこれ本願一実の直道、大般涅槃、無上の大道なり。路はすなはちこれ二乗・三乗、万善諸行の小路なり。四五寸といふは衆生の四大五陰に喩ふるなり。「能生清浄願心」といふは、金剛の真心を獲得するなり。本願力廻向の大信海なるがゆゑに破壊するべからず。これを金剛のごとしと喩ふるなり。」
善導の自釈を補うものだが、まず注目するのは白道が善導は「清浄の願往生心」が生じたものとしているのに対して、親鸞は「選択摂取の白業、往相廻向の浄業」としていることである。これは衆生が起こすというよりも、如来廻向のものなのだということをより明確に述べている。
この中心を衆生から如来に転換することによって、白道が「路」に対する「道」であって「大道」であると述べられている。「四五寸といふは衆生の四大五陰」であって、衆生の四大五陰のこの体の中に宿った信心が大道であることが示されている。人一人の道だが大道なのである。それがさらに拡大するのが「大信海」である。本願海がそのまま大信海になる。これは拡大の極めつけである。ここまで拡大すると二河白道の構図が壊れてしまうほどなのだが、これが実感なのである。足下から拡大、拡張するものなのである。水火の二河は元々無い幻なのだからこれは当然とも言える。砂漠の中に現れた幻なら、それを見破ればまた足下には大地が広がっているだけだ。もはや踏み外しようがない無碍の大道である。これが自力の小乗ではない大乗の道である。
親鸞聖人がこの「二河白道の譬喩」を門弟に語っておられたことは『親鸞聖人御消息』「十三」にある慶信にあてられた返事に付けられた蓮位の添え状に出てくる覚信坊の話からもわかる。高田の覚信坊が京に上る時に、国を発ち、「ひといち」(不明の地名)という所で病気になり始め、同行たちが帰れと勧めたにもかかわらず、「死するほどのことならば、帰るとも死し、とどまるとも死し候はんず。また病はやみ候はば、帰るともやみ、とどまるともやみ候はんず。同じくは、みもとにてこそをはり候はば、をはり候はめと存じてまゐりて候ふなり」と語ったという。
これを蓮位は「この御信心まことにめでたく候ふ。善導和尚の釈の二河の比喩におもひあはせられて、よにめでたく存じ、うらやましく候ふなり」と褒めている。この添え状のついた返書を親鸞聖人の前で読み上げたとろこ、聖人は「ことに覚信坊のところに、御涙をながさせたまひて候ふなり」と書かれている。覚信坊が親鸞聖人のもとで往生を遂げたことは『口伝抄』「十六」にも述べられている。親鸞聖人の当時、「二河白道の譬喩」をそのまま生きたような人がいたのである。この譬喩が強く人々の心を捕えたことがこの話からもよくわかる。我々がこの師弟の信心から学ぶところはあまりに多い。
5 「二河白道」変奏曲 ―文学作品に見る「二河白道」―
二河白道の譬喩は非常に優れた比喩であり、善導の文学的、芸術的才能を感じさせる。二河白道は宗教芸術なのである。またこの比喩は人間の深層意識にその原型が潜んでいるように思う。すでに平山郁夫の画業や唯識との関連でそのことを見たが、一見仏教とは関係ない文学作品にもその変奏曲と言うべきものがあり、そのことを感じさせる。最後に近代以降での作品で、中学生向きの作品、高校生以上向きの作品、児童文学の三作をあげて、二河白道が今も生きていることを示したい。
まず初めはよく知られた太宰治の『走れメロス』である。中学の国語教科書に定番作品として入っている作品である。そのあらすじを述べながら二河白道との対応を考える。舞台は古代イタリア。村の牧人の青年メロスは、シラクスの街に妹の結婚式の準備のためにやってくるが、その街が以前来たときと変わっているのを知る。それは人間不信のために多くの人を処刑している暴君ディオニスのせいだった。それを聞いたメロスは激怒し、王を暗殺しようと王宮に入ったが、警吏に捕らえられ、処刑されることになる。メロスは親友のセリヌンティウスを人質として王のもとにとどめておくことと引き替えに、妹の結婚式を済ますために三日間の猶予を得て村に帰る。王はメロスにもし遅れて来ればお前を許してやるという。メロスは自分が信じられていないのを悔しがるが、ともかく村に帰って結婚式を済ませる。そして「信実」を示そうと約束通り街に帰ろうと村を出発する。
ところがまずメロスを襲うのが洪水である。次に山賊。そして灼熱の太陽である。これは二河白道の水の難、群賊の難、火の難に当たる。ここにきてついにメロスは疲労困憊して倒れ、いっそこのまま生き延びようかとも思う。こうして自分も王と同じ醜い人間だと知る。そのメロスの耳にふと水の流れる音が聞こえる。岩の裂け目から清水が湧いていたのである。それを飲むと夢から覚めた気がする。そうして再び信頼に応えようと走り始める。この転機となるのは、まず自力の限界によって倒れたメロスに起こる悪人の自覚であり、それとともにその時に耳に聞こえてくる清水の音である。自我の裂け目から聞こえる声である。それが二河白道の如来の発遣と招喚の呼び声である。
ここからメロスを動かすのはそれまでの勇者になろうという名誉欲ではない。間に合うかどうかも問題ではない。欲心からではなく「もっと恐ろしく大きいもののために走っているのだ」、「わけのわからぬ大きな力にひきずられて走った」のである。言わば彼を動かすのは「信実」の力であり、「他力」なのである。自信家としてのメロスは死に、信実の人として蘇ったのだ。夕陽を追いかけるようにメロスは西の街に向かって走る。市の塔が夕陽を受けて光っている。そしてついに街にたどり着き友人と抱き合って涙を流す。それを見た王も改心する。王は言う「信実とは決して空虚な妄想ではなかった」と。この夕陽と西の街に向かって走るのは二河白道を歩むことと同じ、友人と再会を喜ぶのも二河白道の善友との再会と同じだ。王は人間の無明、群賊悪獣を代表する存在だが、それは結局「信実」を証明するためにある仮の姿であり、阿闍世と同様の逆縁的存在である。
次に新しい作品として村上春樹の『鏡』を取りあげる。これは最近の高校の教科書に入っている作品である。二河白道と完全に対応しているわけではないが基本構造がよく似ている。村上春樹の父は国語教師で僧侶だったそうだが、村上春樹は二河白道の話を知っていたのかもしれない。
大学に行くことなく、アルバイトをしながら各地を放浪していた青年はある中学校に夜警として勤務する。ある深夜、警備の見回りを終えて、東から西へと長く延びる廊下を西の端にある自分の部屋に帰ろうとした青年は、その中間にある玄関で、本来そこにあるはずのない鏡が突然現れたのを見る。自分が知らない間に鏡が取り付けられたのかと思う。ところが鏡に映った自分が、自分でありながら自分ではなく、自分を激しく憎悪しているのを見る。青年は恐怖のあまりその鏡を壊して部屋に逃げ帰るのだが、翌朝そこに行って見ると鏡はなかった。それ以来青年は恐くて鏡を見ることができない。
この作品は青少年がもつモラトリアム、猶予、逃避の問題と、自己嫌悪、自己憎悪の問題を小説の形で提示している。自分が最も向き合いたくなく、向き合うのを避けていた自分に、深夜に夜警として勤務した学校の廊下で、鏡を通して向き合う。この廊下が東から西に延びその中間で本来そこにあるはずのない鏡が突然現れ、そこに自分を激しく憎悪するもう一人の自分を見るという展開は、二河白道の譬喩とよく似ている。火の河、水の河、群賊悪獣もすべて自分のもつ無明の表れである。青年が鏡に見たのも自分の無明である。二河白道ではここに「白道」という救いの道があるが、小説の青年は鏡を打ち壊して逃げる。救いの手前までが描かれる。
この作品が「鏡」によって表すように、避けていても人は自分といつか向き合わなければならない。人間の自我は仮のものなので、仮の自己が自分で自分を否定しようとする自己否定の衝動がしばしば起こる。ここに自己嫌悪、自己憎悪が起きる。自我の確立期である青年期に起きやすい。これは本当の自分に目覚めていく一つの過程である。問題はその自己否定の衝動が下手をすると自己破壊となり、自傷行為や自死につながることだ。二河白道でも旅人に襲いかかるのは自分の分身である。宗教はその自己否定の衝動を本当の自分に目覚めることに導くものだ。この衝動がなぜ起こるのか示すことはその予防にもなる。二河白道はすべて自分の心の中に起こることを描いており、人間自我の問題とそれを越えたものの関係に直結している。人間の自我の問題を扱った『鏡』のような現代文学にもその原型が反映しているのを見ると、二河白道が今も新しい形をとって生き続けていることがわかる。
最後に取り上げるのは、今年一月に発行されたばかりの児童文学の新作、朽木祥・著『彼岸花はきつねのかんざし』(学習研究社)である。この作品は先に取り上げた平山郁夫の世界と重なるものがある。それは作者が被爆二世で、広島での被爆を扱った作品だからである。
物語は広島市の近郊に住む一家と、その家の裏の竹藪と鎮守の杜に住む狐一族の、祖母、母、孫娘の三代にわたる交流を描く。化かしたり、化かされたりしながら、一家と一族が同じ自然の懐に抱かれて生きている。人間一家の主人公となるのは小学四年生の孫娘の「也子(かのこ)」。狐一族の主人公が孫の子狐。子狐はまだそれほど人を化かすのに慣れておらず、白いしっぽが美しい。子狐の母は街に出て行ったまま帰って来ないという。也子の父も戦争に行ったまま帰って来ない。この二人(一人と一匹)の交流が中心となる。
二人はともに花が大好きで、出会いの場面は春の一面の蓮華畑から始まる。夏になり戦争がますます激しくなり空襲警報が絶え間なく出された八月の初めのある日、二人の話題は季節にはまだ早い彼岸花の話になる。花を持ってきてあげると言う子狐に、也子が彼岸花がほしいと言うのだ。それもできれば白い彼岸花がいいと。子狐は白い彼岸花は街の近くにしかないと言う。
そして八月六日。也子は学校の校庭で被爆する。プラタナスの木陰にいて助かったものの、それ以来寝たきりとなる。その病床で也子は子狐と会う夢を何度も見る。子狐と鬼ごっこをしたり、狐の嫁入りや、子狐と約束した彼岸花の夢である。一家は竹藪と鎮守の杜のお陰で助かったが、お手伝いの「ねえやん」は街に友達を捜しに行き、街で「毒を拾って」原爆症となり秋を前に亡くなる。
そして秋になり、やっと起きられるようになった也子に、祖母がこのあいだ、お彼岸のころ、裏の竹藪の地蔵石に妙な花束が供えてあったのを見たという。「白い彼岸花」である。それを聞くか聞かぬかの内に也子は家を飛び出す。駆けつけた地蔵石には確かにすでに干からびた白い彼岸花が供えてあった。しかしそこに子狐の姿は見えなかった。いったい子狐はどこに行ったのだろう。
子狐は急に姿の見えなくなった也子を心配しながら、約束の白い彼岸花を見付けるために、何も知らずにまだ毒の残っている街に出かけて行ったのだろう。也子が夢に見た、一面の赤い彼岸花の畑の中に、一点のように咲く白い彼岸花。それを持ち帰って也子の無事を祈って地蔵に供えられた白い彼岸花。しかし素足で被爆後の街に入った子狐にピカの土の毒はきつかったに違いない。白い彼岸花は二人の信と友情の印だった。それは子狐の命とひき替えだったのだろうか。実は地蔵に供えられていたのは子狐の命だったのだろうか。すでに子狐は、街に出て行ったまま帰らなかったという母の国に旅立ったのかもしれない。その胸に白い彼岸花を抱いたまま。
私は自分がよく見てきた、川土手の道沿いに一面に群れ咲く彼岸花を思い出した。あれも二河白道に見える。秋のお彼岸に墓参りに行くときに見る光景だ。山の懐に抱かれて「南無阿弥陀仏」と刻まれた我が家の母方の墓の回りにもなぜか彼岸花が咲く。いつか誰かが植えたのだろうか。そこには被爆死した私の伯母と伯父が入っている。真っ赤な彼岸花の列は確かに彼岸へと続いている。そこに白い彼岸花があれば、それは二河白道の信心の色だろう。私は白い彼岸花を見たことはないが、薄紅色、ピンクがかった彼岸花を見たことがある。これは遠目には白に見える。
この物語を読んで私の目には、焼け跡に咲いた真っ赤な彼岸花の中を、やっと見付けた白い彼岸花を大事にくわえて、白いしっぽを揺らしながら帰って来る子狐の姿が焼き付いた。信じ合う朋のために、朋と会うために。その白い道は彼岸へと続いている。子狐がその後どうなったかに関係なく。子狐と「かのこ」はいずれ「かの岸」で会うに違いない。この岸で会ったとしてもそれはすでに「かの岸」である。二人が信じ合っているからだ。
それはまた広島に生き、二河白道を生きる私達念仏者の姿ではないのか。親や朋との再会を喜び合う「倶会一処」の浄土だけが約束の地ではない。広島に生きる私達にとっては、ここ広島もまた約束の地である。被爆二世の作者にもその思いがあるのではないだろうか。今回この作品を読んで、あらためて私はそのことを思った。
また作者は前作『たそかれ』(福音館書店)でも鎌倉を舞台に戦災をテーマにした作品を描いている。舞台は鎌倉、心は広島という作品である。その主人公は河童の「不知」。浄土教で重んじる「一文不知」の「不知」である。浄土教で「一文不知」の精神が大事なのは、その「不知」が、ただ文字を知らず知識がないということだけではなく、知識や分別を積み重ねることによっては決して得ることのできない「信」を表し、「信心の智慧」に通じるからだ。こうして「不知」は「信」を介して真の智慧、無分別智と同じになる。二河白道は決して知識や分別知では渡ることはできない。知的に分析すればするほどその道は狭く危険になる。転落必至である。信や無分別智が生じない限り。人にとって知はしばしば躓きの石となる。信や無分別智が生じて初めて知識も分別知も活きてくる。
この『たそかれ』の「不知」も人間の友人の言葉を信じて六十年間待ち続ける。それによって人間の友人「司」も河童の「不知」も救われる。この物語は戦災に遭った学校とプールを舞台にしており、ここにも火と水が出てくる。そこから「信」が浮かび上がってくる。これも二河白道に通じるものがある。二河白道は戦乱の時代を生きた人間の姿を一つの原型としているとも考えられるので、戦災を扱った作品では共通点が生まれやすいのだろう。『彼岸花はきつねのかんざし』とともに合わせてご一読をお勧めする作品である。

2007.10.4真宗学寮報恩講 渡辺郁夫
1 はじめに
・困難を越えて
本年2007年は、承元の法難から800年に当たる。この法難により法然教団は壊滅的とも言える打撃を被るが、法然上人によって灯され、親鸞聖人をはじめとする法然門下の人々によって継承された法灯は決して消えることはなかった。この時以来、日本の浄土教、特に真宗は幾多の困難、即ち法難、論難、受難、戦難を乗り越えてきた。織田信長との戦い、江戸時代から明治初年まで続いた薩摩藩、相良藩での念仏禁制、明治時代の廃仏毀釈
、太平洋戦争、特に広島においては原爆という人類史上まれに見る災厄を被った。私は戦後の広島の復興に当たっては安芸門徒の真宗信仰が大きな力を発揮したと思っている。この法灯を絶やすことなく次代に引き継ぎ、日本のみならず世界に伝えていくことが、「恩徳讃」にあるように仏恩と祖師の恩に報いることであろう。
・新たなる困難
しかし戦後五十年を過ぎたあたりから世代交代の波とともに、平和を願うヒロシマの声も、念仏の声もともに小さくなってきているのではないかという危惧を抱かざるを得ない。私の祖母もそうだったが、戦中戦後の困難な時代を念仏によって生き抜いた人々が次々と亡くなる一方で、その後に続くべき人が少ないためだろう。自然減である。これは人が亡くなっていくことだから止めようがない。
現代の困難がこれまでの真宗にふりかかった困難と違うのはこれまでの困難が法難、論難、受難、戦難といった目に見える形であり、それに対して結束を強めて対処するという面があったのに対し、直接的ではないことにある。それだけに対処がしにくい。人々の宗教への無関心や宗教の必要性を認めない心が一般化している。放っておけばいずれ消えてなくなるだろうし、無くなってもかまわないくらいに思われているのだろう。それに加えてより魅力的に見えるのだろうが、他の新しい宗教への流出もある。死による自然減の場合とは違うが、去る者を止めることは難しい。こうして自然減、無関心、流出という非常に対処しにくいものに襲われているのが今の真宗だろう。
私が「こころの回廊」の連載の最後に書いた、「末広がりの末代」、「還相廻向の時代」ということは、浄土教の精神に照らして見れば当然のことだと思うが、あえてこの現状を打破するという観点から書いた面がある。今回この御縁をいただき継承について考えたい。
2 継承させるもの
・法則
普通に考えれば、継承するためには我々が伝え、広めるという努力をすることが必要である。しかし本当にそうなのだろうか。人間が作り出したものなら人間の努力なしには伝わらないだろう。しかし人間が作り出したものには限界がある。ここ百年の思想の世界を見ても、人間が作り出した思想は一時期はもてはやされてもいずれ消え去る。「無常」の風の前には耐えられない。人間が作り出したものでなく自然界にあるものでも、一見無尽蔵に見えながらも枯渇する資源はいくらでもある。エネルギー問題は資源に依存する限りは資源を乗り換えるだけで根本的な解決にはならないだろう。しかし「法則」は別である。この世界を支配する法則は変わることはない。
仏教の法は人間によって発見され、表現されるものではあるが、人間が作り出したものではない。ここに永遠性がある。この世界と人間存在そのものの中にある変わらないあるものが、仏法として表されている。浄土教も当然その一部を担っている。親鸞聖人の「自然法爾」「法則」はこうした理解に基づく。経典や文書はそれを表現したものであり、我々の原点はその表現の基にあるものである。それが常に我々を動かしているのであり、「本願」「本願力」として表されているものである。「自ずから然り」も法だが、「自ずから然らしむ」と言われるように、浄土教の場合は特に法の働きに中心がある。継承の原動力は人間の努力ではなく、この「自ずから然らしむ」という人間に働きかけてくる力にある。
・縁と因
従って伝えるとは、過去から未来へという時間の中で古いものを守って伝えるリレーではなく、本当は常に新しいものを伝えることになる。変わらないが新しいものである。それが「無量寿」という永遠の命の本質である。炎が常に新しく燃えているように、伝統ではなく、伝灯である。浄土教は経典や人を縁とし、本願を因として伝わるのである。経典、寺院、教団を引き継いでも、それを成り立たせているあるものが伝わらなければ意味はない。昔は輝いていましたではなく、今輝いていなければ意味はない。宗教は文化財や文化遺産ではなく、今我々が生きていることそのものの中にある。「今、ここ、私」が仏法である。このことを忘れると、原理主義に走ったり、制度をいじくり回したりと、いらだちから結局は破壊的な方向にエネルギーを発散させることになりかねない。
3 親鸞聖人の場合
・『教行信証』「後序」
親鸞聖人の活動は、自分に働いているあるものを表し、伝え続けるものだった。教化、著述はみなその一環であり、そしてその活動は自分のこの世での生とともに終わるようなものではなかった。今回の講題は『教行信証』「後序」に引用された『安楽集』の言葉「前に生まれんものは後を導き、後に生まれんひとは前を訪へ、連続無窮にして、願はくは休止せざらしめんと欲す。無辺の生死海を尽くさんがためのゆゑなり。」から採らしていただいた。私の好きな言葉の一つである。親鸞聖人は自分がこの「無辺の生死海」を尽くそうとする「連続無窮」の働きの中にあることを自覚されていた。また同じく『教行信証』「後序」に引用される法然上人との出会いも、法然上人からの『選択集』の付属も、この「連続無窮」の中にある。無窮の本願の表れである。「無窮」は「無休」となり、「休止せざらしめん」となる。その由来を語る「悲喜の涙」は本願海の潮が溢れ出たものである。
ここに限らず私は親鸞聖人の著述にしばしば「涙」を感じる。自分を飲み込む本願海の潮が、口からは念仏として、目からは涙として溢れ出る。溢れ出る念仏は「非行非善」だが、涙も「非行非善」である。念仏の中に阿弥陀様はおられるが、ナミダの中にもアミダ様はおられる。むしろナミダの中のアミダ様の方が人間の「自然」をよく表しているかもしれない。人がナミダを流す限りアミダ様は消えることなく、浄土教が消えることはない。このことは後で、宮沢賢治と中村久子の項においてもう一度述べたい。
・『歎異抄』第二章
この「連続無窮」が人を介して歴史の上に展開しつつ、そのたび毎に直接「本願」から出ていることを表すものとして『歎異抄』の第二章を挙げたい。「弥陀の本願まことにおはしまさば、釈尊の説教虚言なるべからず。仏説まことにおはしまさば、善導の御釈虚言したまふべからず。善導の御釈まことならば、法然の仰せそらごとならんや。法然の仰せまことならば、親鸞が申すむね、またもってむなしかるべからず候か。」ここに浄土教が経典や人を縁とし、本願を因として伝わることがよく表されている。この中で直接の師弟関係があるのは法然と親鸞だけである。それ以前は普通に言う伝授ではない。またはじめにある阿弥陀仏と釈尊の関係も大乗非仏説を定説とする仏教学の常識からは否定される。
しかしこの伝授は間を飛ばして「弥陀の本願まことにおはしまさば、親鸞が申すむね、またもってむなしかるべからず候か。」でも成立する。誰であっても「本願力にあひぬれば むなしくすぐるひとぞなき」である。しかしはじめにその存在を知らせていただいたのは経典であり、師である。本願という根本の因があってもこの縁がなければ、地図無くして荒野をさ迷うようなもので、本願と出会うことは極めて難しい。ここに継承ということの重要さがある。比叡山で長く迷いの中にあった法然上人も親鸞聖人も、そのことを誰よりもよく分かっておられた。
この『歎異抄』の第二章の背景には親鸞聖人の長子である善鸞の言動が関東の人々を惑わした事件があると言われている。親鸞聖人から義絶された善鸞は後に祈祷師のようなことをしていたと言われている。ここに親子にしてすでに伝わらないという問題が起きているのである。本願寺の系統では親鸞聖人から孫の如信に伝わったとする。父と子で伝わって当然のはずなのだが、現実には伝わらないこともある。そこで親子、近親者の間で、伝わらなかった例と、困難を越えて伝わった例をあげて継承の問題を考える参考としたい。
4 宮沢賢治(1896〜1933)
・浄土教から法華経へ
宮沢賢治は私にとっては大きな課題である。多くの人がそうだと思うが、子供時代に宮沢賢治の伝記を読み、またその作品を読み、一種の聖者のような印象をもって育った。国語教師になってからはその作品を何度も授業で扱っている。文学者としてだけ考えればそれほど問題はないのだが、宗教者としての面を考えると私にとっては大きな問題がある。
彼は篤信の真宗(大谷派)信者の家に育ち、普通の人よりもかなり濃厚な真宗の宗教的環境の中で育ちながら、結局は浄土教から法華経の信者となり、そのことを全面に出して活動し、臨終に当たっては法華経の頒布を遺言し、宮沢家は日蓮宗に改宗してしまった。
賢治が転向した法華経は大乗仏教の一つの大きな流れである中国・日本の天台の正統の経典であり、親鸞聖人、法然上人も比叡山で修学されたものである。日蓮は題目を唱えてこれをより熱狂的に支持する日蓮宗を開き、その系統の団体は大きな力をもち、特に戦後は相当数の真宗からの転入者を吸収していると考えられる。永遠(久遠実成)の釈迦仏への帰依を中心とする天台・法華の系統、またその世界観を継承する教団は大きな力をもっているということを認めた上でこの問題を考えるべきだろう。
また宮沢賢治の場合は旧家における家と個人、父と長男の確執という問題が宗教の問題と絡んでいて、賢治の転向を宗教だけの問題として考えていいのか、家や父への反抗の結果として考えていいのか、あるいはその両方なのか、非常に難しいものがある。確かに家と個人、父と子の問題も含んでいる。それは親鸞聖人と長子の善鸞の間でも起こったかもしれないことである。さらにこの問題は観無量寿経の阿闍世父子の問題ともつながる。アジャセ・コンプレックス、エディプス・コンプレックスと言われる根深い父子確執の問題として決して特殊な出来事ではない。即ち賢治において起こった、浄土教と法華経、家と個人、父と子の問題のいずれも特殊な出来事ではなく、そこから学ぶべきことが多い。
まず宮沢賢治の場合は、家や父への反抗が、家の宗教、父の宗教からの離反を招いたという面がかなりあると思われる。それは束縛を嫌う青年期には誰でも起こりうることだが、宮沢家の場合、岩手県花巻という東北の農村地帯での質屋・古着屋として貧しい農民からの収奪によって家業が成り立っており、そのことに賢治が罪悪感を感じていたことは著作から明らかであろう。農学校教師を経ての、羅須地人協会での農民への献身的な活動は贖罪意識と菩薩道とが重なったものだろう。体を壊してまでの活動には多分に贖罪意識が働いていたと思われる。篤信の真宗信者の家であり、その財力で仏教講習会を開くほどの家のあり方が、農民の間に生きた親鸞聖人の同朋同行の教えと全く矛盾するのではないかという批判意識が高まったからだろう。
父が有志とともに主催していた仏教講習会では毎年、明烏敏、村上専精といった当時の第一級の真宗僧が講師を務めている。その教えが賢治の身にしみこんでいたことは容易に想像がつく。賢治の中学四年の時の父への手紙には「歎異鈔の第一頁を以て小生の全信仰と致し候」と述べているほどである。
家や父への反抗といいながら、この家の持つ罪業が自分の罪業意識として自覚される上で、家と父の宗教である真宗は確かに賢治の中に根をおろしていたはずである。家や父以上に彼の方が教えを忠実に受け取っているのである。賢治から見れば父の念仏は家業に対する免罪符のように見え、悪人正機の教えも都合のいい隠れ蓑に見えたのではなかろうか。それなら家や父を批判しながら、そこからより純粋な真宗信者が生まれる可能性があってもいいはずである。しかしそうはならなかった。彼は自分の苦しみと農民の苦しみを同時に解決する道を求めたのである。浄土教は現世変革の力にはならないように見えたのだろう。またこの岩手の地の浄土教に、表立って寺で説かれる正統派とされる真宗とは別に「隠し念仏」と言われる秘事法門の系統のものがあり、そのことも賢治が浄土教を離れる原因となったと言われる。しかしそれもやはり自分はそこで、その地での浄土教改革者として、純粋な真宗信仰に生きるという形で克服する道もあったはずである。しかし浄土教では満たされない何かを賢治は求めたのだろう。
この転換のきっかけを与えたのは意外にも本願寺派の僧であった島地大等の訳した法華経だった。島地大等は島地黙雷の養嗣子で盛岡市の北山願教寺第26世住職となった。賢治はその教えを受けることができた。賢治が法華経に帰依した時期については諸説あるが、盛岡中学を卒業したころから盛岡高等農林学校時代のどこか、二十歳前後になるだろう。法華経の「従地涌菩薩品」の地涌の菩薩や「如来寿量品」に説く久遠実成の釈迦仏が若い賢治の心を捕らえたことが想像できる。特に地面から涌きだしてくるという地涌の菩薩は農学校に学び農民の生活を何とかしたいと念願していた賢治にとってこれこそ自分の姿だと思えたに違いない。自分は地涌の菩薩だという高揚感が賢治を支えたことが想像できる。しかしそれは罪悪感の裏返しとも言うべき面があり、慎重になるべきだったのではないかと思う。賢治は活動的な菩薩像を自画像として選択したわけだが、それはまだ理想像というべきものであり、それと自分が一致していたとは言い難い。その精神的葛藤が「修羅」として表されている。理想像に追いつこうとして精神的葛藤を抱えたままの活動が始まる。ここが信心という安心を出発点とする真宗との違いとなる。すでに救われているという安心から生きるのが真宗である。宗教者とし見たとき彼がどこまでこの理想像と自分の距離を埋めることができたのかが、一つの評価になる。理想像である限りは常に距離がある。
農民の生活を何とかしたいという思いは関東で農民の暮らしを見た親鸞聖人の中にも常にあった思いではないかと思う。しかし宗教家として親鸞聖人はまことの救いを本願の念仏一つに定めてそれを伝えられたのである。念仏者は弥勒菩薩と等しいという如来等同の教えは、法華経の地涌の菩薩に匹敵するかそれ以上のものである。親鸞聖人は法華経の地涌の菩薩を念頭にそれを説いたのかもしれない。久遠実成の釈迦仏はそれと同等のものが久遠実成の阿弥陀仏として親鸞聖人においても説かれている。おそらく親鸞聖人の場合は法華経を越えて浄土教だったのである。賢治はそれが逆になってしまった。宗教家になるか農民とともに生きるか、ここが一つの分かれ目だったのだろう。
こうして活動的な菩薩像を自画像として賢治は生きることになるが、さらにそれが同じ法華経信仰に生きるとしてもかなり現世志向の強い国柱会への入会となった。当時の法華経信仰の最も活動的で戦闘的な地点に立つのだが、こうなると私はついていけないものを感じる。国柱会は国粋主義的主張でも知られる。賢治は昭和8年に37歳(満)で亡くなるが、戦争の時期まで生きていたら、かなり苦しむことになったのではないかと思われる。
宮沢賢治は父には強く改宗を迫ったが、著作上では浄土教をとりたてて批判しているわけではない。我々に対しては無言の論難というべきものがそこにある。それは今も続いていると考えるべきだろう。私は親鸞聖人は法華経を越えて浄土教に行き着いたと考えているので、親鸞聖人の中ではこの問題は解決済みの問題だったと思っている。救いなのか行動なのか、信者なのか行者なのか、ということに集約してもいいだろう。青年の心を捕らえやすいのは行動かもしれない。しかし自分を見つめる人間にとってはそれはそう簡単なことではない。内を見つめる人間であることが私は仏教の出発点であると思っている。まず内省がある。内省がなければしばしば政治へと走ることになる。実際賢治の活動は宗教ではなく政治的な労農運動の一環としてとらえることも可能だろう。宗教ならまず内省がある。そしてそこからどうするかは「面々の御はからひ」である。
・共通するもの
賢治が浄土教を離れたとして、おそらく彼の表面上の意識ではそうだったとして、本当に浄土教を捨てきってしまったのだろうか。私はそうとは限らないという思いがあるので、そのことに触れておこう。
賢治は確かに法華経信仰に生きた。それを信奉する日蓮宗は「折伏」という他宗の者に論難を挑んで屈服させるという戦闘的な布教方法で知られている。他の宗教を邪教扱いし、浄土教に対しては「念仏無間」という言葉で厳しく批判している。賢治は父を折伏しようとしそれが親子の激しい対立を生むが、すべての宗教に対してそれが通用すると思っていたのだろうか。できればそれをしたいという思いもあったかもしれないが、賢治は一方で科学者として、教育者として、文学者としても生きた人である。科学、教育、文学にあるような普遍性を宗教において求めたとしても不思議ではない。宗教にも真、善、美と同様の普遍性があるはずである。というかむしろ科学が発達するまでは宗教こそが普遍性の代表だった。それが逆転してしまったのだが、宗教もいずれは科学と同じような普遍性のもとに共通の認識に至ると考えていたと思う。
そのことを表すものとして一つは「四次元」の主張がある。これはアインシュタインの理論を取り込んだもので、宗教的世界を三次元のこの世界を越えた四次元の世界としてとらえている。これが賢治にとっての科学と宗教の接点となっている。賢治の代表作である『銀河鉄道の夜』は主人公のジョバンニが川に落ちた友人カンパネルラとともに、本当の幸いを求めてする一種の霊界旅行とでも言うべきものだが、そこでこの銀河鉄道のことを「幻想第四次の銀河鉄道」と呼んでいる。ジョバンニがこの列車に乗ることができたのはどこまでも行ける切符をもっていたからだが、これが賢治にとっては法華経であり、題目だったのだろう。しかしそれは浄土経典であり、念仏だったとしてもおかしいとは思えない。それぞれの人の信仰、宗教に合わせて読めるように書かれている。文中の記述としては仏教よりもむしろキリスト教の方が表に出ている。知らない人が読めば、クリスチャンが書いた作品と思うのではなかろうか。
また作品中に、「みんながめいめいじぶんの神さまがほんとうの神さまだというだろう。けれどもお互いほかの神さまを信ずる人たちのしたことでも涙がこぼれるだろう。」、「信仰も化学と同じようになる。」とも書いている。いずれは信仰も科学と同じように普遍的なものとあることを賢治は考えている。それはすでに親鸞聖人が「法則」としてとらえられていたことと同様である。それが証明されるまでは例えば素晴らしい行為には「涙」が出るということに普遍性を見ている。文学者でもあった賢治が「涙」に注目したことは卓見だと思う。もちろん涙にもいろいろあるが、素晴らしいもの、感動に涙が溢れるのは、そこに「自然」の働きを感じる。ナミダの中にアミダ様がおられると思うのである。これは「悲」を極めれば「大悲」となることの中にも表れている。この機微は元来は浄土教の中にあるものだろうと思う。
もう一つ別の作品を挙げよう。『なめとこ山の熊』という作品である。これは熊撃ちの猟師小十郎と熊たちのつながりを描いた作品である。小十郎は猟師だが決して好きで熊を撃っているわけではない。山も畑もない彼は本当は熊が好きなのだが、熊を撃って、その毛皮と熊の胆を売るしか生きる道がないのだ。熊たちも本当は彼が好きなのだ。その彼がとうとう熊によって倒される日がくる。熊はお前を殺すつもりはなかったと言う。そして最後の場面では山の小高いところに小十郎をおいて何頭もの熊がその前にひれ伏したまま動かないでいるのである。小十郎の顔は何か笑っているようにさえ見えるのだった。
この同じ世界に生きるあらゆる生き物への共感、生き物同士の共感がここにある。それは仏教の「悉有仏性」であり、『歎異抄』の「一切の有情はみなもって世々生々の父母兄弟なり」の精神である。また『改邪抄』の「某閉眼せば、賀茂河にいれて魚にあたふべし」も同様だろう。私はこの作品を読むと因幡の源左が熊の胆を仕入れて持ち歩き、僧に与えて、食べて供養してやってくれと言ったという話を思い出す。源左は生き物をかわいがり、牛にも話かけていたという。小十郎が源左に見えてくる。私にはこれは浄土教的作品に見える。大乗仏教の精神を極めていけば、本当は浄土教も法華経も同じものが流れているのだろう。またそれは他の宗教においても同様のはずである。
5 補足 植木徹誠(1895〜1978)
なお賢治とほぼ同じ時代に生まれた真宗(大谷派)僧侶に植木徹誠がいる。タレントの植木等の父君である。彼は東京に出でてクリスチャンになったが、労農運動にも関わり、郷里三重県の寺の息女との結婚を契機に郷里で真宗僧侶となった。徹誠に一貫しているのは人間平等の精神である。「等」の名もそこから採られたという。徹誠は住職であった地域の労農運動や解放運動に関わり反戦思想の持ち主として、戦争中は投獄されていた。植木等は父の投獄中はその代理を務めて檀家回りをしている。しかしやがて時局の変化とともに檀家は徹誠一家の追放を決め、一家は寺を追い出され、さらに困窮することになる。植木等は僧侶になるべく東京の真宗の寺で小僧をしながら東洋大学を卒業する。在学中の戦争中から続けていた音楽による慰問活動がそのまま卒業後の芸能活動となり、僧侶にはならなかった。寺を失った父も二度と住職になることはなかった。
徹誠は晩年に等に「俺は、あの世に行っても親鸞に合わせる顔がない。俺は恥ずかしい」と言ったという。その植木等も故人となった。これは継承された例なのか、されなかった例なのか。親鸞聖人を知る人ほど、「合わせる顔がない」と思うのだろう。
6 中村久子(1897〜1968)
・その生涯
中村久子も宮沢賢治、植木徹誠と同じ時代の生まれである。様々の点で宮沢賢治と対照的である。飛騨高山の貧しい畳職人の長女として生まれる。2歳の時に足のしもやけがもとで突発性脱疽になり、両手両足を失う。久子の家は真宗(大谷派)の家で、特に祖母は熱心な念仏者だった。しかし久子の病気をきっかけに父親が病気を治してもらおうと一族の反対を押し切り天理教に入信する。6歳の時に父を失う。母は久子を連れて再婚するが、再婚先での久子は二階の一部屋から出してもらえず、つらい生活を送る。母が製糸工場に出稼ぎに出ている間は久子を可愛がる祖母と暮らし、これが心の支えとなる。勉強は学校に行けなかったので、祖母から読み書きを習う。字は口にくわえた鉛筆や筆で書く。天理教の教会に長く預けられることがあるが、天理教には入信しなかった。
19歳の時に見せ物小屋に売られ、芸人となる。口で書いた習字や、口と短い手での裁縫などの芸を見せる。この見せ物小屋での生活は昭和17年まで26年間続く。この間に四度の結婚、死別二度、離婚一度、はじめの夫と二番目の夫、三番目の夫の間に各一人三人の娘をもうけるが、三女は幼くして亡くなる。四度目の結婚相手が中村敏雄で、久子を最期まで看取る。晩年の久子はこの敏雄と次女の富子の献身的な世話で、背中に背負われて請われるままに全国に慰問や講演に出かける。敏雄に背負われた久子の写真は実に幸せそうである。敏雄は多くの人から慕われ、久子の没後も敏雄は高山の朝市の顔として親しまれる。富子は敏雄からよくしてもらったと言う人に多く会ったという。久子は戦前に一度、戦後に二度ヘレン・ケラーと会見している。昭和43年、高山で71歳で亡くなる。
・宗教との関わり
何不自由なく育った賢治と、経済的にも身体的にも不自由だった久子とは全く対照的な生まれと育ちである。賢治は浄土教から法華経へと転向した。しかし久子は父親が天理教に入信しその教会に長く預けられながら、天理教に入ることはなかった。また昭和4年32歳の時クリスチャンでベッドに寝たきりの生活をしていた神戸女学院の座古愛子を知り、心の師とする。座古女史からは直接聖書の教えを受けるが、クリスチャンにはならなかった。中村久子には多くの宗教からの勧誘があったがどれもなじまなかったという。結局真宗に行き着くのだが、真宗が本当に彼女の心に届くには長い時間が必要だった。
昭和13年、ある婦人会で書家の福永鵞邦を知る。彼から大須賀秀道の『歎異鈔真髄』をもらう。この本を読んだことがきっかけとなり、念仏者としての生活が新たに始まる。幼い頃祖母の唱えていた念仏が久子の心についに届いたのだった。自伝『こころの手足』に言う。「長い間土の中にうずめられていた一粒の小さい種子がようやく地上にそうっとのぞいて出始めた思いがしました。そして幼い日に抱かれながら聞いた祖母のお念仏の声が心の裡に聞こえたのです。どれほど自分で考えてみたところで何ができよう、そうだ、お念仏させて頂きましょう。そして仏様にすべてはおまかせ申し上げよう。ようやく真実の道が細いながらも見出せた思いがいたしました。 〜一度心にともされた正法の灯は、かぼそくも消えなかったことは大きな幸いでした。」
それ以来仏書をあさり読み、足利浄円、梅原真隆、曽我量深、金子大栄などを読む。賢治も聞いた明烏敏の講習会も聞き、花山信勝にも教えを受ける。昭和三十三年『大乗』での甲斐和里子との対談は実にほほえましい。そこで甲斐和里子は中村久子に初めて会ったときのことを告白している。中村久子は「先生はお気の毒ですね、手があるから、ややもすると、お土産さげて行こうとする、私は幸いなるかな、手が無いから、いつでも、やァす、やァす、と手ぶらでお浄土に参りますヮ」と言ったという。「実際頭が下がりましたんです。このことはあなたには初めて告白するんじゃけれど」と中村久子に語っている。
このころの歌「手足なく六十年はすぎにけりお慈悲のみ手にともなはれつつ」中村久子は真宗を中心としながらも付き合いは宗派を越えたものがあった。臨済宗の山田無文老師とも親しく、「このバァサンご安心を得たな」と老師は羨ましくさえ思ったという。
昭和41年に転居した新居の玄関には因幡の源左の言葉「ようこそようこそ」の言葉を口で書いて掲げる。42年には心の師として慕った恩人、座古愛子の23回忌法要を神戸でつとめる。43年脳溢血により高山で亡くなる。
中村久子の『歎異抄』との出会いは彼女の心境がそれを受け入れるのを待っていたかのようである。その縁は祖母によって幼い心にしみ込んでいた念仏の声によってつながっていたのだが、時機が整って初めてわかったのだろう。次女の中村富子に久子は「歎異抄は本当に困ったとき、本当に悲しいとき読まなくては分かりません。表面だけ読んでも読み違えます」と言ったという。中村富子は25歳の時に親友に死なれ、仏壇の前で『歎異抄』を読んだときに号泣し、初めて母の言葉がわかったという。
こうして親は他の宗教に転向したものの、祖母から孫の久子へ、久子から娘の富子へと本願の念仏は伝えられたのである。中村久子の伝記は涙無くしては読めない。彼女ほど幼い時から泣き続けた人はいないかもしれない。幼い頃はその泣き声のために親は何度も転居したという。これでもかというくらい痛めつけられ泣き続けた人生だった。受難の連続だったが、ある時そのナミダの中にアミダ様が住み、泣いていたのは自分ではない、親様なのだということが分かったのだと思う。それが『歎異抄』との出会いであり、娘に語った「歎異抄は本当に困ったとき、本当に悲しいとき読まなくては分かりません。」ということである。人に悲しみがある限り大悲は決して消えることはない。人にナミダがある限りアミダ様が消えることはない。アミダ様がおられる限り人のナミダが涸れることはない。必ずナミダが本願海の潮であることに気付く時がくる。この打ち寄せる波は「連続無窮」である。
 「ヒロシマ・ナガサキ・真宗」 渡辺郁夫
「ヒロシマ・ナガサキ・真宗」 渡辺郁夫
2007.8.8昼席 善徳寺原爆逮夜法座1
1 私とナガサキ
・1枚の写真
明日8月9日は長崎の原爆忌なので、初めに私とナガサキの関わりから始めたい。後に述べるように小学校2年生のころ、心理的な被爆体験をし、自分にとっては原爆は他人事ではなくなった。「心の被爆者」になってしまった。その後、あることをきっかけに目に焼き付いて離れなくなった写真がある。それが「おにぎりを持つ母子」である。写真を見てから30年後に私はその写真と再会した。ある写真展での出来事だった。そこでその写真が、広島ではなく、長崎での被爆者の写真であり、しかもその少年の名が「郁二」であると知った。自分にとってはヒロシマとナガサキはそれぞれ大きな意味を持つが、長崎との関わりはおそらく普通の広島の人よりは大きかったかもしれない。
・永井隆
私の学校はかつて長崎への修学旅行を行っており、事前学習として、長崎についての学習を重視し、またそれに関連して、私は島根県出身の被爆医師である永井隆との関わりがあった。また長崎で被爆し、広島で修学旅行を手伝う会をしておられた江口保さんとも付き合いが始まり、学校で長崎での被爆体験を話していただいたりした。
永井隆から学ぶことは非常に大きく、「こころの回廊」連載の中で、私は津和野への巡礼の中で「最後の殉教者」として永井隆を取り上げた。「最後の殉教者」は遠藤周作の作品で、長崎から津和野へと流罪になった長崎のカトリック信者を描いたもので、それに先だった作品として同じ殉教を扱った永井隆の「乙女峠」がある。「乙女峠」は津和野で信者が収容された場所であり、現在そこにマリヤ聖堂が建っている。
私には永井隆自身が「最後の殉教者」に思える。彼は島根から長崎に行き、長崎医大に入ることで浦上のカトリックとの縁ができ、信者となった。専攻は放射線医学であり、まるでその時のために備えられていたかのようだった。ナガサキに落ちたのが原子爆弾であることを永井隆はいち早く知り、治療活動に当たった。実は彼は原爆での被爆の前にすでに研究してきた放射線の被曝により、白血病を患っており、二重の被曝者だった。原爆投下前から彼は放射線障害を知っていたのである。
永井隆は8月9日は大学で被曝し、その後も放射能障害により動けなくなるまで救護と治療を続ける。病床に伏してからは著作活動を続ける。元来永井隆はかつて長崎にいた斎藤茂吉のアララギ派の歌人だった。歌とともに文筆を続け、現在知られている作品はほとんどこの病床でのものである。被爆から6年後の1951年に亡くなる。43歳。彼の人生と原爆を考えると「備えと供え」であったように感じる。彼はそれを自らの役目として受け入れていたように思える。
永井隆が「最後の殉教者」であるなら、日本での最初のキリスト教の殉教者は長崎にその像がある「二十六聖人の殉教」である。私の学校ではかつてこの「二十六聖人の殉教」碑から長崎の研修を始めていた。この「二十六聖人の殉教」記念日が1597年2月5日なのだが、実は私の長男の誕生日がその2月5日である。このように私はこれまで「私、ナガサキ、カトリック」の間に何か不思議な縁があることを感じてきた。そしてこの関係が「私、ヒロシマ、真宗」の関係と二重写しになるのである。
2 私とヒロシマ・真宗
・我が家と原爆・戦争
*父方 父方(渡辺家)は沼田(広島市安佐南区)に実家がある。父は戦争中は満州にいた。敗戦により戦争後苦労して何とか日本に帰国した。父の兄(故人)は陸軍暁部隊(船舶部隊)で宇品におり、本土決戦に備えて、モーターボートに爆弾を積んで敵艦に体当たりする訓練を重ねていた。伯父は特攻隊員の生き残りだとよく言い、もう少し終戦が遅ければこの世にはいなかったと生前語っていた。昨年公開された佐々部清監督の「出口のない海」は回天の特攻を描いたものだが、私は感慨深いものがあった。特攻に関心をもったのはこの伯父の存在が大きいかもしれない。鹿児島の知覧に行ったのもそうであり、そこで私は特攻記念館の横にあるミュージアム知覧で薩摩の隠れ念仏の展示を見て、隠れ念仏にも関心を持つようになった。
父は満州で広島が全滅したと聞き、帰国をやめようかと思ったそうである。帰国して広島に着く前に家に連絡したところ、広島駅に親が迎えに来てくれて本当にうれしかったと語っていた。後に一緒に中国に行った時、父が満州時代のことを懐かしさとともに負い目としてももってきたのだということを知った。
*母方 母方(大平家)も沼田であるが、母方の方が原爆の影響ははるかに大きかった。その経緯が昨年亡くなった伯母の手記(別紙)に書かれており、これは私が母から聞き、祖母からも聞いてきた話である。原爆は広島市中心部だけではなく、生活圏をともにする周辺部にまで及んでいたことがよくわかる。私の母はこの手記に出てくる妹に当たるが、母は小学校で原爆に会い、爆風を体験し、その後家への帰途で黒い雨に打たれる。この雨が恐かったと言う。「黒い雨」は広島市西部にかなり降ったらしい。沼田は広島市中心部とは己斐の山を隔てただけであり、現在中心部に直結するトンネルができたため、車では十数分の距離になった。伯母が熱線を感じたり、黒い雨が降ったのがよくわかる。
祖母(大平マサノ)は夫を亡くし、子供2人を原爆で亡くし苦難の戦中戦後を歩んだ。父方も母方も沼田町伴の専念寺の門徒だったが、特に祖母は御法義に厚い人だった。妙好人というものを知ってから私は祖母がその人だと思うようになった。私は普段は祖母と離れて暮らしていたが、よく長期に渡って我が家に滞在し、仏壇で念仏する祖母の姿を見て育った。アポロの月面着陸を一緒に見たことが忘れられない。私が心理的な被爆体験をしてからは特にこの祖母が慕わしくよく可愛がってもらった。私が大学で仏教学を専攻したことを非常に喜んでくれた。帰省しては祖母と二人で話すことが多かった。最後に祖母は自分の聖教をもう覚えたからいらないと私にくれた。それが祖母の形見となった。
・私とヒロシマ・真宗
私は母から上記の話を聞いて育ったがそれ以上に大きな影響を受けたのが、原爆資料館だった。7歳の時に資料館を見学し、あまりの恐ろしさに衝撃を受けた。家に帰ってから泣き続け、夜が恐くて眠れなくなった。死ぬのが恐く、広島の地にいることが恐くてしかたなかった。この世界が根本的にひっくり返ってしまい、自分の楽しい少年時代はそこで終わってしまった。自分が熱心に仏壇にお参りするようになったのはこの時からである。
高校時代から仏教書を読み、大学では仏教青年会に入り「歎異抄」を読み、東洋哲学科で仏教学を専攻した。20歳の時に本願と出会い「本願力にあひぬればむなしくすぐるひとぞなき」ということを実感した。卒論では「末燈抄」を書き、修士論文では「一念多念」を書き、博士課程では「横超」について書いた。帰郷後は国語教師をしながら、三十代では仏教の枠を越えて宗教心を育てる「心の国語」を書き続けた。その後、大学時代に書き残した「歎異抄」について書き、四十代ではさらにその心をエッセイにした「発掘歎異抄」を書き続けている。まだ多くの章が残っているので今後も書き続けるつもりである。
映画「夕凪の街 桜の国」より 渡辺郁夫
2007.8.8夜席 善徳寺原爆逮夜法座2
1 第一部「夕凪の街」から
・母子の住むバラック街
この街は被爆後にいたるところに生まれたバラックで最後まで残った街だろう。立ち退き勧告の立て看とそれに反対する看板が建つ。皆実は最期にその看板の前で息を引き取る。平和公園の一帯もバラックが立ち退きに会い、その中には幾つもの寺院があったが公園となった。やむをえなかったとは言え、そのことをこの映画は見据えている。時代は代わっても結局自分達を追い詰める権力の非情さを感じさせる。しかしそこに住む人々は原爆により心と体に傷を負い、肩を寄せ合って暮らしていた。この作品はそこに美しさを見ている。街の犬にまで声をかける皆実に共感させられる。「ALWAYS 三丁目の夕日」と同じく昭和33年が舞台だが、同年生まれの私にはこの幻の街は被爆とともに決して忘れてはならない「ヒロシマのALWAYS」として写った。
・皆実の抱える罪悪感
このことは原作の方がより詳しく書かれている。助けを求める人々の声をよそに逃げたこと、家族を失いながら自分だけが生き残ったことの後ろめたさ。井上ひさし原作の映画「父と暮らせば」(宮沢リエ主演)でも父を失い、級友を失った主人公の罪悪感が恋愛を阻むものとなり、それを幽霊になった父が決着のついた問題として娘の幸せを願う。
「夕凪の街 桜の国」の原作ではさらにこの罪悪感を「自分達は誰かに死ねばいいと思われた人間であり、それ以来自分がそう思われても仕方のない人間になってしまったことに自分で時々気付いてしまうことだ」と表されている。人間のエゴイズムによって滅ぼされようとした人間がその事態の中で自分のどうしようもないエゴイズムを見せられてしまう。罪悪が罪悪を呼び覚ましたのであり、自分も同じとわかってしまうと大きい声で相手を非難できない。街には「原水爆禁止世界大会」の看板が立つが、大きい声で原爆反対を叫び、原爆投下国を非難できるのはあの日この街にいなかった人だけではないのか。いわゆる平和運動とは距離を置かざるをえない人間の根源的な罪悪にさいなまれる主人公の姿が見える。
このことは親鸞の人間理解(というより親鸞自身の自己認識)に通じるものであり、「歎異抄」の「さるべき業縁のもよほさば、いかなるふるまひもすべし」を思い起こさせる。
またこれはこの主人公だけでなく戦場にかり出された人、また戦災にあった人が等しく感じたことだろう。真宗の門信徒も僧侶も戦場に送られた。その人達はいったいどうやって戦場で過ごしたのだろうか。法然門下の熊谷直実は戦場で無常を感じ出家したというが、出家後は戦場には立っていない。念仏者が戦場に送られることほど残酷なことはない。
親鸞はこのような深刻な自己認識の上に立ち、その自分を救うのは、自分のためにたてられた「選択本願」しかないと知った。人の本願ではなく、私の本願だけなのである。自分と向き合い全てを受け入れてくれる一対一の深い愛しか救いがないことをこの作品も示している。それが皆実の告白を聞いた打越の「生きとってくれてありがとう」である。
2 第二部「桜の国」から
・二人の女性
第一部の主人公皆実と第二部の主人公の七波の関係が最後になって暗示される。私は原作を読まずに一度目を見たので、七波の父となる皆実の弟旭と皆実とも親しかった被爆者である京花との触れ合いを、回想シーンの中で七波が見ているのが不思議だった。それまでの場面で何度か不思議に思ったことが後で種明かしされていたので、何かあるのだろうと思っていたが、その二人を見つめているのが、生まれてくる前の七波であり、七波が二人を選んで生まれて来たのだと広島への旅の中で気付くという展開に驚かされた。かつて生まれる前の自分が二人を見つめていた場所に帰ることで自分もそれを思い出すという設定なのである。自己発見の物語なのである。
この二人を最もよく知り、その二人を父母として生まれようと思うのはそれまでの登場人物では原爆症で亡くなった皆実が候補として上がってくる。しかし原爆症で亡くなった人間が被爆二世として再び生まれてくるという選択を果たしてするだろうか。
ラストシーンで父の旭は皆実の恋人だった打越から渡された写真を七波に見せ、お前は姉に似たところがあると言う。七波はその写真を見て涙ぐむ。原作では姉に似ているということは言うが、この写真を見せられて涙ぐむ場面はない。涙ぐむ七波のクローズアップで作品は終わる。二人の女性の関係は暗示されたままで終わり、後は受け取る者の想像に任されているが、皆実が七波として再び生まれたという受け取り方は許されるだろう。他にはそれまでの登場人物からの候補としては皆実の妹だった翠くらいだ。しかし翠は旭は知っていても京花は知らない。
それ以外の全く別の人でも成り立たない訳ではないが、最も驚かされる展開としては七波は皆実だということだろう。そうすると二つの物語が一人の女性の物語としてぴったりと一つになる。おそらく映画化にあたってはこの二人を一人の女性で演じることが検討されたのではないかと思う。しかしそれでは予測がつき意外性に欠ける。自己発見という点に重点を置くなら二人で演じることになるだろう。
・念仏者のありようと重ねて
私は皆実が七波となるという受け取り方をしてしまったので、それが念仏者のありようと重なって見えた。親鸞の言う還相である。この女性は自分が原爆症で亡くなりながら再び被爆者を母に被爆二世になろうとする。それは念仏者となったことによって迫害を受けながらそれでも再び生まれてこようとする念仏者のありようと同じではないか。少なくとも親鸞は念仏者として生きたことによっての喜びは本願と出会った喜びだけと言ってもよく、この世的には何もいい思いをしたわけではない。今年は承元の法難から800年の年だが、それ以後も繰り返し念仏停止令が出た。それにも関わらず親鸞は還相を説いたのである。七波は選んだと言うがこうなるとそれは迷いと裏腹の選択ではなく迷いのない真実である「センチャク」と同じである。
・受け継ぐもの
この映画で非常に重要な役割を果たすいわゆる小道具に「髪留め」がある。旭が京花に皆実の形見の髪留めを渡す場面は最も感動的な場面だろう。私は念仏が止まらなかった。それは親鸞が伝授された本願の念仏と重なって見えたからである。この髪留めは原作にはない。佐々部監督の見事な発想である。七波はそれを母の京花の形見としてもっていたのだが、実はそれは自分の形見を再び自分で受け取っていたことに気付くことになる。この受け継がれていくものあることが本当の縁というものだろう。「一切の有情はみなもて世々生々の父母兄弟なり」と言うが、我々はこの縁を通して本願の念仏をリレーしていく。
「異国の丘」より 渡辺郁夫
2007.8.9朝席 善徳寺原爆逮夜法座3
1 私と満州
・父と満州
すでに述べたように私の父は戦争中満州にいた。満鉄の社員であるとともに、満鉄が創設した満鉄育成学校という旧制中学の生徒であった。子供時代から私は母親から聞く原爆の話と父の語る満州、満鉄の思い出と戦後の苦難の話を聞いて育った。敗戦後の混乱の中で父のいた大連にソ連軍が進駐してきた時の混乱と恐怖は大変なものだったらしい。今の高校生くらいの年齢で必死に生き延び、ソ連兵につかまり、殺されそうになったこと、またシベリア抑留になったかもしれないことなど聞かされた。広島は全滅したと聞き、帰国してもどうなるかわからない状態の中で引き揚げたのだと聞かされた。もし父がソ連兵に殺されていたら父と母の結婚も私が生まれることもなかったのだと感じていた。
我が家には満鉄関係の同窓会、OB会の方の出入りもよくあり、私もその雑誌を時々見ていた。しかしその関係者も次々に故人になり、定期的な同窓会の開催は難しくなっているそうである。私はそのせいもあり、満州関係のものには比較的関心がある。よく知られた愛新覚羅溥儀の「ラスト・エンペラー」や溥儀の弟に嫁いだ嵯峨浩の「流転の王妃の昭和史」などは強く印象に残っている。作詞家なかにし礼の自伝や「赤い月」も印象深い。 しかし父が満鉄の社員であったということは懐かしい思い出というだけでは済まないものがある。父は自ら望んで満州に渡ったという。少年が松岡洋右の演説に踊らされたのだと述懐したことがある。血気にはやったのだろう。父の意向を聞いた祖父は激怒し強く反対したそうである。しかしすでに親に隠れて受験した学校に合格した息子の希望をやむなく聞き入れ、心配してわざわざ広島から満州まで送って来てくれたそうである。こういう経緯があるので、父は帰国に当たっては親に合わす顔がないというのが実情だったろう。
・日中関係の中で
この時期の日中関係の中で満鉄は中国大陸における権益の中心とも言える存在であり、満州からの撤退を迫ったアメリカと結局は太平洋戦争に突入することになった。満鉄は中国侵略の一端を担っていたと言える。私はアジア・太平洋戦争というものが何だったのか、どうしても自分で納得したい気持ちがあり、「アジア太平洋戦争を考える視点」という100ページほどの論を研究紀要にまとめたことがある。自分が学校で平和教育をするのに、広島の被爆だけを言い、日本が海外で何をしたのかに目を背けるわけにいかなかったのである。私にとって被爆二世であるとともに旧満鉄社員の子という自分の生い立ちは両方ともに見つめなければならないものだった。
父がこの自分の過去をどう思っていたかを面と向かって聞いたことはない。松岡洋右に云々ということからも推察はついていたが、一緒に中国を旅行した時、初対面のガイドの女性に頭を下げて自分達は中国の人々に大変申し訳ないことをしたと私の前で謝罪した。ガイドの女性は若い方だったが、「政府と人民は別ですから」と答えた。この当時は反日感情が今ほど強くない時期だった。私はこの時初めて父の気持ちを聞くことができた。父は満鉄社員だったことだけではなく、戦後に満州で生き延びていく中でつらい出来事があったのだろう。支配国の人間が被支配国の人間にどう思われていたか痛感したはずである。当時、満州をはじめとする旧植民地にいた人々が戦後自分のことをどう思ったかはわからない。父のような思いをもって戦後を生きた人もいるだろうし、政府や軍部の責任にして自分には関係ないと思う人もいるだろう。しかし結局は人間の罪である。私にとって大事なのはこの人間の罪であり、本願に背く自分のありようだからである。そのことから逃れられる人はいないと思う。それを自分のこととして受け止められるかどうかである。私は人を責めるのは仏法ではないと思っている。人ではなく自分がどうなのかが問題なのだ。
2 ミュージカル「異国の丘」と「最後の法蔵菩薩」
・シベリア抑留
上記のように私と満州の関わりがあるが、私の教員の友人、知人には父親がシベリア抑留の体験者だったという人が二人いる。しかもいずれも母親は広島での被爆者である。広島で平和教育に携わってきた我々の世代にはそういう人が多かったのだろう。劇団四季の「異国の丘」はそのシベリア抑留を題材にした作品であり、広島では昨年2006年秋に上演された。シベリア抑留の体験者は無料ということが知らされていたが、実際に劇場ではその世代と思われる方々がおられた。
1945年8月9日、日ソ中立宣言を破棄したソ連は満州に侵攻した。シベリア抑留の発端である。本日8月9日は長崎の原爆記念日だが、シベリア抑留にもし記念日があるなら同じく8月9日だろう。精鋭と言われた関東軍はもろくも崩壊した。この侵攻はソ連・アメリカ・イギリスの密約であるヤルタ協定によるものである。ソ連軍の捕虜となり、シベリア抑留にあったのは57万から65万と言われ、約1割の6万人が死亡したと言われる。一説では抑留者107万、死者行方不明者37万とも言われる。これらの犠牲は戦後のことである。帰国事業は1947年から昭和31年1956年にかけて行われた。戦後は容易には終わらなかった。
・ミュージカル「異国の丘」
劇団四季のミュージカル「異国の丘」はこのシベリア抑留を題材としたもので、主人公は近衛秀隆。これは元首相近衛文麿の子息近衛文隆をモデルとし、実話に取材したフィクションである。原作は西木正明・著『夢顔さんによろしく』だが、これ自体に創作があり、さらに「異国の丘」は大幅に改変されている。あらすじは別紙に書いている。このミュージカルは日中和平工作にともに従事しながら、愛人を死なせてしまったことを前半に描き、後半はシベリア抑留された秀隆を中心に描くが、前後が交錯しながら物語が進んでいく。
特に後半の、彼女との愛と平和への願いを胸に、シベリアでソ連の協力者にしようとの企みを退けて同胞の帰国を優先させる秀隆の姿は、私にはこれも一つの願いに生きる念仏者の姿と重なって感じられる。本願の一つの表れに見える。自分は最後まで留まり、仲間を先に本国に帰そうとする姿は、自分が彼岸に渡ることより他者が渡ることを優先する大乗の菩薩道の精神でもある。本願と出会い救われた念仏者も同様であり、自分は願いを胸に最後までここに留まろうとする。私はそれを「最後の法蔵菩薩」と名付けたい。法蔵菩薩こそ最初の仏弟子であり、最後の仏弟子である。末通りたる大慈悲心の姿である。これを実現するのは一つの生では難しい。故に還相が必要になる。
私がこの「最後の法蔵菩薩」というものを念仏者のありようと考えるのは、一つは宮沢賢治の無言の論難への答えでもある。宮沢賢治は真宗の篤信者の家に生まれながら、日蓮宗、「法華経」の行者への道を歩んだ。文学では大乗の菩薩道を表現する作品を書いた。その活動は念仏者としてはできないことだったのだろうか。賢治の遺言により宮沢家は日蓮宗に改宗している。また宮沢家ならずとも現在も真宗から日蓮宗、あるいは天台法華の教えの流れの中にある宗教へと流出が続き、真宗の弱体化を招いていると思われる。
賢治が「法華経」の行者になった理由の一つには彼が「法華経」の「地涌の菩薩」に惹かれたことがあるのではないかと思う。自分も「地涌の菩薩」となろうとしたのだろうと思われるのである。この積極的に救済活動を続ける「地涌の菩薩」に当たるものが真宗にも必要だろう。それは親鸞においては弥勒等同という形ですでに念仏者は弥勒菩薩に等しいという形で提示されていると思うのだが、それで物足りなければ「最後の法蔵菩薩」という言い方もあっていいと思っている。先を争って浄土に行くのが念仏者の生き方ではなく、またこの世界は往生が決定した後の浄土へのただの待機場所ではないということだ。妙好人「因幡の源左」の言行、生き方にその例がある。「異国の丘」はそれを感じさせる。
「安心と安穏」 渡辺郁夫
2007.8.9昼席 善徳寺原爆逮夜法座4
1 安心について
・原爆慰霊碑の碑文
原爆慰霊碑の碑文は「安らかに眠って下さい 過ちは繰り返しませぬから」と刻まれている。これは自身も被爆者で広島大学教授だった英文学者の、故・雑賀忠義教授が当時の浜井信三広島市長の「祈りと誓いの言葉を刻みたい」という意向を受けて考案したと言われる。1952年8月6日に除幕したが、早くもその年の11月に東京裁判で日本無罪を主張した「パル判決書」で知られるインドの国際法学者パル博士が広島を訪れ、この碑文の後半の主語を日本人として受け取り、日本だけの過ちではないと批判した。これは「パル判決書」にも通じる博士の考え方が碑文解釈にも影響を及ぼしたものだと考えられる。雑賀教授は主語は「We」であり、全人類であると反論している。こうして碑の除幕直後からこの碑文は、いわゆる「碑文論争」として、ともすれば日本擁護の立場からこの碑文を自虐的とする意見をもつ人々からの攻撃を受けてきた。その意味では受難の碑文である。
私はかつて「アジア・太平洋戦争を考える視点」を書いた時、「パル判決書」を読み、ネール首相の意向も受けたと思われるこの書の意図は理解しているつもりである。ただこの碑文論争の後半の主語の部分については起草者の雑賀教授の言われる通りだと思う。
・信心と安心
私にとっての問題はそこより、むしろ前半の「安らかに眠って下さい」という表現にある。これは被爆者の冥福を祈るという趣旨なのだと思うが、私の宗教的立場からはいつもしっくりこないものを感じている。特に私にとっては「安らか」と「眠る」というのがつながらないのである。安眠という言葉があるのだから何ら問題ないと感じる人もいるだろう。それは死者は沈黙していると考える人の考え方だろう。それは一歩間違えれば唯物的な考え方と同じになってしまう。
しかし原爆で無くなった人、特にそれを念仏者として考えた場合、それが往生した人なら「安らか」は当然だが、「眠る」ということはありえない。生前「安心」という如来廻向の信心を得ていた人は浄土の平安の中で「安らか」に「目覚め」ているのであり、そしてまたその「安らかな目覚めの心」を我らに送り、我らを導き続けるはずである。それが浄土にあっての還相廻向である。私はこの如来廻向の「安心」こそが「安穏」という平和をもたらすのだと思っているので、この碑文は方向が逆に見えるのである。
この碑文は前半と後半が倒置されているので元に戻すと「過ちは繰り返しませぬから 安らかに眠って下さい」となる。つまりこの世の人間が平和を実現することであの世の人が安らかになるという考え方がここにある。それはいわゆる普通の仏教で言う、この世の人があの世の人のためにする追善供養の「回向」と同様の考え方になる。即ちこの世からあの世へという自力の回向である。
しかし我々はそうは考えない。逆に如来の涅槃という絶対の安らぎの徳が我々に廻向されて我々の信心という安心になり、それが肉体を失い肉体の煩悩を去った後は往生しての涅槃となり、さらにまたそれがこの世界に廻向される。あるいは再びこの世界に戻って来る。こちらは仮の世界であり、本当の中心は如来、浄土、彼岸の側にあるのでる。
従って本当の主語は前半部での往生した被爆者になければならない。それが後半の我々を廻向によって導くのである。自力回向の碑文ではなく、往生し成仏した覚者からの廻向の碑文こそが念仏者、安芸門徒にとっての真の碑文ではないだろうか。私の場合は例えば「安らかに目覚めていて下さい 過ちを繰り返しませぬよう」となる。それでは何のことかわからないと言う人もいるだろうが、その意味を受け取る人こそが真の平和の担い手であると思う。
2 安穏について
・二種類の平和
このように考えることは平和に二種類あると考えることである。即ち浄土でのすでに実現している完全なる平和と、この世界での成就しつつある平和である。すでに実現している平和を知らない人がこの世界に平和をもたらすことはできないはずである。それ故に「大無量寿経」に「兵戈無用」が説かれるのである。仏法が広まれば自ずと人々の心が安らかになり、兵も武器もいらなくなるのである。
「兵戈無用」自体を目的とする平和論もあるかもしれない。しかしそれでは「無用」となるのではなく無くそうとすることになる。その努力は新たな争いを生むもとになる。そう考える人はこの世界での平和しか見えない人だろうと思う。結局平和は力によってしか実現できないことになる。この過ちを我々は繰り返してきたのではないだろうか。「過ちを繰り返さない」ためには、すでに実現している平和を知ることが最も肝要なのである。
・「世のなか安穏なれ」
「世のなか安穏なれ」は2011年親鸞聖人750回大遠忌の本願寺派のテーマだが、私はすでに述べたように、これを「安心」による「安穏」の実現であると思っている。「世のなか安穏なれ、仏法ひろまれ」という親鸞聖人の言葉からもそれは明らかだろう。この安穏はこの世界での平和であるが、それは浄土の平安をこの世にもたらすことによって可能となる。それを僧団、教団の中だけのことにするのではなく世の中全体のことにするのは我々一人一人の信心のありようによる。この大遠忌を我々の信心を見つめ直し、その徳を世に伝える契機としたい。
・仏教、浄土教と他の宗教
ここで仏法が広まれば、それでその世の中が平和になるのはいいとして、では仏教以外の宗教との関係はどのように考えればいいのかという問題が出てくる。それは世界の中ではいわゆる宗教戦争とか、一つの宗教の中でも宗派間対立という問題が起こっているからである。このような事態を見て、人によっては宗教こそが平和の障害になっていると考える人もいるだろう。そういう人は文明が進歩すれば宗教はいずれ消えてなくなるはずだと考えているだろう。宗教を頑迷な迷信と同じように考えているわけである。
しかし本当にそうだろうか。宗教が平和の障害になるように見えるのは、人間の自我を宗教の教義による信念がより強固にするからである。それは自分の抱く信念であって「如来より賜る信心」という無我の信ではない。この信心と信念の違いがわかっていないのが大きな問題であると思う。無我を説くのが主として仏教だからやむをえないのかもしれないが、このことをいわゆる信仰を説くすべての宗教の人々に理解してほしい。
また浄土教の本願は存在の根本願としてあらゆるものに及ぼされるものであり、そこから漏れるものは何一つとしてない。全てが本願の中で生きている。一対一の一人一人のための本願であり、世界に60億の人がいれば60億の本願がある。しかしてそれは一つの本願なのである。60億の宗教があってしかも実は一つである。様々な宗教があるように見えるのは個別の相から見た場合の見え方である。
これは教義というよりむしろ一つの表現である。芸術が様々な作品を通して美というものを表現しているように、宗教もある根源的なものの現れ方を様々に表現したものだと考えてもよい。芸術的宗教観である。多様性と一元性は宗教の二つの顔である。多即一、一即多という相即である。浄土とはその両面性をもつ世界である。それは阿弥陀仏の浄土に無数の聖衆がいるように、一つの浄土の中でも言えることだが、また他の無数の仏国土があるように他の仏土との関係でも言えることである。他の仏土が他の宗教に当たる。
また別の考え方として宗教学にあるような、理知的、学問的に宗教現象に共通点を見出していくことで相互理解を深めることも大事なことだと思う。宗教の構造化といってもよい。建築に例えれば建物は違っても共通の構造、力学をもっているということだ。私は宗教で重要な要素として救済原理、覚醒原理、創造原理ということを挙げているが、これはこうした考え方に基づく。浄土教は救済原理を中心としているが、救済原理を中心とする宗教は共通の要素をもっている。如来(無限者、超越者、絶対者、神、仏)の本願(超越的意志、御心、恩寵、慈悲、愛)、信(信心、信仰)、行(行為、奉仕、報恩、冥想)。念仏という称名行も御名を呼ぶ、唱えるという形で他の宗教にも類似したものがある。本願信受の念仏が「自然法爾」であるのはそれが世界と人間の共通の本性に基づくからだ。放送に例えれば、放送局(如来)から電波(本願)が発信され(廻向)、ラジオ(衆生)が受信し(信心)、音が出る(称名念仏)。ラジオが勝手に音を出している(自力)のではない。ここにあるのは「法則」である。
このように宗教理解を進めていく時代だと思う。そのように理解した上で各自が自分にふさわしい道を歩めばよい。すべてが調和する華厳の「事々無礙」の世界である。

唯説弥陀本願海―法難・論難を越えて
2007.6.13 広島別院・総講習会にて 渡辺郁夫
はじめに
今年2007年は、1207年の承元(建永)の法難から800年の年に当たる。これを機にほぼ600年おきに起こったこれまでの法難と論難を振り返り、それによって決して衰えることのない本願の働きを明らかにし、浄土の新たなる千年紀への一歩としたい。
まず承元の法難に先立つものとして聖徳太子の時代に仏教伝来とともに起こった法難である破仏をとりあげる。両者を結ぶ存在として聖徳太子があり、これによって承元の法難が浄土門という新たなる仏教興隆のうねりの中で起きたものであることを示したい。
またこの法難に伴って提起された明恵の論難をとりあげる。そこで提起された問題が再び形を変えて宗門内で起こり、三業惑乱へとつながったと思われるので、この問題について考え、今後の浄土教を考える参考としたい。
[仏教伝来・破仏](法難)←(法難)[浄土門興隆](論難)→(論難)[三業惑乱]
1 物部守屋の破仏
・『皇太子聖徳奉讃』、『聖徳太子奉讃』和讃等により、親鸞聖人は自分の身に起こった法難と、聖徳太子時代の法難とを重ねて受け取っておられたと思われる。1201年(建仁元年辛酉)に聖徳太子の示現を得て法然上人に帰した親鸞聖人にとっては、600年前、聖徳太子時代の仏法興隆の一度目のうねりの中で起きた法難が、今また形を変えて、自分達の身に起こっていると感じられたはずである。これは浄土門興隆という仏法興隆の第二のうねりがきていることであり、初めの法難を乗り越えた太子の導きによってこの法難を乗り越え、新たなる仏法を興隆していくのだという確信があったはずである。太子が自分を導く意味がそこにあることを受け取っておられたはず。
・『日本書記』に欽明天皇13年(552年)に仏教公伝の記事。なお一般には仏教公伝は『上宮聖徳法王帝説』、『元興寺縁起』による538年戊午とされる。戊午の年は革命説による「革運」の年。また『上宮聖徳法王帝説』では破仏の年は570年とされる。
552年は釈迦入滅を紀元前949年(周の穆王五十三年)とし、正法500年・像法1000年で計1500年とすればこの年から末法。日本では、普通は正法・像法2000年とし、500年後の1052年(永承7年)を末法元年とする。『上宮太子御記』(正嘉元年1157年親鸞聖人)の末尾に、仏法公伝の年を「入像法五百歳也」。
また552年は『大無量寿経』が康僧鎧により訳出されたという252年から300年後になる。252年は先の計算では仏滅後1200年になる。252年の康僧鎧訳は疑わしいと言われている。これらの年代にはある歴史観が働いているのかもしれない。
また『教行信証』に仏滅算定年代としてあげられている1224年(元仁元年)は立教開宗の年とされ、この年親鸞聖人は52歳だった。教と時と機(人)との不思議な縁を感じさせられるものがある。
『日本書記』の記事。百済の聖明王「仏の『我が法は東流せむ』(『大般若経』による)と記(のたま)へるを果たすなり」「〜天皇、聞こしめし已りて、歓喜踊躍したまひて(『最勝王経』による)〜」この記事の「仏法東流」と、それを聞いて「聞即信」を思わせる天皇の言葉は出典は異なるが浄土教の精神に通じるものがある。
しかし物部尾輿と中臣鎌子が反対。蘇我稲目が個人的に仏像を祀る。まもなく疫病がはやり、物部尾輿と中臣鎌子の申し出で仏像は難波に流され、寺は焼かれる。仏教伝来とともに第一次の法難。
・574年(敏達天皇3年)聖徳太子誕生(〜622年49歳)
・584年(敏達天皇13年)蘇我馬子が仏像を祀る。還俗していた高麗の法師・恵便を師とする。司馬達等の娘・島が出家し、善信尼となる。日本初の出家者。この名は聖徳太子が親鸞にお告げで与えた「善信」と同じ。他に善信尼の弟子二人、禅蔵尼と恵善尼。(恵善尼の「恵」と善信尼の「信」をとれば恵信尼となる。)
・585年 物部守屋と中臣勝海が疫病の流行を理由に仏法停止を奏上。守屋が寺を焼き、焼け残った仏像を難波に捨てる。三人の尼は法衣を奪われ鞭打たれる。第二次の法難。
「やけのこりし仏像は 難波のほりえにすていれき 三人の尼をばせめうちて おいいださしむときこえたり」(『聖徳太子奉讃』)
「如来の遺教を疑謗し 方便破壊せむものは 弓削の守屋とおもふべし したしみちかづくことなかれ」(『皇太子聖徳奉讃』)
この「方便破壊」に、守屋を非難しつつも、本当に仏法を破壊することはできないということとともに、それを縁に結果的に仏法興起につながったということが読み取れるように思う。すなわち、『観無量寿経』の「王舎城の悲劇」を「浄邦縁熟して、調達、闍世をして逆害を興ぜしむ」(『教行信証・序』)として浄土教が興る機縁としてとらえる見方と同様の見方がうかがえる。これは親鸞聖人の法難に対する見方に共通のもの。『教行信証』は「序」に「王舎城の悲劇」(受難)を語り、「後序」に「承元の法難」を語る。釈尊在世中の「王舎城の悲劇」、守屋の破仏、承元の法難はいずれも浄土教が興る機縁として一貫したものとしてとらえられているように見える。
「正・像・末」という衰退の三時説の一方で、三時共通でしかも拡大し展開していく本願の歴史観(「浄土史観」「本願史観」)がある。それは逆縁を順縁に「転」じていく本願の働きよる。また聖者が点と線によって結ばれて高さを維持していこうとする「高さ」の宗教である「竪超」の聖道門に対して、面として広がっていく「広がり」の宗教である「横超」の浄土門のあり方による。これも本願の働き。
その後、蘇我馬子だけが個人的に崇仏を許され、三人の尼は馬子に返される。
・587年 蘇我馬子が物部守屋を討つ。聖徳太子(14歳)も他の皇子とともに馬子方として参戦。形勢が不利となる時、ヌリデの木で四天王像を刻み、寺を建てることを誓って戦勝を祈願し、勝利する。四天王寺の起こり(造営は太子が推古天皇の摂政となった593年から。)翌588年 蘇我馬子は「本願の依(まにま)に」法興寺を建てる。善信尼等は志願して百済に留学。590年に帰国し桜井寺に住む。
・601年(辛酉)聖徳太子は斑鳩宮を建てる。斑鳩寺(後の法隆寺)を併設。『聖徳太子奉讃』の末尾に引用文で「神武天皇始即位元年辛酉歳、釈迦滅後数二百五十年成」とあり、日本の歴史と仏教史を重ねる見方が読み取れ、親鸞聖人も同様の見方をされていたと思われる。それはまたその歴史の中に身を置く自分の位置づけと重なっていたと思われる。
2 承元(建永)の法難
・1175年(安元元年)法然、専修念仏に帰す(43歳)。比叡山を出る。西山広谷を経て、東山大谷に住す。
・1186年(文治2年)大原談義。
・1190年(文治6年)東大寺で浄土三部経を講じる。
・1198年(建久9年)『選択本願念仏集』撰述。
・1201年(建仁元年)親鸞聖人、聖徳太子の示現を受け、法然上人に入門。
「建仁辛酉の暦、雑行を捨てて本願に帰す」(『教行信証』)
・1204年(元久元年)延暦寺の衆徒、専修念仏停止を座主真性に訴える。
法然上人「七箇条制誡」を示し門弟を戒める。親鸞聖人も「綽空」として署名。
・1205年(元久二年)4月親鸞聖人『選択本願念仏集』を授かる。「綽空」から「善信」に改名。10月「興福寺奏状」(解脱房貞慶・起筆)九箇条の失をあげ、念仏停止を院に訴える。「興福寺奏状」は内容的には念仏停止を求めたことを除けば、「論難」と言うべきものがあり、教理的裏付けを持ち、法然の教えが聖道門的立場から見て不当であることを示している。後のより緻密な明恵の論難につながるものがある。
第六「浄土に暗き失」、第七「念仏を誤る失」は法然浄土教がそれまでの浄土教と異なる点、法然浄土教の特徴をとらえていると言えるだろう。特に第七「念仏を誤る失」は法然の「口称」の念仏を念仏の中で観念等の念仏に比べて最下のものと批判。この批判は当然予想されるものだが、『一枚起請文』にあるように、最下を自認する法然上人にとってはこれこそ本願の行。上から脱けていくのが聖道門、下から横に抜かれていくのが浄土門。最下の自覚がなければ理解できないものがある。
・1206年(建永元年)3月朝廷は遵西、行空を配流。行空は破門される。暮れに住蓮、安楽の事件。後鳥羽上皇(1180〜1239)の熊野臨幸の留守に院の女房が住蓮、安楽の勤めた鹿ヶ谷の別時念仏に加わり、発心して尼になる者(松虫、鈴虫)が出て、院の逆鱗に触れる。翌年2月住蓮、安楽は死罪。
・1207年(建永2年10月改元承元元年)2月法然上人は四国(土佐から讃岐に変更)に、親鸞聖人は越後に流罪。住蓮、安楽を含む死罪四人、流罪八人(『歎異抄』)。「主上臣下、法に背き義に違し、忿りを成し怨みを結ぶ。これによりて真宗興隆の太祖源空法師ならびに門徒数輩、罪科を考へず、猥りがはしく死罪に坐す。あるいは僧儀を改めて姓名を賜うて遠流に処す。予はその一つなり。しかればすでに僧にあらず俗にあらず。このゆゑに禿の字をもって姓とす」(『教行信証・後序』)。法然上人は12月に赦免。
・1211年(建暦元年)法然上人帰洛を許される。親鸞聖人赦免。
・1212年(建暦2年)法然上人入寂。明恵『摧邪輪』を著す。
・1214年(建保2年)親鸞聖人、関東に移住。
・1221年(承久3年)後鳥羽上皇、承久の乱。この時動揺した鎌倉方をまとめた尼将軍・北条政子は法然上人に帰依していた。後鳥羽院は敗れて隠岐に配流。土御門院は土佐、順徳院は佐渡流罪。『百人一首』の最後は後鳥羽院、順徳院二人の歌。九十九首目後鳥羽院、百首目順徳院。一つの時代の終わり。
・聖覚は後鳥羽院と関係があり、敗れた後鳥羽院のために書いたのが『唯信抄』ではないか(千葉乗隆)。親鸞聖人は『唯信抄文意』を書いて門弟に勧める。
・また後鳥羽院が隠岐で晩年に書いた『無常講式』は浄土信仰の書。「およそはかなきものは、人の始中終、まぼろしのごとくなるは一期のすぐるほどなり。三界無常なり、いにしへより、いまだ万歳の人身あることをきかず、一生すぎやすし。いまにありてたれか百年の形体をたもつべきや、われやさき、人やさき、けふともしらず、あすともしらず、をくれさきだつひとは、もとのしづく、すゑのつゆよりもしげしといへり。」本願寺三世覚如の子・存覚上人の『存覚法語』に引用され、さらに本願寺八世・蓮如上人の『白骨の御文章』に引用されて今日まで広まる。
・後鳥羽院は結果的には、阿闍世と同様に「逆謗摂取」の例を自ら演じたと言える。逆縁を順縁に「転」じていく本願の働きを証したことになり、『教行信証』の「序」と「後序」は対応する。
・親鸞聖人はなぜ関東に向かわれたのか。恵信尼の実家三善氏との関係や、念仏聖、善光寺の勧進聖として関東に向かったなど、諸説ある。それに加えて思うに、東の端に向かわれたのではないか。西方浄土から最も遠いところに本願を伝えることが、本願にかなうことであり、自分をそうさせるものがあることを感じられたのではないか。端へ端へ、末へ末へと向かう本願の働きが今自分に臨んでいるという実感。本願と向き合い救われた後は、さらに進んでいく本願の後ろ姿を感じられ、それに随われたのだろう。またそれは浄土教のみならず、日本への仏法伝来の時の『我が法は東流せむ』という釈尊の言葉にかなうことでもある。弥陀・釈迦、二尊の発遣。こうして仏法が西天・印度からはるか東の端の「粟散片州」日本に伝わり、さらにその東の端である東国・常陸に自分が行くことで、世の隅々まで仏法、本願が伝わることになり、伝道を全うすることができる。また日本国内でも法然上人は四国へ、さらに鎮西に聖光聖人(善導寺)があり、自分が東の端を担うことで浄土門のネットワークが完成する。
浄土教がもつ東西軸は、地球が丸くて自転し、さらに太陽の周りを公転しているということが自明の現代では、特定の方向を指すものでないことは明らかである。浄土の本質はどこにあるかということよりも、それが何であるかということの方にあり、他界、生の根源の世界としての浄土はどこにあってもかまわないものである。「尽十方」ということから言えば世界の中心である。しかし人間の深層心理の中では依然として東西軸は太陽の運行と結びついた「生と死」の軸のイメージとして生き続けており、それが人生という「道」のイメージと重なっていると思う。また「東西」は南北や上下に比べて「横」を意識しやすい軸である。さらに「十万億土」も人間が自分で埋めることができない果てしない隔たりとして意味がある。「横超」の思想はそれらと結びついており、本願力によって、品位階次を言わず、「横」さまに果てしない隔たりを「超」える宗教である。よってこれらの意味は大きい。浄土教は具体相によって救う宗教であり、イメージから入って真実に至るという面がある。そのため下手に抽象化して具体相を捨ててしまうと、同時に肝心の救いを捨ててしまうことになる可能性があることに注意すべきである。
・60(〜63)歳頃の帰洛はなぜか。『教行信証』を完成させるためというのは確かに大きい理由だろう。さらにその意味は、東の端に行くことでの空間的な末端への伝道に加え、時間的な末端、すなわち後世への伝道を書物として遺して行うためだったのではないか。『大無量寿経』の「特留此経」(『教行信証・化身土巻』)の精神と同じ。それが時空を越えて働き続ける本願を、末広がりの宗教としての本願の浄土教を彰すことになる。「還相廻向」もその時間的な意味でも末広がりの宗教としての浄土教を表している。すでに述べたように、いかなる逆縁、法難があろうとこの働きは決して止めることはできず、むしろ広がるのに拍車をかけるだけである。こうした思いから『教行信証・後序』に承元の法難が語られる。
また関東と離れたことにより消息等の文書による伝道が中心となり、結果的に『教行信証』以外の著書も増えた。それにより後の蓮如上人の『御文章』(『御文』)による遠方への文書伝道のさきがけとなる。
3 明恵の論難
・1212年(建暦2年)法然上人入寂後に『摧邪輪』を著す。法然上人在世中には『選択本願念仏集』は門外不出で、数人の門弟に筆写が許される。入寂後に刊行。
・「高弁、年来、聖人において、深く仰信を懐けり。聞こゆるところの種種の邪見は、在家の男女等、上人の高名を仮りて、妄説するところなりとおもひき。未だ一言を出しても、上人を誹謗せず。たとひ他人の談説を聞くと雖も、未だ必ずしもこれを信用せず。しかるに、近日この選択集を披閲するに、悲嘆甚だ深し。」
「二の難を出して、かの書を破す。」「一は、菩提心を撥去する過失。二は、聖道門を以て群賊に譬ふる過失。」(『摧邪輪』)
・明恵の聖道門の立場から見れば「菩提心」がないのは仏教ではない。法然上人は口称念仏だけで往生できるとし、菩提心等を諸行とし、廃捨したが、法然浄土教はそれまでの浄土教の立場からも否定されるべきもの。聖道門でも浄土門でもない邪説である。長年法然を高僧として「仰信」していた明恵は裏切られたという気持ちがあったのだろう。落胆と義憤が感じられる。
・明恵の論難は聖道的立場に立てば当然であり、また伝統的浄土教の立場からも疑問をもつのはもっともだろう。親鸞聖人の法然上人への帰依が遅かったのも、伝え聞く法然浄土教に疑問を感じていた可能性があり、聖徳太子の示現があって初めて帰依することができた。そのことを「本願に帰す」と述べられたのであり、法然浄土教を支えていたのが「本願」の感得・信受であり、また自分もそれを受け継ぐのだという自覚があった。従って「本願」の立場、如来廻向の立場からしかこの論難には答えられない。それによって聖道門の立場と浄土門の立場が鮮明になる。こうして「二双四重の教判」が生まれる。親鸞聖人の「横超」に対して、「竪超」は特に明恵を意識したものであろう。
・明恵と親鸞聖人はともに1173年(承安3年)に生まれた。この二人は仏教のもつ、智慧を中心とする「覚醒原理」と、慈悲を中心とする「救済原理」の二つの面をよく表している。親鸞聖人も二人の間にある対応関係を感じておられたのだろう。明恵の考え方の中には親鸞聖人とかなり近いものがある。明恵は十八願文について「至心信楽の文、必ずしも菩提心にあらずと言ふと雖も、もし口称の外に内心を取らば、内心を以て正因とすべし。口称は即ち是れ助業なり。」と言う。また明恵は「欲生心」を取り上げない。後に「三業惑乱」の三業派は「欲生心」を別して取り上げたが、「欲生心」を取り上げない明恵はよく浄土教を理解していたと言える。これは信楽中心の信心正因という親鸞聖人の立場に近い。口称より至心信楽という内心が正因となるのは、明恵に「形より心」という考え方があるからである。これは親鸞聖人も同様である。法然上人が十八願を「念仏往生の願」とし、親鸞聖人が「至心信楽の願」とされたことを考えると、明恵が十八願の中心は「十念」の口称の念仏より「至心信楽」にあるとしたのは明恵の卓見であり、親鸞聖人はこれと同様の立場である。ただし親鸞聖人はそれを如来より賜るものとし、ここが明恵と異なる点である。明恵の菩提心と親鸞聖人の信心とはよく対応し、自力と他力の違い、聖道門と浄土門の違いがわかる。明恵が菩提心を中心としながらも信心もある程度理解できたのは、釈尊崇拝の念が極めて厚く、その心情が親鸞聖人の阿弥陀仏崇拝の念と共通するものがあったからだろう。親鸞聖人は明恵を批判していないがその理由がよくわかる。
また聖道門は主として根本存在の寂静相を表し、浄土門は主として活動相を表すとも言える。浄土門が具体相を好むのはそのためである。如来の人格的表現、浄土、名号、往生、廻向等によってその救いが具体的に表される。親鸞聖人の「浄土真実」である。こうして無相を好む聖道門からは浄土門の具体相が無相に達する前段階に見え、また具体相を好む浄土門からは聖道門の無相は具体相が表れる前段階に見え、相互の誤解を生みやすい。
・『教行信証・信巻』「菩提心釈」「しかるに菩提心について二種あり。一つは竪、二つは横なり。」「横超とは、これすなはち願力廻向の信楽、これを願作仏心といふ。願作仏心すなはちこれ横の大菩提心なり。これを横超の金剛心と名づくるなり。横竪の菩提心、その言一つにしてその心異なりといへども、入真を正要とす、真心を根本とす、邪雑を錯とす、疑情を失とするなり。」「『論の註』にいはく、〜この無上菩提心は、すなはちこれ願作仏心なり。願作仏心はすなはちこれ度衆生心なり。」
このように「竪超」の菩提心を認めつつ、「横超」の菩提心を説く。両者は異なる立場だが、当然成仏という点では一致する。両者の違いをよりいっそう明らかにするに当たり、「願作仏心」を衆生の心に先立つ如来の願心、本願として受け取ると、「願作仏心」はまず如来が我々を成仏させようとする「仏に作さんと願ふ心」となる。それは如来が我々を救おうとする「度衆生心」であるとともに、我々を成仏させることで如来と一体となって衆生済度に参加させ、より多くの衆生を救おうと願う「度衆生心」である。先に如来の「仏に作さんと願ふ心」である「願作仏心」があり、それが廻向されて衆生の「仏に作らんと願ふ心」である「願作仏心」となって表れる。「願力廻向の信楽、これを願作仏心といふ」ということは「願力廻向」の「願作仏心」である。往相、還相、二廻向は「度衆生心」という如来の本願の働きとして一環一体のものである。「横超」の菩提心は如来の度衆生心の表れ、本願の表れである。自ら悟り成仏しようとする聖道門の「竪」の菩提心は覚醒原理の表れ、如来が衆生を成仏させようとする本願の働きである浄土門の「横」の菩提心は救済原理の表れと言える。
成仏を目指す聖道門の「竪」の菩提心は成仏して涅槃に入って終わりかもしれないが、度衆生心の表れである「横」の菩提心では成仏は始まりであり終わりではない。それは成仏が定まった正定聚の段階からすでに始まっている。本願に生が定まったからであり、また本願は常に働き場を求めているからである。こうして信心が本願の働き場となる。それが我らの「無我」である。具体的には「自信教人信」であり、「常行大悲」である。「教人信」は「自信」という如来より賜る信心が「人をして信ぜしむ」(教は使役の助字)のである。如来の願心が本当の主語である。「常行大悲」も同様であり、如来の慈悲が我らをして「常に大悲を行ぜしむ」のである。「自づから然らしむ」働きである。こうして我らは我なすにあらずして浄土でも此土でも本願を表し、終わりなき「無量寿」の徳を表し続ける。
4 三業惑乱
・三業惑乱は江戸時代末期に本願寺派において起こったもので、当初は宗門内の論争・論難だったが、混乱が増しついには幕府という公権力の介入を招く。三業派に反論した安芸の大瀛の著書は発行禁止となる。さらに大瀛は病身にもかかわらず、京都、江戸に呼び出されて取り調べを受け、江戸での寺社奉行の取調中に亡くなる(1804年46歳)。また幕府により、多くは三業派が処分されるが、反対派も処分を被り、本山は百日間の閉門となった(1806年)。大瀛の死には殉教的要素も感じられる。こうして法難の要素ももつ事件と言える。
・三業惑乱の最も大きな争点は「欲生心」の解釈にある。またこれと結びついた「たのむ」、「助け給へ」の解釈も問題となった。「欲生心」を三業派は衆生が浄土に往生しようと欲する心とし、これを十八願文の「至心・信楽・欲生」の「三心」の中で特に重視して、身・口・意の三業によって如来に帰命するとした。
・「今吾宗に伝る弥陀をたのむといふことは、本願の三信を統括して近く六字の名号なることを示し、三信即一の欲生の一心開発をあらわしたまふすかたと見えたり」(巧存『願生帰命弁』)。巧存は学林の第六代能化。第七代智洞がこれをさらに主張し三業惑乱となる。
・反対派(信楽帰命派)は「欲生心」は 「信楽」の表れであるとし、如来の欲生心が衆生に表れたものとした。
・このことを最もよく表すのが大瀛の『横超直道金剛?』。秘密裏に出版計画が進められ、1801年(享和元年・辛酉)5月に京都で刊行され、6月には本山の学林からの申し立てにより幕府が発行禁止にする。
・「欲生」とは「仏、衆生をして我が国に生ぜしめんと欲す」こと。(大瀛『横超直道金剛?』)
・「この至心信楽はすなはち十方の衆生をしてわが真実なる誓願を信楽すべしとすすめたまへる御ちかひの至心信楽なり、凡夫自力のこころにはあらず」(親鸞聖人『尊号真像銘文』)
・親鸞聖人の釈と大瀛の釈を合わせると、十八願文の意は、使役を「信楽」と「生」にかけて「十方の衆生をして至心に信楽して我が国に生ぜしめんと欲す」となる。あるいは同様の意で「十方の衆生をして至心に信楽せしめて我が国に生ぜしめんと欲す」となる。
・大瀛は「願生」についても「欲生」と同様に本願とする。「願生彼国の願は即ち至心に廻向したまへるの願なり。然れば即ち仏の本願なり。衆生は仏の廻向したまへる願をもちいて己が願とす。」(大瀛『横超直道金剛?』)
・「欲生心」は一般的には自分が浄土に往生しようとする心でかまわないが、「純佗力」(大瀛)である真宗的立場では、未徹底となる。はじめは自分が往生しようと思っていたのが、本願との出会いにより、如来が私を往生させようとしておられるのだと信知する。この転換があって真宗となる。「こちらから」が、「向こうから」に向きが変わる。この向きを廻らすのが本願力廻向である。同様に「願生心」も一般的には自分が浄土往生を願う心だが、本願として如来が我々を生じさせようと願われる心である。その如来の願心が衆生に表れたのが衆生の「願生心」である。
結局この問題は「菩提心」の問題と同様に、衆生の側で起こすのか、本願から受け取るのかという構造をもっていることがわかる。主体が衆生にあるのか、如来・本願にあるのかということである。自力か他力かということと同様である。
・このように如来の願心として「欲生心」を受け取ることで浄土往生の往相だけでなく、さらに如来が我らを此土に生じさせようとする還相の「欲生心」ともなる。どこに生じるのも如来の「欲生心」であり、如来の本願による。「勅命」のままである。こうして十八願の中に「還相廻向」の願の二十二願意も含まれ、十八願から展開する「真実五願」(十一・必至滅度の願、十二・光明無量の願、十三・寿命無量の願、十七・諸仏称名の願、十八・至心信楽の願)に二十二願を加えた、言わば真実六願が十八願から展開する。
また「我が国」は第一義的にはもちろん浄土だが、第二義的には一切衆生を「一子地」と見る如来にとっては、我が子のいる国はすべて我が国であり、無礙光の及ぶ処、本願の及ぶ処、十方すべて我が国である。故に「欲生我国」は第一義的には浄土に生じさせようとすることであるとともに、さらに続いて第二義的には此土に生じさせることにもなる。その意味でも「往・還」二廻向を含む。
・また十八願の「唯除文」は、「抑止門」「摂取門」として読み、結局救われるということだけでなく、それを前提としてそれに加えて、「除」かれている「五逆誹謗正法」のことが、それまで本願に背いていた自分のことであるとわかると、その文のままでもいっこうにかまわなくなる。「摂取」の「摂」のことを「もののにぐるをおはえとるなり」(『浄土和讃・左訓』)と言われているように、摂取された時にそれまで自分が本願に背いていたことがわかる。それは「五逆誹謗正法」と同じである。そこで浄土往生することから「除」いてもらい本願によってここに留めおいてもらうことになる。最下の自分が救われ「正定聚」としていただいたのだから、最後までここに留まって「自信教人信」を続けることこそ本願と感じられる。信心が本願の働き場となる。最も罪の重い者が救われたことをここに留まって伝えることが本願の偉大な働きを彰すことになり、報恩となる。もちろん娑婆の縁尽きればいずれ往生することになるが、浄土では成仏しても無余涅槃に入ることなく、最後までここに留まるために浄土から「除」いてもらって再び還り来て本願を行じ続けようとする。こうして「唯除文」が言わばそのまま「唯除門」でかまわなくなる。ここにも還相廻向がある。十八願の「唯除」の「除」は、二十二願の還相の菩薩を浄土から「除」く「除」の構造と精神に一致するものがある。
また最後までここに留まろうとする精神は、一切衆生が救われるまで成仏しないと誓う「不取正覚」の精神と一致する。「不取正覚」は四十八願すべてに共通する本願の精神である。それはまた『教行信証・信巻』に引用される『涅槃経』の「阿闍世の為に無量億劫に涅槃に入らず」「為といふは一切凡夫、阿闍世王とはあまねくおよび一切五逆を造るものなり」という精神でもある。
さらにこの最後まで留まる精神は『大無量寿経』の「経道滅尽」後も「慈悲」をもって此の経を留める「特留此経」の精神とも一致する。法然上人はこれを「特留念仏」(『選択集』)と解釈。これは「特留十八願」であり、「特留念仏者」でもあり、「特留信心」でもある。言わば本願力は求心力(引力、引き寄せる力)としても遠心力(留める力、広げる力)としても働き続ける。十八願には両者が宿っている。未だかつて本願がここを離れたことはなく、親鸞聖人は我らの信心として留まり続けておられるのである。
こうして悪人こそ最初に救われ最後に渡る。最下が最初で最後となる。それによってすべての者が救われる。本願は下から上まで、初めから終わりまで遍く働く。
「悪人正機」は「悪人生機」であり、自分の力では決して往生することのできない我らを浄土に生じさせていただくことだが、それは「生じさせる」だけではなく、まずここで自分の力では決して本当の人生を生きることのできない我らを本願によって「生かし」ていただくことである。本願によって「生かされる」のであり、「生かされている」のである。こうして我らはどこにあろうとも本願を「生きる」ことができる。本願力は「生じさせる」働きであるとともに「生かす」働きである。命の泉である。どこにあっても「自づから然らしむ」働きである。
浄土は我先に行くところではない。自分が浄土に往生したいという「欲生心」では往生したらそれで終わりになってしまう。また早くこの世を捨てて往生した方がいいことになる。実際各種の「往生伝」にはその類の話がある。
確かに本願と出会い信心をいただく時、もうこれで死んでもいいという気持ちになる。生死を越えてすでに浄土の住人となり、「即得往生」がその言葉通りだとわかる。「無量光」なるが故に夜が明け、「無量寿」なるが故に永遠の命を得る。
しかしそれで終わりではない。本願が自分を生かしてしているのだとわかると、そこから新たな生が始まる。本願によって生まれ変わるのである。いったん夜が明けてしまえば雲が出ようが雨が降ろうがもはやたいした問題ではなくなる。こうして浄土教はゴールを競う宗教ではなく、先を譲り最後まで留まろうとする宗教となる。それが大乗の菩薩道である。
・そもそも人間の欲心で行けるのは「天」(欲天)までであり、浄土は人間の欲心で行けるところではない。「西方十万億土」というこの果てしない隔たりをいったい誰が自分で埋めることができようか。欲心は必ずその限界を知ることになる。「欲生心」は念仏者にとってはしばしば躓きの石となりやすく、注意が必要である。
また死が恐くて浄土に往きたいから信じる、浄土に往くために信じるというのも同様である。恐怖心や欲心があるのは信心でも安心でもなく、また信心は手段ではない。しかし人として生まれて恐怖心も欲心もなく計らい心のない者は誰一人としていない。みな悪人である。その人間の恐怖心が欲心が計らい心が、必ず如来の本願力廻向によって転じられて信心となり安心となるのである。
喩えれば本願力廻向はオセロゲームに似ている。「悉有仏性」なるが故に初めの一手は必ず如来の一手であり、その後いかに人が欲望・欲心・自我力によって迷い、いくら頑張って●を続けようとも、必ず再び○がくる。即ち本願と出会う時がくる。そのとき○によってはさまれた●はすべて○に変わる。本願力廻向によってひっくり返されるのである。今が変われば、過去も変わる。未来も変わる。これが「一念」に「八十億劫生死の罪を除く」ということである。
(○●●●●●●●● → ○●●●●●●●●○ → ○○○○○○○○○○)
結び
いかなる法難、論難があろうとも、本願の働きを止めることは決してできない。我らはどこに生まれようがどこにあろうが、ただ我らを生かしてやまない本願の働きのままに生き、本願直系の念仏を申してこの偉大なる働きを称(たた)え続けるだけである。それが我らの「唯説弥陀本願海」である。

2006.12.16 浄土真宗正光寺にて 渡辺郁夫
1「こころの回廊」連載の意図。
○中国地方を中心に関西まで東西軸にそって西から東に足を延ばし、各地を巡りながら、
浄土教を中心とした宗教心をかきたてるものを語る、一種の宗教紀行。
浄土教が中心だが、それに関係する他の宗教や信仰も取り上げる。
キリスト教、古代信仰 、老子、禅など。救済原理、覚醒原理、創造原理を含むもの。
いずれも私にとっては本願の表れ。本願とは存在の根本願であり、『無量寿経』では
それが四十八願として説かれる。救済原理の宗教において本願の慈悲の要素が顕著に
表れるが、本願そのものはすべての源。私にとっての「本願一乗」。宗教和合へ。
○浄土教の部分
親鸞と法然の関係。2011年は法然800回、親鸞750回遠忌。
辛酉革命と聖徳太子、親鸞の関係。1201年辛酉の年のお告げから。
四十八願の構造と本願の歴史的展開、「本願史観」。「東から西へ(往相、浄土願生)」の時代から
「西から東へ(往相の中にある此土願生、還相の此土願生)」の時代へ。
心惹かれる妙好人。六連島のおかる、石見の浅原才市、石見の善太郎、因幡の源左。2妙好人
○『妙好人伝』(初編、第二編)仰誓編。
「妙好人」は善導、親鸞も使った「白蓮華」に喩えられる浄土教の篤信者一般。
現在の「妙好人」は仰誓が『妙好人伝』を編集し、後にそれが刊行されたことによって、奇特な真宗篤信者の代名詞となる。泥中の白蓮華のごとく、俗世、在家にあって念仏一筋の生活を続けた人。特に困難な状況の中でそれを成し遂げた人。「自信教人信」の生活を続け、周囲の人々、真宗信者のみならず一般人にまで感化を与え、結果的に世俗道徳(俗諦)の面からも称揚すべき人物。「非僧非俗」の体現者。
○仰誓(1721年〜1794年)
仰誓は京都に生まれ、伊賀・上野の明覚寺(西本願寺派)に入る。ここで大和清九郎のことを聞く。
清九郎は東本願寺派光蓮寺の門徒で、仰誓は大和吉野まで清九郎に二度会いに行く。翌年清九郎が亡くなる。
清九郎の墓は因光寺。「清九郎伝」を仰誓が 書き、さらに他の妙好人の伝も書く。仰誓はやがて本山の命により、
石見・市木の浄泉寺に入寺。妙好人伝はさらに増補されていく。仰誓没後、美濃の僧純により出版。
○明治以降の妙好人
江戸時代の『妙好人伝』がきっかけとなり、新たな妙好人発掘が続く。その典型が浅原才市と因幡の源左。才市は鈴木大拙の紹介により広く知られるようになる。
○因幡の源左と柳宗悦
因幡の源左を紹介した柳宗悦は学習院時代に鈴木大拙の教えを受けた縁で鈴木大拙と親交があった。
また柳宗悦は民芸運動の創始者。名も無き陶工や職人が作る民芸の美と一般民衆である妙好人のあり方に
共通するものを見出していた。
柳宗悦は鳥取・山根の願正寺に赴き、一月滞在し、衣笠一省住職の協力の下に言行録を編集する。
3因幡の源左 『因幡の源左』(柳宗悦、衣笠一省・編)『妙好人源左さん』(藤木てるみ)
○源左の生涯
天保十三年(1842年)に山根に生まれ、江戸、明治、大正、昭和と生き、昭和5年(1930年)没。89歳(数え年)。
本名は喜三郎。明治になり足利姓を名乗る。 妻くに(三歳年上)との間に五人の子。現在も源左生家が願正寺の裏手に残る。
家業は農業で、傍らに紙漉をした。今でも山根は和紙の里として紙漉が続けられている。源左は紙の取引もあり鳥取県内を広く行き来し、行く先々で人々と法縁を結んだ。
○源左の聞法と獲信
源左が18歳の時の夏に父親が急死。最期の言葉が「おらが死んだら親様を頼め。」
死とはどういうことか、「親様」とは何か。この二つが苦になって仕事が手に付かず、夜も昼も思案する。翌年の春から一生懸命に聞いて回る。願正寺だけでなく「そこらぢう聞いてまはつたいな」本山にも上り、原口針水和上にも教えを受ける。しかしなかなか聞こえない。三十歳のころ、朝、裏山に草刈りに出かけ、牛に草を負わせて楽になったときに「ふいつと聞こへてのう」、「わがはからいではいけんわい、お慈悲もこの通りだちゆうことだらあやあと思つてよろこばしてもらつたいのう。」
以来、89歳で亡くなる直前まで、病床での直次との問答にあるように「自信教人信」の人生が続く。この人生は親鸞が29歳で法然に出会い、90歳まで生きたことを思わせる。口癖が「ようこそようこそ」、「さてもさても」に続いてお念仏。
○源左の言行
才市はもの静かな人であったらしく自分の法悦をひたすらノートに書き続けた。彼の感化は彼の没後にそのノートを読んだ人々に対して本格的に始まったと言える。
源左は読み書きはできなかったが、積極的に法を伝えようとし、その言行が人を惹き付けるものがあった。彼のことを聞いた同行が彼を訪ね、また農閑期にはいたるところから法座に招かれ、法話をした。「おらの親様が、おらの口から出て下さる」
行為としては「柿の木の話」に代表されるように無欲と思いやりに貫かれている。
○源左と悪人正機
・「善人なおもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」(親鸞)「善人尚以て往生す、況や悪人をや」(法然)
「他人より悪いこの源左をなあ、一番真先に助くるの御本願だけえ、助からぬ人なしだがやあ」
「他人より悪い我を先と、云われるだけの」(源左)
これはいわゆる「悪人正機」で、源左の言うように「悪人が先で、善人は後」。
・「罪人猶生る、況や善人をや」(法然)
源左と同じ極楽に参らしてもらうとすると自分の冥加に尽きると言う同行に対して「お前さんの方が先だわいなあ」、
息子の竹藏が死んだ時「竹はなあ、この世のきりかけ(自分の分、碗一杯)を済まして参らしてもらったわいの。
おらあとろいだで、一番あとから戸をたてて参らしてもらうだがよう」(源左)
これは一見「悪人正機」の逆で、「善人が先で、悪人は後」。法然の言葉 としてはこちらが有名だった。
法然の真意はどちらなのか。源左にも同様に両方ある。
・「悪人正機」の悪人とは客観的なものではない。すべて自分の問題。自分が悪人と知った時初めて意味をもつ。
そのような自分を救うための本願と知った時、初めて本願が本願となる。この時一番悪い自分が救われる。
しかし「設我得仏、不取正覚」の誓いのように全ての衆生が救われるまで自分は最後まで悟らないというのが本願なら、
自分のような者が救われたなら、自分は最後までここに留まって人々を先に渡したいと思うのが、
本願のままに生きることではな いのか。
自分の分だけ済ましても往生できるが、自分は親様が全ての人の重荷を背負って下さったように最後まで残り、
生死火宅の家に戸を閉ざして一番最後に参らしてもらうという心境だろう。
「設我得仏、不取正覚」は四十八願全ての願文に共通する大乗菩薩道の精神。
さらに十八願文にだけ「唯除五逆誹謗正法」が付く。親様の心に背いていた自分こそ「誹謗正法」なら
他の人が全て彼岸に渡っても私だけは残してもらってかまわない、どうか私のことはおいて他の人を先に渡して下さい。
この「不取正覚」や「唯除五逆誹謗正法」に大乗至極の浄土門の「無我」が表されている。
本願に出会った源左の人生は何事も自分を後 にし人を先にする一生だった。まさに本願そのものだった。
悪人は最初に救われ最後に渡る。
牛に救われた源左は、早馬のような無常の風の中で、牛歩の道を歩んだ。

2006.7.16 浄土宗西蓮寺にて 渡辺郁夫
○美作国・誕生寺(久米南町)
・美作は吉備が、備前、備中、備後、美作に分割されて生まれた。美作国という名には国作り への思いが感じられる。
・浄土の二つの意味。一つは普通に使う他界としての浄土。もう一つは「浄仏国土」の意味。 この世界は釈迦仏が生まれた仏国土の一つであり、仏弟子はここを仏国土にふさわしいように 浄め続けるという考え方。一種の国作りであり、また救世思想。美作国は浄仏国土を思わせる 名。浄土宗の開祖法然が生まれ、それを記念した誕生寺がある。
・誕生寺は熊谷直実の創建と言われる。直実は坂東武者で、『平家物語』では平敦盛を討ち取 った際に世の無常を感じて出家し、法然の弟子となる。
・法然の少年時代に押領使の父が突如夜襲を受ける。最期の息の下で父は子に報復を戒め、父 の菩提を弔い自ら解脱を求めよと遺言。仏門に入る。1141年(永治元年)辛酉の年。
・誕生寺には旅立ちの法然像がある。法然の幼名を勢至丸とする。勢至菩薩は阿弥陀仏の智慧 を表すと言われる。法然は「智慧第一の法然房」と言われた。比叡山で修行。善導に帰依。
○『選択本願念仏集』
・浄土宗の独立開宗宣言と言うべき書。それまでは天台宗の寓宗的立場。
・『選択本願念仏集』の冒頭「南無阿弥陀仏 往生の業には念仏を先と為す」。法然の自筆は ここだけだが、この書はこの一行目で実質的に終わる。
・題名の「選択」の主語は阿弥陀仏だが、法然の選択ではないのかと思えてくる。「選択」と は「取捨の義」。目に入るのは徹底した「捨」。自分にとっての真実を追究し、不要なものを 切り捨て、最後に残ったものが真実。それが法然にとっては念仏。これを讃嘆する人は如来の 選択と法然の選択とが重なって感じられる人。
○明恵の批判
・明恵は法然を高僧として「仰信」していたが、『選択集』を読んで驚き、『摧邪輪』を著し て批判。法然没後のことだが、仏教を学んだ者ほど法然門下に入るには勇気を要したはず。
・法然は悟りを求める菩提心さえ不要としたが、明恵は『摧邪輪』を著し菩提心の無いのは仏 教ではないと批判。
○革命的仏教
・明恵の仏教(聖道門仏教)は覚醒原理による。人に内在する仏性を中心とし、それが芽を出 す出発点として悟りを求める菩提心を重視する。
・浄土教(浄土門仏教)は救済原理による。根源的な仏性である如来を中心とし、それが本願 力という巨大な引力で人の仏性を自らのもとに引き寄せる。親鸞の言う「法則」。人はただひ たすら惹かれていくだけでそれが信心。これも仏性の表れ。
○親鸞の法然上人への帰依
・誕生寺に出会いの図と像。
・親鸞は辛酉革命の年一二○一年に聖徳太子のお告げにより法然に帰した。専修念仏自体が革 命的だったが、親鸞にとっても如来の「勅命に帰す」という革命。
・親鸞が実践強調した肉食妻帯、同朋同行、非僧非俗、女人成仏は僧界を越え社会的革命性も 含む。太子の理念の反映。信長との戦いや一向一揆はその表れ。教団自体の変革も求める。最 近では一九八一年の辛酉の年に真宗大谷派は宗憲を改正し、新しい門首制に移行。
2006.7.1 浄土真宗・明顕寺にて 渡辺郁夫
○「母の国」
・スサノオは恋い慕う母のイザナミを求めて出雲に行く。「母(妣)の国」。
・「母の国」の普遍性。母性信仰が元にあり、ミオヤ・ムスヒ信仰と結びつく。母性信仰は世界の様々な宗教にその要素がある。
カトリックの聖母信仰もその一つ。永井隆の聖母信仰も「母の国」と結びついていたのかもしれない。ラフカディオ・ハーンが出雲に惹かれたのも出雲のもつ母性的要素のせいかもしれない。
・日本神話の特徴として悪魔のような絶対的悪を説かず、追放されたり、敗れたものも神々の体系に位置付けられるという包容性に富む。スサノオは高天原から追放されるが、カムムスヒは導き続ける。救済原理を中心とする真宗も母性的包容性がある。
・「根の国」の入り口も出雲と言われる。広島市北部の上根峠を越えると川の水は北に流れる(簸(ひ)の川)。簸の川が可愛(え)の川に合流し、江の川になる。南に流れるのが根の谷川。江の川水系の分水嶺は非常に山陽側に近い。広島の中の山陰文化圏。神楽の盛んな地域。『日本書紀』にはスサノオによるオロチ退治の話でスサノオが下ったのは本文では「出雲の国の簸の川上」、第二の一書では「安芸の国の可愛の川上」。上根、根の谷川の名にあるようにこのあたりは「根」と呼ばれた。またイザナミが葬られたという比婆山から流れる西城川も江の川に合流する。
・「母の国」と「根の国」の道家的(老荘思想的)解釈。
*『老子』第六章「谷神は死せず、是(こ)れを玄牝(げんぴん)と謂(い)う。玄牝の門、是れを天地の根と謂う。綿々として存するがごとし。之を用うれども勤(つ)きず。」 第五十九章「国の母を有(たも)てば以(もつ)て長久なるべし。是れを、根を深くし、柢(てい)を固くし、長生久視の道なり、と謂う。」 第一章「無は天地の始めに名づけ、有は万物の母に名づく。(伊福部隆彦)」 第十六章「各(おの)おの其(そ)の根に復帰す。根に帰るを静と曰(い)う、是を命に復すと謂う。」 第五十二章「天下に始め有り、以て天下の母と為すべし。既に其の母を知りて復(また)其の子を知る。」 第六十二章「大国は下流なり。天下の交なり。天下の牝なり。牝は常に静かなるを以て牡に勝つ。」 第十四章「能(よ)く古始を知る。是れを道の紀と謂う。」
*『老子』を出雲神話と対応させると、「玄牝」「国の母」「万物の母」「天下の母」「天下の牝」が「母の国」、「天地の根」「(其の)根」が「根の国」に相当する。また「紀(木)の国」が「根の国」への入り口とする考え方もあるが、これも道家的。また「大国主」の名も道家的に解釈できる。「国譲り」は老子の「謙下不争の徳」と同様。
*「玄牝」は牡に対する女性、母性の奥深い働き。万物を産み出す力。ムスヒに通じる。「根の国」は「母の国」と同様に万物を産み出す命の根源の世界であり、根底から世界を支える(「根の堅州国(かたすくに)」)。万物はそこから生まれそこに帰って行く、すべてのもののふるさと。上や表にあるものが偉大とは限らない。上や表を重んじるのは儒教的発想。
・ ムスヒ(産霊)とミオヤ
・カムムスヒはスサノオを導き亡くなったイザナミに代わりスサノオの親代わりを務める。カムムスヒはミオヤと呼ばれ、『出雲国風土記』では「神魂」と書かれる出雲の祖神。(造化三神の内、アメノミナカヌシは中立的、タカミムスヒはアマテラスと並ぶ高天原の祖神。)
・ミオヤ信仰は各種の宗教における信仰の一つの柱。我々を産み出し、導くものへの信仰。また光(太陽)信仰もこれと並ぶ柱。浄土教もその要素がある。「真宗宗歌」でも如来を「みおや」と呼ぶ。山陰には妙好人が多い。
○妙好人おかる
・下関沖の六連島の大森家に生まれる。
・享和元年(1801年)〜安政3年(1856年)。1801年は辛酉の年。
・気性が激しく男勝りで、島の男達はおかると結婚しない決議。十九歳で向井幸七を婿養 子にとる。幸七「泣く泣く首に綱を巻きつけられてひっぱってこられた」子どもができるが 夫が浮気、家に帰らない。苦しんだおかるは西教寺の門をたたく。
・現道師の言葉「こんなことがなければ、あんたは仏法を聞くような女ではない」に腹を立てて帰る。約十年間苦しむ。
「こうも聞こえにゃ聞かぬがましよ
聞かにゃ苦労はすまいもの
聞かにゃ苦労はすまいといえど
聞かにゃおちるし聞きゃ苦労・・・・」
・めざめ。三十五歳の時、肺炎から意識不明の重体、意識が回復後病床で現道師の法話を聞 く。信心をいただく。女人成仏の願は三十五願。
「聞いてみなんせまことの道を 無理なおしへじゃないわいな」
以後、和歌、俳句、都々逸などで自分の心境を語り、現道師が書き留める。
「きちがい婆々といわれしわれも やがて浄土のはなよめに」
「鮎は瀬に住む小鳥は森に わたしゃ六字の内に住む」
「親が子をなくなくそだつ蛙かな」
・おかるという人。気が狂ったと言われるほどの激しい情熱と純情の持ち主、真の愛を求め 続ける。夫と綱引きをするが、引くほど夫は離れる。苦しさから仏にすがるが、仏と綱引き する。重病となり、ついに自分の側に引き寄せるのではないと知る。情熱が花開き、信心と なり、歌となる。
○金子みすゞの童謡(『金子みすゞ全集』『金子みすゞの生涯』矢崎節夫)
・明治36年(1903年)〜昭和5年(1930年)
・山口県仙崎の生まれ。大正12年(1923年)から以後下関に住む。母親の再婚先の書 店に勤めながら童謡を作り投稿、西條八十に認められる。大正15年(1926年)同じ書 店の店員と結婚。長女が生まれるが夫が浮気。昭和5年(1930年)離婚。まもなく自ら 命を絶つ。
・1980年代に矢崎節夫氏の尽力により広く世に知られるようになる。その童謡の中に流れる宗教的心情。1981年が辛酉の年。その前の辛酉・1921年に恵信尼文書発見。
・金子みすゞはおかるのことを知っていたか。もしおかるのことを知り、その生涯と彼女の歌のことを知ったら、どうっだっただろうか。おかるがみすゞの善知識になった可能性があるのではないか。
○辛酉と真宗
・辛酉は60ある干支の一つ。中国では革命の年と言われる。聖徳太子もこれを重視したと思われる。神武紀元(前660年)が辛酉の年でこれは太子が定めた可能性がある。太子在世中の辛酉は601年。斑鳩宮の造営を始める。併設された斑鳩寺が法隆寺になる。
・親鸞は建仁元年1201年
に京都六角堂に籠もり、聖徳太子の示現を受け、法然上人に帰す。1201年が辛酉の年。次の辛酉は1261年。親鸞の没年は1262年。以後辛酉の年は60の倍数の親鸞の年忌の年に当たる。1561年が三百回忌。1861年が六百回忌。
・おかるの生年1801年、 恵信尼文書発見が1921年。いずれも辛酉。1981年の辛酉には真宗大谷派で宗憲が改正され、新しい門首制に移行。
・革命的仏教を作るという聖徳太子からのメッセージ。覚醒原理が中心の聖道門仏教に対して、救済原理が中心の浄土門仏教。肉食妻帯。同朋同行。非僧非俗。女人成仏。それらは社会的革命性も帯びる。
・女人成仏。太子が講説された「勝鬘経」は女人成仏の経典。太子が仕えた推古天皇は女帝。太子の妻帯と親鸞の妻帯。親鸞が善信と名乗ったのは太子からの再度のお告げと言われる。日本初の出家者は太子の時代の善信(尼僧)。法然上人からいただいた名は綽空だが、それを善信に変える。親鸞と名乗ってからも善信は併用されている。
・女人成仏が「母の国・真宗」を作る。競争原理一色で修羅化する社会を救うのが「母の国・真宗」の役割。

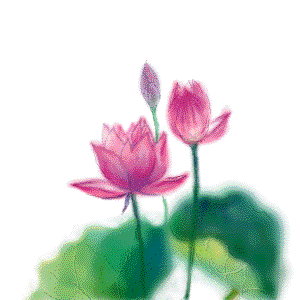
『歎異抄を読むー悪人正機の時代を生きる』
渡辺郁夫・著 洛西書院刊より
増補した新版が『歎異抄を歩む』みずのわ出版刊です。
『歎異抄を歩む』の書籍の紹介のページも御覧ください。
次に浄土教の特色としてあげられることは「願」の強調である。浄土教は「願い」の宗教である。これは親鸞
の場合にその傾向が特に強いが、これも仏教、特に大乗仏教における菩薩思想の影響である。涅槃寂静の静的
な愛・慈悲とともに、それが指向性をもって発揮される本願の強調である。キリスト教における神の恩寵は神の愛と
神の意志とが一体化したものであろうが、浄土教の本願はそれによく似ている。この本願が菩薩の誓願の成就し
たものとして説かれるのが浄土教である。菩薩と如来を結ぶのが「願」であり、さらにそれが衆生に及び仏と衆生
を結びつける。浄土教は信愛の宗教であるとともに「願い」の宗教である。
法身としての阿弥陀仏が、即ち神として絶対者としてはじめから存在する阿弥陀仏が、衆生を救うために一た
んは法蔵菩薩という修行者となって願いを立て、それを成就して報身と応身を得るという物語は、,『無量寿経』に
描かれた非常に示唆深い物語である。神が神のままではなく、一たんは人となって願いをたてる。そうして人から
神へ、神から人へと、人と神を結ぶのが願いである。衆生が絶対者に奉げた愛は、絶対者の側からも衆生に捧げ
られる無償の愛となり、行者にとっては一貫したものである。そしてその願いが今や成就されている。菩薩道にとっ
て「願い」というものがいかに重要であるかこの物語はよく示している。
この法蔵菩蔭の物語は一種の神話と考えてよかろう。十劫という気の遠くなるような昔の話なのだから、
ギリシャ神話や日本神話の数千年前の話の比ではない。従って事実かどうかは問題ではない。小説の場合と同じ
ようにそれによって示された真実は何なのかということである。『聖書』でもイエスはしばしばたとえ話を使って真実
を示しているが、それと同じことだ。『無量寿経』がインド撰述であることはまちがいないが、大乗仏教が成立する中
で菩薩道における「願い」の重要性を説くために書かれた経典なのであろう。菩薩にとっての願いの中心となるの
は自らの悟りと衆生の救済、即ち自利と利他であるが、法蔵菩薩の誓願では両者が結びつけられている。菩薩か
ら如来まで一貫しているのはこの願いなのである。別の言い方をするならば人は自らの願いを生ききることによ
って仏となり、人を救うことができるということである。往相にも還相にも一貫して願いがあるということは、願いとい
うものが根源的存在と結びついているということである。本願とは神の愛と意志が一体化したものだと言ったが、本
願というものはその存在を実感すると、救済の力として働くだけではなく、我々の存在をあらしめている根源的な力
であることがわかる。(p16〜p17)

シンガーソングライター・鬼束ちひろの曲「月光」について
「鬼束ちひろ『月光』ブームの意味探る」より
(中国新聞2001年2月6日洗心欄掲載記事
記事の全文は新聞掲載記事等へにあります。)
「歎異抄を読む」などの著書がある広島市安佐南区の教員渡辺郁夫さん(四二)は「月光」を聴き、「人間を
超えた存在を感じた人の表現」と解釈した。「心を開け渡したままで・・・」という独特の言葉は信仰を意味し、
今は神や仏の沈黙に苦しんで「貴方なら救い出して/私を/静寂から」と求めている、とみる。
「月光」には「この鎖が許さない」「不愉快に冷たい壁」などの言葉があり、「楽園」「天国」などの言葉
はない。しかし、「この世の中で『鎖』や『壁』を感じることは大切だ」と渡辺さん。「月光」の世界はまだ道半
ばだが、「効かない薬ばかり転がってるけど」と安易な逃避を疑う強い意志を感じたという。
(中略)
インターネットの中には「月光」の意味を解釈するホームページが存在し、渡辺さんの見方では宗教性を
感じた人は掲示板書き込み者の半数。しかし、「書き込み者がみな真剣にメッセージを受け止めようとしている
印象は受けた」と言う。
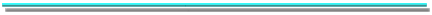
 「月光」 詞・鬼束ちひろ
「月光」 詞・鬼束ちひろ
I am God's child.(私は神の子供)
この腐敗した世界に堕とされた
How do I live on such a field?
(こんな場所でどうやって生きろというの?)
こんなもののために生まれたんじゃない
突風に埋もれる足取り 倒れそうになるのを
この鎖が 許さない
心を開け渡したままで
貴方の感覚だけが散らばって
私はまだ上手に 片付けられずに
I am God's child. この腐敗した世界に堕とされた
How do I live on such a field?
こんなもののために生まれたんじゃない
「理由」をもっと喋り続けて 私が眠れるまで
効かない薬ばかり転がってるけど
ここに声も無いのに 一体何を信じれば?
I am God's child. 哀しい音は背中に爪跡を付けて
I can't hang out this world.
(この世界を掲げる事など出来ない)
こんな思いじゃ どこにも居場所なんて無い
不愉快に冷たい壁とか 次はどれに弱さを許す?
最後になど手を伸ばさないで
貴方なら救い出して 私を 静寂から
時間は痛みを 加速させて行く
I am God's child. この腐敗した世界に堕とされた
How do I live on such a field?
こんなもののために生まれたんじゃない
I am God's child. 哀しい音は背中に爪跡を付けて
I can't hang out this world.
こんな思いじゃ どこにも居場所なんて無い
lyric Chihiro
Onitsuka
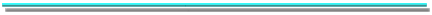
(以下の二つの文章は中国新聞の記者の方からの依頼に応じてコメントしたものの原文です。)
鬼束ちひろ 「月光」について 2001.1.11 渡辺郁夫
まずこの世界に対する認識から述べたいと思います。「この腐敗した世界」、「こんな場所」、「この世
界を掲げることなどできない」、「突風」、「鎖」、「冷たい壁」といった表現が続きますが、これはまさに浄土教
における穢土としてのこの世の認識です。腐敗し、無常の風が吹き、束縛に満ちた、愛のないこの世界に閉じこめ
られている認識です。このような世界に生きるのは苦であり、自分の居場所はないと感じるのは当然です。
釈迦仏教では四諦のはじめに苦を自覚する苦諦がきますが、それと同じです。苦諦と厭世観は一緒に起こる
のが普通です。「月光」という題名は月を見上げて悲しむかぐや姫のイメージが重なります。このような認識を持つ
と、世の中の他の人々は、いったいどうやって生きているのだろうと不思議になります。たいていはあきら
めてもっともらしい「理由」を次々と切れ目がないようにつけ「効かない薬」を次々と飲んで自分をごまか
し、その切れ目から虚無が見えないようにして生きています。親鸞の言う「無明の酒」に酔っている状態です。
この世界を本当に厭い捨てようと思うと、浄土教では欣求浄土、釈迦仏教では出家という形になりますが、
なかなかそこまでいかないのが普通でしょう。しかし、求める気持ちはどこかにあるもので、それがこの世
界を越えたものの予感となったり、あるいは感受性が強い人の場合、この世界を越えたものをかいま見ることがあ
ります。感受性は胸のチャクラ(アナハタ・チャクラ、 チャクラはヨーガでいう異次元との接点)と深い関係
がありますが、深い悲しみや愛を感じたり感動することで一時的に開くことがあります。これを深めていく
と信仰になり、親鸞の言う「信楽」になりますが、そのためにはそれに集中する「行」が必要です。
彼女の場合「貴方の感覚」、「哀しい音」、「爪跡」、と言っているところを見ると、かいま見たのかもしれません。
「最後になど手をのばさないで」と言っているところをみると、深い悲しみ、あるいは絶望感から開いたの
でしょうか。そしてかいま見たことが「私は神の子供」という自覚になっているのかもしれません。仏教で言えば仏性
の自覚です。親鸞が信心は仏性なのだと言っていますが、「心を開け渡したままで」というのは神仏に対して心を
開いていることで信仰と同じことを言っているようです。「私はまだ上手に片付けられず」と言っています
が、突然起こると整理がつかないものです。それを下手に片づけようとすると、イデオロギーになってしまったり、
感傷主義になります。倉田百三がそういう感じです。
一時的に開いた場合、しばらくその余韻が残りますが、また閉じてしまうことがよくあります。その場
合、「行」を持たない人はもう一度経験したいと思ってもそれがかなわず、いわゆる「神の沈黙」に苦しめられます。
親鸞が「信行」として信と行をセットで説くのはそのためです。彼女の言う「静寂」、「時間は痛みを加速
させていく」というのはこの状態なのかもしれません。沈黙からの救いを彼女は求めていますが、まさに「他力」
を求めています。神の子であるにもかかわらず、神に見放されているという痛みの自覚は悪人正機と同様で
す。浄土教の場合、仏は沈黙しておらず、我々に呼びかけており、我々はその呼びかけに念仏で応えると考えま
す。彼女の場合は歌うことが実質的に「行」に当たるようです。念仏も見えざる神仏に対する愛の歌です。
またある程度開いた状態が続くと、感受性がより強くなるので、この世においてはかえって苦しみが増すことにも
なりす。また非常に弱い状態になり、受難癖がつくこともあります。それを乗り越えるには強さが必要です
が、強さを生み出すのは、腹のチャクラ(いわゆる丹田)で、腹式呼吸が有効です。これも「行」があるのが望ましい
のですが、念仏の場合腹式呼吸を伴うので、胸と腹を一緒に開いていくことができます。歌うことはこの場合も
有効だと思います。女性の場合子供が産まれると自然と腹が据わってくることがありますが、それによって
感受性が退行していくこともあります。本当に愛を歌い続けるのは大変なことだと思います。
救いの付録として強さがでてくると、この世を肯定して生きていくことができます。浄土教では「平生業
成」と言っています。あるいは「往相」と「還相」の兼備した生き方です。この世を厭い捨てるだけが浄土教では
なく、浄土に憧れた後、結局はこの世に還ります。華厳教学では「事々無礙」ということを言いますが、これ
が宗教的な存在肯定の姿です。芸術は結局はここを目指すと思います。「月光」の歌の内容はこの段階には
至っておらず、その途中の段階を歌っているようです。そこから引き返してしまうのか、そのまま進んでゆ
くか難しいところです。浄土教では「信心決定」とか「正定聚」と呼ばれるのが引き返すことのない段階です。
彼女は自分のホームページに「打倒月光」と書いていますが、これが弱さや感傷を克服することを目指して
のことなら結構なことだと思います。
以上この歌を宗教心のめばえ、あるいは宗教心のある段階を表した宗教的な歌として解釈してみました。
ただし信や愛を中心にした宗教と恋愛は、対象がこの世を越えたところにあるか、それともこの世の中にあ
るかの違いで、心理としては同様のものです。彼女の言う「貴方」が誰か男性であったとしてもこの歌は成立
するでしょう。よくできた恋愛の歌はそのまま信仰の歌としても聞くことができます。松任谷由美の歌にはそ
れをよく感じました。ひょっとして彼女は恋愛の歌にみせかけて信仰の歌を歌っているのではないかとさえ思う
ことがありました。彼女の活動の息の長さはそこに秘密があるのかもしれません。同様に宗教的な歌の形を
とって恋愛を歌うことも可能でしょう。
次にこの歌がヒットした社会的背景についてですが、この歌を宗教的な歌だと感じた人が多いのなら興味深い
ことです。その場合は「天使の悲しみ」を表していると感じたのでしょうか。あるいはそうでなくても、偽物
臭い大人の世界を拒否し純粋に生きようとする若者の心情を歌ったのだという受け取り方もできるしょう。
それだとありきたりですが、そういう感受性も深めていけば宗教心と同じになります。オウム事件でもそう
でしたが、この世の中に居場所がないと感じている人は多いと思います。経済優先で競争原理一色に染まって
いく世の中に対して違和感を感じている人も多いでしょう。競争、情報化、国際化、こういうものは常に人
の目を外に向けさせますが、そのために自分の内部が空虚になっていくのを感じている人は多いでしょう。
もはや近代的自我さえ確立しないアイデンティティー喪失の時代です。それに対して自分が神の子と感じる
のは窮極のアイデンティティーの獲得です。それをごくあたりまえに歌えることに対しては憧れるかもしれ
ません。もちろんそこには傲慢と転落という危険をはらんでいますが、彼女は神の子の自覚を持ったが
故の悲しみという形で表現しているので、聞く者の抵抗感は和らぐのでしょう。彼女は今年成人式に行けな
かったそうですが、本当の新人類とは成人式で騒ぐ人ではなく、こういう自覚を持った人でしょう。
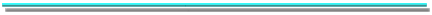
「月光」リスナーの解釈について (解釈サイト「音楽の玉手箱」の感想についてのコメント)
2001.1.22 渡辺郁夫
ホームページの記入者11人の内、5人が宗教的な曲と感じている。キリスト教的とした人が4人で、その
内2人が「神の子の嘆き」を歌ったものと考えている。宗教的とした場合にはこれが最も普通の解釈だろ
う。興味深いのはニーチェと結びつけて、人間を救わない神に対する非難と受け取った人がいたことだ。
これに対して自分を正当化して社会を憂うという青年期によくある心情を歌ったものだという説も1人あ
った。宗教的と感じない場合はこれが普通の解釈だろう。この心情と宗教的心情の間には一つの段差がある
ように思われる。ただし自分を神の子として正当化しているという指摘は大事な点であろう。宗教的に考え
た場合でも、キリスト教の原罪意識や浄土教の悪人意識から見れば、この認識に甘さを感じる人もあるかも
しれない。
宗教的な歌だとは言わないものの、恋愛歌ではなく、戦争と破壊の20世紀を歌ったものだという説も1
人あった。これもこの世界に対する認識としては妥当であると思う。
題名や歌詞に使われた言葉に興味を示している人も多く、主題と関係づけて論じられている。「月光」の
題名の意味に興味を持った人が3人で、月とマリアを重ねた解釈はおもしろいと思う。ある人の言う「ミステリアス」
な題名というのが一般的な受け取り方であろうが、こう感じさせただけでもこの題名は成功だろう。
「開け渡す」で「開」の字を使っていることに注目している人が3人いるが、この使い方に彼女の独特の心情を感じ
ているのはいい感じ方だと思う。「堕とされた」に注目した人も1人いた。これらの用語に注目すれば、宗
教的曲と解釈せざるをえないだろう。
結局、宗教的な歌と受け取らなかったとしても、ある純粋な心情を歌っていると受け取られているようで
あり、掲示板への記入者がみな真剣に彼女のメッセージを受け取ろうとしているという印象を受けた。聞き
流す曲ではなく、真剣に向かい合わざるをえない曲だろう。
一方、私の読者にメールで尋ねたところ、宗教的レベルとしては低いのではないかという意見が3人あった。宗教
書などで高いレベルの境地を見聞しているためだろう。ある男性は詩には共感できるもののある体験を経て
からその視点を脱したと述べている。またある女性の7歳の男の子は自分で望んでこの世に生まれてきたと
表現するそうである。真宗で言う還相を思わせる。
以上まとめてみると、これまで宗教に関心を持たなかった人には自分たちの日常とは違う世界を感じさせ
る新鮮な曲と映ったようであり、一方すでに宗教に強い関心を抱いている人からはまだ不充分に見られてお
り、彼女は両者の間に位置するようだ。宗教心の芽生え、あるいは宗教体験の入り口を歌ったというのが妥当なよ
うだ。
私としてはこれまで宗教に関心がなかった人に別の世界、別の感じ方を伝えた点を評価したいし、そう感じた
人が多い点に希望を見いだしたい。彼女がポピュラー歌手として活動していくにはこの辺の表現が限界だろ
う。これを越えると、ゴスペルソングや妙好人の歌のようになってしまい、一般の人からは理解されなくなってしまう
だろう。私としては彼女が心境としてはそのレベルまで進んで、なおかつ恋愛歌に託して信仰を歌ってもら
いたいと思う。分かる人は分かるだろう。また歌詞だけではなく、彼女はソングライターなのだから、メロ
ディーだけでも心情は伝えられるはずである。今後に期待したい。
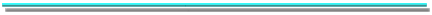
鬼束ちひろ「月光」ブームの意味探る 中国新聞記事の全文(洗心欄 2001.2.6)
次のページにあります。 新聞掲載記事等へ

講演要旨 浄土の歌
(2004.12.14 京都光華女子大にて) 渡辺郁夫
一 和讃
1 親鸞晩年の和讃(「今様」形式)
「浄土和讃」 「高僧和讃」 「正像末和讃」(三帖和讃)
「皇太子聖徳奉讃」 「大日本国粟散王聖徳奉讃」
聖徳太子を詠んだ和讃が、「正像末和讃」収録の「皇太子聖徳奉讃」を入れて、二百首。
2 相聞歌と浄土教の精神
相聞歌、『万葉集』の部立(相聞歌 挽歌 雑歌)の一つ
男女間の恋愛歌だが、慕う心は男女間に限らない。人と神仏の間も同じ。
ベターハーフ(伴侶)になぞらえればベストハーフでありベストオール。
全てを捧げ、還っていくことができるなつかしいもの。
捧げていくことが念仏の精神であり、捧げ尽くすことが浄土教における無我。
しばしば人は神仏と綱引きする。自分の側に引き寄せようとする。自力。
また聞き合う心は観音の心に通じる。
親鸞と阿弥陀仏、聖徳太子の関係も同じで、和讃は一種の相聞歌。
念仏も和讃も捧げる愛の歌。
二 おかるの歌(『妙好人おかるさん』西村真詮 『お軽同行物語』大洲彰然
資料1「タクティクス」記事参照)
1 妙好人おかる
下関沖の六連島の大森家に生まれる。
享和元年(1801年)〜安政3年(1856年)
気性が激しく男勝りで、島の男達はおかると結婚しない決議。
十九歳で向井幸七を婿養子にとる。
幸七「泣く泣く首に綱を巻きつけられてひっぱってこられた」
子どもができるが夫が浮気、家に帰らない。
苦しんだおかるは西教寺の門をたたく。
現道師の言葉「こんなことがなければ、あんたは仏法を聞くような女ではない」に腹を立てて帰る。
約十年間苦しむ。
「こうも聞こえにゃ聞かぬがましよ
聞かにゃ苦労はすまいもの
聞かにゃ苦労はすまいといえど
聞かにゃおちるし聞きゃ苦労・・・・」
2 めざめ
三十五歳の時、肺炎から意識不明の重体、意識が回復後病床で現道師の法話を聞く。
信心をいただく。
「聞いてみなんせまことの道を 無理なおしへじゃないわいな」
以後、和歌、俳句、都々逸などで自分の心境を語り、現道師が書き留める。
「・・・・婆々といわれしわれも やがて浄土のはなよめに」
「鮎は瀬に住む小鳥は森に わたしゃ六字の内に住む」
「親が子をなくなくそだつ蛙かな」
3 おかるという人
気が狂ったと言われるほどの激しい情熱と純情の持ち主、真の愛を求め続ける。
夫と綱引きをするが、引くほど夫は離れる。
苦しさから仏にすがるが、仏と綱引きする。
重病となり、ついに自分の側に引き寄せるのではないと知る。
情熱が花開き、信心となり、歌となる。
4 金子みすゞの童謡(『金子みすゞ全集』『金子みすゞの生涯』矢崎節夫)
明治36年(1903年)〜昭和5年(1930年)
山口県仙崎の生まれ。大正12年(1923年)から以後下関に住む。
母親の再婚先の書店に勤めながら童謡を作り投稿、西條八十に認められる。
大正15年(1926年)同じ書店の店員と結婚。長女が生まれるが夫が浮気。
昭和5年(1930年)離婚。まもなく自ら命を絶つ。
1980年代に矢崎節夫氏の尽力により広く世に知られるようになる。
その童謡の中に流れる宗教的心情。
金子みすゞはおかるのことを知っていたか。もしおかるのことを知り、その生涯と彼女の歌のことを
知ったら、どうっだっただろうか。おかるがみすゞの善知識になった可能性があるのではないか。
三 ユーミンの歌(資料2中国新聞記事「光る海」参照)
1 宗教的感受性の持ち主としてのユーミン(荒井由実、松任谷由美)
恋愛歌のように見えながら、信心を刺激するものがある。
恋愛をより深く歌うことで、信仰の領域と区別がつかなくなるのか。
心の底にある信仰が恋愛歌の形をとって出てくるのか。
2 「顕浄土真実歌曲類」
親鸞の『教行信証』(『顕浄土真実教行証文類』)にならって、ユーミンの曲から。
・『トロピック オブ カプリコーン』
「短すぎる命は 短すぎる命は 愛のためだけにあるの」
・『空と海の輝きに向けて』
「果てのない旅路にやすらぎを求めて いつしか かの胸にいかりをおろす
呼び合う世界で空と海が出会う」(18歳)
・『不思議な体験』
「遠くであなたが見つめてる いつでも心を送ってる」
「遠くであなたが呼んでいる 両手を広げて立っている」
「今 全てが生まれ変わるとき」
・『春よ、来い』
「それはそれは空を越えて やがてやがて迎えに来る」
3 ユーミン浄土教がもつもの
相聞と信仰、親鸞浄土教のもつ「海の浄土教」の要素。
海の浄土教の要素は「横超」の理論的理解より、直に心に響くものがある。
伝統的浄土教における来迎。常世の国を求めた古代人の心。
4 鬼束ちひろ
*「月光」(作詞作曲 鬼束ちひろ)
テレビドラマ『トリック』(テレビ朝日系)のテーマ曲
主人公のマジシャン山田奈緒子(仲間由紀恵・主演)は南方の島、黒門島の巫女
の血を引くという設定。
黒門島は沖縄の久高島がモデルか。久高島は神女の島として知られる。
にせ宗教家や、予言者のトリックを見破っていくというストーリー。
鬼束ちひろの出身地宮崎(日向の国)とその名前から卑弥呼の鬼道を連想。
*「月光」の歌詞 から
「I am GOD'S CHILD この腐敗した世界に堕とされた」
「貴方なら救い出して 私を 静寂から」
「効かない薬ばかり転がっているけど」
*「月光」に見えるもの
厭離穢土という浄土教の精神と通じるものがある。また「神の沈黙」
「効かない薬」というこの世で人を幻惑させるものの限界を知る。
その後、救いを求めるのだが、この形では救われることは難しい。
本当の相聞になっていない。被害者意識、感傷主義、情熱不足。
宗教の入り口に立つ多くの人の姿。
(真宗大谷派系大学である京都光華女子大の宗教講座での講演レジュメです。)
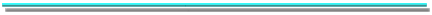
二十一世紀(二十世紀から二十一世紀にかけて)の『歎異抄』
2001.2.11 浄玄寺 渡辺郁夫
(本願寺派安芸教区沼田組仏教壮年会研修会にて)
一 清沢満之(1863〜1903年)
浄土教学の近代化。『宗教哲学骸骨』(1892年)無限と有限、絶対と相対、英訳。
雑誌『精神界』(明治34年 1901年) 精神主義を唱える。『歎異抄』を愛読。
親鸞の精神を一般に開放する。真宗における門戸開放。(内から外へ、外から内へ)
親鸞と個人の向き合い。(親鸞における如来との一対一の向き合いと相似の関係)
他の思想・宗教・哲学と世界的レベルで比肩しうる親鸞思想。
二 倉田百三
『出家とその弟子』(戯曲 大正5年 1916年)
親鸞と唯円(随順者)の関係を軸に親鸞と善鸞(反抗者)の関係を織り交ぜる。
せりふに『歎異抄』の引用。
身近で感傷的な親鸞像。実人生の苦悩に密着した人間ドラマ、文学。
三 鈴木大拙と浅原才市
『日本的霊性』(昭和19年 1944年) 親鸞思想を『消息集』、『和讃』、特に『歎異抄』に見る。
浅原才市の歌を賞賛。
『妙好人』(昭和23年 1948年) 再び浅原才市をとりあげる。
四 二十世紀という時代
文明的側面
西洋文明から地球文明へ。科学技術、経済、戦争、環境問題。
帝国主義と民族主義の衝突、イデオロギー・社会体制の衝突。
世界的市場統合、市場原理、競争原理に世界が飲み込まれる。
人間的(内面的、精神的)側面
自我の肥大化(自信過剰 科学の進歩 自由思想 世界の支配者としての人間)
人間の自画像のゆらぎ(人間と悪 安易な性善思想の限界)
アイデンティティーの危機・喪失(自我の成長の阻害 国際化と情報化)
漂流する人間。
五 二十一世紀へ
灯明としての『歎異抄』の精神。
如来と向き合う中から得られる人間理解と世界理解。
時代を越えた立脚点である普遍性とそこから導き出される時代性、特殊性。
如来と向き合うことによって時代と向き合う。(往相と還相)
世界への貢献
信仰の復権と争いを生まない信仰。人間の作る信念や信条を越えた信楽。
如来より賜る信心、無我の信、仏性としての信心。窮極のアイデンティティー。
競争原理を越えた信愛の原理。
真の同朋意識。心の共同体。
この講演の参考資料として教育部門に載せている「濫読のすすめ 24」の「二十世紀の歎異抄」と
「記事の紹介」のページに載せている「発掘歎異抄20 角のある人」を出しましたので、合わせて御覧下さい。
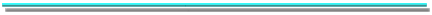
現代と宗教 (講演レジュメ)
渡辺郁夫 ( 2000.10.26.本願寺広島別院にて)
一 時代認識
1 文明と人間
・文明(特に物質科学文明)は積み重ねにより、直線的に加速度をつけて伸びる。
・人間は個人が常にゼロからスタートする。
・文化(特に精神文化)は積み重ねの要素とゼロからの要素を併せ持ち、波状に進
展する。宗教も同様。
・文明の程度と人間の程度の差が拡大する。人間の要求によって肥大化した文明が
人間に多くを要求する。人間の負担の増大。人間が文明を制御できなくなる恐れ。
・国際化、情報化、IT革命など。
変革期の後に安定期がない変化の連続。移動の時代、変動の時代。
2 宗教的時代認識
・三時説。正法(五百年・千年)、像法(五百年・千年)、末法(万年)
・五五百年説(解脱堅固 禅定堅固 多聞堅固 造寺堅固 闘諍堅固)。
僧が自説に固執して相争う闘諍堅固から末法と言われる。
・浄土教における末法意識
末法であるこの世と常に正法である浄土→正法への跳躍台としての末法意識
仏教の成立も、浄土教の興隆、鎌倉新仏教の成立も一つの波。
大きな波の衰退の意識から次の波が生まれている。
真宗の場合、親鸞の後の蓮如。積み重ねによる増幅。
放っておくと波は減衰する。波を受け継ぐ伝灯と増幅させる己証。
・競争原理の肥大化する現代
自由競争の原理を中心とする自由主義・資本主義の独り勝ちで競争原理が
絶対視される。生物の自然淘汰の進化論の影響。
競争原理が競争相手を失ってしまうという矛盾。肥大化とゆがみ。
宗教的に見れば、競争して相手を倒すことだけが目的ならば修羅道、畜生道
と同じではないか。競争の目的は伸びあうことでの繁栄であったはず。
競争よりも闘争(バトル)に見える。修羅の時代、バトルの時代。
・信愛の原理
家族や共同体、人間社会を作る原理は信愛ではないか。「同朋同行」の精神。
仏教の慈悲、キリスト教の愛、儒教の仁。孔子の「信無くば立たず」
人間的な愛から人間を越えたものの愛へ。出発点にあるものとしての親子の愛。
母性の重要性。親となることで神仏の心を学んでいるのではないか。
聞き合う宗教としての浄土教。観音の心。
呼び合い(称名)聞き合う万葉集の「相聞」。
・人類史と人間の一生の相関
人類の親に相当する聖賢の出現
その親の教えをよく守る幼年期、少年期(正)
親を否定し、反抗する青年期(反)→ルネサンスに始まり特に近代以降
親との成熟した関係に入る熟年期(止揚・合)→現代以降の課題
「神は死んだ」というニーチェや「観無量寿経」の父親殺しの阿闍世と人類
弁証法的展開における「悪人正機」の時代としての現代
二 自己認識
1 苦の自覚(自我の芽生えと成長に伴う苦の自覚)
・四諦説 苦、集、滅、道の四諦は苦諦から始まる。
苦の自覚が仏教の人間の側からのスタートライン。
・苦諦と集諦(苦の自覚と苦の原因の探求)
四苦八苦(生、老、病、死、愛別離苦、怨憎会苦、求不得苦、五陰盛苦)
縁起による苦と業の連鎖
無常の世と人間の無明→この世と人間の自我のあり方→存在のあり様、次元。
・多様化する現代の苦
孤独、孤立(自我の確執)。虚無感、生きる意味・生の実感の喪失。
豊かさの中の空白(苦のない苦)。アイデンティティーの喪失
近代的自我という幻想。
世界の中で自立する自分→神仏のいらない人間
→根源を絶ちきった人間→神仏のない文明
2 苦からの脱却
・常に末法である人間と悪人正機
自他の区別から始まる壁としての人間の自我は保護壁であるとともに障壁となる。
人間自我の中には救いも悟りもない。
親鸞の悪人の自覚。「地獄は一定すみかぞかし」の自覚。「機の深心」
時代により個人により異なる苦が展開されるが結局は自我の問題に行き着く。
自分を越えたものを求める心→菩提心、「法の深信」
常に末法である人間と常に正法である仏との向き合い→悪人正機、末法即正法
・念仏と信楽
道諦としての念仏と滅諦としての信楽(正定聚、摂取不捨、自然法爾、往生)。
信楽が如来よりたまわりたる信心の証。仏性の目覚め。
自分の中に湧きあがるが、自分のものではない無所有、無執着、無我の信。
3 自己から人類へ
・往相と還相の兼備した宗教
この世を離れるだけでなくこの世に光をもたらす宗教。死の宗教、生の宗教。
本願力は法蔵菩薩の還相。人に灯る光としての信楽にこもる往相と還相。
「照于一隅(一隅に照る)」(最澄)。
・人類の諸宗教
人間の根本問題を解決する宗教が争いのもとになってはならない。
一神教的世界観の功罪。その対立の克服、終息。用語の違いの克服。
芸術的捉え方。曼陀羅的捉え方。諸仏称揚(認め合い讃え合う)の世界。
如来よりたまわりたる信心は、自我の所有する仮の信である信念や信条とは
次元が異なり、争いを生まない信仰。
ヒロシマから世界へ伝えうるもの。

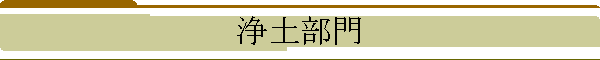
先頭へ
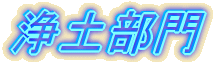
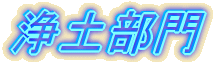
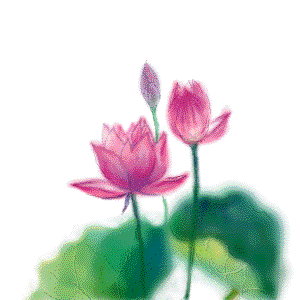 講演要旨 浄土の因果
講演要旨 浄土の因果 講演要旨 唯説弥陀本願海
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
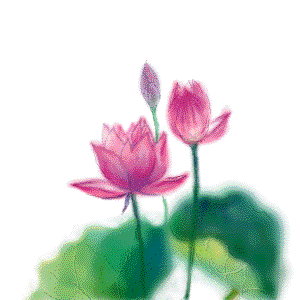
![]()
![]()
 「月光」 詞・鬼束ちひろ
「月光」 詞・鬼束ちひろ ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()