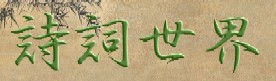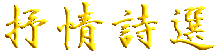
漢詩

七歩詩
魏 曹植
煮豆燃豆萁,
豆在釜中泣。
本是同根生,
相煎何太急?

|
**********************
七歩詩(應聲而作詞)
豆を煮るに 豆萁(まめがら)を 燃やせば,
豆は 釜中に 在りて 泣く。
本 是れ 同根に 生ぜしに,
相ひ煎(に)ること 何ぞ 太(はなは)だ 急なる?
******************
私感訳注:
※曹植:(さうち、さうしょく;cao2zhi2)。(192年~232年)。曹操の子で、曹丕の弟。詩人として有名で建安時
代を代表する作家であり、「建安の傑」と称される。その才能によって、かつて父曹操より太子にされようとしたこともある。父の死後,曹丕らによって種々の迫害を受け、その思いをこの詩に託した。四十一歳の時、兄・曹丕の後を追うように、不幸な裡に世を去った。なお、『世説新語・文學第四 66』に一部が違う六句からなる詩 が載っている。曹植の思いは『吁嗟篇』「吁嗟此轉蓬,居世何獨然。長去本根逝,宿夜無休閑。東西經七陌,南北越九阡。卒遇回風起,吹我入雲間。自謂終天路,忽然下沈泉。驚飆接我出,故歸彼中田。當南而更北,謂東而反西。宕宕當何依,忽亡而復存。飄
が載っている。曹植の思いは『吁嗟篇』「吁嗟此轉蓬,居世何獨然。長去本根逝,宿夜無休閑。東西經七陌,南北越九阡。卒遇回風起,吹我入雲間。自謂終天路,忽然下沈泉。驚飆接我出,故歸彼中田。當南而更北,謂東而反西。宕宕當何依,忽亡而復存。飄 周八澤,連翩歴五山。流轉無恆處,誰知吾苦艱。願爲中林草,秋隨野火燔。糜滅豈不痛,願與根
周八澤,連翩歴五山。流轉無恆處,誰知吾苦艱。願爲中林草,秋隨野火燔。糜滅豈不痛,願與根 連。」
連。」 によく顕れている。
によく顕れている。
日本での彼の読み方は前記二種あるが、前者「さうち(そうち)」が相応しいのではないか。その理由は以下の通りである。正史『三國志』・『魏書・卷一、二』によると、まず、彼・曹植は、諱が「植」、字は「子建」であること。兄の諱は「丕」、字は「子桓」。父の諱は「操」、字は「孟德」で、表にすると次ぎのようになる。
| |
諱 |
字 |
「諱」の読みと意味 |
「字」(あざな)の意味 |
| |
植 |
子建 |
〔しょく〕:うえる。
〔ち〕:たてる、おく、はしら。 |
たてる。はじめる。「植」「建」どちらも「たてる」と訓む。 |
| 兄 |
丕 |
子桓 |
はじめ、もと。大きい。 |
一定の処。しるし、柱、勇ましい |
| 父 |
操 |
孟德 |
|
|
 |
| 『古詩源』 |
 |
| 『古文眞寶』 |
※七歩詩:『古文眞寶』や『古詩源』にある(写真右下・上)。これは『古文眞寶』のもの。 『三國演義』第七十九回「兄逼弟曹植賦詩。姪陥叔劉封伏法」には『七歩詩』が出てくる。曹丕は弟の曹植に対して「吾今限汝行七歩吟詩一首」と命じ、作った「兩肉齊道行,頭上帶凹骨。相遇由山下, 起相
起相 突。二敵不倶剛,一肉臥土窟。非是力不如,盛氣不泄畢。」がそれである。それに対して曹丕は「七歩成章,吾猶以爲遲。汝能應聲而作詩一首否?」といわれ、再び作ったのがこのページの詩である。『兄弟』詩である。兄弟仲、兄弟愛を提起する詩である。
突。二敵不倶剛,一肉臥土窟。非是力不如,盛氣不泄畢。」がそれである。それに対して曹丕は「七歩成章,吾猶以爲遲。汝能應聲而作詩一首否?」といわれ、再び作ったのがこのページの詩である。『兄弟』詩である。兄弟仲、兄弟愛を提起する詩である。
この詩は『三國演義』(元・羅貫中著。日本でいう『三国志演義』『三国志』)第七十九回「兄逼弟曹植賦詩。姪陥叔劉封伏法」に出てくる。(これを漢詩・魏詩(漢魏の詩歌)として、「先秦漢魏六朝詩歌辞賦の頁」で扱っていいかどうか多少疑問もあるが、そのこととは別に『三國演義』での三曹の人間関係を理解するために、古来屡々使われてきた作品であることは事実である。)この詩は普通『七歩詩』といわれているが、『七歩詩』は別の五言詩(後出)であり、これは『三國演義』での表現を借りれば『應聲而作詩』であり、『兄弟』と題してもよいものである(後出紫字部分参照)。皇帝である兄・曹丕と作者・曹植とはともに曹操の息子で兄弟であるものの、才能をめぐり、仲が悪かった。兄・皇帝より才能や行動を疑われ、「七歩進むうちに詩を一首、作ってみせよ」と命じられ、曹植は七歩で「兩肉齊道行,頭上帶凹骨。相遇凹山下、 起相
起相 突。二敵不倶剛,一肉臥土窟。非是力不如,盛氣不泄畢。」と作った。これが『七歩詩』である。するとさらに、「七歩で作るのでは遅すぎる。言われた声と同時に作れるか。『兄弟』という詩題だ。」曹植は即座に「煮豆燃豆
突。二敵不倶剛,一肉臥土窟。非是力不如,盛氣不泄畢。」と作った。これが『七歩詩』である。するとさらに、「七歩で作るのでは遅すぎる。言われた声と同時に作れるか。『兄弟』という詩題だ。」曹植は即座に「煮豆燃豆 ,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急!」(豆を煮るに豆
,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急!」(豆を煮るに豆 (まめがら)を燃やせば,豆は釜中に在りて泣く。本 是れ同根に生ぜしに,相ひ煎(に)ること何ぞ太(はなは)だ急なる?)と口ずさんだ。これを聞いて曹丕は涙をこぼした。「『吾與汝情雖兄弟,義屬君臣。汝安敢恃才蔑禮?昔先君在日,汝常以文章誇示於人,吾深疑汝必用他人代筆。吾今限汝行七歩吟詩一首。若果能,則免一死。若不能,則從重治罪,決不姑恕。』植曰:『願乞題目。』時殿上懸一水墨畫,畫着兩隻牛,鬪於土牆之下,一牛墜井而亡。丕指畫曰:『即以此畫爲題。詩中不許犯着「二牛鬪牆下,一牛墜井死」字樣。』植行七歩,其詩已成。詩曰:「兩肉齊道行,頭上帶凹骨。相遇凹山下,
(まめがら)を燃やせば,豆は釜中に在りて泣く。本 是れ同根に生ぜしに,相ひ煎(に)ること何ぞ太(はなは)だ急なる?)と口ずさんだ。これを聞いて曹丕は涙をこぼした。「『吾與汝情雖兄弟,義屬君臣。汝安敢恃才蔑禮?昔先君在日,汝常以文章誇示於人,吾深疑汝必用他人代筆。吾今限汝行七歩吟詩一首。若果能,則免一死。若不能,則從重治罪,決不姑恕。』植曰:『願乞題目。』時殿上懸一水墨畫,畫着兩隻牛,鬪於土牆之下,一牛墜井而亡。丕指畫曰:『即以此畫爲題。詩中不許犯着「二牛鬪牆下,一牛墜井死」字樣。』植行七歩,其詩已成。詩曰:「兩肉齊道行,頭上帶凹骨。相遇凹山下, 起相
起相 突。二敵不倶剛,一肉臥土窟。非是力不如,盛氣不泄畢。」曹丕及羣臣皆驚。丕又曰:『七歩成章,吾猶以爲遲。汝能應聲而作詩一首否?』植曰:『願即命題。』丕曰:『吾與汝乃兄弟也。以此爲題。亦不許犯着「兄弟」字樣。』植略不思索,即口占一首曰:『煮豆燃豆
突。二敵不倶剛,一肉臥土窟。非是力不如,盛氣不泄畢。」曹丕及羣臣皆驚。丕又曰:『七歩成章,吾猶以爲遲。汝能應聲而作詩一首否?』植曰:『願即命題。』丕曰:『吾與汝乃兄弟也。以此爲題。亦不許犯着「兄弟」字樣。』植略不思索,即口占一首曰:『煮豆燃豆 ,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急!』。曹丕聞之,潸然涙下。」これはまた六句の
,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急!』。曹丕聞之,潸然涙下。」これはまた六句の
| 「 |
煮豆持作羹, |
|
漉豉以爲汁。 |
|
萁向釜下然, |
|
豆在釜中泣。 |
|
本是同根生, |
|
相煎何太急?」 |
ともする。
『世説新語・文學第四・66』では、「文帝(曹丕)嘗令東阿王(曹植)七歩作詩,不成者行大法。應聲便為詩曰:『煮豆持作羹,漉菽以爲汁。 在釜下然,豆在釜中泣;本是同根生,相煎何太急?』帝深有慚色。」とする。
在釜下然,豆在釜中泣;本是同根生,相煎何太急?』帝深有慚色。」とする。
『古詩源』では、
「煮豆持作羹,
漉豉以爲汁。
萁在釜下然,
豆在釜中泣。
本是同根生,
相煎何太急。」
(豆を煮て 持って羹と作し,
豉(し)を漉して 以って汁と爲す。
萁
は 釜の下に 在りて 然え,
豆は 釜の中に 在りて 泣く。
本 是れ 同根に 生ぜしに,
相い煎(に)ること 何ぞ 太(はなは)だ 急なる。)とする。
※煮豆燃豆 :豆を煮るのに、豆がらを燃やす。 ・煮豆:豆を煮る。 ・燃豆
:豆を煮るのに、豆がらを燃やす。 ・煮豆:豆を煮る。 ・燃豆 :豆の茎(豆がら)を燃やす。 ・豆萁:〔とうき;dou4qi2●○〕豆の茎。豆がら。
:豆の茎(豆がら)を燃やす。 ・豆萁:〔とうき;dou4qi2●○〕豆の茎。豆がら。
※豆在釜中泣:豆は釜の中で泣く。 *豆と豆萁とは、本来同一の根から生えている謂わば身内だが、豆がらは燃えて(身内の)豆を煮て来るので、豆は堪えかねてカマの中で泣いている。 ・釜中泣:釜の中で泣く。豆と豆萁とは、本来同一の根から生えている、いわば身内だが、豆萁(豆がら)は燃えて豆を煮て来るので、豆は堪えかねてカマの中で泣いている
※本是同根生:本来は同じ根から生長した。 *ここでは曹丕と曹植の兄弟を指し、兄が弟を殺し除こうとすることを云っている。 ・本是:本来は。 ・同根生:同じ根から生長した。ここでは曹丕と曹植との兄弟をも指す。
※相煎何太急:豆萁が豆をにることにどうしてそんなに急くのか。 *どうしてそんなに激しく攻撃してくるのか。 ・相煎:豆萁が豆をにる。兄が弟を虐めることを云っている。 ・相:…てくる。動作が対象に及ぶ時の表現 。 ・何太急:どうしてそんなに急くのか。 ・何:なんぞ。反問。疑問の辞。 ・太:はなはだ。あまりにも。 ・急:いそぐ。せく。急である。
。 ・何太急:どうしてそんなに急くのか。 ・何:なんぞ。反問。疑問の辞。 ・太:はなはだ。あまりにも。 ・急:いそぐ。せく。急である。
◎ 構成について
五言詩。韻式は「aa」。韻脚は「泣急」で、入声韻。この詩の平仄は次の通り。
●●○●○,
●●●○●。(韻)
●●○○○,
○○○●●。(韻)
2001. 2.15
5.18完
9.15補
2002. 7.10
2003. 1.28
2005. 4.23
2007. 7.23
2009. 4. 2版
2018.10.23
|

唐詩 漢詩 宋詞 漢詩 漢詩
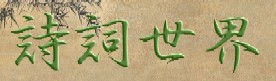
 次のページ 次のページ
 前のページ 前のページ
 先秦漢魏六朝詩メニューへ戻る 先秦漢魏六朝詩メニューへ戻る
*********
 李煜詞 李煜詞
 李清照詞 李清照詞
 秋瑾詩詞 秋瑾詩詞
 碧血の詩編 碧血の詩編
 花間集 花間集
 天安門革命詩抄 天安門革命詩抄
 毛沢東詩詞 毛沢東詩詞
 碇豊長自作詩詞 碇豊長自作詩詞
 漢訳和歌 漢訳和歌
 詩詞概説 詩詞概説
 唐詩格律 之一 唐詩格律 之一
 宋詞格律 宋詞格律
 詞牌・詞譜 詞牌・詞譜
 詞韻 詞韻
 詩韻 詩韻
 詩詞民族呼称集 詩詞民族呼称集
 参考文献(詩詞格律) 参考文献(詩詞格律)
 参考文献(宋詞) 参考文献(宋詞)
 参考文献(唐詩) 参考文献(唐詩)
 本ホームページの構成・他 本ホームページの構成・他
|
 わたしのおもい
わたしのおもい


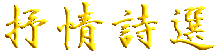



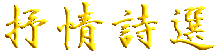


![]() 起相
起相![]() 突。二敵不倶剛,一肉臥土窟。非是力不如,盛氣不泄畢。」がそれである。それに対して曹丕は「七歩成章,吾猶以爲遲。汝能應聲而作詩一首否?」といわれ、再び作ったのがこのページの詩である。『兄弟』詩である。兄弟仲、兄弟愛を提起する詩である。
突。二敵不倶剛,一肉臥土窟。非是力不如,盛氣不泄畢。」がそれである。それに対して曹丕は「七歩成章,吾猶以爲遲。汝能應聲而作詩一首否?」といわれ、再び作ったのがこのページの詩である。『兄弟』詩である。兄弟仲、兄弟愛を提起する詩である。![]() :豆を煮るのに、豆がらを燃やす。 ・煮豆:豆を煮る。 ・燃豆
:豆を煮るのに、豆がらを燃やす。 ・煮豆:豆を煮る。 ・燃豆![]() :豆の茎(豆がら)を燃やす。 ・豆萁:〔とうき;dou4qi2●○〕豆の茎。豆がら。
:豆の茎(豆がら)を燃やす。 ・豆萁:〔とうき;dou4qi2●○〕豆の茎。豆がら。![]() 。 ・何太急:どうしてそんなに急くのか。 ・何:なんぞ。反問。疑問の辞。 ・太:はなはだ。あまりにも。 ・急:いそぐ。せく。急である。
。 ・何太急:どうしてそんなに急くのか。 ・何:なんぞ。反問。疑問の辞。 ・太:はなはだ。あまりにも。 ・急:いそぐ。せく。急である。![]()