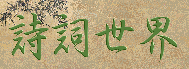|
毛沢東は、著名な詩人、詞人でもある。その詩詞のおもしろさは、なによりも、革命家、政治家として
 |
の彼の存在の大きさに由来しているものだろう。毛澤東がその時代、その時代をどう感じ、考えて切り抜けてきたのか、どう主張して導いてきたのか、その理想と同時に本音の部分も窺えて、興味深いものがある。青年期の恋心を詠ったもの、革命根拠地での生活と闘争を詠ったもの、壮年期の根拠地 での夢想、革命成功後の余裕の詩、文革発動前の憤りの作、と各時代の彼の心の変遷が解り、興味は尽きない。
とりわけ、十年に亘る文化大革命では、多くの中国人と中国の組織は彼の詩詞を覚え込み、活用していたようです。毛沢東の詩詞の面白さは、やはり詠まれている内容と中国現代史とが密接に関聯していることにあると思われる。 での夢想、革命成功後の余裕の詩、文革発動前の憤りの作、と各時代の彼の心の変遷が解り、興味は尽きない。
とりわけ、十年に亘る文化大革命では、多くの中国人と中国の組織は彼の詩詞を覚え込み、活用していたようです。毛沢東の詩詞の面白さは、やはり詠まれている内容と中国現代史とが密接に関聯していることにあると思われる。
1.各時期の作風について
毛澤東の作品と各時期の作風(私見)は、時代を詠み込んでいるので比較的分けやすいと謂えよう。時代順に見ていくと、
①学童期〜青年期前期(〜1926年)
湖南・長沙時代ともいえる。
若年期の習作や、恋心を詠ったものなど、若さや血気に溢れるもの。
習作が多い。
②秋収起義〜福建、湖南の根拠地時期(1927年〜1934年)
福建・湖南時代ともいえる。
根拠地での生活と闘争を詠ったもので、この時期の作品の特徴としては、一般には有名でない地名がよく歌い込まれていることである。そのため、彼のの行動が把握しやすい。
③長征・遵義会議〜陝西北部根拠地時期(1935年〜1949年)
長征・延安(陝西北部根拠地)時代ともいえる。この時期より党主席となり、ナンバー1の地位を確立。
完成度の高い作品が多い。
④建国・建設時期(1949年〜1965年)
新中国建設時代ともいえる。党主席、またある期間は国家主席ともなり、実質ナンバー1の地位を維持。
完成度の高い作品が多い。
⑤文化大革命時期(1966年〜1976年)
政治スローガンのような作品もあり、彼の思想とその情況は解りやすく、素直に詠っているので、内容としてはなかなかおもしろいが、詩詞作品として見れば、あまりおもしろいとは言えない。詩詞の格律に則らない作品も増えている。その意味からは、完成度のあまり高くない作品が屡々見受けられるようになる。この時期のものは、推敲の手があまり入っていないように感じられる。
大体、以上のようになるでしょう。もっと大雑把に区分し直すとすれば、
第一の時期(青年期)
①学童期〜青年期前期(〜1926年)
②秋収起義〜福建、湖南の根拠地時期(1927年〜1934年)
第二の時期(党主席の時期・壮年期)
③長征・遵義会議〜陝西北部根拠地時期(1935年〜1949年)
第三の時期(国家の領袖の時期)
④建国・建設時期(1949年〜1965年)
⑤文化大革命時期(1966年〜1976年)
となるでしょう。
2.表現について
以下、私見になるが、表現については、歴代の詩人に比べて、通俗性が高いことだ。嘗ては文言のみの表現であったものが、白話を混ぜ、より緻密な表現と臨場感を出したこと。民間の諺、成語、民謡をしばしば詠い込んでいること。平仄合わせはきっちりとできて、それに気を遣っていることも読み取れるものの、押韻の韻部が甘く、新たな通押をしていること。屡々歴代の豪放詞 の擬せられるものの、豪放詞の語彙は少なく、北宋の婉約詞派 の擬せられるものの、豪放詞の語彙は少なく、北宋の婉約詞派 の詞人である柳永 の詞人である柳永 と共通する感傷的で華麗な語彙がしばしばある。柳永の使う詞語を使えば(婉約詞の)詞的世界が広がる。適切な方法である。また、政治的な語彙を上手に詠い込んでいること、主題が極めてはっきりとし、明瞭な表現になっていることなど、歴代の作品から比べると異色である。その意味から見れば、毛澤東は古代から続いている民間歌謡の系列の人と謂えるのかも知れない。 と共通する感傷的で華麗な語彙がしばしばある。柳永の使う詞語を使えば(婉約詞の)詞的世界が広がる。適切な方法である。また、政治的な語彙を上手に詠い込んでいること、主題が極めてはっきりとし、明瞭な表現になっていることなど、歴代の作品から比べると異色である。その意味から見れば、毛澤東は古代から続いている民間歌謡の系列の人と謂えるのかも知れない。
3.読み下しについて
彼の詩の内容や表現に関しては、 政治事象を多く詠み込んでおり、用語では現代語、口頭語が多く、伝統的な日本漢詩の読み下しは、出来ない部分が多々ある。しかしながら、そこを日本の伝統と習慣を重んじて、 内容に迫れるように考えて工夫をした。そうは云ものの、現代語を漢文風に読み下すこと自体に少し無理があり、不自然さが出てきてしまった。 そこをなんとか努力して近づけているつもりなのだが、まだまだ気になるところがある。この段、なお今後の工夫がいると自覚している。
4.出典について
詩詞の出典は、先ず「毛主席詩詞三十七首」(人民文学出版社) からにした。「毛主席詩詞三十七首」の詩句が一番整理され、作品としても完成されたものを載せているため、これを底本として、その他 からにした。「毛主席詩詞三十七首」の詩句が一番整理され、作品としても完成されたものを載せているため、これを底本として、その他 から補足して載せている。 から補足して載せている。
------------------
毛沢東自身は、毀誉褒貶の激しい人物ですが、本サイトでは、彼の政治的・思想的な問題には触れずに、
文学的な観点からのみ彼の詩詞に接しています。ご了解下さい。
|