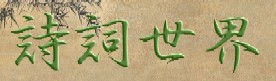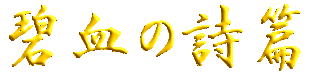
êVû¶

@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@v@«äµ
ÂqØ^B
|
k]û~BHC ½Í@êöC ¶ªtH L¾¾sRSäÝC \ü@êíéfB ¡cì¬ÖRÕB ÁìC z÷Aº`^áB kΡC èêDB _ÍåJàìÒÏ\C âácN@c¶ãC LlÒÛH ½Vàö£qC N²´òyH ZÆ{RlôB äζSä[¯C üÔAÂu@VwB óÚC ÇB  |