
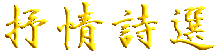

白楽天白居易
對酒
白居易

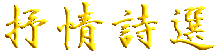

******
蝸牛角上爭何事,
石火光中寄此身。
隨富隨貧且歡樂,
不開口笑是癡人。
酒に對す
蝸牛 角上 何事をか 爭ふ,
石火 光中 此の身を 寄す。
富に 隨ひ 貧に 隨ひ 且(しば)し 歡樂せん,
口を開きて 笑はざるは 是れ 癡人。
*****************
◎ 私感註釈
※白居易:中唐の詩人。772年(大暦七年)~846年(會昌六年)。字は楽天。号は香山居士。官は武宗の時、刑部尚書に至る。平易通俗の詩風といわれるが、詩歌史上、積極的な活動を展開する。晩年仏教に帰依する。
※對酒:酒に向かう。 *「酒」とは、消憂の物でもある。これは『對酒』五首のうち第二首。第四首「百歳無多時壯健,一春能幾日晴明。相逢且莫推辭醉,聽唱陽關第四聲。」とする。
※蝸牛角上爭何事:カタツムリのツノの上(のような狭いこの浮き世の中)で、なにごとを争っているのだ。 *仏教風の悟りの詩である。 ・蝸牛:カタツムリ。 ・角上:ツノの上。 ・爭:あらそう。 ・何事:なにごと。
※石火光中寄此身:石から出る火花の一瞬の輝きにこの身を仮住まいさせている。(我々の人生とはそのような一瞬ではないのか。) ・石火:石を打つと石から出る火花。 ・光中:(一瞬の)輝きに。 ・寄:仮住まいをする。よせる。まかせる。 ・此身:この肉体。
※隨富隨貧且歡樂:豊かな者は豊かなりに、貧しい者は貧しいなりにしばらく、この世に生きている間は、楽しんで過ごそう。 ・隨富隨貧:豊かな者は豊かなりに、貧しい者は貧しいなりに。 *〔隨…隨…〕…ても…ても。…につれて。…しながら。 ・且:しばし、しばらく。短時間を表す。ここでは、この世に生きている間、の意になる。盛唐・杜甫の『絶句漫興』に「二月已破三月來,漸老逢春能幾囘。莫思身外無窮事,且盡生前有限杯。」とある。 ・歡樂:たのしむ。声を上げて笑い出すようなたのしみ方をいう。
※不開口笑是癡人:口を開けて高らかに笑わない者は痴れ者である。 ・不:意思の否定。 ・開口笑:口を開けて高らかに笑う。 ・是:…は…である。これ。主語と述語の間にあって述語の前に附き、述語を明示する働きがある。〔A是B:AはBである〕。 ・癡人:しれ者。馬鹿者。
***********
◎ 構成について
平起。韻式は、「AAA」。 韻脚は「身人」で、平水韻上平十一真。次の平仄はこの作品のもの。
○○●●○○●,
●●○○●●○。(韻)
○●○○●○●,
●○●●●○○。(韻)
| 2004. 2.21完 2007. 4.19補 2010.11.24 |
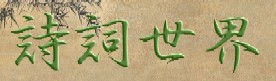
************ |
メール |
トップ |
