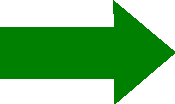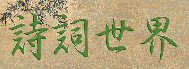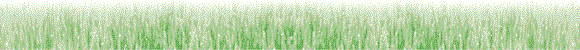| £~Ô¨VvC¡ä¢âûû©FæVC¾Zâå | ||
| Rz | ||
_RçEêâ¾C HÐàlÄnsB äo~Ôà¥nC |¼äÝÊeÎúîB |
||
| |
|
| £~kÌ´³i½¬23.3.10j | Rzä©èÌ^i½¬23.3.10j ȨÄDÉ»Ì|ªL³êÄ¢é |
| |
|
| ^Åw£ÆRzxÆybg̨çèðàÆß½B | XÌëÉÄ |
| XÌëæ詺뵽iF | |
******
£