
@@
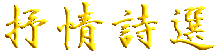
¤Û

@ããú¯RZí

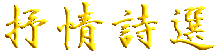

******
àÕÝÙû¸à¨ÙqC
§Àß{veB
ê¡mZío|C
徧ä£äÎêlB
ããú @R ÌZí ð@¯ Ó
àÕ èÙû¸ ÉÝ èÄ@@Ùq ÆਠèC
Àß É§ Ó É@@{ ·e ðvÓB
ê¡ ©Émé@@Zí @«Éoé|C
徧 @ä£äÎ ð µÄ@@êl ð ðB
*****************
| QOOPD@VD@Q® @@@@@@VD@Xâ QOOSD@QD@V QOOTD@TD@R QOOWD@RDPR QOPQDPODRP QOPRD@VDPQ QOQODPODPT @@@@@ PODPV |
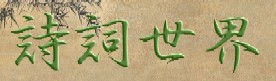
gbv |
