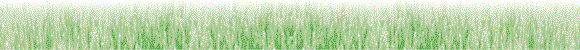|
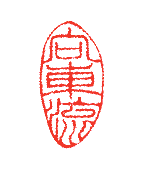 |
| 踏歌詞 | |
|
|
中唐・劉禹錫 |

 |
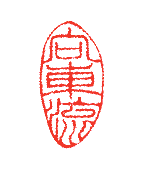 |
| 踏歌詞 | |
|
|
中唐・劉禹錫 |
桃蹊柳陌好經過,
燈下妝成月下歌。
爲是襄王故宮地,
至今猶自細腰多。
******
| 2019.7. 9 7.10 |

************ |