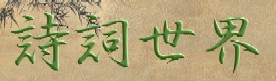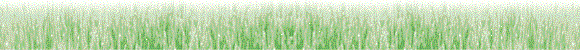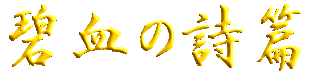
^ç@@@@ @@@@@@@ @@@@

@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ü´ùúC à]àKCsáàVÈCèøFܪC`eÍÇB ©§âVHF uqñOèåväoH½ÌzHvü´HFu¨¢F÷äàÕûCCOlFçËäàÕÁC¥È©úBv HF u¹lsÃú¨C§\äo¢ÚB¢lF÷C½s淈´D§g´gH OlFçËC½séO´§歠´釃H½Ì[v¨C©ßúà¨Hv ü´HF uá·VFVÒK[¥CVÒKUßB À\ÈgV@@Có¨V汶汶ÒÁHJìC]V C À\Èá©á©VC§Ö¢VoºÁHv ΢§ÎCÛúâ§B TÌHF uéQV ûCaCÂÈóäãCéQV ÷aCÂÈóä«Bv Csäo¾B  |