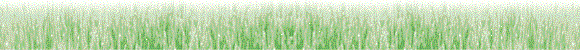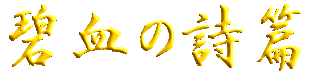 |
 |
| 征婦詞 | |
| 明・劉績 | |

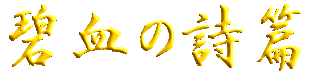 |
 |
| 征婦詞 | |
| 明・劉績 | |
征婦語征夫,
有身當殉國。
君爲塞下土,
妾作山頭石。
******
征婦の詞
征婦 征夫に語 る:
「身 有れば當 に國に殉 ずべし。
君塞下 の土と爲 らば,
妾 山頭の石と作 らん。」と
****************
◎ 私感註釈
※劉績:明代の詩人。字は孟熙。山陰(現・浙江省紹興)の人。経学に通じるも、隠居して仕えず、郷里で村人に教えて過ごした。家は西江草堂にあって、世に西江先生と称された。
※征婦詞:出征していく(/旅立つ)夫(おっと)の詞(言葉)である『征夫詞』「征夫語征婦,死生不可知。欲慰泉下魂,但視褓中児。」に答えた妻の詩。 ・征婦:出征している(/旅立っている)人の妻。留守をあずかる妻。 ・詞:ことば。
※征婦語征夫:(留守をあずかる)妻が、旅立つ(/出征していく)夫(おっと)に語ることには。 ・語:かたる。 *夫の詩『征夫詞』「征夫語征婦」に合わせて作った部分。 ・征夫:出征する人。また、旅人。
※有身当殉国:身命のある限りは、当然ながら、国難に身を捧げるべきです。 *この句から最後までが妻の言った言葉。なお、読み下しで、伝統的な仮定条件の意を含め、「身あれば…」と已然形にし、レバ則に準じた。なお、後半の「君為塞下土」「妾作山頭石」も「為れば」「作れば」と已然形にして揃えた方が統一がとれるだろうが、未然形にした。三者すべて未然形でもよいのだろうが…。 ・当:当然…である。まさに…べし。 ・殉国:〔じゅんこく;xun4guo2●●〕国難のために生命を捨てる。
※君為塞下土:あなたが(死んで)国境の砦(とりで)のほとりの土となった(のならば)。 ・君:あなた。ここでは、夫のことになる。 ・為:…となる。後出・「作」も同様な意味。「為」と「作」との使い分けは、「為」は○となるところ、「作」は●となるところで用いる。それ故、「君為塞下土」「妾作山頭石」中の「為」と「作」との入れ替えや差し替えは、不可能。(○○●●●,●●○○●。) ・塞下土:塞外の塵となる。国境の外で死ぬことを言う。
※妾作山頭石:わたくしめは、山の上にある望夫の石となりましょう。(そして、あなたの帰りを待ちましょう)。 ・妾:〔せふ;qie4●〕わたし(女性の卑下した自称)。あたし。わらわ。しょう。 ・作:…となる。 ・山頭石:山の上にあるという望夫石のこと。望夫石は各地に伝説と共にあり、婦人が夫の帰ってくるのを立ち続けて待ち、やがてその姿が石となって待ち続けている、というもの。南朝・宋・劉義慶の『幽明録』に「武昌北山有望夫石,状若人立。古傳云:昔有貞婦,其夫從役,遠赴國難,攜弱子餞送北山,立望夫而化爲立石。」(武昌の北山に望夫石有り、状(さま)は人の立つが若(ごと)し。古伝に云ふ:『昔、貞婦 有り、其の夫 役(えき(/つとめ))に従(したが)ひ、遠く国難に赴(おもむ)き、弱子(=幼子)を攜(たづさ)へて北山に餞送し、立って夫を望み而(しかう)して 化(くゎ)して立石と為(な)る』と。」(「=武昌の北山に望夫石が有り、状(さま)は人が立っているようである。古伝に云うことには:『昔、貞婦がいて、其の夫が役(えき/つとめ)に従い、遠く国難に赴(おもむ)き、弱子(=幼子)を攜えて北山に餞送し、夫を望んで佇(たたず)んで、化して立った石と為(な)った』とのことである。」)とある。現・遼寧省の興城市西南にある望夫山の望夫石は孟姜女の夫を望むところから変わったもので、その外では現・寧夏回族自治区の隆徳県の西南や江西省分宜県の昌山峽の水中や貴州省貴陽市の北谷の頂埧や広東省清遠市にそれぞれ望夫石がある。中唐・王建の『望夫石』「望夫處,江悠悠。化爲石,不回頭。山頭日日風復雨,行人歸來石應語。」がある。
***********
◎ 構成について
韻式は、「aa」。韻脚は「國石」で、平水韻入声十三職(國)、十一陌(石)。この作品の平仄は、次の通り。
○●●○○,
●○○●●。(韻)
○○●●●,
●●○○●。(韻)
| 2012. 3. 6 3. 7完 2019.12.20補 |
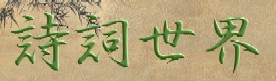
************ |