
liyu LiYu ¿
@

@@ @ 
|
çzCéGHê²dC ~qÂÕ®lñC VúÍSèäogáB ÒräióÀ C üÔêtÎôC oÕsÉXßB |

******
¯â¹
@@@@@@@@@@@@@


@@ @ 
|
çzCéGHê²dC ~qÂÕ®lñC VúÍSèäogáB ÒräióÀ C üÔêtÎôC oÕsÉXßB |

çzC@éGH@@ê²É@dèC
ÂÕð@qËñÆ~µÄ@lÌñÈéð®i¤çjÞC
VÍ@SèðµÄ@@g@äoiÆjái½ªjÍúÍiµjÞB
ðÒÂ@räi@@óiÞÈjµ Àiäj C
Ôðüi©j·@êt@@i ÓjééÎôC
oÕ@Éܸ@@XÉ ßÌiÊjééðB
@@@@@@@@@@@@@@@@**********
´ß
¦¯k¹FvÌê![]() Bég¤ÌìÆà·éB
Bég¤ÌìÆà·éB
¦çzCéGHê²dF¢âÎÌÚèÏíèͬâ©ÅAÉ©êÄòѬ£i³·çj¤MÌæ¤È«UÉÈÁĵÜÁ½ªA²ÅißÌhØÌÉjßÁ½B@EçzCFkÄñµåGzhuan3zhu2l¢âÎÌÚèÏíè̬â©Èg¦BmáÌwÀlxÉuâãLÀlCHÝóJB©]ÇÆqCëËØBèÌrsCZíECB¯½«_Cs¾¾÷B¢î¦[CäÝç¬çzCBv¹çjZCVlß@ÊBvÆ éB@EéGHFÉ©êÄòѬ£¤MÌêíÅAÉ©êĬ£¤³Üðà¤B±ÌuHvÍANX}X[XÌæ¤ÉÈÁÄAÉ©êÄnãð]ªéª³µBfVlBuçzHv̱ÆBfæw©ynxÉ»Ì]HAòHÌlqª`ʳêÄ¢éBAÌwÜlÑxÉuÜlçzHC¢½àÕRB·{ªÀChé³xÕB¼ãSµèCìkzãèB²öñNCäü_ÔB©àIVHCRº¾òBÁéIÚäoCÌdÞcBácì§XkC৽¼Bác½ËCS§¶BéG![]() üªàVCAãÇðÜRB¬çz³|CNmáêä
Bèà¨ÑCHç¬ìÎàBâôÅæ¯sÉCèäoª
üªàVCAãÇðÜRB¬çz³|CNmáêä
Bèà¨ÑCHç¬ìÎàBâôÅæ¯sÉCèäoª![]() ABv
ABv![]() ÆríêÄ¢éB@Eê²dF²ÅißÌhØÌÉjßÁ½BìEûUÌwqéÌxÉul¶D¦½\ÆHç÷°àÕäî½ÀHÌ ²ddCæSÒÔÜIêNäoãH@@@·LH°]B߬óCÒ@ê²Iv
ÆríêÄ¢éB@Eê²dF²ÅißÌhØÌÉjßÁ½BìEûUÌwqéÌxÉul¶D¦½\ÆHç÷°àÕäî½ÀHÌ ²ddCæSÒÔÜIêNäoãH@@@·LH°]B߬óCÒ@ê²Iv![]() âwgO²x IÍÌuàh_|CrúÂßBRÒ¯ê²Cx΢láBv
âwgO²x IÍÌuàh_|CrúÂßBRÒ¯ê²Cx΢láBv![]() ÈǪ éBûUÌwQ¹xuúOJàDàDCtÓèXB
åÎsÏÜX¦B² smg¥qCêéMæÃcB@@@àÕ©ßC³À]RBÊeÕ©ïB¬
ÔtçCVãlÔBv
ÈǪ éBûUÌwQ¹xuúOJàDàDCtÓèXB
åÎsÏÜX¦B² smg¥qCêéMæÃcB@@@àÕ©ßC³À]RBÊeÕ©ïB¬
ÔtçCVãlÔBv![]() ÆA±êà²Å̽ÖAÁÄ¢éBã¢Aú{ÅàAÇ°Íw¼éxÅuññÜ\LéPNClÔ¥ñê²BR[Ü©~JC¼éåJåJàrâxBv
ÆA±êà²Å̽ÖAÁÄ¢éBã¢Aú{ÅàAÇ°Íw¼éxÅuññÜ\LéPNClÔ¥ñê²BR[Ü©~JC¼éåJåJàrâxBv![]() Æg¤B
Æg¤B
¦~qÂÕ®lñFÌÌv¢oÌnðqËæ¤Æµ½ªA¦ßµ¢±ÆÉlÍÏíÁÄ¢½B@E~Fcæ¤Æv¤Bc½¢B@EqF½¸ËéB@EÂÕFÕB@E®Fk¿á¤Gchang4lV«¦ÞB¤çÞB¢½ÞBD¦VB¸Ó̳ÜB@ElñF©R̨ÍÏ»·é±ÆÈ»ÌÜÜÅ éªAlÍ»¤ÅÍÈAlðß®é«âÔiNîjÉÍßÆá¤V½Èà̪ éBií½µÆ¢¤jlðæèªÂ«ªAßÆä×Äå«ÏíÁ½±Æðà¤Bu¨¥lñv̱ÆB©àIÌwdÒaçxÉudÒaCcÓsdBù©ÈSà¨`ðCö®§àÕßBåßVsæ|CmÒÒVÂÇBÀr´¢CæS¡¥§ðñBv![]() Æ éBã¢A´ÆÍwËtxÉuZoÔßá¶CúÓªB¨¥lñxC~êÜæ¬B@@@·àÔât®DCç[ çjMBü°Ôâ
Æ éBã¢A´ÆÍwËtxÉuZoÔßá¶CúÓªB¨¥lñxC~êÜæ¬B@@@·àÔât®DCç[ çjMBü°Ôâ![]()
![]() MCÚs®C½DBv
MCÚs®C½DBv![]() BÆg¤B
BÆg¤B
¦VúÍSèäogáFVÍAí½µÌ¦ÄÌè¢i½ÀȶjÆA¡Ìí½µÌ«Ugi¸újÆðå«á¦ÄµÜÁ½B@EVFVéBVn¨ÌåÉÒB¢¨åB©RÉèÜÁ½^½BV½B@EúÍFcÉciðj³¹éBcðµÄcµÞBgð\»B@ESèFS©çÌè]BOèB_§ÈÇÉASÌÅ©¯éèB@Eäo-FcÆB@EgF±±Åͤäªg̱ÆÉÈé¡@EáF½ª¤Bá¦éBÌwcðâxuûòVLÒôCä¡âtêâVBl³¾s¾CsÈäolç¬Bá§@ò¾ÕOèCûÅá¶ûCPá¢BA©ªnCãÒCJmúü_ûèBÃl¡lá¬
C¤Å¾F@BBèácÌðCõ·ÆàM Bv![]() Æ éB
Æ éB
¦ÒräióÀ
FÌoª©â·¢ÆàíêérÌÙÆè̽©¾¢ÅAÌoðÒƤƵÄàAiÈ©È©»Ìæ¤ÉÍÈçÈ¢ÅjóµÔâ
ª¬êÄäB@EÒräiFÌoªª©èâ·¢rÌÈÌäBuß
êäiæ¾vÌÓB@EÒFÌoª©â·¢BÌoðÒÂB@EräiFrÌârÌÙÆèÌäâ½ÄàÌB·EÌwDSÎåmñáxÉuçËÊôúCoÕÎräiB½ÎåHCdLàMJBHg
CCF¾hqBòHe©Cá¶ètBv![]() Æ éB@EóFÞȵ@EÀ
F¬êsìÌ
B߬sÔðà¤BNÌoßð]¤Ìí
\»Bw_êEqã¥xuqÝìãHFÀÒ@zvIsÉéBv
Æ éB@EóFÞȵ@EÀ
F¬êsìÌ
B߬sÔðà¤BNÌoßð]¤Ìí
\»Bw_êEqã¥xuqÝìãHFÀÒ@zvIsÉéBv![]() ©ç«Ä¢éBÌwcðâxÉuÃl¡lá¬
C¤Å¾F@Bv
©ç«Ä¢éBÌwcðâxÉuÃl¡lá¬
C¤Å¾F@Bv![]() Æ éB
Æ éB
¦üÔêtÎôFÔÍAOt̽ßÉúAÉÈÁĵܢA[úÌõÍOtΩèÉ˵©¯Ä¢éBnãiÌëjÍ©¨ÉÈè©©èAªÅªÁÄ«Ä¢éªA²«ñoÄ»»è§ÁÄ¢éOtÍAܾ[fÉ©ÑãªÁÄ¢éB@*±êªÀiÌ`ÊÅȯêÎuüÔiúAÉÈÁ½ÔjvÍûU̱ÆÅAuOtvÆÍv¤©Ì±ÆÅAuÎôi[újvÍV½Ì±ÆÉÈ뤩B@*ÔÍAOt̽ßÉúAÉÈÁĵܢA[úÌõÍOtΩèÉ˵©¯Ä¢éB@EüÔF±±ÅͤuiOt̽ßÉjúAÉÈÁÄ¢éÔvÌÓÅgíêÄ¢é¡Ü½AÉÁÄ¢éÔB±±ÍAOÒÌÓB@EüFk¢ñGyin4lúAÅ éBAÉÈÁÄ¢éBܽAµ°éBܽA©°BØüB±±ÅͤOñÒ̮ƵÄgíêÄ¢é¡@EêtF½©ÇÌBw̨BmáÌwoêxÉuÔßêqSCäÝû½ïoÕBÑ]tFÒVnCÊÜ_ÌáBkÉ©ìIsüC¼RXNBÂ÷ãåÒâK_CúéãÖ×ÀááBv![]() Æ éB@EFkÜñGman4l ÓêéB¢ÁÏ¢ÉÈéBܽARÆB·XÆB»¼ëÉBuævi¨ë»©É·éBܽAݾèÉBâ½çÉBjÆà·éBég¤ìÆ·éêÍuævB@EÎôF[úBÎzBôB
Æ éB@EFkÜñGman4l ÓêéB¢ÁÏ¢ÉÈéBܽARÆB·XÆB»¼ëÉBuævi¨ë»©É·éBܽAݾèÉBâ½çÉBjÆà·éBég¤ìÆ·éêÍuævB@EÎôF[úBÎzBôB
¦oÕsÉXßF¢ÉoÁ½½ßÉi]½ÌOÅjAXÉßðÜÅGç·±ÆÉÈÁÄà©ÜíÈ¢B@EoÕF¢ÉoÁÄAºûðßéBOoÌurävuOtvÉoé±ÆÉÈéBÌÅuoÕvuËiß~jvÆ¢¤ÌÍAÌûð]ÝâèA̽âeµ¢lXðv¢N±·Æ¢¤SÌ®«ðºÁ½s×Å éBܽAuÒêtvÆð©éÆ¢¤s×ÍAÆ°ðv¢âéÆ¢¤C¿Ì®«Å éBuÌ s¬ññ@¾Bv![]() B»Ì½ßAãoEußvͽÅßðGç·Ì©Æ¢¦ÎAṞÆȪçAù½ÌO©çÌÜÅ éB±ëªûUÌìÅ éÌÈçÎAiêÉég¤Æà éjûUª
B»Ì½ßAãoEußvͽÅßðGç·Ì©Æ¢¦ÎAṞÆȪçAù½ÌO©çÌÜÅ éB±ëªûUÌìÅ éÌÈçÎAiêÉég¤Æà éjûUª![]() Éfv³ê½ÌÅASÌßVÌÉ ÁÄA̽ðvÁÄ¢½BußvðuéIÅßðGç·vÆ©éü«à éªASà÷ÁÄA±êªéVÑÌìÆ·êÎußvÍuéIÅßðGç·vÌÓÉÈ뤪BOoEÌwDSÎåmñáxÉuçËÊôúCoÕÎräiBv
Éfv³ê½ÌÅASÌßVÌÉ ÁÄA̽ðvÁÄ¢½BußvðuéIÅßðGç·vÆ©éü«à éªASà÷ÁÄA±êªéVÑÌìÆ·êÎußvÍuéIÅßðGç·vÌÓÉÈ뤪BOoEÌwDSÎåmñáxÉuçËÊôúCoÕÎräiBv![]() Æ éB@EsÉFɵÜÈ¢BcÄà©ÜíÈ¢BOoEmáwoêxuäÝû½ïoÕv
Æ éB@EsÉFɵÜÈ¢BcÄà©ÜíÈ¢BOoEmáwoêxuäÝû½ïoÕv![]() ÌÓB@EXF¢Á»¤B³çÉB»ÌãB@EßFkÄñGzhan1liÜÅjßðGç·Buè¿ßv̱ÆB@EFkÄñGzhan1itian1jl¤é¨·Buè¿vB
ÌÓB@EXF¢Á»¤B³çÉB»ÌãB@EßFkÄñGzhan1liÜÅjßðGç·Buè¿ßv̱ÆB@EFkÄñGzhan1itian1jl¤é¨·Buè¿vB
@\ƒ墀
@¯â¹Bl\ñio²jBrCÍAudñáôËvÅACæO½ºB½ºCêCêBC®ÍuAAA@AAv![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
@@@![]() CiCj
CiCj
@@@![]()
![]() BiCj
BiCj
@@@![]()
![]() BiCj
BiCj
@@@![]()
![]() C
C
@@@![]()
![]() BiCj
BiCj
@@@![]()
![]() BiCj
BiCj
| QOOVDQDQR @@@@@QDQS @@@@@QDQT @@@@@QDQW® QOPTDPDQTâ |
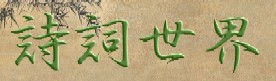
gbv |
