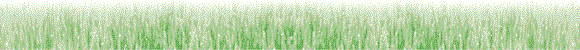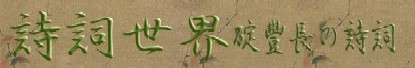
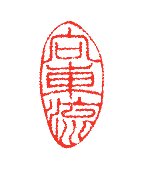
竹溪閑話

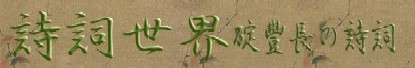
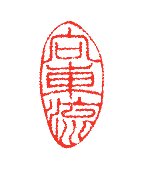
竹溪閑話
李陵 『昭明文選』に遺されている李陵 実をいうと、わたしは「古代人は純朴である」ということに何ら疑問を懐くことはなかった。それ故、ある時、現代人と少しも変わらないということを感じ取ったとき、ショックを受けた。 もっとも、落ち着いて考えてみれば、彼らも私たちも同じ人類で、別段、現代人が生物的に進化を遂げたというものではなかろう。ただ、文明の発達と、文化の集積の結果、私たちは文明社会に生き、文明の利器の恩恵を享受している。先人からの人智の蓄積に感謝する。しかしながら、人の一生を支配する感情は蓄積されないできたようだ。民族の感情は、蓄積されてきたようだが。 昨今、風雲が急を告げている。蘇武や李陵の時代と変わることなく………。 (2003年7月) ****************************** 緑野の憂愁 陶淵明と死 ずっと若かった頃、『飮酒二十首 其三」「道喪向千載,人人惜其情。有酒不肯飮,但顧世間名。所以貴我身,豈不在一生。一生復能幾,倏如流電驚。鼎鼎百年内,持此欲何成。」 わたしの歳が陶淵明に近づいたのだろうか、それとも境遇が似通ったのだろうか、『帰去来の辞』 わたし自身は、陶淵明が隠逸詩人と謂われるのに抵抗を感じている。『晋書』では確かに「隠逸」に分類されているが、わたしのイメージする「隠逸」は、もっと飄然とした生き方であって、このような悶えを出している生き方ではない。陶淵明は、命の尽きるときを見つめている。如何ともし難い有限の生命を活きぬく苦悩が滲んでいる。 こう思うわたしは、やはり自身がそこへ近づいてきたのか……。 (2003年7月) ******************************************** 瘴疫と陶淵明 東晉の陶潛に『歸園田居』五首があり、其四に、「一世異朝市」の句で有名な「久去山澤游,浪莽林野娯。試攜子姪輩,披榛歩荒墟。徘徊丘壟間,依依昔人居。井竈有遺處,桑竹殘朽株。借問採薪者,此人皆焉如。薪者向我言,死沒無復餘。一世異朝市,此語眞不虚。人生似幻化,終當歸空無。」 韓愈が都を逐われたとき、『左遷至藍關示姪孫湘』で「一封朝奏九重天,夕貶潮州路八千。欲爲聖明除弊事,肯將衰朽惜殘年。雲横秦嶺家何在,雪擁藍關馬不前。知汝遠來應有意,好收吾骨瘴江邊。」 一村を以て熄み、終焉を迎えられれば、ある意味では、よかったのだ。文明の発達とは、皮肉なものである。 (2003年7月。11月補) ************************** 汨羅 屈原に関して、「汨羅」の語句で検索した。すると『青年日本の歌』(昭和維新の歌)作詞曲三上卓 ------------------------------------ 汨羅の淵に波騷ぎ 巫山の雲は亂れ飛ぶ 混濁の世に我れ立てば 義憤に燃えて血潮湧く 權門上に傲れども 國を憂ふる誠なし 財閥富を誇れども 社稷を思ふ心なし ああ人榮え國亡ぶ 盲たる民世に躍る 治亂興亡夢に似て 世は一局の碁なりけり 昭和維新の春の空 正義に結ぶ丈夫が 胸裡百萬兵足りて 散るや萬朶の櫻花 古びし死骸乘り越えて 雲漂搖の身は一つ 國を憂ひて立つからは 丈夫の歌なからめや 天の怒りか地の聲か そもただならぬ響きあり 民永劫の眠りより 醒めよ日本の朝ぼらけ 見よ九天の雲は垂れ 四海の水は雄叫びて 革新の機到りぬと 吹くや日本の夕嵐 あゝうらぶれし天地の 迷いの道を人はゆく 榮華を誇る塵の世に 誰が高樓の眺めぞや 功名何ぞ夢の跡 消えざるものはただ誠 人生意氣に感じては 成否を誰かあげつらふ やめよ離騷の一悲曲 悲歌慷慨の日は去りぬ われらが劍今こそは 廓淸の血に躍るかな --------------------- 汨羅をうたうものの、これは屈原の慨世とは異なる。彼の『離騒』 嘗て、「民族の自由を守れ、…民族の敵 国を売るイヌどもを」と、祖国の労働者に蹶起せよと呼びかけた労働歌もあったのを思い出した。民族の慷慨の感情は、内に階級の“敵”を見つけ、外に異民族の侵掠をたたく。「異族」を打倒するのは、生けるものとしては、或いは正当なのかもしれない。然(さ)りとて、人類は経験の蓄積に因って、より賢明な文化を築き、より聡明になっていくべきものなのだろうが…。“現代”人なのだから、過去の人よりも進歩していると思っていたが…。 よくわからない…。何故かよく分からない寂しさと、不安が過ぎる。 (2003年7月) ************************** 豪放詞と慷慨 胡虜 話は飛躍するが、他の動物、ライオンなどの猛獣、また、鮎などの魚類にも自己の縄張り、テリトリーが存すると謂う。自分と同一種類の動物が自己の領域に入ってくるのを拒み、撃退するという。もしや、夷狄を撃退するというこの感情は、わたしたちのDNAに組み込まれている種族維持の行動になるのだろうか………。 “現代”人の知性で、このことを剋服できるのだろうか。わたしたち人間にも他の動物と共通の面はある。二十四史をひもといても、「首級二十萬」…と、似たようなことの繰り返しである。人生「鼎鼎百年内」、その内で、どう処理をしていくか。 話は、また飛ぶが、この問題を解決できる糸口がある。今日の漢民族のようになることである。漢民族は、現在十億人を越している。生物として見た場合、周りの生物を除去しないかぎり、一つの種族だけが特に伸長するということはない。しかしながら、漢民族はここ四十年の内に倍加し、巨大な民族になった。その理由の一つは、「民族」問題だからだと思われる。それは「人種」問題とは異なった概念だからである。「民族」問題は、自他の意識の問題であり、言語や生活習慣といった基層文化の問題が大きな位置を占めている。換言すれば、「ここにいる我々は、同胞である」という意識で、共通の文化をもっており、同化の意欲があれば、解決されてゆくものである。「大民族」は、「同胞意識」を拡大できる条件を備えている民族がなり得る。中華文明圏は、その意味において偉大である。特に、漢字文化は、(異なる発音の)語彙も文字を使うことによって、共通の表現が出来、同文同種となることができ、中国国内では包容力がある。共通の言語、共通の文化を持った一大民族ができあがる。北魏の経験は生かされるべきである。実際、今日の漢民族構成人員の容姿は、北は大きく、南は小さいなどという、地域による人種的な個体差をはっきりと持っている。それもよいことである。まとまることは、平穏な生活を送る上でかけがえのないものである。とりわけ、現在の中国では「中華民族」 ただ、惧れもある。それは、「同胞意識」が広がっていった場合、「同胞意識」でまとめきれない部分が出てくることである。それは、明らかな異民族の存在である。「同胞意識・仲間意識」でまとまる際、それら「異民族」は、共通の敵となり易いことである。人的交流が容易な場所にあって、明らかな異民族の国々、日本を始めとした東亜の国々がそれになり得やすい。「小 * *」「* * 狗」、或いはまた、「* * 鬼子」等、これまでも屡々いわれて来たからであり、公共の電波にものって流れることがある。実際、過去それらの国々の間では、しばしば干戈を交えたことがあったからではある。そこには、拭えぬ民族の怨念が感ぜられる。 われわれ現代人は、やはり聡明になって行かねばならぬ。憂国、慨世のみならず、広く天下の平穏をも願う。 -------------- 又 以前、アメリカ映画に『インディペンデンスデイ』があった。「独立記念日」の意か、異星人からの襲撃に対して、地球人類は人種の壁や民族の確執、宗教の違いを乗り越えて、一致団結してこれを撃滅するという話である。人類としての独立記念日というわけである。「地球人」「世界市民」が絵空事にならないように、この物語が荒唐無稽との評だけで終わることなく、その精神が夢にならないように、わたしたちは努力しなければならない。(2004.10.17補) (2003年7月) ****************** 奈良・寧樂の謎 「奈良」 - この語は、古漢語として見た場合、「どうして、良いのか?」「なぜ、良いのか?」の意になる。(「なんぞ 良からん?」「いかんぞ 良ろしからん?」)。もっとも、「奈」や「良」は、万葉仮名でもあり、平仮名の「な」「ら」の祖型でもあり、偶然の配列だろうと思っていた。 しかしながら、「寧樂」と書いて、「なら」と読む場合がある。この場合、漢語と見れば、「どうして、楽しいのか?」「どうして、素晴らしいのか?」「なぜ、楽しいのか?」の意になる。(「いづくんぞ 楽しからん?」「なんぞ 楽しからん?」)。 こうなると、やはり、「なら」の都を貶したいのではないかと思われてくる。 話は飛ぶが、最近テレビニュースから「ウリ ナラ」「ウリ ミンジョック」と、朝鮮語をよく耳にするようになった。「ウリ ナラ」とは、「我が国」の意で、「ウリ ミンジョック」とは、「我が民族」の意だそうだ。つまり、「ナラ」とは、朝鮮語で「くに」という意味になる。もしや「奈良」「寧樂」の文字表記を始めたのは、朝鮮半島から来た、漢語を能くする帰化人ではないのか。当時の日本の都のさまに、ちょっと批判的な烏有先生の手になったのだろう…。勿論、咎められた時には「いいえ、『寧(ねんごろ)に楽しむ』です。」と言えるようにも配慮した…。 (2003年8月) 又 「『寧楽』は、やはり『青丹よしならの都』で、『寧(ねんご)ろで楽(たの)しい』ところの意ではないのか?!」との思いもあろう。慥かに「寧」字には、「ねんごろ」〔ねい;ning2○〕の義と、なんぞ・いづくんぞ〔ねい;ning4●〕の義…がある。「それではやはり、『寧(ねんご)ろで楽(たの)しい』ところの意とも取れるのではないのか?!」とも思われよう。しかし、その意味で「寧」字と「楽」字を使うのならば、「寧楽」とはせずに「樂寧」〔らくねい;le4ning2●○〕とすべきである。このことは、「寧」字や「楽」字の附く熟語や年号等を見れば瞭然としている。 「なら」は『日本書紀』崇神天皇十年九月に「時官軍屯聚,時官軍屯聚、而蹢跙草木。因以號其山、曰那羅山。〔此云布瀰那羅須〕。更避那羅山…。」にもある。ここの「なら」ならば、心は安らぐ。 (2008年7月9日) ********** 名垂千古 漢の武帝と匈奴 英傑・漢の武帝 (2003年8月) ********** 紂王と伯夷 周の武王をめぐって 伯夷」 登彼西山兮,采其薇矣。 以暴易暴兮,不知其非矣。 神農、虞、夏忽焉沒兮,我安適歸矣? 于嗟徂兮,命之衰矣!」 周の武王は、義人か否か…。滔々たる流れの中では、そのどちらもが正しかろう。 (2003年9月) ********** 無言獨上西樓 西〔せい、さい;xi1〕-そのことばに賦与されたイメージは、現在までに既に固定化されてきているが、それは、いつの時代頃からなのかについて、興味を持ってみている。「西」は日が沈む方向で、その終焉の意味合いは、「語」よりも「義」が優先され、その延伸の義は、万国共通、人類普遍の感情かも知れないが…。(未完) (2003.10) *************** 李煜 『一斛珠』について 李煜に『一斛珠』 (2002.2~) *************** 兄弟鬩于牆,外禦其務 「兄弟鬩于牆,外禦其務。毎有良朋,烝也無戎。」 (2003年11月) **************** 魯迅『自嘲』について 民国の魯迅に『自嘲』「運交華蓋欲何求,未敢翻身已 これは、毛沢東より褒め称えられ まず、この詩を作った頃の魯迅は何を考えていたのか、魯迅の著作を調べた。この年、1932~33年には『南腔北調集』の中の雑文、評論を著している。その中で気になるのが『論“第三種人”』と『世故三昧』である。「内外」ならぬ「内内」の敵と戦っているのがよく分かる。満州事変、中国で謂う“九一八”のすぐ後でである。歴史の表に出てこない32~33年代の中国の事情がよく分かってくる。ここで思うのは、『自嘲』という題である。この詩題は、本ページ初めのような解釈では理解しにくいものの、次のようにとれば、よく納得できる。 そのような意味であるから『自嘲』と題が付けられた。魯迅は時節の急変に即応できない自身の心中の懊悩を文字にしたのではなかろうか。闘将であればこそより一層戦うべきであるのに、日本租界にいて中国国内の文壇、“旧思想”と闘っている自分の姿に“自嘲”の念を懐いたのではなかろうか。 その後、魯迅は毛沢東より高く買われ、上記の『在延安文芸座談会上的講話』でも、英雄的であると褒められ、「”千夫”とは敵のことである、…孺子とは、プロレタリア階級と人民大衆である…と如何様に凶悪な敵であっても、我々は決して屈服しない…」とまでいわれたので引っ込みがつかなくなったのではないか。文革期でもこの聯は、「不当な抑圧にもめげないで“造反有理”を言い続ける“文化の革命の先輩”」と讃えられた。日中の同時代人は、毛沢東の解釈を出られないのではないか。魯迅の作品を見て謂えることだが、彼は作品の主張を言明した用語、用字はないことだ。反語、諧謔はままあるが。しかし、読み進めば、全体として、主張がよくわかる、というやり方である。 魯迅は、確かに闘将ではある。感性豊かな闘将なのである。 作品についての詳しいことは、こちら (2003年12月) **************** 意外、検索結果 わたしのサイトは、CoCoDaの検索機能をお借りしている。閲覧された方がどのような語句で検索されたか、その結果報告が来た。意外だった。なぜ『春曉』が、こんなに高いのか? 『杜牧』はこんなに少ないものなのか……? 『蛇足』がこんなに高いのは、読者の方が、単なる註釈よりも、わたしの脱線の方を好まれるのか??(ものは試しで、「蛇足」で、検索してみた。おもしろかった。) これらが私自身の予想と大きく異なっていた。 やはり、唐詩、盛唐が多い。そちらにも今後一層、目を向けていくことにする。 検索内容は次の通りである。 なお、本サイトの詩詞原文と書き下し文は、旧字、旧仮名遣いで、機種依存文字も多用しています。次はその検索です。 **************** 平成16年(2004年)の分は こちら |
| 2003. 7.25起 2003. 9.29 10.21 11.10 11.22 12月 |
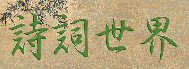
メール |
トップ |