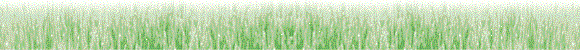漁父
唐・張志和
釣臺漁父褐爲裘, 兩兩三三舴艋舟。 能縱棹, 慣乘流, 長江白浪不曾憂。 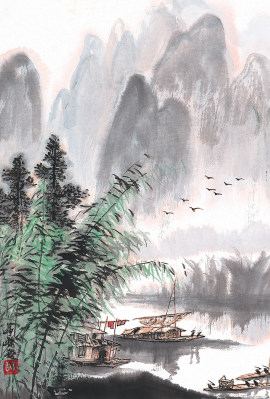 |
**********************


釣臺漁父褐爲裘, 兩兩三三舴艋舟。 能縱棹, 慣乘流, 長江白浪不曾憂。 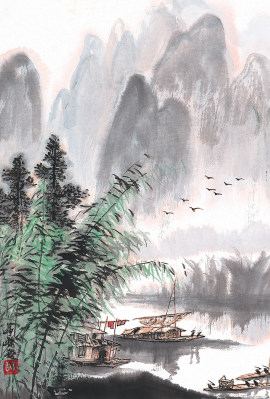 |
漁父******************
釣臺の漁父 褐(かつ)を 裘(きう)と爲(な)し,
兩兩 三三 舴艋(さくもう)の舟。
能(よ)く 棹(さを)を縱(あやつ)りて,
流れに乘るに 慣(な)れ,
長江の白浪 曾(かつ)て憂へず。
大きな地図で見る |
| 2005.11.23 11.24 11.25 11.26 |
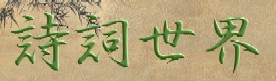
************ |
メール |
トップ |