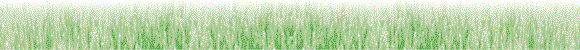| @@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@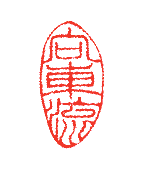 |
|
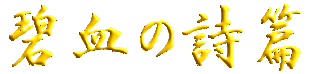 |
]ìt
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìvEÂäo`
| Jã]ãûC qDç¬áVB Ô\¢eC ê]tB ©tDgQ¦C éD³|B ]ìå«Ds@dC VåTç«àl¾ìB |
@@@ B