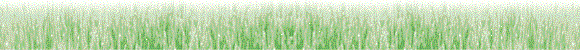ÊäÌ

@@@@@
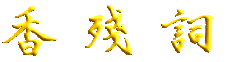
@@@@@@@@@@@ @@@@@@@ ^zãù/£æ
¶¸q
Üãµ®é£C
¾ÓpÚB
å\O·C
êêtéòêB
g_eÕòC
²Ðm½|B
[@½©¨C
wwmÔJB
******
¶¸q
@@@@@@@@@@@@@@@@@


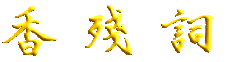
Üãµ®é£C
¾ÓpÚB
å\O·C
êêtéòêB
g_eÕòC
²Ðm½|B
[@½©¨C
wwmÔJB
******
¶¸q
@@@@@@@@@@@@@@@@@
ãµ ÀçÐðÜÝÄ@@é£ ð® ÖC
Óð¾Ä@@p É ÐÚ ÝéB
å @@\O· C
êê@@téò êéB
g_ @@eÕÉò èC
²@Ð ½ê½éÍ@@méâ@½| Èé©ðB
[@ @@©¨ ð½ µC
ww ½é@@mÔ ÌJB
*****************
| ` | 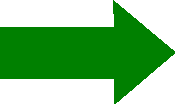 |
B |
| ` | B | |
| QOPQDUDPX @@@@@UDQO @@@@@UDQP @@@@@UDQQ® QOPRDSDPPâ |
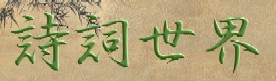
[ |
gbv |