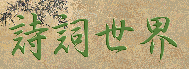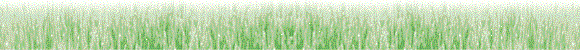| ú{CåD¤ | ||
¡äàF |
||
÷¼g IÍàC äÝ¢RgÒL÷B ~m·S»ÍC JüYªvÇB ¶EDÀrC ìà¨cwÔñÒB ÒRÕün峽C ´狀©YøB äRñÂÅpC ¼ãßߥ¡ÃB ßHFueõwÍX±¬C c »EݧBv ñÂêeÍêrC CppN\B GÍ¿ªäwäçðC ä[Ûñ¬B àÙÍ~Òl@í¾ÒùñC Eñ¦Òã@AßÒOB ½PGøf®øC P GtMÒB jÄäR´Òà¨`NC `V¶æ¯B ðÖ ÞØC áwö@ç¥éÊB Vcd{á¢`RC ÍÍ»¥`ä[mB ·û¹ú{CC ÄGÍSá¶ááB ðs·³Kó´ð¹C RFs`ÍFSB ðá²ðÁû~ û~C ümògB ò¶ò@VqÝC à¨`ã¦B ñêIìNäobF uû~ ¶äÝ¢·Bv |
||
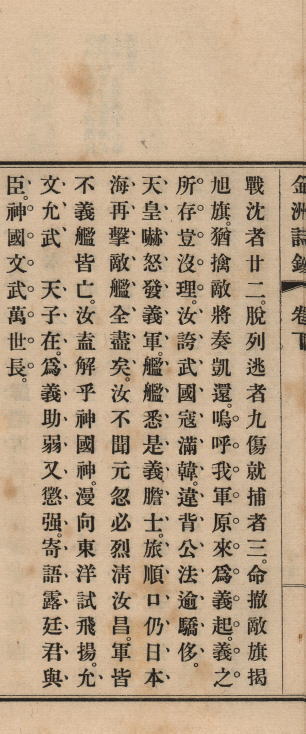 |
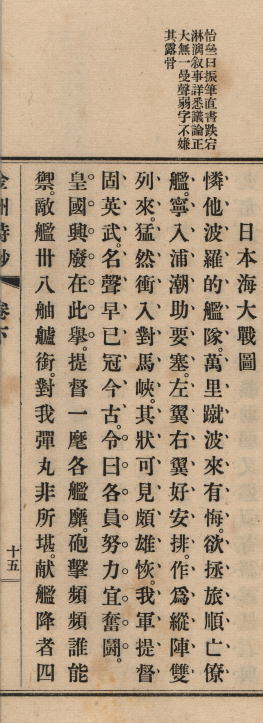 |
| ¡äàFFwàFçâxɺ@å³lN | |
******
ú{C