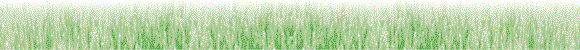| å | ||
BE¼û¸ûé·iUìj |
||
l¶³s·C g毴çjB vävVºC ¼{äÝ¢¼B µácÕÛTÛC êê³pç´ádB ûòR|ÂC Nà¨ê©mÍÄB jZvÝ@æC DgðÚ[sB ê¯ã¼å¤ÊC û|ÀÄ}B HQVní|C VÛ³_nä©ä©B jÄ\ñ\µI궼C xÌ´\½|XB ´ÒáÌáÉ·OC ©mƼmB |
||
 |